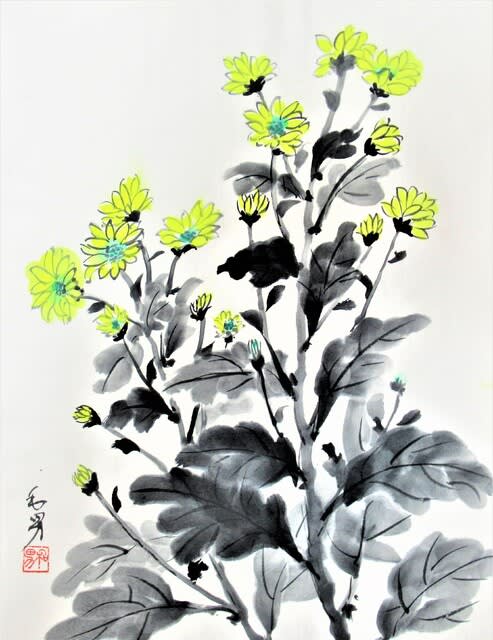10月早々から本格的に穫り始めた長ネギは、近年では一番出来がいいようです。
しかし、土寄せは限界に達し、これ以上の軟白は難しく、後は成り行きに任せます。
ただ、1ヵ月ほど遅れて植付けた手前の1畝を曲がりネギ風にしてみることにしました。
しかし、土寄せは限界に達し、これ以上の軟白は難しく、後は成り行きに任せます。
ただ、1ヵ月ほど遅れて植付けた手前の1畝を曲がりネギ風にしてみることにしました。

当初からの曲がりネギ栽培ではないので、あくまで曲がりネギ風です。
「曲がりネギ」とはネギを直立に伸ばさず、あえて湾曲させるものです。
当県には伝統的な曲がりネギの栽培法があり、発祥の地は仙台市の余目地区です。
地下水が高い悪条件下で軟白部を長く伸ばすため、ヤトイという作業を行うのが特徴。
ネギを寝かせて植え替え、そこに土を盛り長い軟白部を確保すると言うものです。
ネギが生長し伸びるに従い曲がりが生じます。
曲がる時にネギにストレスが掛かることで軟らかく甘味も増すとされます。
当地方では「曲がりネギ」は旨いネギとして高い人気を得ています。
当地のような粘土質で湿害を受けやすい所でも行われてきましたが、植え替えの手間が掛かるので、今では機械作業がやりやすい長ネギ栽培が一般的となりました。
1畝の収穫が終わりスペースのできた部分を利用し、「曲がりネギ」風にするためのヤトイを行ってみます。
「曲がりネギ」とはネギを直立に伸ばさず、あえて湾曲させるものです。
当県には伝統的な曲がりネギの栽培法があり、発祥の地は仙台市の余目地区です。
地下水が高い悪条件下で軟白部を長く伸ばすため、ヤトイという作業を行うのが特徴。
ネギを寝かせて植え替え、そこに土を盛り長い軟白部を確保すると言うものです。
ネギが生長し伸びるに従い曲がりが生じます。
曲がる時にネギにストレスが掛かることで軟らかく甘味も増すとされます。
当地方では「曲がりネギ」は旨いネギとして高い人気を得ています。
当地のような粘土質で湿害を受けやすい所でも行われてきましたが、植え替えの手間が掛かるので、今では機械作業がやりやすい長ネギ栽培が一般的となりました。
1畝の収穫が終わりスペースのできた部分を利用し、「曲がりネギ」風にするためのヤトイを行ってみます。

まず、畝を崩してネギを全て掘り上げます。

本来は軟白を始める時点からヤトイの作業をします。
このように長ネギの土寄せ中途からヤトイの作業をするということはありません。ですから、あくまで「曲がりネギ」風と言うわけです。

植え替えするための溝を作ります。

見にくいですが、ごく緩い傾斜になるような植え溝です。

ここにネギを寝かせた状態で並べます。

ごく軽い斜め植えになります。

正面から見ればこうなります。

分岐部まで土を被せます。

覆土の厚さは数センチ程度。

この後、生長するに従い葉は垂直に伸びてくるので、次第に曲がりができてくるのです。

伸びてきたら、またそこに土を盛っていきます。
そうすると、ネギは湾曲しながら軟白されるというわけです。
時期としてはかなり遅いので、どの程度「曲がりネギ」風になるでしょうか。
時期としてはかなり遅いので、どの程度「曲がりネギ」風になるでしょうか。