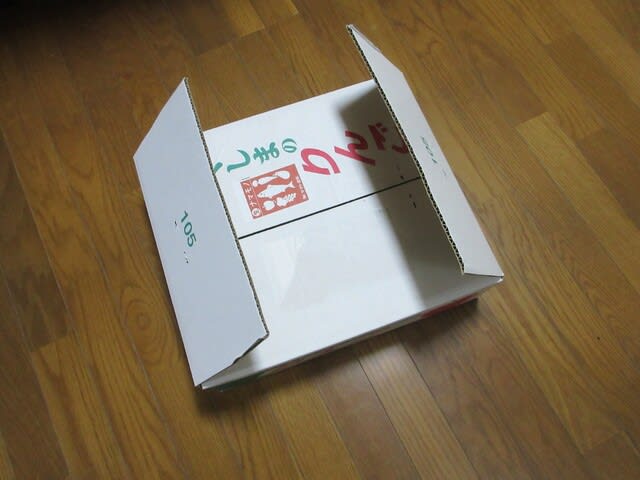干し柿は、干し始めから数えると間もなく4ヶ月になろうとしています。
年が明けころ柿の出来上がりから数えても2ヵ月以上。まだ残っており食しています。ほぼ例年通りと言ったところ。
年内に取り込み、空気に晒したまま放置すると硬くなるので、段ポールの中に入れ、紙にくるんで保管しました。
さらに少なくなったところでポリ袋に入れ集約。2月末からは冷蔵庫で保管しています。
さらに少なくなったところでポリ袋に入れ集約。2月末からは冷蔵庫で保管しています。
簡便な保存方法です。現在はこれだけになりました。

白粉が全体に回り地肌は殆ど見えなくなりました。

これは1ヶ月ほど前ラップに包んでからタッパーに入れて保管していた干し柿。

取ってみました。

ラップに包んで保管すると水分が保たれるためしっとり感があります。

2月の投稿時にも記していますが、改めて昨秋穫った蜂屋柿には種が極めて少ないことが分かりました。
これほど軒並み種の少ない蜂屋柿は初めてでしょう。全くない柿の方が多い。
大玉揃いだった割には縮んでしまった一つの要因と思われます。
これ以外に冷凍している干し柿があります。
長期に同じ状態を保とうとするなら冷凍するのが確実。ラップに包めばなお確実です。
長期に同じ状態を保とうとするなら冷凍するのが確実。ラップに包めばなお確実です。
一部を取り出してみます。これは年明け後白粉が回り始めた「ころ柿」の状態で冷凍している干し柿。

干し柿は水分が少ないため家庭用の冷蔵庫ではカチンカチンにはならず弾力があります。
これは、茶菓子として出ている干し柿。

白粉は全面に厚く回っています。
1個取ってみます。

割いてみます。

ねっとりとしたヨウカン状で、やや硬めながら小生は全く気になりません。
但し白粉の量が多いからより甘いという訳ではありません。この時期らしい旨味が味わえます。
これまでの干し柿の変化を少し見てみます。
これが約1ヶ月前。

さらに約1ヶ月前の年明け頃のころ柿。

さらに半月ほど遡り、年内のあんぽ柿出来上がりの頃。

違いがよく分ります。
その時々の干し柿を味わうのも良いものです。あともう少し楽しめます。
幼少の頃は遅くまで沢山の干し柿が残っていたのでよく天ぷらにして出されました。小生は得意ではありませんでした。
そもそも子供はあまり干し柿を好まないようです。小生も甘柿のほうが好きでした。それが年を重ねるにしたがって干し柿が良くなるから不思議です。