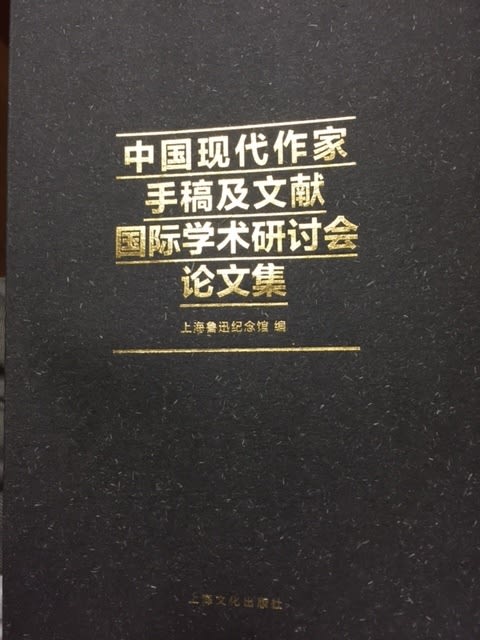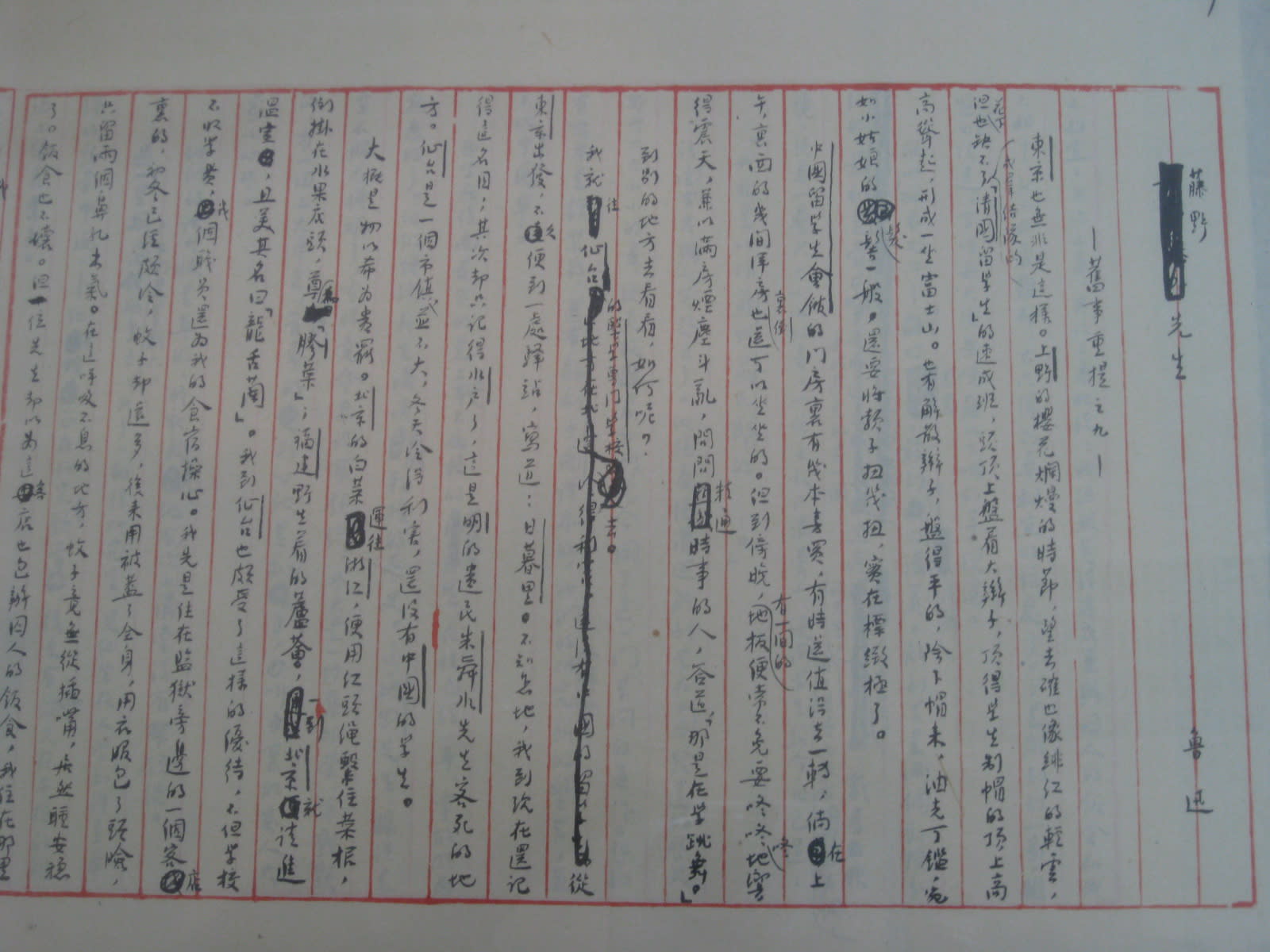先日、友人の結婚パーティーでスピーチをした際、突然、ある人物が頭をよぎった。不思議な体験であった。奇異に思われるだろうが、その人物とはカナダ出身の英文学者、ハーバート・マーシャル・マクルーハン(Herbert Marshall McLuhan、1911~1980)だ。メディア研究の名著『Understanding Media: the Extensions of Man』(1964)=邦訳『メディア論――人間の拡張の諸相』(みすず書房)の筆者として知られる。

一般にメディアは新聞、テレビなどの報道機関を指すが、マクルーハンは「メディアはメッセージだ」と斬新な定義をし、テクノロジーと同様、人間の身体を拡張させたものだと主張した。自動車や自転車は足の拡張、ラジオは耳の拡張で、それぞれメッセージを伝える装置となる。単に言葉と言っても、空気がなければ伝わらないから、空気もメディだということになる。独立した思考による新たな理論は、たとえそれに異論が挟まれたとしても、精神の優れた営みとして尊敬に値する。たとえ半世紀以上を経ようと、時空を超えた真理への追求によって共感を与えるものだ。
なぜ彼のことが思い浮かんだのか。簡単に言えば、音声でメッセージを伝えることの難しさを感じたからだ。
友人の新郎は大学時代の同級生だった。新婦とはいわゆる結婚相談所主催のパーティーで約1年前、知り合った。学校や職場、趣味などで知り合ったケースや友人知人の紹介を受けた関係は、そもそもその土台にある社会関係がしっかりしている「強い絆」だ。昨今、しばしば耳にするネットでの出会いなどを含めたそれ以外の関係は、一昔前には考えなれなかった現代的な「柔らかい縁」である。
当初、新郎新婦は披露パーティーも予定しておらず、「柔らかい縁」に準じて結婚の儀を済ませようと考えていた。だが、私たちの仲間が動いて「強い絆」によるかなり本格的な披露宴が行われた経緯があった。学生時代の恩師も招き、学生時代の友人のほか現在の職場などを含め計4グループが参加した。十分な準備期間はなかったが周到な進行が練られた。
「強い絆」は伝統的にある組織を主体とした関係である。「柔らかい縁」とは組織の背景を持たない、だが一定の価値観を共有した新たな形態のネットワークで生まれる関係である。前者が同質、単一なのに対し、後者は多様、柔軟の性格を持つと言ってよい。仏哲学者リオタールの言葉を強引に用いれば、「大きな物語」と「小さな物語」の違いである。
結婚パーティーは「強い絆」が「柔らかい縁」を取り囲んで祝福する場であった。友人代表としてあいさつを求められた私はまず、四つある「強い絆」のまとまりが「柔らかい縁」を共有できるような内容を心掛けた。仲人もおらず、当の新郎が出席者に対し、なれそめなどの話を十分にしていなかったため、かなり難渋した挙句、長くなり過ぎて野次を受ける始末だった。会場の空気を振動させ、メッセージを音声で伝える難しさを体で感じ、マクルーハンの言葉がよみがえったというわけだった。
「空気」は単に音声を運ぶだけでなく、いかに発声するか、つまりいかなる内容を現場の「空気」に応じて伝えるか、にもかかわっていた。聴衆の空気を目で見て、耳で聞き、肌で感じ、まさに五感を動員してメッセージを伝えることが、つまりメディアなのだと感じた。マイクも必要だったが、それはあまりメッセージにおいて重要ではなかった。相手は目の前にいたからだ。もし文字で伝えなけれなならないとしたら、五感よりも大脳をフル回転しなければならなかっただろう。現場から離れるにしたがって、メディアは臨場感を失い、伝わる力も弱まるのである。
会場には生のブラスバンド演奏も披露され、盛況のうちに幕を閉じた。完全な手作りではあったが、「強い絆」と「柔らかい縁」が響き合ったよい宴だった。メディアは「大きな物語」と「小さな物語」をつなぐ役割を果たしたのではないか、とホッとした。

一般にメディアは新聞、テレビなどの報道機関を指すが、マクルーハンは「メディアはメッセージだ」と斬新な定義をし、テクノロジーと同様、人間の身体を拡張させたものだと主張した。自動車や自転車は足の拡張、ラジオは耳の拡張で、それぞれメッセージを伝える装置となる。単に言葉と言っても、空気がなければ伝わらないから、空気もメディだということになる。独立した思考による新たな理論は、たとえそれに異論が挟まれたとしても、精神の優れた営みとして尊敬に値する。たとえ半世紀以上を経ようと、時空を超えた真理への追求によって共感を与えるものだ。
なぜ彼のことが思い浮かんだのか。簡単に言えば、音声でメッセージを伝えることの難しさを感じたからだ。
友人の新郎は大学時代の同級生だった。新婦とはいわゆる結婚相談所主催のパーティーで約1年前、知り合った。学校や職場、趣味などで知り合ったケースや友人知人の紹介を受けた関係は、そもそもその土台にある社会関係がしっかりしている「強い絆」だ。昨今、しばしば耳にするネットでの出会いなどを含めたそれ以外の関係は、一昔前には考えなれなかった現代的な「柔らかい縁」である。
当初、新郎新婦は披露パーティーも予定しておらず、「柔らかい縁」に準じて結婚の儀を済ませようと考えていた。だが、私たちの仲間が動いて「強い絆」によるかなり本格的な披露宴が行われた経緯があった。学生時代の恩師も招き、学生時代の友人のほか現在の職場などを含め計4グループが参加した。十分な準備期間はなかったが周到な進行が練られた。
「強い絆」は伝統的にある組織を主体とした関係である。「柔らかい縁」とは組織の背景を持たない、だが一定の価値観を共有した新たな形態のネットワークで生まれる関係である。前者が同質、単一なのに対し、後者は多様、柔軟の性格を持つと言ってよい。仏哲学者リオタールの言葉を強引に用いれば、「大きな物語」と「小さな物語」の違いである。
結婚パーティーは「強い絆」が「柔らかい縁」を取り囲んで祝福する場であった。友人代表としてあいさつを求められた私はまず、四つある「強い絆」のまとまりが「柔らかい縁」を共有できるような内容を心掛けた。仲人もおらず、当の新郎が出席者に対し、なれそめなどの話を十分にしていなかったため、かなり難渋した挙句、長くなり過ぎて野次を受ける始末だった。会場の空気を振動させ、メッセージを音声で伝える難しさを体で感じ、マクルーハンの言葉がよみがえったというわけだった。
「空気」は単に音声を運ぶだけでなく、いかに発声するか、つまりいかなる内容を現場の「空気」に応じて伝えるか、にもかかわっていた。聴衆の空気を目で見て、耳で聞き、肌で感じ、まさに五感を動員してメッセージを伝えることが、つまりメディアなのだと感じた。マイクも必要だったが、それはあまりメッセージにおいて重要ではなかった。相手は目の前にいたからだ。もし文字で伝えなけれなならないとしたら、五感よりも大脳をフル回転しなければならなかっただろう。現場から離れるにしたがって、メディアは臨場感を失い、伝わる力も弱まるのである。
会場には生のブラスバンド演奏も披露され、盛況のうちに幕を閉じた。完全な手作りではあったが、「強い絆」と「柔らかい縁」が響き合ったよい宴だった。メディアは「大きな物語」と「小さな物語」をつなぐ役割を果たしたのではないか、とホッとした。