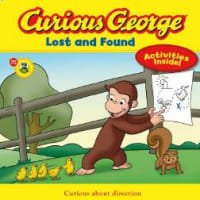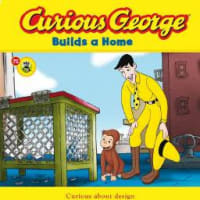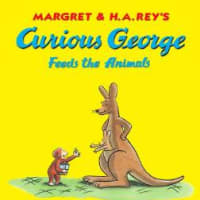児童文学の領域で秀逸な作品を発表し続ける著者によるファンタジー小説。2022年3月に上下2巻の単行本が刊行された。上巻には「西から来た少女」、下巻には「遙かな道」という副題が付いている。
物語は、ウマール帝国とこの帝国の属国である4つの藩王国-西カンタル・東カンタル・オゴダ・リグダール-が舞台となる。著者が創造したフィクションの帝国と属国。ウマール帝国と藩王国全域の存亡を揺るがす大災害の発生とその克服の物語。児童から大人までを幅広く読者対象とする小説。ある意味では大人の為のファンタジー小説と言ってもよいと思う。帝国の運営維持という政治・政策の世界と自然災害-自然の生態系、天敵という形での食物連鎖-との関係を壮大な物語として描いている。なお、そこには自然災害と見えて底流に人為的要因が潜む場合もある。
本書では人と自然との共存を追究するというテーマがベースになっていると思う。
さまざまな香りを嗅ぎ、香りに声を聞き、その意味を理解できるという非凡な能力を持つ少女アイシャの孤独と運命の変転、その成長が物語となっていく。
遙か昔、ウマール帝国の皇祖となる男とカシュガ家の始祖となるアミルが、神郷オアレマズラから一人の女性とオアレ稲を携えて帰国した。その女性はオアレ稲の栽培の方法を人々に教え、オアレ稲の生育を制御する知識・技術を司り、初代香君として、香りで万象を知る活神として奉られる。ウマール人の政権はこのオアレ稲を戦略的に活用して帝国を形成していった。オアレ稲を栽培すると、その土地の人口を増やし豊かにする反面、オアレ稲を植えた土壌はその質が変化し、他の植物が育たなくなる弊害があった。だが、人々は餓える心配がなく豊かさをもたらすオアレ稲を歓迎し、栽培を広げた。ウマール帝国の西に位置する藩王国は、オアレ稲の魅力に屈し、ウマール帝国の支配下に入る。
オアレ稲の種籾を植え、定められた肥料を指示通りに使い栽培すると、豊かな稔りをもたらすが、その稔りから次の種籾はできなかった。種籾はウマール帝国の政権の専売になっていた。この種籾のコントロールと専売は、まさにウマール帝国が周辺国を支配下に置く戦略的な手段となり、繁栄する。
西カンタルを治めていた王ケルアーンは、オアレ稲の問題点を見抜き、西カンタルでの栽培を禁じた。だが餓える民衆はそれに抗うようになり、西カンタルはヂュークチに簒奪されてしまう。ケルアーン家の生き残りはケルアーンの孫、姉アイシャと弟ミルチャのみとなる。アイシャとミルチャが捕縛され、ジュークチの前に引き出された時、アイシャは、ジュークチの体から冥草の匂いを嗅ぎ取り、あなたは毒を盛られていると指摘した。その場に同席していた藩王国視察官のマシュウ=カシュガは、アイシャの非凡な嗅覚に気づく。マシュウの指示で即刻医術師が呼ばれ、ジュークチは一命を取り留める。だが、ジュークチは後悔をなくすために二人の処刑を考える。マシュウは情けをかけるなら斬首でなく苦しまず眠るように逝く毒殺を薦める。
アイシャとミルチャは凍草を使い毒殺される。そして、ジュークチの眼前でユギの木の下に埋葬された。だが、ここにマシュウの謀があった。凍草の毒の量を調整し仮死状態を死と見せかけて、救助するためだった。アイシャとミルチャは蘇生する。
香りの声を聞く非凡な能力を持つアイシャはマシュウに見出され、ウマール帝国の帝都に向かうことになる。「西から来た少女」の誕生だ。
マシュウにより、ミルチャは身の安全を確保できる地に匿われ生活の場を得る。一方、アイシャは、マシュウの意を受けたミジマ=オルカシュガにより香君の住む宮殿である香君宮に誘われる。ミジマは香君宮に仕える上級香使であり、香使たちを束ねる大香使ラーオ=カシュガの次女である。
アイシャは、マシュウの母方の従妹、アイシャ=ロリキという名目で、<リアの菜園>に入園し、香君に仕えるという道を歩み始めることになる。アイシャはミジマに導かれて、御簾越しに、香君を継承する活神に引き合わされる。
アイシャとマシュウの関係は? 物語の後半で明らかになっていく。
読者は徐々に、香君の位置づけと存在価値並びにその役割、オアレ稲とその肥料に秘められた秘密、ネルマール帝国の政権の中枢における人間関係と勢力関係、オアレ稲の取扱についてのそれぞれの立場による思惑の相違などを理解していくことになる。これら諸側面の絡まり行く状況が、読者をこのストーリーに引きこんでいく。
たとえば、ウマール帝国の皇帝のもとで政権を担うのはイール=カシュガである。彼は新カシュガ家の当主。富国ノ大臣であり、帝国の財政を維持する視点からオアレ稲を見据えて政策をとっている。マシューはイールの弟ユーマ=カシュガルの息子である。今は藩王国視察官として、帝国を支える立場に立つ。だが、マシュウは伯父のイールの政治・政策とは異なる視点で帝国の維持運営を捉えている。イールと直接の対立はしないが、イールの政策に同調している訳ではなく、別のあり方を思慮している。
<リアの菜園>で働き始めたアイシャは、菜園で栽培されている植物たちの香りの声を聞き、無自覚に禁忌の行動をとったことから、オリエと直接に会話をする機会を持つ。オリエの発する香りから、アイシャはオリエが香君その人であると認識する。これがアイシャとオリエとの関係が深まっていく契機となる。
<リアの菜園>から<ユギル山荘>で働くようになり、やがて香使の一人として、藩王国との間でオアレ稲に関わっていく。実状からさまざまなことを学び、考え始める。
このストーリー、アイシャが香りの声を聞き、その意味を理解するというステップの一つ一つが読ませどころとなりつつ。その香りの声の広がりと繋がりが、物語の大きなうねり、帝国と藩王国への危機の到来へ突き進んで行く。巧みなストーリー構成になっている。
香君オリエが、<青稲ノ風>儀礼のために、オゴタ藩王国のラパ地方のオアレ稲の栽培地に赴いた時に、水田でヨマの卵に似ているけれど見たことがないほどの大きな卵に気づいた。オアレ稲の根元に付いていたという。ラーオ師がオリエにこのことを知らされたときから、オアレ稲への災害の兆しが始まって行く。それは、オオヨマの発生だった。この虫害発生は、その一帯のオアレ稲を焼き払う処置で被害の拡大を防がねばならなくなる。それは餓える人々の発生に繋がって行く。
一方、オゴダ藩王国の藩王母ミリアは密かに独自にオアレ稲を研究・栽培するという行動をとっていた。このこと自体が、ウマール帝国の脅威になりかねない事象でもあった。アイシャはこの状況の中に投げ込まれていく。このオゴダの秘密自体が大きな山場の一つになっていく。
オオヨマに対処できる<救いの稲>が開発されてくる。だが、<救いの稲>の香りが次の新たな災害をもたらすことになる。バッタの大群が西カンタル藩王国の北側にそびえる天炉山脈の方から襲来するのだ。<天炉のバッタ>と称されるようになるが、このバッタによる虫害との戦いが、下巻でメインストーリーとして進行していく。
<天炉のバッタ>の凄まじい広がりにどのように対処できるのか。藩王国間の意識の差、藩王国とウマール帝国との間での為政者たちの意識の差。ウマール帝国と藩王国との存亡はこの虫害への対処の仕方にかかってくる。
ストーリーの進展とともに、ウマール帝国と藩王国の体制や情勢のイメージが形成され、香君オリエ、藩王国視察官マシュウ、富国ノ大臣イール、大香司ラーオ、そしてこのストーリーの主人公アイシャの人物像のイメージが形成され、ストーリーに引きこまれていく。ストーリーの最終ステージの山場は、涙なくして読めないのではないかと感じる。香君オリエとアイシャの立場と彼らの行動にまさに感情移入して読んでしまった。
最後に、印象深い箇所をご紹介しておきたい。
*ここに来るたびに、思うの。多くの他者が互いに手を差し伸べあっていることの意味を。弱い者を見放さず、手を差し伸べることが、何を守るのかを。 ⇒オリエの言 上p229
*表情をあらため、真剣な眼差しで、自分がこう感じるから、他の人も同じように感じるだろうと思ってはいけない、そう思ってしまったとき隙が生まれる、と言っていたマシュウの顔が目に浮かんだ。 ⇒アイシャの思い 下p41
*生き延びるという、最も大切なことを行うときにすら、人という生き物は様々な思惑にとらわれ、戸惑い、決断するまでに時間がかかる。危機感を共有することすら難しい。
⇒アイシャの思い 下p226
*生き物は、どんな存在に生まれるか、選ぶことはできない。望む力を持って生まれてくるわけでもない。それでも、それぞれが己の持つ力を活かし、あるときは他者を助け、あるときは他者を害して生きていく。
そういう関係が絶えず動き続ける網の目のようにこの世を覆っていて、ちっぽけな虫ですら、それぞれの役割を背負い、その網の目をつくっている。どんな小さな者も己の役割を担って生きている。 ⇒オリエの言 下p318
*権威というのは、・・・互いの関係で成り立つ。幻想だ。幻想だが、いったん身に沁み込んでしまえば、反射的に心身が反応するし、多くの人が同時に抱けば、現実の力となる。
⇒マシュウの言 下p328
*香りで万象を知ることなんて、出来ません。初代の香君は、私などより、ずっとすごい人だったのかもしれないけれど、それでも香りで万象を知ることなんて出来たとは思えません。わからないことも、たくさんあったはずです。その、わからないことすら、わかったふりをして、その偽りを、神という幻想で隠して、これまで-ここまで、来てしまったことが、私には、とても怖いことに思えるんです。 ⇒アイシャの言 下p331
*人々が、神に頼るのではなく、オリエがつくった「場」の中で、自らの立場を再認識し、自らの意思で未来を選ぶ、そういう道をオリエはつくりたかったのだ。
⇒アイシャの思い 下p404
*知識さえあれば、辺境の農夫たちだって、自分たちの未来を、自分たちで救えたかもしれない。 ⇒アイシャの言 下p430
*どんな道にもそれぞれの難点がありますね。 ⇒アイシャの言 下p431
*<語ると、それが現れる>からですよ。 ⇒ユーマの言 下p441
*ひとつの稲に過度に依存することは、もちろん避けねばなりませんが、いまの我々が為すべきは、オアレ稲の排除ではなく、あの稲との共存なのでしょう。 ⇒ユーマの言 p448
人の我欲による行動と自然の生態系について、私たちに考えさせる小説だと思う。
このフィクションのファンタジーな世界は、現実の世界に対する鏡の役割を果たしているようにも思う。
ご一読ありがとうございます。
こちらもお読みいただけるとうれしいです。
[遊心逍遙記]に掲載
『鹿の王 水底の橋』 角川書店
『精霊の木』 偕成社
『鹿の王』 上・下 角川書店
物語は、ウマール帝国とこの帝国の属国である4つの藩王国-西カンタル・東カンタル・オゴダ・リグダール-が舞台となる。著者が創造したフィクションの帝国と属国。ウマール帝国と藩王国全域の存亡を揺るがす大災害の発生とその克服の物語。児童から大人までを幅広く読者対象とする小説。ある意味では大人の為のファンタジー小説と言ってもよいと思う。帝国の運営維持という政治・政策の世界と自然災害-自然の生態系、天敵という形での食物連鎖-との関係を壮大な物語として描いている。なお、そこには自然災害と見えて底流に人為的要因が潜む場合もある。
本書では人と自然との共存を追究するというテーマがベースになっていると思う。
さまざまな香りを嗅ぎ、香りに声を聞き、その意味を理解できるという非凡な能力を持つ少女アイシャの孤独と運命の変転、その成長が物語となっていく。
遙か昔、ウマール帝国の皇祖となる男とカシュガ家の始祖となるアミルが、神郷オアレマズラから一人の女性とオアレ稲を携えて帰国した。その女性はオアレ稲の栽培の方法を人々に教え、オアレ稲の生育を制御する知識・技術を司り、初代香君として、香りで万象を知る活神として奉られる。ウマール人の政権はこのオアレ稲を戦略的に活用して帝国を形成していった。オアレ稲を栽培すると、その土地の人口を増やし豊かにする反面、オアレ稲を植えた土壌はその質が変化し、他の植物が育たなくなる弊害があった。だが、人々は餓える心配がなく豊かさをもたらすオアレ稲を歓迎し、栽培を広げた。ウマール帝国の西に位置する藩王国は、オアレ稲の魅力に屈し、ウマール帝国の支配下に入る。
オアレ稲の種籾を植え、定められた肥料を指示通りに使い栽培すると、豊かな稔りをもたらすが、その稔りから次の種籾はできなかった。種籾はウマール帝国の政権の専売になっていた。この種籾のコントロールと専売は、まさにウマール帝国が周辺国を支配下に置く戦略的な手段となり、繁栄する。
西カンタルを治めていた王ケルアーンは、オアレ稲の問題点を見抜き、西カンタルでの栽培を禁じた。だが餓える民衆はそれに抗うようになり、西カンタルはヂュークチに簒奪されてしまう。ケルアーン家の生き残りはケルアーンの孫、姉アイシャと弟ミルチャのみとなる。アイシャとミルチャが捕縛され、ジュークチの前に引き出された時、アイシャは、ジュークチの体から冥草の匂いを嗅ぎ取り、あなたは毒を盛られていると指摘した。その場に同席していた藩王国視察官のマシュウ=カシュガは、アイシャの非凡な嗅覚に気づく。マシュウの指示で即刻医術師が呼ばれ、ジュークチは一命を取り留める。だが、ジュークチは後悔をなくすために二人の処刑を考える。マシュウは情けをかけるなら斬首でなく苦しまず眠るように逝く毒殺を薦める。
アイシャとミルチャは凍草を使い毒殺される。そして、ジュークチの眼前でユギの木の下に埋葬された。だが、ここにマシュウの謀があった。凍草の毒の量を調整し仮死状態を死と見せかけて、救助するためだった。アイシャとミルチャは蘇生する。
香りの声を聞く非凡な能力を持つアイシャはマシュウに見出され、ウマール帝国の帝都に向かうことになる。「西から来た少女」の誕生だ。
マシュウにより、ミルチャは身の安全を確保できる地に匿われ生活の場を得る。一方、アイシャは、マシュウの意を受けたミジマ=オルカシュガにより香君の住む宮殿である香君宮に誘われる。ミジマは香君宮に仕える上級香使であり、香使たちを束ねる大香使ラーオ=カシュガの次女である。
アイシャは、マシュウの母方の従妹、アイシャ=ロリキという名目で、<リアの菜園>に入園し、香君に仕えるという道を歩み始めることになる。アイシャはミジマに導かれて、御簾越しに、香君を継承する活神に引き合わされる。
アイシャとマシュウの関係は? 物語の後半で明らかになっていく。
読者は徐々に、香君の位置づけと存在価値並びにその役割、オアレ稲とその肥料に秘められた秘密、ネルマール帝国の政権の中枢における人間関係と勢力関係、オアレ稲の取扱についてのそれぞれの立場による思惑の相違などを理解していくことになる。これら諸側面の絡まり行く状況が、読者をこのストーリーに引きこんでいく。
たとえば、ウマール帝国の皇帝のもとで政権を担うのはイール=カシュガである。彼は新カシュガ家の当主。富国ノ大臣であり、帝国の財政を維持する視点からオアレ稲を見据えて政策をとっている。マシューはイールの弟ユーマ=カシュガルの息子である。今は藩王国視察官として、帝国を支える立場に立つ。だが、マシュウは伯父のイールの政治・政策とは異なる視点で帝国の維持運営を捉えている。イールと直接の対立はしないが、イールの政策に同調している訳ではなく、別のあり方を思慮している。
<リアの菜園>で働き始めたアイシャは、菜園で栽培されている植物たちの香りの声を聞き、無自覚に禁忌の行動をとったことから、オリエと直接に会話をする機会を持つ。オリエの発する香りから、アイシャはオリエが香君その人であると認識する。これがアイシャとオリエとの関係が深まっていく契機となる。
<リアの菜園>から<ユギル山荘>で働くようになり、やがて香使の一人として、藩王国との間でオアレ稲に関わっていく。実状からさまざまなことを学び、考え始める。
このストーリー、アイシャが香りの声を聞き、その意味を理解するというステップの一つ一つが読ませどころとなりつつ。その香りの声の広がりと繋がりが、物語の大きなうねり、帝国と藩王国への危機の到来へ突き進んで行く。巧みなストーリー構成になっている。
香君オリエが、<青稲ノ風>儀礼のために、オゴタ藩王国のラパ地方のオアレ稲の栽培地に赴いた時に、水田でヨマの卵に似ているけれど見たことがないほどの大きな卵に気づいた。オアレ稲の根元に付いていたという。ラーオ師がオリエにこのことを知らされたときから、オアレ稲への災害の兆しが始まって行く。それは、オオヨマの発生だった。この虫害発生は、その一帯のオアレ稲を焼き払う処置で被害の拡大を防がねばならなくなる。それは餓える人々の発生に繋がって行く。
一方、オゴダ藩王国の藩王母ミリアは密かに独自にオアレ稲を研究・栽培するという行動をとっていた。このこと自体が、ウマール帝国の脅威になりかねない事象でもあった。アイシャはこの状況の中に投げ込まれていく。このオゴダの秘密自体が大きな山場の一つになっていく。
オオヨマに対処できる<救いの稲>が開発されてくる。だが、<救いの稲>の香りが次の新たな災害をもたらすことになる。バッタの大群が西カンタル藩王国の北側にそびえる天炉山脈の方から襲来するのだ。<天炉のバッタ>と称されるようになるが、このバッタによる虫害との戦いが、下巻でメインストーリーとして進行していく。
<天炉のバッタ>の凄まじい広がりにどのように対処できるのか。藩王国間の意識の差、藩王国とウマール帝国との間での為政者たちの意識の差。ウマール帝国と藩王国との存亡はこの虫害への対処の仕方にかかってくる。
ストーリーの進展とともに、ウマール帝国と藩王国の体制や情勢のイメージが形成され、香君オリエ、藩王国視察官マシュウ、富国ノ大臣イール、大香司ラーオ、そしてこのストーリーの主人公アイシャの人物像のイメージが形成され、ストーリーに引きこまれていく。ストーリーの最終ステージの山場は、涙なくして読めないのではないかと感じる。香君オリエとアイシャの立場と彼らの行動にまさに感情移入して読んでしまった。
最後に、印象深い箇所をご紹介しておきたい。
*ここに来るたびに、思うの。多くの他者が互いに手を差し伸べあっていることの意味を。弱い者を見放さず、手を差し伸べることが、何を守るのかを。 ⇒オリエの言 上p229
*表情をあらため、真剣な眼差しで、自分がこう感じるから、他の人も同じように感じるだろうと思ってはいけない、そう思ってしまったとき隙が生まれる、と言っていたマシュウの顔が目に浮かんだ。 ⇒アイシャの思い 下p41
*生き延びるという、最も大切なことを行うときにすら、人という生き物は様々な思惑にとらわれ、戸惑い、決断するまでに時間がかかる。危機感を共有することすら難しい。
⇒アイシャの思い 下p226
*生き物は、どんな存在に生まれるか、選ぶことはできない。望む力を持って生まれてくるわけでもない。それでも、それぞれが己の持つ力を活かし、あるときは他者を助け、あるときは他者を害して生きていく。
そういう関係が絶えず動き続ける網の目のようにこの世を覆っていて、ちっぽけな虫ですら、それぞれの役割を背負い、その網の目をつくっている。どんな小さな者も己の役割を担って生きている。 ⇒オリエの言 下p318
*権威というのは、・・・互いの関係で成り立つ。幻想だ。幻想だが、いったん身に沁み込んでしまえば、反射的に心身が反応するし、多くの人が同時に抱けば、現実の力となる。
⇒マシュウの言 下p328
*香りで万象を知ることなんて、出来ません。初代の香君は、私などより、ずっとすごい人だったのかもしれないけれど、それでも香りで万象を知ることなんて出来たとは思えません。わからないことも、たくさんあったはずです。その、わからないことすら、わかったふりをして、その偽りを、神という幻想で隠して、これまで-ここまで、来てしまったことが、私には、とても怖いことに思えるんです。 ⇒アイシャの言 下p331
*人々が、神に頼るのではなく、オリエがつくった「場」の中で、自らの立場を再認識し、自らの意思で未来を選ぶ、そういう道をオリエはつくりたかったのだ。
⇒アイシャの思い 下p404
*知識さえあれば、辺境の農夫たちだって、自分たちの未来を、自分たちで救えたかもしれない。 ⇒アイシャの言 下p430
*どんな道にもそれぞれの難点がありますね。 ⇒アイシャの言 下p431
*<語ると、それが現れる>からですよ。 ⇒ユーマの言 下p441
*ひとつの稲に過度に依存することは、もちろん避けねばなりませんが、いまの我々が為すべきは、オアレ稲の排除ではなく、あの稲との共存なのでしょう。 ⇒ユーマの言 p448
人の我欲による行動と自然の生態系について、私たちに考えさせる小説だと思う。
このフィクションのファンタジーな世界は、現実の世界に対する鏡の役割を果たしているようにも思う。
ご一読ありがとうございます。
こちらもお読みいただけるとうれしいです。
[遊心逍遙記]に掲載
『鹿の王 水底の橋』 角川書店
『精霊の木』 偕成社
『鹿の王』 上・下 角川書店