私が入手したのは、1999年9月に刊行された文庫本、第1刷。
本書のタイトルには「文庫版」という語句が冠されている。本作の後のページを見て、理由がわかった。『魍魎の匣』は1995年1月に講談社ノベルズとして刊行された。その後「文庫版として出版するにあたり、本分レイアウトに併せて加筆訂正がなされています」という変更による。しかし、「ストーリー等は変わっておりません」と記されている。「本分レイアウト」の語句は記載通りママで引用した。この文庫版からの読後印象を記す。
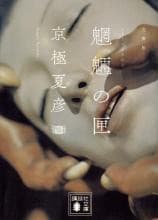
調べてみると、現在の文庫版はこの表紙に切り替わっている。
本書は『姑獲鳥の夏』に次ぐ京極堂シリーズ第2弾。30年前に出版された作品を今頃やっと読み終えた。文庫サイズで、作品本文の最終ページはなんと1048ページである。こんな分厚い小説のシリーズはこれくらいではないか。ノベルズでの購入本があるので、1冊の文庫としてこれだけの厚みの作品を読むのは初めて。第1作はノベルズで読んだ。文庫で上・下本に分冊されている他の作家の作品は数多くある。上・下巻合わせて600~800ページくらいのものが多いと思う。なので本の内容に入る前に、まずこのボリュームが驚きである。読み始めるには少し気合がいる。
「魑魅魍魎」という熟語がある。手元の『新明解国語辞典 第5版』(三省堂)を引くと、「魑魅」は「山の精。すだま」。「魍魎」は「古代人がその存在を信じていた、山・川や木・石の精」と説明してある。
本書の冒頭には、『今昔續百鬼・巻之下』に収載の魍魎の絵図が引用掲載され、その続きに、絵図に記載の文が載っている。「魍魎---形三歳の小児の如し、色は赤黒し、目赤く、耳長く、髪うるはし。このんで亡者の肝を食ふと云」と。こちらの方がより具象的な説明となっている。
いずれにしても、現代人の意識・感覚では乏しくなっている領域になる。自然界にリンクして想像力が生み出した神霊・悪霊の領域、そんな世界を作品の背景に重ねている。こわいもの見たさというムードを漂わせているところが読者の心理としておもしろさの根底にある。
「匣」は、「①はこ。こばこ。てばこ。②おり(檻)」と説明されている。(『角川新字源』)
ストーリーは、昭和27年時点の事件として扱われていく。「荒川バラバラ殺人事件が起きたのは今年---昭和27年の5月のことである」(p135)という記述からわかる。
冒頭に二人の少女が登場する。楠本頼子と柚木加菜子。同じクラスであり、加菜子が頼子に話しかけたことがきっかけで二人は友人となる。加菜子は頼子に「楠本君。君は私の、そして私は君の生まれ変わりなんだ」「私が死んで君になる。君が死んで私になるのさ。死んでしまえば時間なんて関係ない」(p22)という語りかけをする場面がある。また頼子は母との口論の中で「そんなの人間じゃなくて、お化けか、もうりょうです!」(p26)という言葉を母親からなげかけられる。冒頭から異界にリンクする接点が織り込まれている。巧みな伏線が敷かれていく。
頼子と加菜子は、夏休みの三度目の金曜日に、最終列車に乗って、どこか遠くの湖へ行く約束をした。だが、待ち合わせた駅、中央線武蔵小金井駅のホームで、加菜子は入って来た最終列車が止まる直前に転落し、瀕死の重傷を負う。この列車にたまたま東京警視庁捜査一課所属の木場刑事が乗り合わせていた。
木場は重症を負った少女の顔を見て、見覚えがあると感じた。そのこだわりが、木場を事件に巻き込んでいく。加菜子が応急処置を受けた病院から、母の柚木陽子は、懇意にしているという「美馬坂(ミマサカ)近代医学研究所」に加菜子を移す。木場は己の本務を棚上げし、上司すら無視して、この研究所に張り付き、この事件に対し単独行動をとるようになっていく。病院を移る時に、加菜子は全身ギブスだらけで身動きできない状態だった。
この研究所は、神奈川県に所在し、普通の病院とは全く異なり、四階建てくらいに見える完全な立方体の箱のような奇抜な建物だった。建物内部も、奇妙なところである。
なぜか、その加菜子の誘拐予告状が届いたということで、国家地方警察神奈川県本部から警部以下多数の警察官がこの研究所の警備に集まるという事態に進展する。木場は邪魔者扱いされる。
そんな最中で、身動きできないはずの加菜子が誘拐されたのだ・・・・・・。
この事件とはパラレルに、作家関口巽の行動が進展していく。関口は生活の為にカストリ雑誌の生き残り『月刊實録犯罪』に楚木逸巳のペンネームで寄稿している。その出版社・赤井書房の青年編集者鳥口守彦に頼まれる形で、取材活動に関口が巻き込まれる羽目になる。荒川バラバラ殺人事件の後、連続して直近でバラバラ殺人事件が発生していたからである。鳥口が運転するポンコツの車に同乗し、相模湖の現場まで出かけて行く。だが、その後、武蔵野連続バラバラ殺人事件が起こる展開となっていく。
車で相模湖へ向かう道中で、鳥口は関口に「穢封じ御筥様」というお祓い憑き物落としが流行っていると語った。悪霊とか憑き物を教祖が祈祷して箱の中に祈り封じ込めるというのだ。これが別途、サブ・ストーリーとして動き出す。
関口は連続バラバラ殺人事件と「穢封じ御筥様」に関わりを深めて行くことに・・・・。
さらに、もう一つの動きが加わる。増岡という弁護士が、榎木津礼二郎の探偵事務所に調査依頼を持ち込んでくる。誘拐された加菜子を探すという仕事である。加菜子には遺産相続問題が絡んでいたのだ。榎木津は木場と行動をともにする局面も生まれていく。
本作には、異質な独白的ストーリーがさらに断続的に挿入され、こちらも怪奇猟奇的点描として進展していく。祖母の葬儀のために休暇を取って郷里に向かう男は、匣を持つ男と乗り合わせる。その男から匣の中に日本人形のような綺麗な娘の顔、胸から上がぴったり入っているのを見せられる。帰郷途中の男はその匣に魅了されてしまう。別れた後に、その男はその匣が欲しくなっていく。幻想的ですらある点描が続く。
それぞれ異なる観点で活動している主な登場人物が出そろってくる。木場、関口、榎木津。彼らは順次、己の疑問を抱え、古本屋の京極堂を訪ねることになる。中禅寺秋彦は彼らの持ち込んできた情報と状況をじっくりと聴くことから、関りを深めていく。
これがどうもこの京極堂シリーズの一パターンになりそうな気がする。
紆余曲折し、複雑に絡みあった情報を、陰陽師でもあり、様々な領域の知識・造詣のある中禅寺秋彦が、情報を整理・分析し、状況を明解にしていく。自らも必要であれば事実を解明するために現場に乗り出していくことを厭わない。
読者をあちらこちらに振り回すストーリーの流れ、その構成がまずおもしろい。
混沌とした情報群の間で、徐々にそれぞれの相互関係が見いだされていく。その関係性が思わぬ大きな絵を描いていく形となる。この作品の面白さはここにある。
このストーリーで興味深いことの一つは、中禅寺秋彦が美馬坂を知人として熟知していたという設定である。それは最終段階で初めて明かされる事実なのだが・・・・・。ここで、この点に触れておいても、関心が高まるだけで、本作を読むにあたって特に影響はないだろうと思う。
本作のおもしろい点としてハコづくしの趣向が組み込まれていることに触れておこう。・列車に乗り合わせた男がもつ匣
・バラバラにされた体の一部を入れたハコ
・美馬坂(ミマサカ)近代医学研究所のハコ形の奇抜な建物
・穢封じ御筥様が悪霊・憑き物を封じ込める箱
・<箱屋>と呼ばれるようになった木工製作所
・風呂屋に預けてあった桐の箱。京極堂は福来友吉助教授の忘れた箱という。
・木場が事件に関わる中で、刑事である己の存在を菓子の空き箱みたいだと感じる
・関口が稀譚舎という出版社で紹介された若手幻想文学界の旗手・久保竣公の部屋の箱
・「怖気づいた。これは開けてはならぬ。穏秘(オカルト)の匣だ」 p1005
・「私は何もかも心の匣に仕舞い込んで、蓋をして、目を瞑って耳を塞いで生きて、
それが幸せだろうと思えるようになった」 p1006
そして、重要なもう一つの箱について、京極堂が語る箇所がある。それは本作を読んでのお楽しみにとっておこう。
1027ページ に、「私は、魍魎の匣だ」という一文が出て来る。本作のタイトルはここに由来する。
最後に、この小説から興味深い記述箇所をいくつか抽出して、ご紹介しよう。
*事件は、人と人----多くの現実----の関わりから生まれる物語だ。
ならば、物語の筋書きーーーー事件の真相----もまた、関わった人の数だけあるのだ。
真実はひとつと云うのはまやかしに過ぎぬ。事件の真相などそれを取り巻く人間達が便宜的に作り出した最大公約数のまやかしに過ぎない。 p579
*動機とは世間を納得させるためにあるだけのものにすぎない。
世間の人間は、犯罪者は特殊な環境の中でこそ、特殊な精神状態でこそ、その非道な行いをなし得たのだと、何としても思いたいのだ。 p717
*事実関係に関する供述は兎も角、自白に証拠性などないと僕は思うがね。
動機は後から訊かれて考えるものなんだ。 p719
*「犯罪はね、常に訪れて、去って行く通り物みたいなものなんだ」
通り物といのは妖怪の名である。通り魔と云うのもそもそもその類の妖怪のことだと、京極堂は云っていた。
p721
*犯罪は、社会条件と環境条件と、そして通り物みたいな狂おしい瞬間の心の振幅で成立するんだよ。
p834
*中身ではなく、外側が決めることも多いのだ。
箱は、箱自身に存在価値があったのだ。 木場の自己認識として p864
*京極堂の云う通り、科学とは何も入っていない箱だ。それ自体にどんな価値を見出すのかは、それを用い、使う者次第なのだ。 p959
*いずれにしても関口君。魍魎は境界的(マージナル)なモノなんだ。だからどこにも属していない。そして下手に手を出すと惑わされる。 p1044
ご一読ありがとうございます。
本書のタイトルには「文庫版」という語句が冠されている。本作の後のページを見て、理由がわかった。『魍魎の匣』は1995年1月に講談社ノベルズとして刊行された。その後「文庫版として出版するにあたり、本分レイアウトに併せて加筆訂正がなされています」という変更による。しかし、「ストーリー等は変わっておりません」と記されている。「本分レイアウト」の語句は記載通りママで引用した。この文庫版からの読後印象を記す。
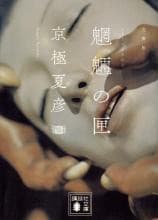
調べてみると、現在の文庫版はこの表紙に切り替わっている。
本書は『姑獲鳥の夏』に次ぐ京極堂シリーズ第2弾。30年前に出版された作品を今頃やっと読み終えた。文庫サイズで、作品本文の最終ページはなんと1048ページである。こんな分厚い小説のシリーズはこれくらいではないか。ノベルズでの購入本があるので、1冊の文庫としてこれだけの厚みの作品を読むのは初めて。第1作はノベルズで読んだ。文庫で上・下本に分冊されている他の作家の作品は数多くある。上・下巻合わせて600~800ページくらいのものが多いと思う。なので本の内容に入る前に、まずこのボリュームが驚きである。読み始めるには少し気合がいる。
「魑魅魍魎」という熟語がある。手元の『新明解国語辞典 第5版』(三省堂)を引くと、「魑魅」は「山の精。すだま」。「魍魎」は「古代人がその存在を信じていた、山・川や木・石の精」と説明してある。
本書の冒頭には、『今昔續百鬼・巻之下』に収載の魍魎の絵図が引用掲載され、その続きに、絵図に記載の文が載っている。「魍魎---形三歳の小児の如し、色は赤黒し、目赤く、耳長く、髪うるはし。このんで亡者の肝を食ふと云」と。こちらの方がより具象的な説明となっている。
いずれにしても、現代人の意識・感覚では乏しくなっている領域になる。自然界にリンクして想像力が生み出した神霊・悪霊の領域、そんな世界を作品の背景に重ねている。こわいもの見たさというムードを漂わせているところが読者の心理としておもしろさの根底にある。
「匣」は、「①はこ。こばこ。てばこ。②おり(檻)」と説明されている。(『角川新字源』)
ストーリーは、昭和27年時点の事件として扱われていく。「荒川バラバラ殺人事件が起きたのは今年---昭和27年の5月のことである」(p135)という記述からわかる。
冒頭に二人の少女が登場する。楠本頼子と柚木加菜子。同じクラスであり、加菜子が頼子に話しかけたことがきっかけで二人は友人となる。加菜子は頼子に「楠本君。君は私の、そして私は君の生まれ変わりなんだ」「私が死んで君になる。君が死んで私になるのさ。死んでしまえば時間なんて関係ない」(p22)という語りかけをする場面がある。また頼子は母との口論の中で「そんなの人間じゃなくて、お化けか、もうりょうです!」(p26)という言葉を母親からなげかけられる。冒頭から異界にリンクする接点が織り込まれている。巧みな伏線が敷かれていく。
頼子と加菜子は、夏休みの三度目の金曜日に、最終列車に乗って、どこか遠くの湖へ行く約束をした。だが、待ち合わせた駅、中央線武蔵小金井駅のホームで、加菜子は入って来た最終列車が止まる直前に転落し、瀕死の重傷を負う。この列車にたまたま東京警視庁捜査一課所属の木場刑事が乗り合わせていた。
木場は重症を負った少女の顔を見て、見覚えがあると感じた。そのこだわりが、木場を事件に巻き込んでいく。加菜子が応急処置を受けた病院から、母の柚木陽子は、懇意にしているという「美馬坂(ミマサカ)近代医学研究所」に加菜子を移す。木場は己の本務を棚上げし、上司すら無視して、この研究所に張り付き、この事件に対し単独行動をとるようになっていく。病院を移る時に、加菜子は全身ギブスだらけで身動きできない状態だった。
この研究所は、神奈川県に所在し、普通の病院とは全く異なり、四階建てくらいに見える完全な立方体の箱のような奇抜な建物だった。建物内部も、奇妙なところである。
なぜか、その加菜子の誘拐予告状が届いたということで、国家地方警察神奈川県本部から警部以下多数の警察官がこの研究所の警備に集まるという事態に進展する。木場は邪魔者扱いされる。
そんな最中で、身動きできないはずの加菜子が誘拐されたのだ・・・・・・。
この事件とはパラレルに、作家関口巽の行動が進展していく。関口は生活の為にカストリ雑誌の生き残り『月刊實録犯罪』に楚木逸巳のペンネームで寄稿している。その出版社・赤井書房の青年編集者鳥口守彦に頼まれる形で、取材活動に関口が巻き込まれる羽目になる。荒川バラバラ殺人事件の後、連続して直近でバラバラ殺人事件が発生していたからである。鳥口が運転するポンコツの車に同乗し、相模湖の現場まで出かけて行く。だが、その後、武蔵野連続バラバラ殺人事件が起こる展開となっていく。
車で相模湖へ向かう道中で、鳥口は関口に「穢封じ御筥様」というお祓い憑き物落としが流行っていると語った。悪霊とか憑き物を教祖が祈祷して箱の中に祈り封じ込めるというのだ。これが別途、サブ・ストーリーとして動き出す。
関口は連続バラバラ殺人事件と「穢封じ御筥様」に関わりを深めて行くことに・・・・。
さらに、もう一つの動きが加わる。増岡という弁護士が、榎木津礼二郎の探偵事務所に調査依頼を持ち込んでくる。誘拐された加菜子を探すという仕事である。加菜子には遺産相続問題が絡んでいたのだ。榎木津は木場と行動をともにする局面も生まれていく。
本作には、異質な独白的ストーリーがさらに断続的に挿入され、こちらも怪奇猟奇的点描として進展していく。祖母の葬儀のために休暇を取って郷里に向かう男は、匣を持つ男と乗り合わせる。その男から匣の中に日本人形のような綺麗な娘の顔、胸から上がぴったり入っているのを見せられる。帰郷途中の男はその匣に魅了されてしまう。別れた後に、その男はその匣が欲しくなっていく。幻想的ですらある点描が続く。
それぞれ異なる観点で活動している主な登場人物が出そろってくる。木場、関口、榎木津。彼らは順次、己の疑問を抱え、古本屋の京極堂を訪ねることになる。中禅寺秋彦は彼らの持ち込んできた情報と状況をじっくりと聴くことから、関りを深めていく。
これがどうもこの京極堂シリーズの一パターンになりそうな気がする。
紆余曲折し、複雑に絡みあった情報を、陰陽師でもあり、様々な領域の知識・造詣のある中禅寺秋彦が、情報を整理・分析し、状況を明解にしていく。自らも必要であれば事実を解明するために現場に乗り出していくことを厭わない。
読者をあちらこちらに振り回すストーリーの流れ、その構成がまずおもしろい。
混沌とした情報群の間で、徐々にそれぞれの相互関係が見いだされていく。その関係性が思わぬ大きな絵を描いていく形となる。この作品の面白さはここにある。
このストーリーで興味深いことの一つは、中禅寺秋彦が美馬坂を知人として熟知していたという設定である。それは最終段階で初めて明かされる事実なのだが・・・・・。ここで、この点に触れておいても、関心が高まるだけで、本作を読むにあたって特に影響はないだろうと思う。
本作のおもしろい点としてハコづくしの趣向が組み込まれていることに触れておこう。・列車に乗り合わせた男がもつ匣
・バラバラにされた体の一部を入れたハコ
・美馬坂(ミマサカ)近代医学研究所のハコ形の奇抜な建物
・穢封じ御筥様が悪霊・憑き物を封じ込める箱
・<箱屋>と呼ばれるようになった木工製作所
・風呂屋に預けてあった桐の箱。京極堂は福来友吉助教授の忘れた箱という。
・木場が事件に関わる中で、刑事である己の存在を菓子の空き箱みたいだと感じる
・関口が稀譚舎という出版社で紹介された若手幻想文学界の旗手・久保竣公の部屋の箱
・「怖気づいた。これは開けてはならぬ。穏秘(オカルト)の匣だ」 p1005
・「私は何もかも心の匣に仕舞い込んで、蓋をして、目を瞑って耳を塞いで生きて、
それが幸せだろうと思えるようになった」 p1006
そして、重要なもう一つの箱について、京極堂が語る箇所がある。それは本作を読んでのお楽しみにとっておこう。
1027ページ に、「私は、魍魎の匣だ」という一文が出て来る。本作のタイトルはここに由来する。
最後に、この小説から興味深い記述箇所をいくつか抽出して、ご紹介しよう。
*事件は、人と人----多くの現実----の関わりから生まれる物語だ。
ならば、物語の筋書きーーーー事件の真相----もまた、関わった人の数だけあるのだ。
真実はひとつと云うのはまやかしに過ぎぬ。事件の真相などそれを取り巻く人間達が便宜的に作り出した最大公約数のまやかしに過ぎない。 p579
*動機とは世間を納得させるためにあるだけのものにすぎない。
世間の人間は、犯罪者は特殊な環境の中でこそ、特殊な精神状態でこそ、その非道な行いをなし得たのだと、何としても思いたいのだ。 p717
*事実関係に関する供述は兎も角、自白に証拠性などないと僕は思うがね。
動機は後から訊かれて考えるものなんだ。 p719
*「犯罪はね、常に訪れて、去って行く通り物みたいなものなんだ」
通り物といのは妖怪の名である。通り魔と云うのもそもそもその類の妖怪のことだと、京極堂は云っていた。
p721
*犯罪は、社会条件と環境条件と、そして通り物みたいな狂おしい瞬間の心の振幅で成立するんだよ。
p834
*中身ではなく、外側が決めることも多いのだ。
箱は、箱自身に存在価値があったのだ。 木場の自己認識として p864
*京極堂の云う通り、科学とは何も入っていない箱だ。それ自体にどんな価値を見出すのかは、それを用い、使う者次第なのだ。 p959
*いずれにしても関口君。魍魎は境界的(マージナル)なモノなんだ。だからどこにも属していない。そして下手に手を出すと惑わされる。 p1044
ご一読ありがとうございます。













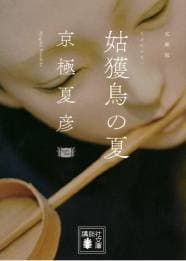 こちらは現在の新刊カバーの表紙である。
こちらは現在の新刊カバーの表紙である。
