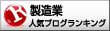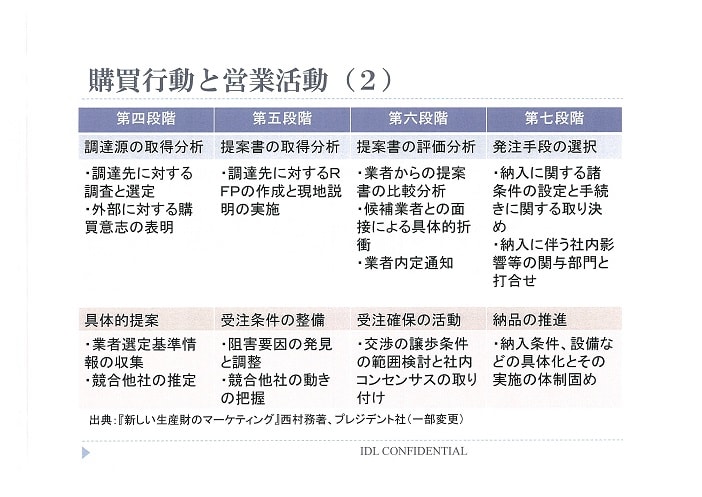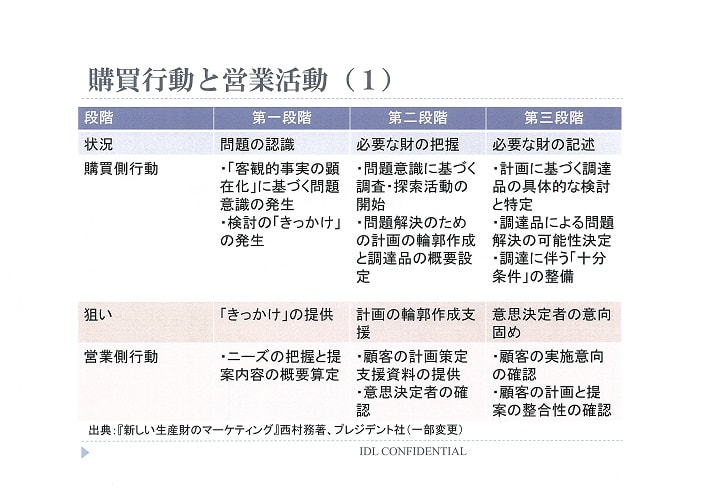顧客はサプライヤーを2~3社に絞り込み、仕様等を公開し、見積依頼(RFQ:Request For Quotation)や提案の依頼(RFP:Request For Proposal)をします。会社(役所)の規則で一定金額以上の案件は、3社見積もり必須というところが多いかと思います。
RFQ、RFPの説明会を行う場合もあります。私の経験では、各サプライヤーが個別に呼ばれ説明を受け、質疑応答を行う形式がほとんどでした。
米国大使館の入札の場合は、ホームページ上で入札説明会の案内が行われ、申し込んだサプライヤーを一堂に集めた説明会・現場調査が実施されました。質疑応答は行わず、質問は決められた日時までにメールで提出。回答はすべてのサプライヤーからの質問を整理してホームページに掲載されます。前回の入札価格について質問しても回答してくれませんが、前回の落札時に落札者名とともにホームページに掲載されているので、調べれば出てきます(データベースが大きすぎて私は調べきれませんでした)。
営業はRFQ、RFPの内容を精査し、提出書類の種類と内容、提出期限、サプライヤー選定基準などを確認します。一般的に提出書類には会社の財務諸表、会社の組織、対応チームのスキル・資格、品質管理体制など多岐に亘るため、社内の関係者を集めて説明会を行い、手分けして進めることが肝要です。
また、阻害要因がないか確認します。例えば、自社の製品では実現できない機能はないかチェックします。逆に言うと、第三段階までにインサプライヤーとして活動してきた営業は、他社にない機能などを仕様書に盛り込むように顧客を誘導し、自社の優位性を確立します。
実際に資料を作成し始めると、不明な点がでてきます。改めて質問できる場合もありますが、追加質問を許さない場合もあります。実際、現場調査を一回行っただけでは十分な情報は、得られません。このため現行のサプライヤーがいる場合は、彼らが有利になります。特に、顧客が現状のサプライヤーを気に入っているが、会社(役所)の規則でRFPを実施しなえればならない場合は、他のサプライヤーが落札するのは困難です。
以前、大阪のある役所の設備管理の業務を新規受注したことがありました。当該役所と長期間契約していたサプライヤーを価格差でひっくり返した例です。選ばざるを得ないくらいに価格差のあった例で、役所の担当者からは、「おたくが安すぎる値段を出したからこんなことになった。」といまだに文句を言われています。
また、現在、私は見積もりをお願いする立場にありますが、本当に真剣にサプライヤーを一から選びたい場合は別として、会社の仕組み上の理由で3社見積もりをする場合は、「それとなく」その旨、知らせてサプライヤーが無駄な労力を使わないように調整します。
また、「5段階、価格交渉をする。最後は社長が交渉」「50%以上値下げさせる」などのルールがある顧客もあるので予め聞き出しておきましょう。
RFQ、RFPの説明会を行う場合もあります。私の経験では、各サプライヤーが個別に呼ばれ説明を受け、質疑応答を行う形式がほとんどでした。
米国大使館の入札の場合は、ホームページ上で入札説明会の案内が行われ、申し込んだサプライヤーを一堂に集めた説明会・現場調査が実施されました。質疑応答は行わず、質問は決められた日時までにメールで提出。回答はすべてのサプライヤーからの質問を整理してホームページに掲載されます。前回の入札価格について質問しても回答してくれませんが、前回の落札時に落札者名とともにホームページに掲載されているので、調べれば出てきます(データベースが大きすぎて私は調べきれませんでした)。
営業はRFQ、RFPの内容を精査し、提出書類の種類と内容、提出期限、サプライヤー選定基準などを確認します。一般的に提出書類には会社の財務諸表、会社の組織、対応チームのスキル・資格、品質管理体制など多岐に亘るため、社内の関係者を集めて説明会を行い、手分けして進めることが肝要です。
また、阻害要因がないか確認します。例えば、自社の製品では実現できない機能はないかチェックします。逆に言うと、第三段階までにインサプライヤーとして活動してきた営業は、他社にない機能などを仕様書に盛り込むように顧客を誘導し、自社の優位性を確立します。
実際に資料を作成し始めると、不明な点がでてきます。改めて質問できる場合もありますが、追加質問を許さない場合もあります。実際、現場調査を一回行っただけでは十分な情報は、得られません。このため現行のサプライヤーがいる場合は、彼らが有利になります。特に、顧客が現状のサプライヤーを気に入っているが、会社(役所)の規則でRFPを実施しなえればならない場合は、他のサプライヤーが落札するのは困難です。
以前、大阪のある役所の設備管理の業務を新規受注したことがありました。当該役所と長期間契約していたサプライヤーを価格差でひっくり返した例です。選ばざるを得ないくらいに価格差のあった例で、役所の担当者からは、「おたくが安すぎる値段を出したからこんなことになった。」といまだに文句を言われています。
また、現在、私は見積もりをお願いする立場にありますが、本当に真剣にサプライヤーを一から選びたい場合は別として、会社の仕組み上の理由で3社見積もりをする場合は、「それとなく」その旨、知らせてサプライヤーが無駄な労力を使わないように調整します。
また、「5段階、価格交渉をする。最後は社長が交渉」「50%以上値下げさせる」などのルールがある顧客もあるので予め聞き出しておきましょう。