
 | サイコパス (文春新書) |
| クリエーター情報なし | |
| 文藝春秋 |
中村公園では梅が咲き始めていました。まだまだ寒い日は続きますが春は着実に近づいているようです。
とんでもない犯罪を平然と遂行する。ウソがバレても、むしろ自分の方が被害者であるかのようにふるまう…。脳科学の急速な進歩により、そんなサイコパスの脳の謎が徐々に明らかになってきており新書でヒットとなったのがこの本。実際サイコパスは日本人としても120万人程度いるそうで100人に一人の割合です。そういわれると結構多いようにも感じます。
サイコパスの心理的、身体的特徴としてはテストステロンの多さや心拍数の低さ、不安感情の低さ、共感性の乏しさ、感情が表情に表れない等々があります。彼らは飴と鞭を悪用することで相手との上下関係を完成させる一方で道徳性を重んじることもあり。それは根本的なものではなく自身の生存戦略として合理的だからとのこと。また自分の損得と関係のない人には関心を持たない。周囲が自分の敵意を持っていると認識しているので、他人に敵意をもって対抗する、他人と絆を結べないだけでなく、自分自身との関係も希薄といった特徴があるようです。 あのスティーブジョブスもサイコパスだったとの話も…
もともと人間は捕食の関係からすれば自然界の中でそれほど強くない存在でもあったのにもかかわらず生き残れたのはその頭脳という面だけでなく集団で協力し合うというのがベースにあったと考えると集団をコバンザメのようにするサイコパスの存在は遺伝子的には淘汰されても良いはずでした。特に日本は自然災害も多く、四季の変化もあるため食べ物もさほど豊かではない環境であったはずで集団での協力はより強固なものが求められたはずです。にもかかわらずサイコパスが今日まで生き残っているのは、進化心理学的にはそれが生存に有利だからというのが本書の説明で恐怖を知らないがゆえに先頭に立って開拓出来たり普通の人の神経ではできない危険な仕事(戦争なんかは良い例)を担当して来たいというわけである意味、歴史の進行はサイコパスに支えられていたのかもしれません。また生殖活動や生存競争においても女性がサイコパスに引き寄せられる可能性も高く、遺伝子が保存されることは当然の成り行きのようです。ただ非サイコパスの大多数にとって日常的には迷惑をこうむることが多いのが実情でしょう。
サイコパスとどう向き合って行くのかというのが本書の最終章にあり、サイコパスには向いた職業についてもらおうというのが提案です。たとえば小説家、外科医、ジャーナリストなどある意味人としてはプレッシャーのかかる領域で働いてもらうというのは一つの手のようです。ある程度は遺伝が大きそうなのですが実際に発現するかどうかは生活環境がきいているとの指摘です。










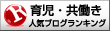

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます