A.姫路城とその周辺
最近ちょっとした「お城ブーム」らしくて、日本の城めぐりとかお城博覧会とかに人が集ったり(もちろんコロナ前の話)、城郭本とか城特集の雑誌とかが本屋に並んでいる。ぼくは、何を隠そう小学生の時からの城マニアで、城と名のつく本や写真集はみな集め、石垣の写真を見ただけでそれがどこの城かを当てられるほど半世紀以上のめりこんでいる。大人になってからは、外国も含め全国どこへ行ってもそこに城跡があれば必ず歩き、縄張り図を書いていた。今でこそ、さまざまな城情報は簡単に手に入るが、インターネットなどない昔はそれなりに現地まで行かないと分からないことが多く、であればこそそれぞれの城跡を歩けば発見があり、自分だけの密かで大きな愉しみである。長い間この趣味は、誰かに話しても?と変な顔をされるだけで興味をもつ人にはほとんど会ったことがなく、人畜無害で不要不急、それだけに単なる観光絵葉書程度のもので大方の興味は惹かないものだと思っていた。

それで先日、書斎でふと書棚の上の方に「城とその周辺」というシリーズ本が7冊積んであり、隣には『日本城郭史』(大類伸・鳥羽正雄著、雄山閣)という分厚い学術書があることに気がついた。「その周辺」シリーズは日本城郭協会編となっていて1960・61年の刊行、「日本城郭史」の方は唯一の本格的な歴史研究の学術書だが、原著発行が昭和11年、ぼくの持っている上製本が昭和35年重版発行、定価二千円。つまり1960年に出ている当時としてはかなり高価な本を、ぼくは高校生くらいの時に買っている。そんな昔のことはよく思い出せないが、中にある写真はみな記憶の底にあるので、ぼくはかなり熱心にこれを読んでいたはずだ。そういえば、この日本城郭協会というのは井上宗和という写真家が中心になっていて、その出版部の住所は東京都豊島区池袋三の一六三〇とあって、ぼくの住んでいた場所のすぐ近く、立教大学のあたりなのだった。ぼくがそもそも城好きになったきっかけは、小学校6年生のとき担任教師が、この井上宗和氏が各地の城の写真を解説付きで著した『日本の城』という本を、これ面白いぞと教室に持ってきたことに始まる。
日本城郭協会を訪ねようと何度も思ったけれど、まだ中学生だったぼくは相手にされないだろうと思って行けなかった。そして約半世紀、これらの本は書棚の隅で埃をかぶっていた。コロナ禍で時間がたっぷりあり、久々に手に取ってみたら、そのモノクロ写真に写る城の背景の形式や人が、遠い過去になっており、そこに添えられた文章も今となっては歴史の方にしまわれていることに気づいた。『姫路城とその周辺』を見ると、「周辺」と言っているのは、姫路のあたりではなく、竜野城、三木城、竹田城、洲本城など兵庫県あたりの城という意味だが、同範囲の明石城、赤穂城などは抜けているし(たぶん井上氏が撮った写真がなかったのだろう)、本文も旧藩主の子孫や作家の文章があったり、歴史随筆もあり、他方で年表や系図が載っていたり、やや散漫な印象だ。
1960年当時、城郭研究は西洋史の大家・東北大名誉教授大類先生と、林業史研究もやっていた東洋大学の鳥羽正雄教授、それに建築史家で東工大の藤岡通夫教授が必ず名前の出てくる三大巨頭だったが、この「周辺」シリーズもこの3人が監修しているというものの、あまり学術的でない。今回、読んでみてまったく別の視点で興味を感じた。それは近世城郭と日本陸軍との結びつきということで、戦国時代や江戸時代の話ばかりのお城ブームではまったく出てこない話題である。きっかけは『姫路城とその周辺』に載っていた作家山田風太郎の次の文章である。
「姫路城の想い出 山田風太郎
昭和十八年三月に私の見た姫路城は、悪夢の中の幻影のように美しく、そして恐ろしい姿であった。その一か月前、私はひどい熱を出し、肋膜炎と診断され、ようやく床の上に起きあがれるようになったころ、召集令状をうけ、姫路の部隊に入営を命じられたのである。身体検査の結果、むろん即日帰郷組に入れられたが、城のすぐ下にある広い練兵場は、青い国民服をきた若者の海となり、このなかに即日帰郷組だけ、悄然と肩身せまくひとかたまりになっていた。入営組はみな誇らかに顔をかがやかしていた。その後彼らのうちのどれくらいが生きてかえったであろうか。運命の岐路である。
しかし、そのときは、私は死神からはねのけられたという意識はなかった。私たちをみて、「可哀そうだな、可哀そうだな」と、心からきのどくそうにつぶやいていた入営組の若者の声は、いまも耳にのこっている。肋膜の痛みよりも、恥の痛みが胸にうずいた。練兵場では、一台の砲に五六人の兵隊がかかって、号令のたびに電流にかかったようにはねあがり、とびつき、砲撃訓練をしていた。「けえれーっ」という絶叫がひびくと、それらの兵はもとより、練兵場にいた召集の若者たちも、ばねのようにみな起立敬礼した。騎馬の聯隊長が威風堂々とやってきたのである。敬礼しないのは、地面に座って、うすぼんやりと大砲をみていた私と、やはり即日帰郷組の白痴の若者だけだった。
夕日の中に、城の天守閣は寂然と赤くもえて、その光景を見下ろしていた。即日帰郷ということのみならず、そのころすべて八方ふさがりのどん底にあった私には、それは夢魔のように恐ろしく、また美しくみえた。そのころ城に上がることがゆるされていたかどうかわからないが、私は城にのぼる気力もなく、浮浪者のように姫路を離れた。
昭和二十八年五月、私は再びこの城を訪れた。ちょうど十年後である。私は一応世に出ていた。そして私は新婚の妻を同伴していた。練兵場には、何か町の祭りがあったらしく、装飾店やらサーカスの天幕などが残って、どこやらからまだジンタの音がながれて来そうであった。平和と幸福の陽光は、あたりの風物にも私の心にもあふれていた。十年前、陰惨きわまる心でこの練兵場を去ったことを思い出すと、私はやはり私なりの感慨にふけらずにはいられなかった。城は春の空にその名の白鷺のように羽搏きそうにみえた。
城にのぼったが、内部は暗く、梯子段は急で、また歳月にへりもまるみ、五層まで昇ったら、筋肉的労力のみならず神経的労力にへとへとになったが、その後まもなく修理にかかり、八年かかってまだ完成しないというこの城の、改修後の内部状態はどうなるのであろうか。不便ではあっても、やはり大阪城みたいにエレベーターなどつけなければいいがと思う。
しかし、外見はたしかに美しい。いったいこの城にかぎらず、ほかの城でも、神社仏閣また一般の民衆でもそうだが、日本建築の屋根や甍の美しさというものは、世界でも一流の芸術美を主張していいのではあるまいか。それからまた、城、甲冑、刀剣、このような戦争のための建築や道具をたちまち芸術品にかえてしまう日本人の心性も特別のものだと思う。
なかでも、この城が、現存する城のうちでは日本一美しいことはまちがいあるまい。千姫の化粧櫓という一劃が残っているように、千姫がかつてここに住んだ、千姫を主人公とした小説は二三にとどまらないが、千姫をいわゆる「吉田御殿」の主人公として淫婦妖婦あつかいにした作品は、あとを断ったのではないか。悲劇の美姫として彼女をえがくのに、この城の白鷺のような清麗さと優婉さは、作家によい影響をあたえずにはおかないと思う。
千姫以前に、黒田官兵衛、羽柴筑前という二大英雄を城主としながら、この城をめぐる攻防の戦争というものがなかったのも姫路城の幸福であった。そのうえ、明治の版籍奉還後の鉄槌を受けず、その後の盲目的な旧物破壊の風潮ものがれ、さらに空襲さえもまぬがれたということは、この美女のごとき城を、天人ともに惜しんだからであろうと思う。 (作家)」日本城郭協会編『姫路城とその周辺』1961年、pp44-45.
小説家山田 風太郎(1922年〈大正11年〉1月4日 - 2001年〈平成13年〉7月28日)の本名は山田 誠也。兵庫県養父郡関宮村に生まれ、豊岡中学卒業後、旧制高校を受験するも2年浪人、20歳で徴兵検査を受け肋膜炎で丙種合格の徴兵免除。東京へ出て品川区の沖電気に勤めながら受験勉強。昭和19年、22歳で東京医専(現東京医科大)入学。昭和25年、28歳で医専卒業、医学博士になるも医者にはならず、推理小説作家となる。伝奇小説、推理小説、時代小説の3分野で名を馳せた、戦後日本を代表する娯楽小説家の一人で、『魔界転生』や忍法帖シリーズに代表される、奇想天外なアイデアを用いた大衆小説で知られている。『南総里見八犬伝』や『水滸伝』をはじめとした古典伝奇文学に造詣が深く、それらを咀嚼・再構成して独自の視点を加えた作品を多数執筆した。
ぼくは、1990年代パーキンソン病にかかったこの人が自身を見つめたエッセイ『あと千回の晩飯』を新聞紙上で愛読していた。 2001年7月28日、肺炎のため東京都多摩市の病院で死去。79歳。兵庫に本籍のあった山田さんは、徴兵検査をこの姫路城にあった陸軍歩兵連隊で受けたときの思い出をここに書いている。
姫路城は世界遺産の歴史的木造建築の金字塔として、世界的に知られているが、今残っている城が築造されたのは慶長五(1600)年、関ヶ原で勲功のあった三河吉田城主池田輝政が52万1500石で姫路に封じられてからである。完成まで九年ほどを要した大規模な城郭は、その後城主は交代したが明治維新後までほぼそのまま残り、戦災にも遭わずに残っているわけだ。だが、明治以降の姫路城について語られることはまずない。それは、日本中にあった城が明治の廃藩置県で廃城となり、多くは毀され、わずかに濠と石垣の一部を残すのみとなったのだが、やはり明治以降のことは忘れ去られて、戦後に世の中が落ち着き経済発展してから、天守閣などが観光施設のように復興したが、その間どうなっていたかは語られない。
ぼくも考えたことはなかったが、この山田風太郎さんの回顧文を読んで、ほうそうかと気がついた。姫路城が明治4年陸軍が全国に4つの鎮台を置き、大阪鎮台軍管区のもとにある聯隊のひとつが姫路城三の丸に置かれた。その後鎮台が師団制に変わっても、歩兵第39連隊と聯隊本部がここにあり「姫路聯隊」と呼ばれた。陸軍の聯隊(連隊)というのは、平時に兵隊と武器を備えた拠点に置かれた組織で、師団というのは聯隊を2つか3つ合わせた形で地域を分けて統括していた。陸軍兵士の徴集は都府県単位の本籍地が属する聯隊で行われたので、戦前の軍隊は出身地と強く結びついていた。聯隊は日清・日露戦争と軍備を拡大するたびに増えていくのだが、明治期にできた聯隊は2年半の兵役で入隊した兵士を訓練した。歩兵連隊は平時定員で3個大隊12個中隊からなり、中隊が130名くらい、聯隊長以下将校が70名くらいだから全部で1700名前後、それに軍馬14匹となっていた。つまり、日本軍が敗戦でなくなるまでの73年間、この姫路城の三の丸という平地には兵舎が並び、関連人員も含め2000人近い人間(ほとんど若い男性のみ)が暮らしていたのだ。今のような観光地などではなく、一般人は立ち入りできなかったはずだ。ただ、軍隊の需要に応える商店・旅館・飲食店・娯楽で姫路市は栄えたわけですね。
そう思って「お城周辺」シリーズの他のも見たら、大阪城、熊本城、金沢城、広島城などみな軍隊が置かれていたらしいことがわかった。ちょっと面白いので、この城と軍隊についてこのブログで何回かとりあげてみたい。

B.ダンスを踊る?
東京を中心にコロナ感染者数が一向に減らない。いやでも不安は高まるけれど、ではどうすればいいか、一向によくわからない。こればかりは自己決定・自己責任というには、あまりに事態が見えないし、情報が頼りない。
「ダンスをうまく踊る:週のはじめに考える 社説 2020.7.26
うまいことを言う人があるもので、コロナ禍への社会としての対応を二つの段階に分けて曰く、ハンマーとダンス(The Hammer and Dance)と。米国のライターがネット上で書いた記事から知られるようになった言葉だそうで、山中伸弥・京都大iPS細胞研究所長も自身のコロナ関連のサイトで紹介しています。
「ハンマー」の後が大事 : 「ハンマー」は、諸外国の都市封鎖、ロックダウンのような厳しい行動制限の段階。わが国の場合は木槌ぐらいかもしれませんが、先の緊急事態宣言下の休業要請・外出自粛の時期が当てはまるでしょう。対して、制限を緩めて、経済の回復と感染拡大防止をうまくバランスしながらやっていく時期が、「ダンス」というわけです。やっかいな疫病の動きに柔軟に合わせて動いていく、というイメージでしょうか。
日本人の特に年配者にとってはダンスは苦手科目のイメージがありますが、もし、自然の脅威との柔軟なつきあい方をそう呼ぶのなら、話は違ってきます。
俵屋宗達の『風神雷神図屏風』は、どこかで一度は目にしたことがあるという人が多いでしょう。
古来、この国に生きる人を悩ませてきた豪雨や台風など自然の脅威。それを表彰するキャラクターが風神、雷神です。しかし、宗達の両神は奇妙なことに、全然怖くない。にやけた、というか、愛嬌のある顔に描かれています。漫画家の黒鉄ヒロシさんに言わせれば、妙に親しみがあって、まるで落語の「熊さん、八つぁん」。
ただ怖がるのではなく、戦うというより受け入れて、ともに生きていく。そんな日本人の自然とのつきあい方が表れているのではないかー。それが、Eテレ『日曜美術館』の中で披歴した黒鉄さんの“謎解き”でした。
毛色は違いますが、コロナも自然の脅威といえば、自然の脅威かもしれません。
Go To トラブル? : 目下、人々は次第に日常を取り戻しつつも、一方で「三密」を避け、できるだけマスクを着け、こまめに手指消毒をしと、それなりに気をつけて暮らしています。いわば、みな、何とかうまくダンスを踊ろうとしているのです。
ですが、それを助ける情報を当局が十分に提供できているかというとそうでもない。
例えば、実際に起きた感染のパターンのようなものを示せないものでしょうか。既に三万人を超える感染例があるのですから、ある程度まで経路を追えて、こうして感染したと推定できるケースは少なくないはずです。 無論、感染者が特定されるような情報は不要です。Aさんは、すでに感染していた人と、こういう場所で、こんな位置関係、これほどの距離で、これぐらいの時間、こういう接触をした結果、感染したようだ、といった類型をマスク着用や換気の有無など含めて、なるべくたくさん、わかりやすく示してもらえないかと思うのです。
ダンスをうまく踊る、という点で、今、心配なのは国民より、むしろ政府の方です。
しばらく前、東京で始まった再度の感染拡大は周辺、さらには地方へと広がり、おさまる様子がありません。ところが、そのさなかに、政府は国民に旅行を促す「Go To トラベル」事業を始めてしまいました。
観光業などの急回復をはかるための施策であり、大打撃の業界を助けること自体異論はありませんが、問題は時期です。本来はコロナ終息後のはずが、いつのまにか今月の四連休前のスタートに決まりました。しかし、東京などでの感染者増で「延期」を求める声が各方面から澎湃と。にもかかわらず、政府は「東京発着除外」の一部修正で見切り発車してしまったのです。
この感染拡大局面で、求められるのは人の移動の抑制。なのに、むしろ移動を促す政策を、しかも多額の税金を投入して打つというのはやはり間尺に合わない。事業が感染を広げる「Go To トラブル」になりかねません。決めたことに固執する姿勢は、柔軟にコロナの動きに合わせていくダンスとはほど遠いものがあります。
緊張と解緊の連続 : 最近の感染者の急増ぶりを見ていると、ハンマーの絵が頭にちらつきますが、今のところ政府には緊急事態宣言の再発出の考えはないようです。経済や暮らしへの打撃が大きすぎるという判断でしょう。でも、日本ボールルームダンス連盟のサイトによると、ダンスという英語の語源はdeanteというラテン語であり、それ自体、「緊張と解禁の連続」の謂だといいます。ワクチン到来の時まで、時に締めときに緩め、上手にダンスを踊っていきたいものです。」東京新聞2020年7月26日朝刊5面、社説。
正直なところ、ぼくは2年前から山形県鶴岡市内にアトリエを借りていて、毎月五日か六日程通って絵を描いているのだが、3月に行ったきり緊急事態宣言で行かれなくなった。解除後の6月末に1回だけ新幹線に乗って行ってきたけれど、7月には自由に往復できるようになっていることを期待したが、残念ながら東京からの山形への移動は禁止ではないけれど、感染の危険があるということで自粛を求められる。山形の人たちの気持ちとしては、やはり怖いから控えてくれという状況になっている。さてどうしたものか。周藤大電気代も払わなければならないしなあ。個人的にも困っている。

















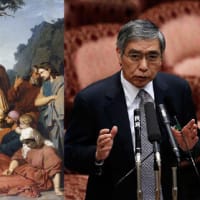








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます