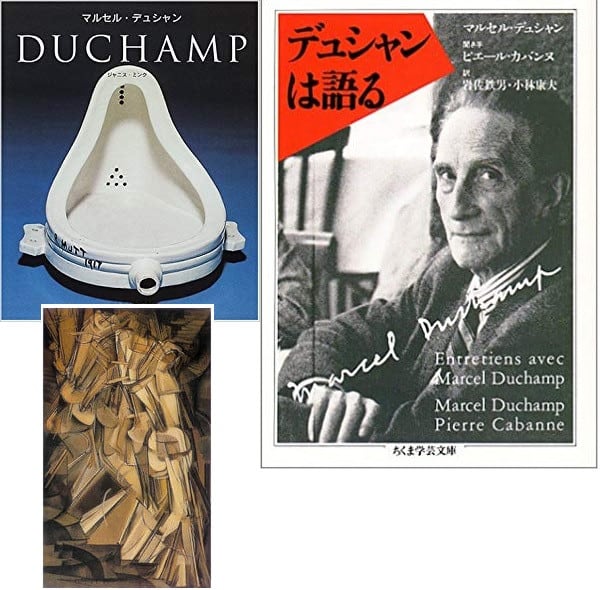A.具象対抽象という誤解
第2次大戦後、美術の中心がパリからニューヨークに移り、次々新しい潮流が現れることになるのだが、一般に「絵画」が風景や人物や静物などを題材に、その形象をキャンバスなどに描く写実的な「具象的」作品と、眼に見える形姿をそのままで描くのではなく、色や形を分解したり組み合わせたりする「抽象的」作品があるのだ、という二分法が定着する。「西欧絵画」の歴史をみてくると、この意味の「抽象的」作品が現れるのは、20世紀に入ってからだと考えられ、セザンヌやモネなどがその先駆と見られるようになるのも、キュビスムやダダイスムなどが出てきたからだろう。しかし、キュビスムやシュールレアリスムなどは、見たものをそのまま描くのをやめたが、現実にある形象を完全に離れた幾何学的な図像や無秩序な偶然によるようなものではないから「抽象的」といっても、「具象的」要素を含んでいた。そして、第2次大戦後に現れる、それ以前の「絵画」概念を塗り替えるような新しい「抽象主義」は、まずアメリカ人らしいアメリカ人、ジャクソン・ポロックからはじまる。「抽象表現主義」と呼ばれる作品は、かれがそう名付けたわけではない。
「「抽象表現主義」という用語を正当なものとするあらゆる真の根拠は、これらの画家たちの幾人かが、キュビスムおよびフランス的なものを一般に反発するようになった時に、ドイツやロシアやユダヤの表現主義に傾き始めたという事実に在る。しかしそれでも、彼らの全てがフランス美術から出発し、フランス美術から様式に対する己の直感を得たことに変わりはない。また、彼ら全てが優れた野心ある芸術とはどのような感触のものでなければならないかについてのもっとも鮮明な概念を得たのもフランス人からである。
これらの若いアメリカ人たちが共有したと思われる最初の問題は、三人の主要なキュビスト――ピカソ、ブラック、レジェ――が総合的キュビスムの終り以来固守してきた、比較的限定された浅い奥行きのイリュージョンを緩めることだった。彼らはまた、自分たちの言わなければならないことを言えるようにしたければ、先行する抽象芸術の殆ど全てにキュビスムが課していた、ドローイングやデザインにおける直線的または曲線的な規則正しさについての規範を緩めなければならなかった。これらの問題は、計画に従って取り組まれたのではない。「抽象表現主義」には計画的なものは皆無に等しく、またこれまでもそうであった。個々の芸術家たちは「声明」は発したかもしれないが、そこにはいかなる宣言書もなかったし、また「スポークスマン」もいない。むしろそこで起きたのは、1943年から1946年までの間にニューヨークのペギー・グッゲンハイムの「今世紀の美術」画廊において最初の個展を開いた6人、7人の画家たちが、別個に、しかし殆ど同時に、ある一群の難題に直面したということである。当時、30年代のピカソ、および1910-1918年のカンディンスキーはそれよりは劣るもののおそらくはそれよりは決定的な度合いで、抽象及び抽象に近い芸術にとっての表現の新しい可能性を暗示していた。それは、クレーが最後の10年に抱いていた、非常に創意に富んではいたが実現されることのなかった着想を超えるものであった。ゴーキーやデ・クーニングやポロックのようなアメリカ人にとって重大な刺激となったのは、実現されなかったクレーというよりはむしろ実現されなかったピカソであり、彼ら三人全ては、ピカソが狩り出したが捕らえられることのなかった野兎の幾羽かを捕えようとし、そして実際ある程度捕えたのである(少なくともポロックは捕らえた)。」クレメント・グリーンバーグ「『アメリカ型』絵画」『グリーンバーグ批評選集』藤枝晃雄(編訳)、勁草書房、2005年。
「ポロックは、西部のワイオミング州の生まれ。しかし、生後10カ月頃からは、貧しい一家とともにカリフォルニア州、アリゾナ州などの各地を転々。15歳のとき、はじめてアルコールを口にするが、これが彼の人生にとっては決定的。予備役将校訓練部隊(ROTC)に所属するが、酒に酔った暴行事件で除名。そこからはじまって、アルコール中毒とそれに絡み合った暴力という症候群は生涯かれにつきまとうことになる。1930年にかれはニューヨークに移り住み、アート・ステューデント・リーグで、画家のトーマス・ハート・ベントン(1889-1975年)の教室に所属。このベントンの指導のもとで絵画を学びながら、苦しい生活をやりくりする苦闘に満ちた模索の過程がポロックの1030年代でしょうか。特筆すべきは、かれが、ホセ・クレメンテ・オロスコや、ダビド・アルファロ・シケイロス、ディエゴ・リベラといったメキシコの壁画家たちの仕事と出会っている事。実際、1936年にはシケイロスの「実験ワークショップ」に参加して、壁画制作のためのさまざまな技法を習得しています。だが、同時に、1930年代を通じてかれのアルコール中毒は悪化し、ついにみずから入院して治療を受けることになる。その過程でユング派の精神分析を受けるのですが、その分析のためのドローイングが今でも残っています(かれの一貫した「西部」、すなわち「余白」、「野生の限界領域」への志向を端的に示す作品を掲げておきます)。
こうして、生活においても心理においてもはじめからある種の根源的な「破綻」を抱え込んでいるポロックが、続く1940年代の後半になると、「ニューヨーク・スクール」あるいは「抽象表現主義」と呼ばれることになる、アメリカ合衆国の新しい絵画の流れの先頭を切って走っている。このジャンプがどのように可能になったのか。
言うまでもなく、ひとりのアーティストが世界レベルの絵画史のなかに登録されるに至るジャンプを果たすためには、さまざまな補助者との出会い、独自の世界を切り開くためのきっかけ、社会に受容される歴史的条件などたくさんの要素が複雑に絡み合っています。その絡み合いのなかから、わたしとしては、1937年の『マガジン・オブ・アート』に発表された論文「原始美術とピカソ」を読んで感動したポロックが、わざわざ著者を探して会いに行ったという美術理論家のジョン・グレアム、そしてそのグレアムが企画した「アメリカとフランスの絵画」展(1942年、マクミラン画廊)に、アメリカ側の若手のひとりとしてポロックとともに出品を要請されるが、ポロックの作品に圧倒されて、かれを世に出すことを決意し、後には結婚することになる画家のリー・クラズナー(1908-84年)、そして1943年にみずから運営する「今世紀の美術」画廊における「若き芸術家のための春のサロン」第1回展にポロックを招き、同じ年にかれの初の個展をオーガナイズし専属の契約をすることになる、世紀の大コレクターともいうべきペギー・グッゲンハイム(当時の夫は、なんとあのエルンストでした!)、そして1945年の同画廊での第2回目の個展について「私の意見では、かれの世代の中の最強の画家。そしておそらくミロ以来のもっとも偉大な画家としてみずからを確立している」と宣言したグリーンバーグなどとの一連の出会いをじっくり物語りたいところです。」小林康夫『絵画の冒険 表象文化論講義』東京大学出版会、2016.pp.290-292.
ポロックといえば、床に拡げたキャンヴァスの上で、顔料を入れたバケツをもって踊るように色をまき散らすパフォーマンス映像が有名だ。かれは1950年代にこれで、現代美術のヒーローになる。しかし、はじめからこうした方法で絵を描いていたわけではない。その初期の《誕生》などの作品から追いかけてみると、かれがどうやってこうした表現にたどり着いたか、想像できる。
「こうして、とうとう準備が整ったと言いましょうか。われわれは、ポロックという野生の野兎が、数世紀に及ぶ伝統を誇る「西欧絵画」という歴史的運動体を、決定的な仕方で突破するそのモーメントにさしかかっている。すべては準備された。ただ、この「突破」が起こるために必要なことは、画家がマンハッタンを離れて、「西部」へ――いや、実際の「西部」ではなかったのだけど――大西洋に面したロングアイランド島の農業と漁業の村スプリングスへと引っ越すことだけ。その「自然」のなか、納屋を改造したアトリエの床に、かれは、下塗りをしていないカンヴァスを拡げ、その上から、エナメルやアルミニウムといった工業用の顔料を、棒や固めた筆などで、滴らせたり注いだりする、いわゆるドリッピング(dripping)、あるいはポアリング(pouring)と呼ばれる技法を使って、画面一面にさまざまな顔料のラインが乱舞するオール・オーヴァー(all over)の作品を制作するようになるのです。このポイントのひとつは、顔料の流動性でしょう。それは流れなければならない。しかし、ポロックがコントロールを失うほどに流動的ではいけない。かれの身体の動きがそのままダイレクトに反映され、かれがカンヴァスの上の「空中」で絵を描くことができるように、流動的でなければならないのです。その流動性が、その制作の「時」の統一性・全体制を保証するのです。
たとえば、そのような制作の比較的初期の作品のひとつ《五尋の深み》(1947年)。驚くべきことに、この画面には、釘、鋲、ボタン、鍵、櫛、たばこ、マッチも同時に塗りこめられているのです。しかも、ここには、もはやいかなる形象断片も残されてはいない。「意味」を求め探ろうとする読み取りの眼差しは、縦横に走る顔料のラインの「無秩序」に途方に暮れるだけ。タイトルも――おそらく他人がつけたもの――なんの指示も与えてはくれそうにもありません。ここでは、われわれの頭脳の「表象」のモダリテイが完全に機能不全に陥ってしまう。しかも、ここには、いわゆる抽象画の核にあったようなコンポジションは少しも見えては来ない。むしろ全体は、ディコンストラクションどころか解体(ディコンポジション)の様相を強く帯びているのです。われわれ観る者はこれに耐えなければならないということになる。すなわち、この作品を対象的に見るのではなく、そう、ポロックが制作においてそうしていたように、われわれもまた、この絵画の「中に」入れなければならないのです。 ポロックは次のように言っています。
私の絵はイーゼルから生まれてくるのではない。描く前にキャンヴァスを張ることさえ滅多にしない。わたしは張っていないキャンヴァスを固い壁や床の上にとめるほうが好きだ。硬い表面の抵抗が必要だし、床の上だとずっとのびのびできるからだ。このやり方だと、絵のまわりを歩き、四方から制作し、文字通り絵のなかにいることができるのだから、わたしは絵をより身近に、絵の一部のように感じられる。これは西部のインディアンの砂絵師たちの方法に近い。
イーゼル、パレット、絵筆といった普通の画材を段々使わなくなってきている。棒、こて、ナイフや、流動的な顔料や砂、割れたガラスその他異質な物質を加えた重い厚塗りの絵具をドリッピングするほうが好きだ。
自分が絵のなかにいるとき、自分が何をしているのか意識しない。いわば“なじんだ”あとになってはじめて自分が何をしていたかを知る。わたしは変更することやイメージをこわすことを恐れない。なぜなら絵はそれ自体の生命をもっているのだから。わたしはそれを全うさせてやろうとする。結果が駄目になるのは、わたしが絵との接触を失ったときに限られる。他の場合には、純粋なハーモニー、楽々としたギブ・アンド・テイクが生まれます。絵はうまくゆく。
そう、だから、われわれもまた、絵の「中に」入る。でも、そうすると、奇妙なことに、―-まったくの蛇足、個人的な「無双」のようなものですが――サイズと比率が似通っているせいもあるが、わたしには、この《五尋の深み》の「ヴェール」の下に、われわれが最初に見たあの《誕生》が透けて見えてくるようにも感じられたりする。渦巻く黒のライン、白の断片的な肉体、あの恐ろしい「眼」は隠れて消えているが、しかしこれもまた《誕生》ではないのか――わたしだったら、《誕生Ⅱ》とタイトルをつけたかもしれません。いずれにしても、そこに、単なる偶然のデタラメという意味での「カオス」を見る(それはじつは、「見ることができない」という意味ですが)のではなく、この始まりも終わりもない「無秩序」が、しかし「聖なるもの」として開かれているということを自分なりに感じることが重要になってくるのです。
こうして、ポロックとともに、ジョットから始まった「西欧絵画」は、画家の存在そのものの「野生」という平面に激突する。いや、「激突」という強い表現を使ったのは、この作業は、あるいは人が誤解するかもしれないけれど、じつが、けっして簡単な、イージーな制作などではないということ。むしろ逆で、この「中にいる」アクションを保ち続けることは、おそらく――あらゆるシャーマニズム的儀礼がそうであるように――きわめて危険なことでもあるのです。
そして、ポロックもその危険な道を行く。1950年、かれはまたアルコールに溺れるようになる。1951年頃からは、いわゆる「ブラック・ペインティング」と呼ばれる、まるでもう一度、具象的な形態を追い求めるかのような作品を制作するようになる。ここには、「絵画」の「復讐」とでも呼びたくなるような何か壮絶なものがあるとわたしは思うのですが、ここではもう論じることはできません。「ブラック・ペインティング」とドリッピングやポアリングを用いた絵画のあいだで揺れ動きながら、1954年以降、かれは次第に絵が描けなくなる。18カ月ものあいだ、絵が描けない。クラズナーとの関係も破綻。そして、1956年8月、新しい恋人の女性とその友人を乗せて、飲酒運転をしていて道端の木に激突。恋人の女性は助かったが、その友人も運転していた本人も即死。ポロック、享年44歳。
「絵画」が「自然」に「激突」した「事件」で、それはあったのだ――と、いささかパセテイックに、わたしは言ってしまうのです。」小林康夫『絵画の冒険 表象文化論講義』東京大学出版会、2016.pp.297-300.
小林氏の文章は、劇的な短い生涯を終わらせたポロックに触発されて、昂奮しているのだが、もしポロックが生きながらえていたとしても、かれのこの方法は行き着くところまで行きついて、後はなかったかもしれない。

B.消費税10%はやらざるをえない・・しかし。
べつの話題だが、大相撲の横綱稀勢の里は休場を繰り返したあげく、やっと9月場所で10勝を挙げこれでかろうじて復活かというファンの期待を裏切って、九州場所では初日から四連敗してまた休場。大方の相撲ファンはかれは横綱を張る力はなく、もう見限るしかあるまいと思っただろう。消費税の引き上げは、やるといっては延期し、いよいよやらざるをえないとなったら、対象を選んで軽減税率を適用するという姑息な弥縫策を出している。現実を直視することを避け、引き延ばしと言い訳でだらだら続ける、というのはどうもみっともない、と誰も思う。
「軽減税率は撤回を: 消費税率の8%から10%への引き上げが、来年10月に迫ってきた。社会保障の財源確保のためには必要だ。
しかし、同時に導入される軽減税率制度には、この期に及んでも納得がいかない。撤回すべきだ。
政府は「低所得者に配慮する観点から、『酒類・外食を除く飲食料品』と『定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞』を対象に消費税の『軽減税率制度』が実施される」と広報する。だが、同制度はかねて問題点が指摘されている。
まず、恩恵をより多く受けるのは高所得者である。低所得者への配慮をうたうのであれば、「給付付き税額控除」が有効だ。これは税金から一定額を控除する減税で、課税額より控除額が大きい場合はその分を現金で給付する措置だ。
また、同じ食品を購入しても店内で食べれば「外食」となり軽減税率非適用だが、持ち帰りは適用になる。現場の混乱と手間が増える。
さらに適用品目を何にするかで、業界と政治の間に駆け引きが発生する。
新聞通信調査会が8,9月に18歳以上の5千人を対象に行った「第11回メディアに関する全国世論調査」(回答率62.7%、3135人)によると、自宅で月ぎめ新聞を購読している人は69.4%、初回2008年の88.6%から低下傾向が続いている。
必需品とはいえなくなった新聞が食品とともに適用対象なことに、違和感を覚える国民は多いのではないか。
政治に対し「ペンの力」を乱用した結果だと嫌みも言いたくなる。日本新聞協会は前言を翻し、適用を返上してはどうか。さもないと、新聞への信頼は低下する。 (玄)」朝日新聞2018年11月29日朝刊14面、経済気象台。
政治家の評価は、5年10年では定まらない。いやそこそこ公正な評価が出てくるのは、当人が世を去って時代がすっかり過去のものになる30年以上は必要だろう。だとすれば、安倍晋三という政治家がなにをやったか、その意味は、今すぐには難しいかも知れないが、田中角栄と比べてみると、この国の未来へのグランドデザインを構想する能力と、国民大衆の心情への無関心という点で、大きな資質の欠陥が現れるのではないかと危惧する。保守政治という理念でも、田中角栄のそれと安倍晋三のそれは、向いている方向とその中身が正反対ではないか。だからといって、もちろん角栄礼賛に傾くには躊躇するが、時代のめぐりあわせという偶然の要素もあるな。
「角栄氏と保守政治 弱者包み込む情 今こそ:編集委員 駒野 剛
神宮外苑のイチョウ並木を過ぎると2020年東京五輪・パラリンピックの主会場、新国立競技場の建設現場にぶつかる。
五輪を先導役に建設や投資が東京周辺で盛んだ。今年上半期に首都圏で売り出された新築マンションの平均価格はバブル末期以来の高水準を記録。地価の上昇に人件費、資材費の上昇が拍車をかける。景気の長続きを祈りたいが、悪しき前例がある。
「昭和40(1965)年不況」。前回の東京五輪があった64年から翌年にかけて、公共事業は一巡する一方、日本銀行の金融引き締めもあり放漫経営の企業が次々と息詰まる。65年3月に会社更生法を申請した山陽特殊鋼は戦後最大の倒産となった。
客から預かった再建で資金調達していた山一證券も金繰りが悪化。取引銀行が支援にちゅうちょする中、「それでもお前は銀行の頭取か」と一喝、日銀法25条による無制限無期限の特別融資で一気に沈静化させた男がいた。蔵相、田中角栄氏である。
◇ ◇
今年は角栄氏の生誕100年。10月、故郷の新潟県柏崎市西山町に向かった。生家と田中家の墓が特別公開されており、私も500円を払って参加した。
玄関前で記念撮影する女性ら、近くの「田中角栄記念館」で生前の映像や角栄氏の揮毫を求める人たち。誰の顔にも懐かしさと笑みがあふれていた。
没後25年。いまだこれほど人々の心を捉える政治家は他にいまい。なぜだろう。
こんな角栄氏に言葉が残っている。
「人間は、やっぱり出来損ないだ。みんな失敗もする。その出来損ないの人間そのままを愛せるかどうかなんだ。政治家を志す人間は、人を愛さなきゃダメだ」「東大を出た頭のいいやつはみんな、あるべき姿を愛そうとするから、現実の人間を軽蔑してしまう。それが大衆蔑視につながる。それではダメなんだ。そこの八百屋のおっちゃん、叔母ちゃん、その人たちをそのままで愛さなきゃならない。そこにしか政治はないんだ。政治の原点はそこにあるんだ」
飾り気のない優しさと大衆への愛。いまの政治家が失った「情」があふれている。
看板政策「日本列島改造論」も、底流にあるのは弱者を包み込む情でなかったか。
「住みよい国土で将来に不安なく、豊かに暮らし」ていくため、都市集中の資源投資を大胆に転換して、工業を全国的に再配置する一方、全国新幹線と高速道の建設、情報通信網のネットワーク形成をテコに、「都市と農村、裏日本と表日本の格差は必ずなくすことができる」と改造論は説く。
高度成長で栄えた太平洋ベルト地帯に対し、日本海側はおいてけぼりだった。若者は東京などに奪われ寂れた反面、都会は発展の反動で公害や交通地獄が慢性化する。国土の均衡ある発展こそ都市の矛盾を減らし国富を地方に分散させる悲願になった。
考えは正しかった。「これだけの総合戦略を考えた政治家はいません。しかしタイミングが悪かった」と角栄氏の評伝の著者、新川敏光法政大学教授は話す。米国がベトナム戦争に伴い膨大なドル資金を海外に流出させていた。日本も「過剰流動性」と呼ばれた余剰資金が蓄積された結果、列島改造を当て込んだ土地投機が激化した。
第4次中東戦争で石油価格が急騰、狂乱物価と呼ばれるほどに。角栄氏は列島改造の旗を降ろし、構想は未完で終る。
金権批判で下野後、ロッキード事件で法廷へ。栄光と屈辱と。今太閤から闇将軍と。激変した人生が私には悲劇に見える。
◇ ◇
新潟県長岡駅から自動車で20分ほど進むと信濃川と交差する妙見堰に着く。全長524㍍、八つの水門が上下して流量を調整、幾度も流域を変えた川を安定させた。
88年5月末、濃紺のベンツが停車した。角栄氏は関わった公共事業の行く末を気にかけていた。最晩年、確かめに来たのだ。
先日、私が訪ねた堰の記念館には見学に来た小学生の感想文が残され、様々な役割を知り感心したなどとあった。保守政治とは何か、遺産が静かに問いかけてきた。
弱肉強食を疑い、弱者の救済を掲げた彼の考えは、低成長にあえぐ一方で格差が拡大する今、改めて吟味されるべきだ。五輪と万博という高度成長の夢を後追いする時こそ、「決断と実行」が求められている。」朝日新聞2018年11月29日朝刊16面、オピニオン欄「ザ・コラム」。
第2次大戦後、美術の中心がパリからニューヨークに移り、次々新しい潮流が現れることになるのだが、一般に「絵画」が風景や人物や静物などを題材に、その形象をキャンバスなどに描く写実的な「具象的」作品と、眼に見える形姿をそのままで描くのではなく、色や形を分解したり組み合わせたりする「抽象的」作品があるのだ、という二分法が定着する。「西欧絵画」の歴史をみてくると、この意味の「抽象的」作品が現れるのは、20世紀に入ってからだと考えられ、セザンヌやモネなどがその先駆と見られるようになるのも、キュビスムやダダイスムなどが出てきたからだろう。しかし、キュビスムやシュールレアリスムなどは、見たものをそのまま描くのをやめたが、現実にある形象を完全に離れた幾何学的な図像や無秩序な偶然によるようなものではないから「抽象的」といっても、「具象的」要素を含んでいた。そして、第2次大戦後に現れる、それ以前の「絵画」概念を塗り替えるような新しい「抽象主義」は、まずアメリカ人らしいアメリカ人、ジャクソン・ポロックからはじまる。「抽象表現主義」と呼ばれる作品は、かれがそう名付けたわけではない。
「「抽象表現主義」という用語を正当なものとするあらゆる真の根拠は、これらの画家たちの幾人かが、キュビスムおよびフランス的なものを一般に反発するようになった時に、ドイツやロシアやユダヤの表現主義に傾き始めたという事実に在る。しかしそれでも、彼らの全てがフランス美術から出発し、フランス美術から様式に対する己の直感を得たことに変わりはない。また、彼ら全てが優れた野心ある芸術とはどのような感触のものでなければならないかについてのもっとも鮮明な概念を得たのもフランス人からである。
これらの若いアメリカ人たちが共有したと思われる最初の問題は、三人の主要なキュビスト――ピカソ、ブラック、レジェ――が総合的キュビスムの終り以来固守してきた、比較的限定された浅い奥行きのイリュージョンを緩めることだった。彼らはまた、自分たちの言わなければならないことを言えるようにしたければ、先行する抽象芸術の殆ど全てにキュビスムが課していた、ドローイングやデザインにおける直線的または曲線的な規則正しさについての規範を緩めなければならなかった。これらの問題は、計画に従って取り組まれたのではない。「抽象表現主義」には計画的なものは皆無に等しく、またこれまでもそうであった。個々の芸術家たちは「声明」は発したかもしれないが、そこにはいかなる宣言書もなかったし、また「スポークスマン」もいない。むしろそこで起きたのは、1943年から1946年までの間にニューヨークのペギー・グッゲンハイムの「今世紀の美術」画廊において最初の個展を開いた6人、7人の画家たちが、別個に、しかし殆ど同時に、ある一群の難題に直面したということである。当時、30年代のピカソ、および1910-1918年のカンディンスキーはそれよりは劣るもののおそらくはそれよりは決定的な度合いで、抽象及び抽象に近い芸術にとっての表現の新しい可能性を暗示していた。それは、クレーが最後の10年に抱いていた、非常に創意に富んではいたが実現されることのなかった着想を超えるものであった。ゴーキーやデ・クーニングやポロックのようなアメリカ人にとって重大な刺激となったのは、実現されなかったクレーというよりはむしろ実現されなかったピカソであり、彼ら三人全ては、ピカソが狩り出したが捕らえられることのなかった野兎の幾羽かを捕えようとし、そして実際ある程度捕えたのである(少なくともポロックは捕らえた)。」クレメント・グリーンバーグ「『アメリカ型』絵画」『グリーンバーグ批評選集』藤枝晃雄(編訳)、勁草書房、2005年。
「ポロックは、西部のワイオミング州の生まれ。しかし、生後10カ月頃からは、貧しい一家とともにカリフォルニア州、アリゾナ州などの各地を転々。15歳のとき、はじめてアルコールを口にするが、これが彼の人生にとっては決定的。予備役将校訓練部隊(ROTC)に所属するが、酒に酔った暴行事件で除名。そこからはじまって、アルコール中毒とそれに絡み合った暴力という症候群は生涯かれにつきまとうことになる。1930年にかれはニューヨークに移り住み、アート・ステューデント・リーグで、画家のトーマス・ハート・ベントン(1889-1975年)の教室に所属。このベントンの指導のもとで絵画を学びながら、苦しい生活をやりくりする苦闘に満ちた模索の過程がポロックの1030年代でしょうか。特筆すべきは、かれが、ホセ・クレメンテ・オロスコや、ダビド・アルファロ・シケイロス、ディエゴ・リベラといったメキシコの壁画家たちの仕事と出会っている事。実際、1936年にはシケイロスの「実験ワークショップ」に参加して、壁画制作のためのさまざまな技法を習得しています。だが、同時に、1930年代を通じてかれのアルコール中毒は悪化し、ついにみずから入院して治療を受けることになる。その過程でユング派の精神分析を受けるのですが、その分析のためのドローイングが今でも残っています(かれの一貫した「西部」、すなわち「余白」、「野生の限界領域」への志向を端的に示す作品を掲げておきます)。
こうして、生活においても心理においてもはじめからある種の根源的な「破綻」を抱え込んでいるポロックが、続く1940年代の後半になると、「ニューヨーク・スクール」あるいは「抽象表現主義」と呼ばれることになる、アメリカ合衆国の新しい絵画の流れの先頭を切って走っている。このジャンプがどのように可能になったのか。
言うまでもなく、ひとりのアーティストが世界レベルの絵画史のなかに登録されるに至るジャンプを果たすためには、さまざまな補助者との出会い、独自の世界を切り開くためのきっかけ、社会に受容される歴史的条件などたくさんの要素が複雑に絡み合っています。その絡み合いのなかから、わたしとしては、1937年の『マガジン・オブ・アート』に発表された論文「原始美術とピカソ」を読んで感動したポロックが、わざわざ著者を探して会いに行ったという美術理論家のジョン・グレアム、そしてそのグレアムが企画した「アメリカとフランスの絵画」展(1942年、マクミラン画廊)に、アメリカ側の若手のひとりとしてポロックとともに出品を要請されるが、ポロックの作品に圧倒されて、かれを世に出すことを決意し、後には結婚することになる画家のリー・クラズナー(1908-84年)、そして1943年にみずから運営する「今世紀の美術」画廊における「若き芸術家のための春のサロン」第1回展にポロックを招き、同じ年にかれの初の個展をオーガナイズし専属の契約をすることになる、世紀の大コレクターともいうべきペギー・グッゲンハイム(当時の夫は、なんとあのエルンストでした!)、そして1945年の同画廊での第2回目の個展について「私の意見では、かれの世代の中の最強の画家。そしておそらくミロ以来のもっとも偉大な画家としてみずからを確立している」と宣言したグリーンバーグなどとの一連の出会いをじっくり物語りたいところです。」小林康夫『絵画の冒険 表象文化論講義』東京大学出版会、2016.pp.290-292.
ポロックといえば、床に拡げたキャンヴァスの上で、顔料を入れたバケツをもって踊るように色をまき散らすパフォーマンス映像が有名だ。かれは1950年代にこれで、現代美術のヒーローになる。しかし、はじめからこうした方法で絵を描いていたわけではない。その初期の《誕生》などの作品から追いかけてみると、かれがどうやってこうした表現にたどり着いたか、想像できる。
「こうして、とうとう準備が整ったと言いましょうか。われわれは、ポロックという野生の野兎が、数世紀に及ぶ伝統を誇る「西欧絵画」という歴史的運動体を、決定的な仕方で突破するそのモーメントにさしかかっている。すべては準備された。ただ、この「突破」が起こるために必要なことは、画家がマンハッタンを離れて、「西部」へ――いや、実際の「西部」ではなかったのだけど――大西洋に面したロングアイランド島の農業と漁業の村スプリングスへと引っ越すことだけ。その「自然」のなか、納屋を改造したアトリエの床に、かれは、下塗りをしていないカンヴァスを拡げ、その上から、エナメルやアルミニウムといった工業用の顔料を、棒や固めた筆などで、滴らせたり注いだりする、いわゆるドリッピング(dripping)、あるいはポアリング(pouring)と呼ばれる技法を使って、画面一面にさまざまな顔料のラインが乱舞するオール・オーヴァー(all over)の作品を制作するようになるのです。このポイントのひとつは、顔料の流動性でしょう。それは流れなければならない。しかし、ポロックがコントロールを失うほどに流動的ではいけない。かれの身体の動きがそのままダイレクトに反映され、かれがカンヴァスの上の「空中」で絵を描くことができるように、流動的でなければならないのです。その流動性が、その制作の「時」の統一性・全体制を保証するのです。
たとえば、そのような制作の比較的初期の作品のひとつ《五尋の深み》(1947年)。驚くべきことに、この画面には、釘、鋲、ボタン、鍵、櫛、たばこ、マッチも同時に塗りこめられているのです。しかも、ここには、もはやいかなる形象断片も残されてはいない。「意味」を求め探ろうとする読み取りの眼差しは、縦横に走る顔料のラインの「無秩序」に途方に暮れるだけ。タイトルも――おそらく他人がつけたもの――なんの指示も与えてはくれそうにもありません。ここでは、われわれの頭脳の「表象」のモダリテイが完全に機能不全に陥ってしまう。しかも、ここには、いわゆる抽象画の核にあったようなコンポジションは少しも見えては来ない。むしろ全体は、ディコンストラクションどころか解体(ディコンポジション)の様相を強く帯びているのです。われわれ観る者はこれに耐えなければならないということになる。すなわち、この作品を対象的に見るのではなく、そう、ポロックが制作においてそうしていたように、われわれもまた、この絵画の「中に」入れなければならないのです。 ポロックは次のように言っています。
私の絵はイーゼルから生まれてくるのではない。描く前にキャンヴァスを張ることさえ滅多にしない。わたしは張っていないキャンヴァスを固い壁や床の上にとめるほうが好きだ。硬い表面の抵抗が必要だし、床の上だとずっとのびのびできるからだ。このやり方だと、絵のまわりを歩き、四方から制作し、文字通り絵のなかにいることができるのだから、わたしは絵をより身近に、絵の一部のように感じられる。これは西部のインディアンの砂絵師たちの方法に近い。
イーゼル、パレット、絵筆といった普通の画材を段々使わなくなってきている。棒、こて、ナイフや、流動的な顔料や砂、割れたガラスその他異質な物質を加えた重い厚塗りの絵具をドリッピングするほうが好きだ。
自分が絵のなかにいるとき、自分が何をしているのか意識しない。いわば“なじんだ”あとになってはじめて自分が何をしていたかを知る。わたしは変更することやイメージをこわすことを恐れない。なぜなら絵はそれ自体の生命をもっているのだから。わたしはそれを全うさせてやろうとする。結果が駄目になるのは、わたしが絵との接触を失ったときに限られる。他の場合には、純粋なハーモニー、楽々としたギブ・アンド・テイクが生まれます。絵はうまくゆく。
そう、だから、われわれもまた、絵の「中に」入る。でも、そうすると、奇妙なことに、―-まったくの蛇足、個人的な「無双」のようなものですが――サイズと比率が似通っているせいもあるが、わたしには、この《五尋の深み》の「ヴェール」の下に、われわれが最初に見たあの《誕生》が透けて見えてくるようにも感じられたりする。渦巻く黒のライン、白の断片的な肉体、あの恐ろしい「眼」は隠れて消えているが、しかしこれもまた《誕生》ではないのか――わたしだったら、《誕生Ⅱ》とタイトルをつけたかもしれません。いずれにしても、そこに、単なる偶然のデタラメという意味での「カオス」を見る(それはじつは、「見ることができない」という意味ですが)のではなく、この始まりも終わりもない「無秩序」が、しかし「聖なるもの」として開かれているということを自分なりに感じることが重要になってくるのです。
こうして、ポロックとともに、ジョットから始まった「西欧絵画」は、画家の存在そのものの「野生」という平面に激突する。いや、「激突」という強い表現を使ったのは、この作業は、あるいは人が誤解するかもしれないけれど、じつが、けっして簡単な、イージーな制作などではないということ。むしろ逆で、この「中にいる」アクションを保ち続けることは、おそらく――あらゆるシャーマニズム的儀礼がそうであるように――きわめて危険なことでもあるのです。
そして、ポロックもその危険な道を行く。1950年、かれはまたアルコールに溺れるようになる。1951年頃からは、いわゆる「ブラック・ペインティング」と呼ばれる、まるでもう一度、具象的な形態を追い求めるかのような作品を制作するようになる。ここには、「絵画」の「復讐」とでも呼びたくなるような何か壮絶なものがあるとわたしは思うのですが、ここではもう論じることはできません。「ブラック・ペインティング」とドリッピングやポアリングを用いた絵画のあいだで揺れ動きながら、1954年以降、かれは次第に絵が描けなくなる。18カ月ものあいだ、絵が描けない。クラズナーとの関係も破綻。そして、1956年8月、新しい恋人の女性とその友人を乗せて、飲酒運転をしていて道端の木に激突。恋人の女性は助かったが、その友人も運転していた本人も即死。ポロック、享年44歳。
「絵画」が「自然」に「激突」した「事件」で、それはあったのだ――と、いささかパセテイックに、わたしは言ってしまうのです。」小林康夫『絵画の冒険 表象文化論講義』東京大学出版会、2016.pp.297-300.
小林氏の文章は、劇的な短い生涯を終わらせたポロックに触発されて、昂奮しているのだが、もしポロックが生きながらえていたとしても、かれのこの方法は行き着くところまで行きついて、後はなかったかもしれない。

B.消費税10%はやらざるをえない・・しかし。
べつの話題だが、大相撲の横綱稀勢の里は休場を繰り返したあげく、やっと9月場所で10勝を挙げこれでかろうじて復活かというファンの期待を裏切って、九州場所では初日から四連敗してまた休場。大方の相撲ファンはかれは横綱を張る力はなく、もう見限るしかあるまいと思っただろう。消費税の引き上げは、やるといっては延期し、いよいよやらざるをえないとなったら、対象を選んで軽減税率を適用するという姑息な弥縫策を出している。現実を直視することを避け、引き延ばしと言い訳でだらだら続ける、というのはどうもみっともない、と誰も思う。
「軽減税率は撤回を: 消費税率の8%から10%への引き上げが、来年10月に迫ってきた。社会保障の財源確保のためには必要だ。
しかし、同時に導入される軽減税率制度には、この期に及んでも納得がいかない。撤回すべきだ。
政府は「低所得者に配慮する観点から、『酒類・外食を除く飲食料品』と『定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞』を対象に消費税の『軽減税率制度』が実施される」と広報する。だが、同制度はかねて問題点が指摘されている。
まず、恩恵をより多く受けるのは高所得者である。低所得者への配慮をうたうのであれば、「給付付き税額控除」が有効だ。これは税金から一定額を控除する減税で、課税額より控除額が大きい場合はその分を現金で給付する措置だ。
また、同じ食品を購入しても店内で食べれば「外食」となり軽減税率非適用だが、持ち帰りは適用になる。現場の混乱と手間が増える。
さらに適用品目を何にするかで、業界と政治の間に駆け引きが発生する。
新聞通信調査会が8,9月に18歳以上の5千人を対象に行った「第11回メディアに関する全国世論調査」(回答率62.7%、3135人)によると、自宅で月ぎめ新聞を購読している人は69.4%、初回2008年の88.6%から低下傾向が続いている。
必需品とはいえなくなった新聞が食品とともに適用対象なことに、違和感を覚える国民は多いのではないか。
政治に対し「ペンの力」を乱用した結果だと嫌みも言いたくなる。日本新聞協会は前言を翻し、適用を返上してはどうか。さもないと、新聞への信頼は低下する。 (玄)」朝日新聞2018年11月29日朝刊14面、経済気象台。
政治家の評価は、5年10年では定まらない。いやそこそこ公正な評価が出てくるのは、当人が世を去って時代がすっかり過去のものになる30年以上は必要だろう。だとすれば、安倍晋三という政治家がなにをやったか、その意味は、今すぐには難しいかも知れないが、田中角栄と比べてみると、この国の未来へのグランドデザインを構想する能力と、国民大衆の心情への無関心という点で、大きな資質の欠陥が現れるのではないかと危惧する。保守政治という理念でも、田中角栄のそれと安倍晋三のそれは、向いている方向とその中身が正反対ではないか。だからといって、もちろん角栄礼賛に傾くには躊躇するが、時代のめぐりあわせという偶然の要素もあるな。
「角栄氏と保守政治 弱者包み込む情 今こそ:編集委員 駒野 剛
神宮外苑のイチョウ並木を過ぎると2020年東京五輪・パラリンピックの主会場、新国立競技場の建設現場にぶつかる。
五輪を先導役に建設や投資が東京周辺で盛んだ。今年上半期に首都圏で売り出された新築マンションの平均価格はバブル末期以来の高水準を記録。地価の上昇に人件費、資材費の上昇が拍車をかける。景気の長続きを祈りたいが、悪しき前例がある。
「昭和40(1965)年不況」。前回の東京五輪があった64年から翌年にかけて、公共事業は一巡する一方、日本銀行の金融引き締めもあり放漫経営の企業が次々と息詰まる。65年3月に会社更生法を申請した山陽特殊鋼は戦後最大の倒産となった。
客から預かった再建で資金調達していた山一證券も金繰りが悪化。取引銀行が支援にちゅうちょする中、「それでもお前は銀行の頭取か」と一喝、日銀法25条による無制限無期限の特別融資で一気に沈静化させた男がいた。蔵相、田中角栄氏である。
◇ ◇
今年は角栄氏の生誕100年。10月、故郷の新潟県柏崎市西山町に向かった。生家と田中家の墓が特別公開されており、私も500円を払って参加した。
玄関前で記念撮影する女性ら、近くの「田中角栄記念館」で生前の映像や角栄氏の揮毫を求める人たち。誰の顔にも懐かしさと笑みがあふれていた。
没後25年。いまだこれほど人々の心を捉える政治家は他にいまい。なぜだろう。
こんな角栄氏に言葉が残っている。
「人間は、やっぱり出来損ないだ。みんな失敗もする。その出来損ないの人間そのままを愛せるかどうかなんだ。政治家を志す人間は、人を愛さなきゃダメだ」「東大を出た頭のいいやつはみんな、あるべき姿を愛そうとするから、現実の人間を軽蔑してしまう。それが大衆蔑視につながる。それではダメなんだ。そこの八百屋のおっちゃん、叔母ちゃん、その人たちをそのままで愛さなきゃならない。そこにしか政治はないんだ。政治の原点はそこにあるんだ」
飾り気のない優しさと大衆への愛。いまの政治家が失った「情」があふれている。
看板政策「日本列島改造論」も、底流にあるのは弱者を包み込む情でなかったか。
「住みよい国土で将来に不安なく、豊かに暮らし」ていくため、都市集中の資源投資を大胆に転換して、工業を全国的に再配置する一方、全国新幹線と高速道の建設、情報通信網のネットワーク形成をテコに、「都市と農村、裏日本と表日本の格差は必ずなくすことができる」と改造論は説く。
高度成長で栄えた太平洋ベルト地帯に対し、日本海側はおいてけぼりだった。若者は東京などに奪われ寂れた反面、都会は発展の反動で公害や交通地獄が慢性化する。国土の均衡ある発展こそ都市の矛盾を減らし国富を地方に分散させる悲願になった。
考えは正しかった。「これだけの総合戦略を考えた政治家はいません。しかしタイミングが悪かった」と角栄氏の評伝の著者、新川敏光法政大学教授は話す。米国がベトナム戦争に伴い膨大なドル資金を海外に流出させていた。日本も「過剰流動性」と呼ばれた余剰資金が蓄積された結果、列島改造を当て込んだ土地投機が激化した。
第4次中東戦争で石油価格が急騰、狂乱物価と呼ばれるほどに。角栄氏は列島改造の旗を降ろし、構想は未完で終る。
金権批判で下野後、ロッキード事件で法廷へ。栄光と屈辱と。今太閤から闇将軍と。激変した人生が私には悲劇に見える。
◇ ◇
新潟県長岡駅から自動車で20分ほど進むと信濃川と交差する妙見堰に着く。全長524㍍、八つの水門が上下して流量を調整、幾度も流域を変えた川を安定させた。
88年5月末、濃紺のベンツが停車した。角栄氏は関わった公共事業の行く末を気にかけていた。最晩年、確かめに来たのだ。
先日、私が訪ねた堰の記念館には見学に来た小学生の感想文が残され、様々な役割を知り感心したなどとあった。保守政治とは何か、遺産が静かに問いかけてきた。
弱肉強食を疑い、弱者の救済を掲げた彼の考えは、低成長にあえぐ一方で格差が拡大する今、改めて吟味されるべきだ。五輪と万博という高度成長の夢を後追いする時こそ、「決断と実行」が求められている。」朝日新聞2018年11月29日朝刊16面、オピニオン欄「ザ・コラム」。