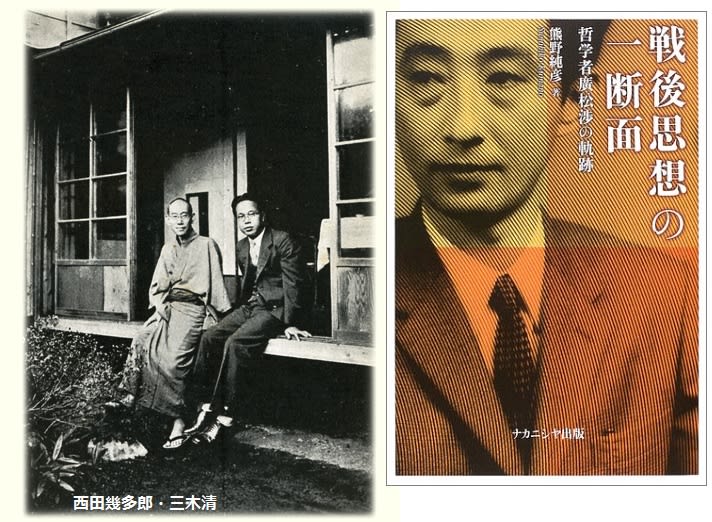A.野球のこと
だいぶ前、ぼくはプロ野球を熱心に見ていた時期がある。子どもの頃は、野球は嫌いだった。男の子の友だちはみんな野球が好きで、しばしば空き地の原っぱで野球ごっこをした。ぼくはボールを握ったり投げたりするたびにこんなこと、何が面白いんだろうと気分が沈んだ。スポーツといっても、あの頃は野球か相撲くらいしか知らなかった。王長嶋の読売ジャイアンツが王者の時代だったから、みんなYGの帽子を被っていた。「巨人軍」に拍手を送る世の大勢にぼくは嫌悪を感じた。そこで、高校生の頃、大洋ホエールズに平松という投手がいて、普段はいい加減に投げているのに、巨人戦になると見違えるように張り切って健闘するので、ほう!と思った。やがてぼくの高校の部活の後輩が、なぜか横浜大洋のトレーナーになったこともあって、川崎球場から横浜に拠点を移したホエールズのファンになり、横浜球場にも何度か行くようになった。
その頃、田代というバッターがいて、めちゃくちゃ空振りするのだが、当たると小気味のよいホームランを飛ばす。巨人の川上・広岡流管理野球に対して、大洋は大らかな野性を野放しにしている気がして好きになった。大洋漁業はプロ野球を手放して、横浜大洋ベイスターズになったがぼくは、すっかり弱小球団横浜のファンになったのだ。そして、昔の伝説奇跡的な三原大洋の一回だけの優勝以後は絶対に優勝などするはずがないと思われた横浜が、1998年再び権藤監督の指揮と奇跡の大魔神の佐々木の活躍でリーグ優勝、さらに日本シリーズを制するという信じられないドラマが実現した。
投手の野村弘樹、斎藤隆をはじめ石井琢朗、波留敏夫、鈴木尚典、R・ローズ、駒田徳広、佐伯貴弘、進藤達哉、谷繁元信のマシンガン打線に、この年両親を連れて四国八十八カ所を巡礼していたぼくは、秋の四国で横浜の優勝の夜、一人で万歳!を叫んだ記憶がある。あれはもう、17年も昔の出来事なのか。それ以後、横浜ベイスターズは再び低迷し、DeNAベイスターズになって落ち目の巨人にせっせと星を献上する球団に逆戻りしている。でも、昨日は一矢を報いた、らしい。東京ドームでの対巨人戦、10対2で巨人に圧勝!嬉しい。
「開幕戦では土壇場で飛び出した関根のプロ初アーチで1点差まで追い上げるも、僅差での悔しい敗戦。今日からの巻き返しを図りたい横浜DeNAは、初回に2本の適時打と相手失策で一挙3点を先制!!さらに6回には梶谷・筒香の連続適時打にロペスの1号2ランHRが飛び出し一挙5得点と打線が爆発!!打線の援護に先発・山口も8回2失点と応えると、9回に筒香がダメ押し2号ソロHRを放ち、最後はプロ初登板のルーキー・山康が締めてゲームセット!!投打がガッチリ噛み合い、今季初勝利を飾った!!
昨日は相手を上回る9安打を放ちながらも2得点に終わった打線が、今日は初回から奮起!!先頭・石川の四球と盗塁に桑原の犠打でいきなり1死3塁の好機を作り出すと、梶谷が左線を破る適時2塁打を放って幸先良く先制に成功!!さらに梶谷の三盗に相手悪送球が重なり2点目、2死後からバルディリスにも左中間適時2塁打が飛び出すなど、一挙3点を先制!!昨日とは打って変わって横浜DeNAがペースを握る!!
一方、打線の援護を受けた先発・山口は、序盤から走者は出しながらも落ち着いて要所を締めるピッチング!!川村コーチも「テンポ良く、ストライクゾーンへ低く行ってくれれば、大きな心配はないだろう」と評価する投球でスコアボードに0を並べていく!!
すると6回、山口の好投に喚起された打線が爆発!!先頭・黒羽根、桑原の中前打などで2死1.3塁の好機を作り出すと、梶谷が「Goodです」と右中間を破る適時2塁打を放てば、続く筒香も「得点圏で打てたことが嬉しいです」と右前適時打を放ち巨人を突き放す!!そしてとどめはロペスが古巣へ恩返しの一発!!レフトスタンドへ移籍後初となる1号2ランHRを叩き込んで9点差とし、試合を決定付ける!!!
その裏、山口は2点を失ったものの大きく崩れることはなく、丁寧に低めをつく投球で巨人打線から凡打の山を築き上げ、8回を投げきって2失点。先発の役目を十二分に果たし、上々の今季初登板となった!!そして7点差で迎えた9回には、先頭・筒香が巨人5番手・西村のストレートを完璧に捉え、ライトスタンドの看板に直撃する2試合連続2号ソロHRを放ってダメ押し!!その裏は2番手・山康がプロ初登板のマウンドに上がり巨人打線を三者凡退に封じてゲームセット!!終始巨人を圧倒し、今季初勝利を快勝で飾った!!
昨日の鬱憤をすべて吐き出すような快勝で今季初勝利を挙げた横浜DeNAは、梶谷・筒香の3・4番コンビが合わせて8安打5打点と大暴れ!!明日は1勝1敗で迎える今カード最終戦。先発のマウンドにはオープン戦で好投を続けた三嶋が上がり、そこへ今日大爆発の3・4番コンビが加わる万全の体制で明日の一戦に臨む!! 結果はすでに知れているのだが、まいっか。

B.交換様式D!
世界史がある法則の下に一定の方向に向かってすすんでおり、そこには気まぐれな無秩序や行き当たりばったりな偶然などではなく、厳然たる唯物論的な必然性があるのだ、という理論はとびきり頭脳優秀なエリートにとって、とても魅力的な状況だろうと思う。問題はそれが、実証主義的な面倒臭い、ドン臭い社会科学の論理ではなく、天才的な頭脳が生み出すエレガントな理性の産物に帰するかどうか、ということだろう。柄谷行人の明晰さというものは、どこまでもアタマの勝負であり、まるでバベルの塔のように堅固に構築された言葉の体系的構成体である。それが読んでみると意外に簡潔で、寄り道をしない思考の構築物だと思う。
彼は交換様式を重視して、それを世界史上の発展段階(という言い方は避けるが)に適用した先に、第4番目の交換様式のヴィジョンとして「交換様式D」を提出する。これは未だ現実には存在していない、かくあるべき未来、可能かもしれないがさまざまな困難を必死で克服しなければならない理論上の到達点ということになる。
「それらに加えて、ここで、交換様式Dについて述べておかねばならない。それは、交換様式Bがもたらす国家を否定するだけでなく、交換様式Cの中で生じる階級分裂を越え、いわば、交換様式Aを高次元で回復するものである。これは、自由で同時に相互的であるような交換様式である。しかしこれは、前の三つのように実在するものではない。それは、交換様式BとCによって抑圧された互酬性の契機を想像的に回復しようとするものである。したがって、それは最初、宗教的な運動としてあらわれる。
交換様式の区別に関して、もう一つ付け加えておこう。カール・シュミットは「政治的なもの」に関して、他から相対的に独立したそれに固有の領域を見出そうとして、つぎのように述べている。《道徳的なものの領域においては、究極的区別とは、善と悪とであり、美的なものにおいては美と醜、経済的なものにおいては利と害、たとえば採算がとれる、とれない、であるとしよう》。それと同様に、政治的なものに固有の究極的な区別は、友と敵という区別である、とシュミットはいう。だが、それは私の考えでは、交換様式Bに固有のものである。したがって、「政治的なもの」に固有の領域は、広い意味で経済的な下部構造に由来するといわねばならない。
ついでにいうと、道徳的なものに固有の領域も、交換様式と別にあるわけではない。一般に、道徳的な領域は、経済的な領域とは別に考えられている。しかし、それは交換様式と無縁ではない。たとえば、ニーチェは、罪の意識は債務感情に由来すると述べた。ただし、彼は罪感情が交換様式Aから生じる負い目であることを見なかった。交換様式Cが浸透した近代では、罪感情は希薄になる。負い目を金で返せるからだ。このように、道徳的・宗教的なものは、一定の交換様式と深くつながっている。したがって、経済的下部構造を生産様式ではなく交換様式として見るならば、道徳性を経済的下部構造から説明することができる。
交換様式A(互酬)を例にとろう。部族的な社会では、これが支配的な交換様式である。ここでは、富や権力を独占することができない。国家社会、すなわち、階級社会が始まると、交換様式Aは従属的な地位におかれる。そこでは交換様式Bが支配的となる。その下で、交換様式Cも発展するが、従属的である。交換様式Cが支配的となるのは、資本制社会においてである。この過程で、交換様式Aは抑圧されるが、消滅することはない。むしろ、それは、フロイトの言葉でいえば、「抑圧されたものの回帰」として回復される。それが交換様式Dである。
交換様式Dは、交換様式Aへの回帰ではなく、それを否定しつつ、高次元において回復するものである。それは先ず、交換様式BとCが支配的となった古代帝国の段階で、普遍宗教として開示された。交換様式Dを端的に示すのは、キリスト教であれ仏教であれ、普遍宗教の創始期に存在した、共産主義的集団である。それ以後も、社会主義的な運動は宗教的な形態をとってきた。
一九世紀後半以後、社会主義は宗教的な色彩をもたなくなる。が、大事なのは、社会主義が根本的に、交換様式Aを高次元において回復することにあるという点である。たとえば、ハンナ・アーレントは、評議会コミュニズム(ソヴィエトあるいはレーテ)に関して、それが革命の伝統や理論の結果としてではなく、いつどこででも、「まったく自発的に、そのたびごとにそれまでまったくなかったものであるかのようにして出現する」ことを指摘している。これは、自然発生的な評議会コミュニズムが、交換様式Aの高次元での回復であることを示すものである。
交換様式Dおよびそれに由来する社会構成体を、たとえば、社会主義、共産主義、アナーキズム、評議会コミュニズム、アソシエーショニズム……といった名で呼んでもよい。が、それらの概念には歴史的にさまざまな意味が付着しているため、どう呼んでも誤解や混乱をもたらすことになる。ゆえに、私はそれを、たんにXと呼んでおく。大切なのは、言葉ではなく、それがいかなる位相にあるかを知ることであるから。」柄谷行人『世界史の構造』岩波現代文庫、2015. pp.12-15.
なぜこれが記号Xと呼ぶしかないのか?社会主義、共産主義、アナーキズムをそのまま言葉で訴えることは、あまりにも手垢にまみれていて、20世紀後半から21世紀初頭における社会理念としてはふさわしくないと思われるからだろう。でも、メジャーな権力が追求しているあるべき社会とは、交換様式BあるいはCに依拠する市場原理を僕たちの社会に隅々にまで定着させることに目標設定されている。頭のいい理論家は、マルクスもヘーゲルもエンゲルスもフロイトも咀嚼したうえで、これに対抗するヴィジョンとしての交換様式Dを書きつける。でも、理論家玉野井先生や柄谷先生の議論を正面切って戦える人がどれほどいたのかな?
「以上をまとめると、交換様式は、互酬、略取と再分配、商品交換、そしてXというように、四つに大別される。これらは図1のようなマトリックスで示される。これは、横の軸では、不平等/平等、縦の軸では、拘束/自由、という区別によって構成される。さらに、図2に、それらの歴史的派生態である、資本、ネーション、国家、そして、Xが位置づけられる。
つぎに重要なのは、実際の社会構成体は、こうした交換様式の複合として存在するということである。前もっていうならば、歴史的に社会構成体は、このような諸様式をすべてふくんでいる。ただ、どれが主要であるかによって異なるのである。しかし、それはBやCが存在しないことを意味するのではない。たとえば、戦争や交易はつねに存在する。が、BやCのような要素は互酬原理によって抑制されるため、Bがドミナントであるような社会、つまり、国家社会には転化しないのである。一方、Bがドミナントな社会においても、Aは別なかたちをとって存続した、たとえば農民共同体として、また、交換様式Cも発展した、たとえば都市として。だが、資本制以前の社会構成体では、こうした要素は国家によって上から管理・統合されている。交換様式Bがドミナントだというのは、そのような意味である。
つぎに、交換様式Cがドミナントになるのが、いうまでもなく、資本制社会である。マルクスの考えでは、資本制社会構成体は、「資本制生産」という生産様式によって規定される社会である。だが、資本制生産を特徴づけるものは何であろうか。それは分業と協業、あるいは機械の使用などといった形態にあるのではない。というのは、そのようなものなら奴隷制でも可能だからだ。また、資本制生産は商品生産一般に解消されない。奴隷制生産も農奴制生産もむしろ商品生産として発展したのだからだ。資本制生産が奴隷制生産や農奴制生産と異なるのは、それが「労働力商品」による商品生産だということにある。奴隷制の社会では人間が商品となる。したがって、人間が商品化されるのではなく、人間の「労働力」が商品化されるような社会でなければ、資本制生産はありえないのである。また、それは、土地の商品化をふくめ、社会全体に商品交換が浸透しないと生じない。ゆえに、「資本制生産」は生産様式ではなく、交換様式から見なければ理解できないのである。
資本制社会では、商品交換が支配的な交換様式である。だが、それによって、他の交換様式およびそこから派生するものが消滅してしまうわけではない。他の要素は変形されて存続するのだ。国家は近代国家として、共同体はネーションとして。つまり、資本制以前の社会構成体は、商品交換様式がドミナントになるにつれて、資本=ネーション=国家という結合体として変形されるのである。こう考えることによってのみ、ヘーゲルがとらえた『法の哲学』における三位一体的体系を、唯物論的にとらえなおすことができる。さらに、それらの揚棄がいかにしてありうるかを考えることができる。」柄谷行人『世界史の構造』岩波現代文庫、2015. pp.12-15.
だいぶ前、ぼくはプロ野球を熱心に見ていた時期がある。子どもの頃は、野球は嫌いだった。男の子の友だちはみんな野球が好きで、しばしば空き地の原っぱで野球ごっこをした。ぼくはボールを握ったり投げたりするたびにこんなこと、何が面白いんだろうと気分が沈んだ。スポーツといっても、あの頃は野球か相撲くらいしか知らなかった。王長嶋の読売ジャイアンツが王者の時代だったから、みんなYGの帽子を被っていた。「巨人軍」に拍手を送る世の大勢にぼくは嫌悪を感じた。そこで、高校生の頃、大洋ホエールズに平松という投手がいて、普段はいい加減に投げているのに、巨人戦になると見違えるように張り切って健闘するので、ほう!と思った。やがてぼくの高校の部活の後輩が、なぜか横浜大洋のトレーナーになったこともあって、川崎球場から横浜に拠点を移したホエールズのファンになり、横浜球場にも何度か行くようになった。
その頃、田代というバッターがいて、めちゃくちゃ空振りするのだが、当たると小気味のよいホームランを飛ばす。巨人の川上・広岡流管理野球に対して、大洋は大らかな野性を野放しにしている気がして好きになった。大洋漁業はプロ野球を手放して、横浜大洋ベイスターズになったがぼくは、すっかり弱小球団横浜のファンになったのだ。そして、昔の伝説奇跡的な三原大洋の一回だけの優勝以後は絶対に優勝などするはずがないと思われた横浜が、1998年再び権藤監督の指揮と奇跡の大魔神の佐々木の活躍でリーグ優勝、さらに日本シリーズを制するという信じられないドラマが実現した。
投手の野村弘樹、斎藤隆をはじめ石井琢朗、波留敏夫、鈴木尚典、R・ローズ、駒田徳広、佐伯貴弘、進藤達哉、谷繁元信のマシンガン打線に、この年両親を連れて四国八十八カ所を巡礼していたぼくは、秋の四国で横浜の優勝の夜、一人で万歳!を叫んだ記憶がある。あれはもう、17年も昔の出来事なのか。それ以後、横浜ベイスターズは再び低迷し、DeNAベイスターズになって落ち目の巨人にせっせと星を献上する球団に逆戻りしている。でも、昨日は一矢を報いた、らしい。東京ドームでの対巨人戦、10対2で巨人に圧勝!嬉しい。
「開幕戦では土壇場で飛び出した関根のプロ初アーチで1点差まで追い上げるも、僅差での悔しい敗戦。今日からの巻き返しを図りたい横浜DeNAは、初回に2本の適時打と相手失策で一挙3点を先制!!さらに6回には梶谷・筒香の連続適時打にロペスの1号2ランHRが飛び出し一挙5得点と打線が爆発!!打線の援護に先発・山口も8回2失点と応えると、9回に筒香がダメ押し2号ソロHRを放ち、最後はプロ初登板のルーキー・山康が締めてゲームセット!!投打がガッチリ噛み合い、今季初勝利を飾った!!
昨日は相手を上回る9安打を放ちながらも2得点に終わった打線が、今日は初回から奮起!!先頭・石川の四球と盗塁に桑原の犠打でいきなり1死3塁の好機を作り出すと、梶谷が左線を破る適時2塁打を放って幸先良く先制に成功!!さらに梶谷の三盗に相手悪送球が重なり2点目、2死後からバルディリスにも左中間適時2塁打が飛び出すなど、一挙3点を先制!!昨日とは打って変わって横浜DeNAがペースを握る!!
一方、打線の援護を受けた先発・山口は、序盤から走者は出しながらも落ち着いて要所を締めるピッチング!!川村コーチも「テンポ良く、ストライクゾーンへ低く行ってくれれば、大きな心配はないだろう」と評価する投球でスコアボードに0を並べていく!!
すると6回、山口の好投に喚起された打線が爆発!!先頭・黒羽根、桑原の中前打などで2死1.3塁の好機を作り出すと、梶谷が「Goodです」と右中間を破る適時2塁打を放てば、続く筒香も「得点圏で打てたことが嬉しいです」と右前適時打を放ち巨人を突き放す!!そしてとどめはロペスが古巣へ恩返しの一発!!レフトスタンドへ移籍後初となる1号2ランHRを叩き込んで9点差とし、試合を決定付ける!!!
その裏、山口は2点を失ったものの大きく崩れることはなく、丁寧に低めをつく投球で巨人打線から凡打の山を築き上げ、8回を投げきって2失点。先発の役目を十二分に果たし、上々の今季初登板となった!!そして7点差で迎えた9回には、先頭・筒香が巨人5番手・西村のストレートを完璧に捉え、ライトスタンドの看板に直撃する2試合連続2号ソロHRを放ってダメ押し!!その裏は2番手・山康がプロ初登板のマウンドに上がり巨人打線を三者凡退に封じてゲームセット!!終始巨人を圧倒し、今季初勝利を快勝で飾った!!
昨日の鬱憤をすべて吐き出すような快勝で今季初勝利を挙げた横浜DeNAは、梶谷・筒香の3・4番コンビが合わせて8安打5打点と大暴れ!!明日は1勝1敗で迎える今カード最終戦。先発のマウンドにはオープン戦で好投を続けた三嶋が上がり、そこへ今日大爆発の3・4番コンビが加わる万全の体制で明日の一戦に臨む!! 結果はすでに知れているのだが、まいっか。

B.交換様式D!
世界史がある法則の下に一定の方向に向かってすすんでおり、そこには気まぐれな無秩序や行き当たりばったりな偶然などではなく、厳然たる唯物論的な必然性があるのだ、という理論はとびきり頭脳優秀なエリートにとって、とても魅力的な状況だろうと思う。問題はそれが、実証主義的な面倒臭い、ドン臭い社会科学の論理ではなく、天才的な頭脳が生み出すエレガントな理性の産物に帰するかどうか、ということだろう。柄谷行人の明晰さというものは、どこまでもアタマの勝負であり、まるでバベルの塔のように堅固に構築された言葉の体系的構成体である。それが読んでみると意外に簡潔で、寄り道をしない思考の構築物だと思う。
彼は交換様式を重視して、それを世界史上の発展段階(という言い方は避けるが)に適用した先に、第4番目の交換様式のヴィジョンとして「交換様式D」を提出する。これは未だ現実には存在していない、かくあるべき未来、可能かもしれないがさまざまな困難を必死で克服しなければならない理論上の到達点ということになる。
「それらに加えて、ここで、交換様式Dについて述べておかねばならない。それは、交換様式Bがもたらす国家を否定するだけでなく、交換様式Cの中で生じる階級分裂を越え、いわば、交換様式Aを高次元で回復するものである。これは、自由で同時に相互的であるような交換様式である。しかしこれは、前の三つのように実在するものではない。それは、交換様式BとCによって抑圧された互酬性の契機を想像的に回復しようとするものである。したがって、それは最初、宗教的な運動としてあらわれる。
交換様式の区別に関して、もう一つ付け加えておこう。カール・シュミットは「政治的なもの」に関して、他から相対的に独立したそれに固有の領域を見出そうとして、つぎのように述べている。《道徳的なものの領域においては、究極的区別とは、善と悪とであり、美的なものにおいては美と醜、経済的なものにおいては利と害、たとえば採算がとれる、とれない、であるとしよう》。それと同様に、政治的なものに固有の究極的な区別は、友と敵という区別である、とシュミットはいう。だが、それは私の考えでは、交換様式Bに固有のものである。したがって、「政治的なもの」に固有の領域は、広い意味で経済的な下部構造に由来するといわねばならない。
ついでにいうと、道徳的なものに固有の領域も、交換様式と別にあるわけではない。一般に、道徳的な領域は、経済的な領域とは別に考えられている。しかし、それは交換様式と無縁ではない。たとえば、ニーチェは、罪の意識は債務感情に由来すると述べた。ただし、彼は罪感情が交換様式Aから生じる負い目であることを見なかった。交換様式Cが浸透した近代では、罪感情は希薄になる。負い目を金で返せるからだ。このように、道徳的・宗教的なものは、一定の交換様式と深くつながっている。したがって、経済的下部構造を生産様式ではなく交換様式として見るならば、道徳性を経済的下部構造から説明することができる。
交換様式A(互酬)を例にとろう。部族的な社会では、これが支配的な交換様式である。ここでは、富や権力を独占することができない。国家社会、すなわち、階級社会が始まると、交換様式Aは従属的な地位におかれる。そこでは交換様式Bが支配的となる。その下で、交換様式Cも発展するが、従属的である。交換様式Cが支配的となるのは、資本制社会においてである。この過程で、交換様式Aは抑圧されるが、消滅することはない。むしろ、それは、フロイトの言葉でいえば、「抑圧されたものの回帰」として回復される。それが交換様式Dである。
交換様式Dは、交換様式Aへの回帰ではなく、それを否定しつつ、高次元において回復するものである。それは先ず、交換様式BとCが支配的となった古代帝国の段階で、普遍宗教として開示された。交換様式Dを端的に示すのは、キリスト教であれ仏教であれ、普遍宗教の創始期に存在した、共産主義的集団である。それ以後も、社会主義的な運動は宗教的な形態をとってきた。
一九世紀後半以後、社会主義は宗教的な色彩をもたなくなる。が、大事なのは、社会主義が根本的に、交換様式Aを高次元において回復することにあるという点である。たとえば、ハンナ・アーレントは、評議会コミュニズム(ソヴィエトあるいはレーテ)に関して、それが革命の伝統や理論の結果としてではなく、いつどこででも、「まったく自発的に、そのたびごとにそれまでまったくなかったものであるかのようにして出現する」ことを指摘している。これは、自然発生的な評議会コミュニズムが、交換様式Aの高次元での回復であることを示すものである。
交換様式Dおよびそれに由来する社会構成体を、たとえば、社会主義、共産主義、アナーキズム、評議会コミュニズム、アソシエーショニズム……といった名で呼んでもよい。が、それらの概念には歴史的にさまざまな意味が付着しているため、どう呼んでも誤解や混乱をもたらすことになる。ゆえに、私はそれを、たんにXと呼んでおく。大切なのは、言葉ではなく、それがいかなる位相にあるかを知ることであるから。」柄谷行人『世界史の構造』岩波現代文庫、2015. pp.12-15.
なぜこれが記号Xと呼ぶしかないのか?社会主義、共産主義、アナーキズムをそのまま言葉で訴えることは、あまりにも手垢にまみれていて、20世紀後半から21世紀初頭における社会理念としてはふさわしくないと思われるからだろう。でも、メジャーな権力が追求しているあるべき社会とは、交換様式BあるいはCに依拠する市場原理を僕たちの社会に隅々にまで定着させることに目標設定されている。頭のいい理論家は、マルクスもヘーゲルもエンゲルスもフロイトも咀嚼したうえで、これに対抗するヴィジョンとしての交換様式Dを書きつける。でも、理論家玉野井先生や柄谷先生の議論を正面切って戦える人がどれほどいたのかな?
「以上をまとめると、交換様式は、互酬、略取と再分配、商品交換、そしてXというように、四つに大別される。これらは図1のようなマトリックスで示される。これは、横の軸では、不平等/平等、縦の軸では、拘束/自由、という区別によって構成される。さらに、図2に、それらの歴史的派生態である、資本、ネーション、国家、そして、Xが位置づけられる。
つぎに重要なのは、実際の社会構成体は、こうした交換様式の複合として存在するということである。前もっていうならば、歴史的に社会構成体は、このような諸様式をすべてふくんでいる。ただ、どれが主要であるかによって異なるのである。しかし、それはBやCが存在しないことを意味するのではない。たとえば、戦争や交易はつねに存在する。が、BやCのような要素は互酬原理によって抑制されるため、Bがドミナントであるような社会、つまり、国家社会には転化しないのである。一方、Bがドミナントな社会においても、Aは別なかたちをとって存続した、たとえば農民共同体として、また、交換様式Cも発展した、たとえば都市として。だが、資本制以前の社会構成体では、こうした要素は国家によって上から管理・統合されている。交換様式Bがドミナントだというのは、そのような意味である。
つぎに、交換様式Cがドミナントになるのが、いうまでもなく、資本制社会である。マルクスの考えでは、資本制社会構成体は、「資本制生産」という生産様式によって規定される社会である。だが、資本制生産を特徴づけるものは何であろうか。それは分業と協業、あるいは機械の使用などといった形態にあるのではない。というのは、そのようなものなら奴隷制でも可能だからだ。また、資本制生産は商品生産一般に解消されない。奴隷制生産も農奴制生産もむしろ商品生産として発展したのだからだ。資本制生産が奴隷制生産や農奴制生産と異なるのは、それが「労働力商品」による商品生産だということにある。奴隷制の社会では人間が商品となる。したがって、人間が商品化されるのではなく、人間の「労働力」が商品化されるような社会でなければ、資本制生産はありえないのである。また、それは、土地の商品化をふくめ、社会全体に商品交換が浸透しないと生じない。ゆえに、「資本制生産」は生産様式ではなく、交換様式から見なければ理解できないのである。
資本制社会では、商品交換が支配的な交換様式である。だが、それによって、他の交換様式およびそこから派生するものが消滅してしまうわけではない。他の要素は変形されて存続するのだ。国家は近代国家として、共同体はネーションとして。つまり、資本制以前の社会構成体は、商品交換様式がドミナントになるにつれて、資本=ネーション=国家という結合体として変形されるのである。こう考えることによってのみ、ヘーゲルがとらえた『法の哲学』における三位一体的体系を、唯物論的にとらえなおすことができる。さらに、それらの揚棄がいかにしてありうるかを考えることができる。」柄谷行人『世界史の構造』岩波現代文庫、2015. pp.12-15.