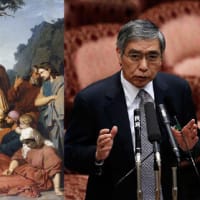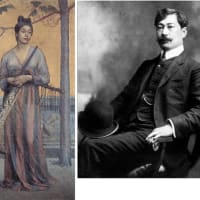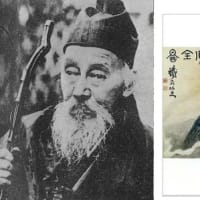A.天井桟敷の市街劇
寺山修司という名は、ぼくには『書を捨てよ街へ出よう』という書物の記憶に結びついている。この本は1969年芳賀書店から刊行された評論集で、表紙は横尾忠則のイラストだった。この頃、寺山は詩人・歌人としての活動から演劇に重点を移す一方、青少年に向けたメッセージを次々本にしていた。「家出のススメ」とか「競馬」とかの本も書いていた。同じ頃に旗揚げした劇団・演劇実験室・天井桟敷の第7回公演(1968年)で「ハイティーン詩集 書を捨てよ町へ出よう」がこんどは演劇作品として発表された。当時はアングラ演劇と呼ばれたブームが起こり、69年夏に新宿・花園神社隣にあった建物(閉店したスナック「パニック」の建物を公演用に改装)で2ヶ月間のロングラン公演。この公演は夜の新宿名所を巡るはとバスツアーで毎夜、団体客で満席となった。
1971年には寺山修司自身が監督・製作・脚本を務める同名の映画が公開。同年、評論集「続・書を捨てよ町へ出よう」が出版される。これらの評論集・公演作品・映画は、題名は同じであるが、内容はそれぞれ別個の物である。ぼくが強く記憶しているのは、映画のATG版『書を捨てよ街へ出よう』では、主人公である「私」を演じた佐々木英明という青年が、ラストでリングの上から長い独白を東北弁でしゃべるのだが、その台詞によれば、彼はぼくとまったく同じ日に生まれている。つまり映画の時点では21歳。そして映画の舞台はぼくのよく知っている都電の走っている早稲田の神田川沿いや、早稲田のグラウンドで、今もテレビなどに出ている平泉征(現平泉成)にサッカーでしごかれたりする。1969年にぼくは紛争でほとんど授業もない大学に入り、この主人公とは少し違う道をすすむのだが、書を捨てて街に出てももうそこには、可能性も希望も見いだせない気がしていた。とにかく寺山修司はつねに若いぼくらを挑発し、普通の生きかた、当たり前の生活、というものをぶち壊さなければ世界は何も変わらないと言い続けていた。
「観客を外に連れ出し、都市の不可視のレイヤーから 新たな「非日常」を創出する
■都市のリアリティを再発見する
「市街劇」とは何か、この定義を厳密に考えるならば、そもそも演劇/劇場/Theaterが、その起源において都市の中でどのように形成されてきたがを考察する必要があるでしょう。しかし、ここではさしあたり、「劇場内ではなく都市空間で展開される演劇」と仮定してみれば、そのような演劇は今や珍しいものではありません。観客を劇場の外に連れ出し都市全体を劇場と見立てる。都市の中に演劇的想像力のリソースを見出し、そこからあらたなるドラマや出会いを生成させる。観客は、演劇というフィクションのレンズを通して都市のリアリティを再発見する。このように、演劇は都市に展開することによって、都市との共犯関係を結んできました。
■「社会参画」としての市街劇
日本現代演劇史における市街劇の金字塔といえば、」寺山修司率いる天井桟敷による30時間市街劇「ノック」(1975)が挙げられます。寺山が仕掛けた市街劇は、住民票と引き換えに地図を手に入れた観客が、30時間にわたり阿佐ヶ谷界隈の18箇所で同時多発する戸別訪問演劇、密室劇、街頭演劇などに遭遇し、巻き込まれていくというものでした。のちに寺山は、自らの演劇実験を「俳優のいない演劇と誰もが俳優である演劇、劇場のない演劇、あらゆる場所が劇場である演劇、観客のいない演劇と、相互に観客になり代わる演劇、市街劇(後略)」と振り返り、「私は演劇を芸術表現の一様式としてではなく、私自身の社会参加の手段として選択してきた」と明言しています。
寺山が演劇実験を繰り返していた1960~70年代の都市空間は、戦後復興から東京五輪に向けた急速な整備がすすみ、学生運動デモが路上にも拡散し、異物同士が排除と衝突を繰り返し、混沌を生み出す場でもありました。寺山のみならず、同時代のアングラ演劇の担い手、例えば状況劇場(紅テント)の唐十郎、黒テントの佐藤信らも確信的に「テント」を自らの演劇創作の現場とし、美術の分野では前衛芸術グループ「ハイレッドセンター」が路上パフォーマンスを行うなど、都市への積極的かつ無許可の介入こそが芸術による「社会参画」の戦略として成立し得た時代。そこでは、都市の日常を攪拌する挑発や警察沙汰など、メディアを賑わせるスキャンダルもがドラマの一部として機能したのです。
■ゆるやかな散策/ツアー
あれから40年。今日、多くの演劇が生産・上演されている大都市圏の空間に、かつてのような混沌は存在していません。浄化とゾーニングが進み、異物は合法的に排除され、平面的でピカピカとした広告が、不動産価値に従ってグラデーション的に都市空間を覆い尽くしています。これは、東京だけでなくグローバリゼーションで均質化する日本中の、そして世界の都市にも共通する現象といえるでしょう。そうした都市空間に、寺山的な演劇理論を継承しつつも、モバイル化するテクノロジーや都市のインフラを巧みに借用しながら、新たな演劇的想像力を持ち込むアーティストが世界のあちこちで同時的に出現してきました。
日本において代表的かつ、演劇ユニットPort B(ポルト・ビー)で演劇実権を繰り返す高山明でしょう。今ではすっかり一般名詞として定着した「ツアーパフォーマンス」という言葉が日本の演劇史上最初に用いられたのはPort B の市街劇『一方通行路』(2006)においてでした。巣鴨地蔵通りという一本の「道」を舞台/主人公としたこの作品では、観客はヘッドフォンを装着し、音源のナビゲーションに従いながら街を散策します。
その後高山は、1964年の東京五輪にまつわる複数のサイトを本物の「はとバス」に乗車して巡る『東京/オリンピック』(2007)、巣鴨プリズン跡地に出現したサンシャイン60をモニュメント/墓標と見立て、五人一組で観客がサンシャインの見える場所を散策する『サンシャイン62』(2008)を立て続けに発表しました。これらPort B 初期のツアーパフォーマンス三連作は、劇場の椅子に安住することに慣れていた演劇関係者からのクレームこそ受けたものの、かつて寺山が創出したような、都市の日常に異物を持ち込む挑発やスキャンダルとは無縁のものでした。むしろ観客は、高山が設定した演劇的フレームを自由に着脱し、そのフレームが指し示す矢印に従って都市を遊歩するのです。時に終了時間さえ告げられないゆるやかな散策/ツアーの先にある、あたかも偶然のように仕掛けられた風景や、占い師や移民、ホ-ムレスといった他者との出会い、そして都市の記憶との交錯、これらによって、観客は自らの身体の感覚が書き換わっていることを実感することになります。
■「演劇を問い直す」という批評精神
ほぼ時を同じくして、世界のあちこちで、都市へと拡張される演劇実権が展開されていたことも忘れてはなりません。オーストリアの極右政党の台頭に対抗し、差別的な言動を先導し脱臼する演劇的キャンペーンをウィーン国立歌劇場前で展開した『外国人よ出て行け!』(クリストフ・シュリンゲンジーフ昨・演出、2002)、ブエノスアイレス市内に本物そっくりの人形を放置し、人々や警察の反応を演劇として記録した「ピロクテーテス・プロジェクト」(エミリオ・ガルシア・ウェービ作・演出、2002)、複数のショーウィンドウに同時多発する物語を挿入し、一本のストーリー全体を劇場化した『ラ・マレア』(マリアーノ・ベンッソッテイ作・演出、2005)など劇場空間を都市へと拡張し演劇を社会との接触面に晒すものから、都市そのものを劇場と捉えてフィクションのグレームで都市の現実を浮かび上がらせるものまで、筆者が知るだけでも枚挙に暇がありません。
なかでも、ベルリンの劇場HAUに拠点を置きながら活動していた演劇ユニット、リミニ・プロトコルの世界的成功は、2000年以降の演劇的潮流を象徴するものでした。ネット電話を介してつながるインドの電話オペレーターとの対話に導かれて都市をツアーする「Call Cutta」(2005)、リアルなトラック運転手の語りを聞きながら荷台目線で物流の拠点を移動するトラック演劇『Cargo X』(2006)など、彼らのプロジェクトは、いずれも社会学的なリサーチから出発しつつ、徹底してその都市のリアリティを浮かび上がらせる批評精神と遊び心に満ちています。
しかし、なぜ彼らは都市に出ていったのでしょうか。その背景には、いわゆるヨーロッパにおける劇場制度の中で、システマティックに生産され続ける舞台作品への問題提起が含まれていると考えられます。現実とは乖離した安全な舞台上から社会を批判することに対する矛盾や、舞台上で職業的な俳優によって表象される身体が、結局当事者のリアルな身体より弱いのではないかという演劇的リプリゼンテーションに対する概念。こうした「演劇を問い直す」プロセスの中で、再び観客を都市へ連れ出し、普段出会わない他者との出会い――難民、外国人労働者、そして歴史からこぼれおちた死者さえも――を仕掛けていった一連の試みは、極めて正統的な演劇論の延長線上に花開いたものと言えるでしょう。
■そして筆者自身もまた、この2000年代以降の「同時代」を生きる「プレイヤーとして、東京において劇場以外の場所で展開する作品を集中的にプロデュースしてきました。ディレクターを含めた国際舞台芸術祭、「フェスティバル/トーキョー(F/T)では、「都市=トーキョー」と「祝祭=フェスティバル」の関係性を更新すること、そして「演劇というメディアの今日的可能性を問い直す」ことを主要なコンセプトに掲げ、その具体的な戦略として、演劇/劇場の外に出るということを徹底して実践しました。上述した「Cargo-X」の日本バージョンを製作し、維新派『風景画』(2011)、飴屋法水『わたしのすがた』(2010)、ロメオ・カステルッチ+飴屋放水『宮沢賢治/夢の島から』(2011)、Port B 『完全避難マニュアル東京版』(2010)『光のないⅡ』(2012)『東京へテロトピア』(2013)などもプロデュースしました。雑居ビル、百貨店の屋上、空き地、廃墟、港湾施設など、あらゆる場所が演劇を生成する/演劇によって生成される場所となっていきました。
これらの試みについては、F/T09~13の記録集『フェスティバル/トーキョー/ドキュメント』をご覧いただきたいと思います。今後、2020年の東京オリンピックやテロ対策によってさらに管理と浄化が強まる東京の都市空間において、私たちはいかにその裏をかき、都市の不可視のレイヤーからあらたな非日常を創出することができるのか。都市空間における演劇的想像力が再び試されるはずです。その時、F/Tで紡がれた言説や思想は、あらたな必然性とともにリロードされるのではないかと期待します。相馬千秋「「市街劇という実験」(鈴木理映子+編集部『〈現代演劇〉のレッスン 拡がる場、越える表現』フィルムアート社、)pp.058-063.
このアートプロデューサーだという著者がどんな人か知らないので、何ともいえないが、年齢的にあの60年代末から70年代初めの小劇場演劇をリアルタイムで経験した世代よりは下ではないかと推測する。それは戦後復興、東京五輪、学生デモを一緒くたにした乱暴な要約から、ちょっと上滑りな説明に同調できないからで、寺山修司についても同時代を生きていた人という感覚はないだろうと思う。だからダメだとは言わないが、いろいろ気になる記述はある。日本の現代演劇を自分の目で観続けてきた扇田昭彦さんの仕事にはとても及ばない。
天井桟敷の市街劇「フック」1975について、扇田昭彦はこのように回想している。
「演劇の取材や原稿の依頼で私は生前の寺山修司と会う機会がかなりあった。私より五つ年長の寺山はまばゆい才気と独特のカリスマ的魅力をもつ人物だったが、人柄は親しみやすく、その口調に交じる東北弁のイントネーションのように、いつも懐かしさを感じさせる人物だった。
その寺山は1983年5月4日、肝硬変のため、四十七歳で世を去った。彼が主催した演劇実験室「天井桟敷」が解散したのは、それから二か月余りたった七月末である。
寺山の早すぎた死は、一人の劇作家・演出家の死以上の意味を持つ象徴的な死だった。実験劇のシンボルとも言える寺山の死で、六〇年代に始まったわが国の小劇場運動は幕を降ろしたというのが私の考えだ。
寺山が横尾忠則、東由多加、九條今日子(当時は映子)とともに演劇実験室「天井桟敷」を結成したのは1967年である。六〇年代後半から七〇年代前半にかけては、唐十郎、鈴木忠志、佐藤信、蜷川幸雄、太田省吾らがそれぞれ劇団を率いて、先鋭的な活動を続けていた時代である。
その中にあって、寺山が率いる天井桟敷はやや異端視される存在だった。寺山自身が演劇畑の出身ではなかったし、『青森県のせむし男』(67年)、『毛皮のマリー』(同)をはじめとする天井桟敷の初期の舞台が、寺山自身が認めるように、「風俗的な意味で新聞をにぎわせた」せいもある。
だが、天井桟敷の実験劇はしだいに過激な急進性をおびていった。そして彼らのパフォーマンスは演劇の枠組みを超えて、演劇そのものを解体する地点、演劇が演劇で亡くなる極北にまでたどり着いてしまうのである。
その過激な精神の運動が、1970年から天井桟敷が始めた一連の「市街劇」だ。『イエス』(竹永茂生作・演出、70年)を第一作として、フランス、オランダでも上演された『人力飛行機ソロモン』(寺山作、竹永演出、70年)を経て、社会的事件になった『ノック』(寺山修司企画、岸田理生・幻一馬台本、幻一馬構成・演出)で頂点に達するシリーズである。幻一馬とは、天井桟敷の演出部員だった小暮泰之のことだ。
天井桟敷の「市街劇」は、普通の野外劇とはまるで違う種類のパフォーマンスだった。それは何でもない市街の日常的現実の中に「劇」を持ちこみ、それによって人々の閉ざされた心と日常感覚を「ノック」し、強い揺さぶりをかけることを目的としていた。
具体的に、『ノック』がどう「上演」されたかを書いてみよう。
この市街劇は75年4月19日午後から翌20日夜までの30時間、東京都杉並区阿佐ヶ谷周辺の二十七カ所で同時多発的に「上演」された。
約千人の観客の一人だった私は十九日午後三時、新宿駅東口で入場券と引き換えに一枚のイラスト入り地図を受け取った。その地図には、阿佐ヶ谷一帯で起きるはずの多くの「劇」とその日時と場所が謎めいた表現で書かれていた。こうして私は友人の大笹吉雄(演劇評論家)と親しい編集者とともに、まるで宝探しのように「劇」を求めて、このあたりを深夜まで猛然と歩き回ることになったのである。
歩きだして分かったことは、虚構の劇が組み込まれていると期待することで、現実の街並みがまるで「劇場」のように変容して見えたことだ。向こうからやってくる警官は、もしかしたら俳優が扮した虚構の警官かもしれない。目の前にある古びた時計屋は、ひょっとして「時計商人ドロッセルマイヤーの失踪」という「劇」の舞台ではないのか。
むろん、いかにも「劇」らしいことも起きた。路上のマンホールのふたがあいて、白衣を着た男たちが出入りしたり、団地の公演で男女四人が優雅な正餐をとる光景も目にした。激しい言い争いをしながら夜の五日市街道を駆け抜けていく男女二人を追って、多くの観客が伴走する。“マラソン演劇”を、私たち自身、実演したりもした。深夜の公園を、舞台美術家の小竹信節が考案した機械に支えられて移動していく黒マント姿の「空中散歩者」を、私は自分のカメラに収めた。
何の予告もなく、ふいに千人もの「観客」が現れ、意味不明の「劇」を求めてうろつき回ったのだから、地元の人々が不安を覚えたのも無理はない。とくに、全身に包帯を巻いた車椅子の「ミイラ男」の戸別訪問劇に身重の主婦がショックを受けて110番、パトカーが駆けつけた事件は騒ぎを大きくした。演出の幻一馬は警察の取り調べを受け、翌日の各新聞の社会面には、無関係の一般市民を巻き込む「市街劇」を非難する記事が大きく出た青森市。
天井桟敷では19日夜、「上演」を続けるか中止するかで遅くまで議論が交わされたと言われるが、翌20日も『ノック』は続行された。私はこの日も南阿佐ヶ谷の銭湯の浴槽につかり、洗い場で全裸の男たちがするパフォーマンス「ぼたん湯における男湯事件」を目撃した。
『ノック』の反響は大きかった。晩年の寺山は「市街劇をもっとつきつめてみたい」と語っていたが、警察の規制は厳しく、彼は二度と市街劇を手掛けることができなかった。
だが、昨年(1998年)秋、思いがけなく、「市街劇」がよみがえった。青森市で開かれた日本文化デザイン会議の同時開催イベントとして、「一日だけの天井桟敷」と銘打ち、『人力飛行機ソロモン 青森篇』(J・A・シーザー総指揮・演出・音楽)が11月1日、青森市内で上演されたのである。
私もおよそ約三千人の観客とともに半日、青森市内を歩き回ったが、そこで観たのは、県と市、警察が協力する平穏で祝祭的な、楽しめる「市街劇」だった。時代の違いと言えばそれまでだが、かつての不穏な「市街劇」に興奮した者としては、ちょっと拍子抜けがしたのも事実である。」扇田昭彦『こんな舞台を観てきた 扇田昭彦の日本現代演劇50年史』河出書房新社、2015、pp.027-030.
来年のオリンピックをめぐる日本のメディアや当局の対応を見ていても、とにかく事故や批難を極力避けて、国民の祝祭を演出したいという願望と裏腹に、秩序を乱すことはやるな、公共の指示に従え、という権威主義は強まっている。寺山が『ノック』でやろうとしたこととは正反対の、人間の感情・意欲・パッションを公共空間で刺激し開放するのではなく、型と規則にあてはめて窒息させるようなイベントしか、もうこの国は許さない状況になってしまっているのかもしれない。演劇の可能性は、そこをどう破炸できるのか。

B.声を上げた科学者・まだ間に合うのか?
「科学者一万人 気候危機宣言 【ニューヨーク=赤川肇】世界の科学者らが「地球は気候危機に直面している」と宣言し、化石燃料から再生可能エネルギーへの転換などを提言した論文が、米科学専門誌「バイオサイエンス」(電子版)に5日付で掲載された。日本など153カ国の計1万1000人以上が名を連ねている。
「科学者の枠を超えた問題」
「気候危機の警告」と題された論文は「科学者は破局的脅威を人類に警告する道義的責任がある」と目的を説明。国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の調査結果などから地球温暖化の影響や対策の遅れを指摘し、エネルギーや食料、経済、人口など六分野で気候変動を抑えるための方策を例示している。
食料分野では、ウシなど反すう動物を中心とした畜産物の消費を減らして植物由来の食料を増やすことにより、健康状態や大気汚染も改善でき、農地を家畜用ではなく人間の食糧生産に充てられると指摘。経済分野では、経済成長や豊かさの追求を見直し、最低限必要なものや不平等の是正を優先させることで、生態系の維持や人間の幸福を目指す必要性を説いた。
論文を主導した米オレゴン州立大のウィリアム・リップル教授は米紙ワシントン・ポストに「気候変動の現状は、気候科学者だけの枠を超えた問題であることを示している」と指摘した。
気候変動対策を巡っては、トランプ米政権が四日、地球温暖化対策の国際枠組「パリ協定」について「米国の労働者やビジネスに不公平な経済的負担を強いる」(ポンペオ国務長官)などの理由で正式に離脱を通告するなど、国際社会の足並みが乱れている。」東京新聞2019年11月7日夕刊1面。
問題はとっくに科学者や専門家の範囲を越えて、ぼくたち一般市民の生活の未来に及んでいる。それでもまだ、何が問題かさえ考えていない政治家、官僚、企業家がなんと多いことか。