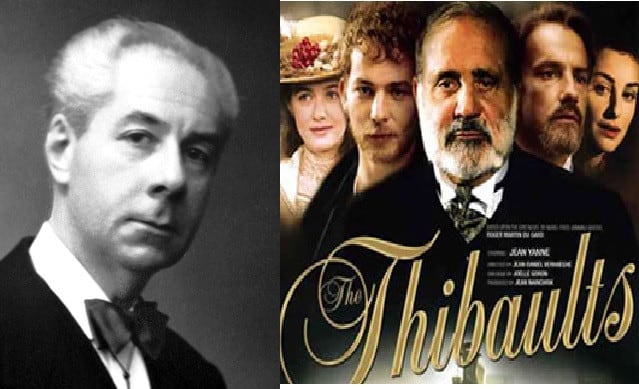A.サン=テグジュペリの戦争
「星の王子さま」Le Petit Princeは、フランスの飛行家にして作家サン=テグジュペリ(Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, comte de Saint-Exupéry、1900年6月 - 1944年7月)の書いた小説。第二次世界大戦中の1943年にフランス語で書かれ、アメリカで出版された。挿絵も作者が描いている。2015年現在、初版以来、200以上の国と地域の言葉に翻訳され、世界中で総販売部数1億5千万冊を超えたロングベストセラーである。砂漠、星、宇宙、そして飛行機。
宮崎駿の「紅の豚」というアニメ作品があるが、飛行機という乗り物が現われてしばらく、空を飛び回る飛行機乗りは、いつ死んでもおかしくないほど危なっかしい、それ故に大いなる冒険とロマンに満ちた仕事だったことがよく解る。その英雄のような男が、夢のような小説を書いたのだから、これに魅了される読者は世界中にいるだろうし、日本でも何度か「星の王子さま」のブームが起き、亡くなった三遊亭円楽師匠は自ら「星の王子さま」を自称した。
物語の中の少年王子は、いろんな星を経めぐり、愚かな人々を眺めて最後に地球に来て砂漠に墜落した飛行士と出会う。大人でありながら少年の無垢で理想的な心を強く印象づけられ、気がつくと王子はまたどこかの星に向かって消えている。この寓意に満ちた世界は、日本の東北にいた宮沢賢治(1896年8月 - 1933年9月)とも通底するファンタジー・ロマンではないか。サン=テグジュペリより少し年上の宮沢賢治は、飛行機には乗らなかったが、銀河鉄道というアイディアでやはり星に向かう。
「アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリは、しばしば遍歴の騎士と呼ばれた。だが、かれが騎士道的理想を生きたその道は、あくまでも二十世紀そのものであった。サン=テグジュペリとともに、われわれは新しい経験世界を見出す。これまでにわれわれが考察してきた人びとはみな、第一次世界大戦が勃発したときもう成熟した人であった。かれらが作品を発表し名声をえた時代は戦後であったが、彼らの精神は、それに先立つ長い平和の間に形成された。そして、かれらは、かれらが投げ込まれた激動の時代をあくまで異常なものと考えた。サン=テグジュペリとかれよりさらに若いものたちの場合は、その激動は、与えられた人間の条件と思われた。過去への郷愁など問題ではなかった。いまや問題は、破滅から救いうる人間的価値があれば何であれ、救い上げ、定義しなおすことであった。
サン=テグジュペリは、ベルナノスよりもわずか十二歳年下であったが――かれは一九〇〇年に生れた――、ちがった精神的世代に属していた。つまり、従軍経験をもつには若すぎたものたちの世代である。もう一歳か二歳年をとっていたら、サン=テグジュペリは、おそらく欣然と兵役に志願していたであろう。彼の祖先は貴族であった。かれは、カトリックの優秀校で、男らしさと自己鍛錬の高潔な考え方をもつように教育された。そして、信仰は失ったものの、その宗教教育から明らかにキリスト教に発する英雄主義の理想をもちつづけた。かれのはじめの志望はフランス海軍兵学校に入ることだった。それから、その入学試験に失敗して、建築の勉強をはじめた――それは一時的な興味ではあったが、かれの思想に消えぬ痕跡を残したものであった。一九二〇年代のはじめに、かれは飛行機操縦をはじめた。これにかれは自分に一番適した職業を見出した。そして、二十年後の死に至るまで、途中短い間他の職についたが、ずっと飛行士であった。
サン=テグジュペリが商業飛行士になったとき、飛行機はまだ日常茶飯のものではなかった。実際、かれや仲間たちがパイロットになることを選ぶことは、ブルジョワ社会の安穏と退屈から脱出することであった。かれらは必然的にパイオニア、冒険家であり、後の世代が当たり前のことと考えている航空路を、はじめて設定したひとびとであった。はじめ西部アフリカで、のちには南アメリカで、サン=テグジュペリは、日々の仕事として生命を賭けた。彼は二度墜落し、友人のメルモスは別の墜落事故で死んだ。このような危険と、それを乗り越える高揚した気分は、かれの書物の主題となった。そのうち、一九三一年に刊行されてかれの名声を確立した『夜間飛行』を含む二冊だけが、小説と呼ばれうるものであった。その他のものは僚友愛と孤独の、砂漠と山岳とエキゾティクな情景の、さらには、今までの世代の作家が誰も見たことのなかった雲の上の地上にはない風景の回想であった。
第二次世界大戦は、サン=テグジュペリに、祖国のために飛ぶ機会を与えた。一九四〇年の敗北のあと、かれはニューヨークに赴き、そこで二年以上を執筆と焦燥を癒すのに費した。連合軍が北アフリカに上陸するとともに、かれは戦闘に戻る機会を摑んだ。年をとりすぎ、また以前の負傷のために身体が固くなって、かれは助けなしには操縦席につけなかったが、それでも上官が渋々許した割当て以上の任務につくことを主張した。かれは、かれの飛行中隊で誰も押えのきかぬものになった。死に挑戦することだけを考えている人間だけがかれと同じくらい頑固になりえたであろう。かれの最期となった飛行は一九四四年六月も末のことであった。それはマルク・ブロックの処刑の六週間後のことであり、またフランスの解放が確定的となったちょうどそのときであった。
サン=テグジュペリの飛行機がコルシカ北方に消えたとき――その機体も彼の遺体も発見されずじまいであった――、かれの死に方は、かれが送った生にふさわしいものに思えた。だが、実際には、かれは、マルタン・デュ・ガールを氷のような恐怖でとらえ、ベルナノスの宗教的信仰を養い、マルローのような人間に自分の勇気を確かめるためにあえて危険に身をさらすことをさせたあの死への耽溺を決して育んでいたのではなかった。サン=テグジュペリにあっては、生命を賭けることは、単に仕事の一部なのであった。かれは、死を美化もしなければ、行動の事歴をそれだけで讃美もしなかった。危険は、充分に遂行される任務に避け難く伴うものにすぎなかった。
自分の職業に対するこの事務的な二十世紀的技術家の態度は、少なくともサン=テグジュペリが自分のものとしていたものだった。だが、それだけのことだとしても、なぜかれはこんなにも危険な職業を選んだのだろうか。飛行機の操縦で彼の心を惹いたものは、それがひき出す特別な精神心的努力、人間の規範をのりこえる諸々の可能性であった。ベルナノスにとってと同様かれにとっても、人類の凡庸さなどはほとんど存在しなかった「人間は、こねまわして形をつくるべき蠟の塊りにすぎなかった」。たとえ残酷な犠牲を払っても、「この死んだ素材に魂を与え、意志力を注入すべき」なのであった。そこで、サン=テグジュペリは、かれの上官のドーラについて書いた。それは『夜間飛行』の実際の主人公であり、新しい飛行勤務の必要を人間性に優先させ、パイロットに悪天候下の飛行を命ずることで死に送りこむのを義務と心得る人物であった。同じ尊敬の心をもって、サン=テグジュペリは、アンデス山脈の高地に不時着した友人のギョーメが、ついに救助されて救助隊員に「誓っていうが、ぼくがやってきたことはどんな動物だってやれやしないよ」と語るまで、五日四晩雪と氷とどのように闘ったかを物語った――かれは、この言葉を今まで聞いた「もっとも気高い文章」と考えたのである。」スチュアート・ヒューズ『ふさがれた道 失意の時代のフランス社会思想 1930-1960』荒川幾男・生松敬三訳、1970.みすず書房 pp.88-90.
二十世紀の新しいヒーローは、書斎に籠った蒼白い読書家ではなく、誰よりも行動的な冒険家であり、同時に時代に対して明確な思想的スタンスを貫き、美しい言葉を紡ぎ出す無垢な精神をもった文筆家でもあるような人間だった。だとすれば、二一世紀のヒーローは、どのような人間なのか?

B.立憲的改憲論のひとつの視点
安倍政権がここぞと実現を賭ける憲法の改悪に、日本国民はどう対処するのか?彼らが最終的に目指していることは分かっている。現行憲法は敗戦日本を占領したアメリカに押しつけられた不本意な憲法で、独立国としての主権の根拠のひとつである軍事力を9条の規定によって否定されている。それを朝鮮戦争で米軍が動きやすいように、日本も自衛権はあるという論理で「軍隊ではない自衛隊」を作った。これは再軍備だという声を抑えるために、憲法解釈を「日本の領土防衛」に限定するという理屈で凌いできた。幸い戦後70年、日本は戦争の当事国にならなかったし、自衛隊が戦争をすることもなかった。しかしそれは日本に武力攻撃をかける可能性のある国、たとえばソ連や北朝鮮が冒険を犯さない国際的な条件がなんとか機能しただけで、なによりも米軍の駐留と「核の傘」があったからだ、という見方を80%否定はできない。しかし、それで今の憲法を変えるやむをえぬ必要があるかといえば、ぼくはどう考えてもないと思う。
専守防衛と日米同盟は定着した環境で、自衛隊をなくせという意見はごく少数にとどまる。9条の規定との論理的な整合性は、かなり怪しいと分かった上で、日本が米軍と一体化して世界の紛争に軍事的介入を行なうことなど、それこそ初めから想定外だった。それをやったら、自衛隊が存立する前提条件が崩壊してしまう。しかし、それを集団的自衛権を認める安保法制の解釈改憲で、安倍政権は踏み破ってしまった。このことの意味を多くの日本国民は、理解していない。すでに世界有数の軍事力を有する自衛隊を、こんどこそ改憲によって安倍政権は交戦権を発揮する日本軍に変えようと願っている。その理念は「美しい国、輝かしい国ニッポン!」を回復するのだと意気込み、君主国家大日本帝国をもう一度出現させたいのだろう。それはあまりに歴史と時間を逆戻しする無茶な妄想である。
「解釈の歪曲 止めるために:立憲的改憲論 中島 岳志
安倍内閣の最大の問題は、先人たちが共有してきた慣習や常識を平気で破ることである。安倍内閣は、内閣法制局長官について政権の意向に沿った人事を行い、集団的自衛権を認める解釈改憲を行なった。憲法五三条の要件を満たしているにもかかわらず、強引な解釈によって臨時国会召集要求を無視した。これらは明文化されずとも「やってはいけないこと」と認識されてきた。政治家たちは慣習への信頼を共有してきた。
日本国憲法はかなり短く、解釈の余地が大きい。だから、成文化されない部分は、年月をかけて確認されてきた解釈の蓄積を重視してきた。憲法の短さを不文律の合意や慣習によって保管してきたのである。
現政権は、歴史の風雪に耐えてきた解釈の体系を強引に変えてしまう。共有されてきたルールを守らない。慣習を重んじるはずの保守派が、平気で慣習をないがしろにする。過去の蓄積に対する畏敬の念を欠如させている。
このような政治の劣化に対応するためには、何をなすべきか。どうすれば慣習破壊の暴走を食い止められるのか。
真剣に検討しなければならないのが、「長い憲法」への漸進的移行である。これまで不文律の合意として共有してきたものを、しっかりと成文化し、明確な歯止めをかける。日本はもうその段階にきているのではないか。
この点で、山尾志桜里・衆議院議員が提起する「立憲的改憲」論は重要な意味を持っている。「立憲的憲法改正のスタートラインとは」(WEB RONZA 2017年12月26日)で山尾が問題視するのは、日本国憲法の「規律密度」の低さである。日本国憲法は分量が短いため、歯止め機能が不十分である。そのため「その行間を埋めてきた憲法解釈を逆手にとって解釈を恣意的に歪曲するタイプの政権に対して、その統制力が弱い」。だから規律密度を高める改正が必要である。
山尾が提起するのは、個別的自衛権を明文化し、その範囲を限定する憲法改正だ。集団的自衛権は認めない。「国会・内閣・司法、さらには財政面からなどのコントロール」を検討し、憲法による自衛権の制限を明確にする。さらに、憲法裁判所を設置し、恣意的憲法解釈を是正する手段を確保する。
このような改正は、安倍内閣が進めようとしている「自衛隊明記」とは根本的に異なる。安倍改憲は「歯止めなき自衛権の根拠規定を憲法に新設すること」であり、断じて認められない。「憲法による自衛権統制規範力をゼロにするものであって、グロテスクな『最悪の憲法改悪』として拒絶する。
この議論に賛意を示すのが、伊勢崎賢治である。彼は安倍改憲を批判するとともに、護憲派のごまかしについてもメスを入れる。「憲法9条を先進的だと思ってる日本人が、根本的に誤解していること」(WEB現代ビジネス2月6日)では、護憲のための解釈改憲を厳しく批判する。
現状において、個別的自衛権は憲法上、認められている。日本は他国からの攻撃に対して応戦する権利を有している。この自衛権の行使は、戦争にほかならない。
戦争では、国際人道法違反としての「戦争犯罪」が生じることを想定しなければならない。しかし、日本には戦争犯罪を扱う法体系が整備されていない。「自らが侵す戦争犯罪への対処を、想定すらしない」
なぜか、それは、自衛隊を軍隊と見なしてこなかったからだ。軍隊でない以上、軍司法制度は必要ない。そう見なされてきた。
この重大な瑕疵こそ非人道的であると、伊勢崎は主張する。日本はジブチに自衛隊を駐留させ、地位協定を結んでいる。自衛隊が公務内外で起こす事故について、その裁判権をジブチ政府に放棄させている。にもかからわず、過失を扱う法整備がなされていない。「これは詐欺である。極めて、非人道的な詐欺である」
なぜこんなことが放置されてきたのか。それは「戦後ずっと、アメリカの軍事的管理下にあったこと」と深くかかわっている。日本は地位協定を一度も改定せず、「世界で唯一、平和時において軍事的主権をアメリカに委ねたままの親米保護国」である。だから、自分たちで軍事的責任を負うことを想定してこなかった。この対米従属こそ、非人道的な「詐欺」に無頓着な状況を産み出している。
対米追随を強化すると同時に、立憲主義や不文律のルールをないがしろにする安倍内閣は、どう考えても危険である。国民による歯止めをかけるためには、立憲的改憲と地位協定改定をしっかりと議論の俎上にのせるべきではないか。「護憲」対「改憲」というイデオロギー化した二分法を超えた議論が求められている。(なかじま・たけし=東京工業大教授)」東京新聞2018年2月26日夕刊、4面論壇時評。
まあ、日本国憲法の保証する言論の自由、思想信仰の自由を享受する有り難さを身に染みて感じながら、精強な日本軍を持って他国に宣戦布告をできる権利をもちたいと願望する政治家は、とにかくここで一度憲法を変えてしまえば、後は一気呵成に天皇制国家を復活させることができると、着々と国民投票の準備をしている。しかし、安倍的ナショナリズムは基本的な矛盾を抱えていて、日本の独立した国家主権を追求するといいながら、政治的・軍事的な意思決定はすべて米軍の意のままで、日本のどこかで米軍の事故が起きても、自前の調査も捜査もできないお粗末な状況にある。かれらの考える「国家の独立」の中身は、昭和戦前のゾンビのような皇国思想と、最後の頼みの綱アメリカへの忠誠従属のセット以外は考えていない。そんなの独立でも自立でも何でもない。
しかし、とにかく後生大事に「平和憲法を守れ!」という護憲派の旧来の主張だけではもう、改憲の動きは押しとどめるのは難しい。むしろ憲法を真剣に議論し、あるべき日本国の姿を描くのなら、積極的な対案を出して国民投票を安倍政権の意図を逆手にとって、二度と大日本帝国を理想とするような奴隷的改憲を二度と立ち上がれないほどに国民投票で否定し、同時に現行憲法の不備、新たな理想を国家指導者に要求するような改憲案を出すことも必要かもしれない、と思った。
「星の王子さま」Le Petit Princeは、フランスの飛行家にして作家サン=テグジュペリ(Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, comte de Saint-Exupéry、1900年6月 - 1944年7月)の書いた小説。第二次世界大戦中の1943年にフランス語で書かれ、アメリカで出版された。挿絵も作者が描いている。2015年現在、初版以来、200以上の国と地域の言葉に翻訳され、世界中で総販売部数1億5千万冊を超えたロングベストセラーである。砂漠、星、宇宙、そして飛行機。
宮崎駿の「紅の豚」というアニメ作品があるが、飛行機という乗り物が現われてしばらく、空を飛び回る飛行機乗りは、いつ死んでもおかしくないほど危なっかしい、それ故に大いなる冒険とロマンに満ちた仕事だったことがよく解る。その英雄のような男が、夢のような小説を書いたのだから、これに魅了される読者は世界中にいるだろうし、日本でも何度か「星の王子さま」のブームが起き、亡くなった三遊亭円楽師匠は自ら「星の王子さま」を自称した。
物語の中の少年王子は、いろんな星を経めぐり、愚かな人々を眺めて最後に地球に来て砂漠に墜落した飛行士と出会う。大人でありながら少年の無垢で理想的な心を強く印象づけられ、気がつくと王子はまたどこかの星に向かって消えている。この寓意に満ちた世界は、日本の東北にいた宮沢賢治(1896年8月 - 1933年9月)とも通底するファンタジー・ロマンではないか。サン=テグジュペリより少し年上の宮沢賢治は、飛行機には乗らなかったが、銀河鉄道というアイディアでやはり星に向かう。
「アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリは、しばしば遍歴の騎士と呼ばれた。だが、かれが騎士道的理想を生きたその道は、あくまでも二十世紀そのものであった。サン=テグジュペリとともに、われわれは新しい経験世界を見出す。これまでにわれわれが考察してきた人びとはみな、第一次世界大戦が勃発したときもう成熟した人であった。かれらが作品を発表し名声をえた時代は戦後であったが、彼らの精神は、それに先立つ長い平和の間に形成された。そして、かれらは、かれらが投げ込まれた激動の時代をあくまで異常なものと考えた。サン=テグジュペリとかれよりさらに若いものたちの場合は、その激動は、与えられた人間の条件と思われた。過去への郷愁など問題ではなかった。いまや問題は、破滅から救いうる人間的価値があれば何であれ、救い上げ、定義しなおすことであった。
サン=テグジュペリは、ベルナノスよりもわずか十二歳年下であったが――かれは一九〇〇年に生れた――、ちがった精神的世代に属していた。つまり、従軍経験をもつには若すぎたものたちの世代である。もう一歳か二歳年をとっていたら、サン=テグジュペリは、おそらく欣然と兵役に志願していたであろう。彼の祖先は貴族であった。かれは、カトリックの優秀校で、男らしさと自己鍛錬の高潔な考え方をもつように教育された。そして、信仰は失ったものの、その宗教教育から明らかにキリスト教に発する英雄主義の理想をもちつづけた。かれのはじめの志望はフランス海軍兵学校に入ることだった。それから、その入学試験に失敗して、建築の勉強をはじめた――それは一時的な興味ではあったが、かれの思想に消えぬ痕跡を残したものであった。一九二〇年代のはじめに、かれは飛行機操縦をはじめた。これにかれは自分に一番適した職業を見出した。そして、二十年後の死に至るまで、途中短い間他の職についたが、ずっと飛行士であった。
サン=テグジュペリが商業飛行士になったとき、飛行機はまだ日常茶飯のものではなかった。実際、かれや仲間たちがパイロットになることを選ぶことは、ブルジョワ社会の安穏と退屈から脱出することであった。かれらは必然的にパイオニア、冒険家であり、後の世代が当たり前のことと考えている航空路を、はじめて設定したひとびとであった。はじめ西部アフリカで、のちには南アメリカで、サン=テグジュペリは、日々の仕事として生命を賭けた。彼は二度墜落し、友人のメルモスは別の墜落事故で死んだ。このような危険と、それを乗り越える高揚した気分は、かれの書物の主題となった。そのうち、一九三一年に刊行されてかれの名声を確立した『夜間飛行』を含む二冊だけが、小説と呼ばれうるものであった。その他のものは僚友愛と孤独の、砂漠と山岳とエキゾティクな情景の、さらには、今までの世代の作家が誰も見たことのなかった雲の上の地上にはない風景の回想であった。
第二次世界大戦は、サン=テグジュペリに、祖国のために飛ぶ機会を与えた。一九四〇年の敗北のあと、かれはニューヨークに赴き、そこで二年以上を執筆と焦燥を癒すのに費した。連合軍が北アフリカに上陸するとともに、かれは戦闘に戻る機会を摑んだ。年をとりすぎ、また以前の負傷のために身体が固くなって、かれは助けなしには操縦席につけなかったが、それでも上官が渋々許した割当て以上の任務につくことを主張した。かれは、かれの飛行中隊で誰も押えのきかぬものになった。死に挑戦することだけを考えている人間だけがかれと同じくらい頑固になりえたであろう。かれの最期となった飛行は一九四四年六月も末のことであった。それはマルク・ブロックの処刑の六週間後のことであり、またフランスの解放が確定的となったちょうどそのときであった。
サン=テグジュペリの飛行機がコルシカ北方に消えたとき――その機体も彼の遺体も発見されずじまいであった――、かれの死に方は、かれが送った生にふさわしいものに思えた。だが、実際には、かれは、マルタン・デュ・ガールを氷のような恐怖でとらえ、ベルナノスの宗教的信仰を養い、マルローのような人間に自分の勇気を確かめるためにあえて危険に身をさらすことをさせたあの死への耽溺を決して育んでいたのではなかった。サン=テグジュペリにあっては、生命を賭けることは、単に仕事の一部なのであった。かれは、死を美化もしなければ、行動の事歴をそれだけで讃美もしなかった。危険は、充分に遂行される任務に避け難く伴うものにすぎなかった。
自分の職業に対するこの事務的な二十世紀的技術家の態度は、少なくともサン=テグジュペリが自分のものとしていたものだった。だが、それだけのことだとしても、なぜかれはこんなにも危険な職業を選んだのだろうか。飛行機の操縦で彼の心を惹いたものは、それがひき出す特別な精神心的努力、人間の規範をのりこえる諸々の可能性であった。ベルナノスにとってと同様かれにとっても、人類の凡庸さなどはほとんど存在しなかった「人間は、こねまわして形をつくるべき蠟の塊りにすぎなかった」。たとえ残酷な犠牲を払っても、「この死んだ素材に魂を与え、意志力を注入すべき」なのであった。そこで、サン=テグジュペリは、かれの上官のドーラについて書いた。それは『夜間飛行』の実際の主人公であり、新しい飛行勤務の必要を人間性に優先させ、パイロットに悪天候下の飛行を命ずることで死に送りこむのを義務と心得る人物であった。同じ尊敬の心をもって、サン=テグジュペリは、アンデス山脈の高地に不時着した友人のギョーメが、ついに救助されて救助隊員に「誓っていうが、ぼくがやってきたことはどんな動物だってやれやしないよ」と語るまで、五日四晩雪と氷とどのように闘ったかを物語った――かれは、この言葉を今まで聞いた「もっとも気高い文章」と考えたのである。」スチュアート・ヒューズ『ふさがれた道 失意の時代のフランス社会思想 1930-1960』荒川幾男・生松敬三訳、1970.みすず書房 pp.88-90.
二十世紀の新しいヒーローは、書斎に籠った蒼白い読書家ではなく、誰よりも行動的な冒険家であり、同時に時代に対して明確な思想的スタンスを貫き、美しい言葉を紡ぎ出す無垢な精神をもった文筆家でもあるような人間だった。だとすれば、二一世紀のヒーローは、どのような人間なのか?

B.立憲的改憲論のひとつの視点
安倍政権がここぞと実現を賭ける憲法の改悪に、日本国民はどう対処するのか?彼らが最終的に目指していることは分かっている。現行憲法は敗戦日本を占領したアメリカに押しつけられた不本意な憲法で、独立国としての主権の根拠のひとつである軍事力を9条の規定によって否定されている。それを朝鮮戦争で米軍が動きやすいように、日本も自衛権はあるという論理で「軍隊ではない自衛隊」を作った。これは再軍備だという声を抑えるために、憲法解釈を「日本の領土防衛」に限定するという理屈で凌いできた。幸い戦後70年、日本は戦争の当事国にならなかったし、自衛隊が戦争をすることもなかった。しかしそれは日本に武力攻撃をかける可能性のある国、たとえばソ連や北朝鮮が冒険を犯さない国際的な条件がなんとか機能しただけで、なによりも米軍の駐留と「核の傘」があったからだ、という見方を80%否定はできない。しかし、それで今の憲法を変えるやむをえぬ必要があるかといえば、ぼくはどう考えてもないと思う。
専守防衛と日米同盟は定着した環境で、自衛隊をなくせという意見はごく少数にとどまる。9条の規定との論理的な整合性は、かなり怪しいと分かった上で、日本が米軍と一体化して世界の紛争に軍事的介入を行なうことなど、それこそ初めから想定外だった。それをやったら、自衛隊が存立する前提条件が崩壊してしまう。しかし、それを集団的自衛権を認める安保法制の解釈改憲で、安倍政権は踏み破ってしまった。このことの意味を多くの日本国民は、理解していない。すでに世界有数の軍事力を有する自衛隊を、こんどこそ改憲によって安倍政権は交戦権を発揮する日本軍に変えようと願っている。その理念は「美しい国、輝かしい国ニッポン!」を回復するのだと意気込み、君主国家大日本帝国をもう一度出現させたいのだろう。それはあまりに歴史と時間を逆戻しする無茶な妄想である。
「解釈の歪曲 止めるために:立憲的改憲論 中島 岳志
安倍内閣の最大の問題は、先人たちが共有してきた慣習や常識を平気で破ることである。安倍内閣は、内閣法制局長官について政権の意向に沿った人事を行い、集団的自衛権を認める解釈改憲を行なった。憲法五三条の要件を満たしているにもかかわらず、強引な解釈によって臨時国会召集要求を無視した。これらは明文化されずとも「やってはいけないこと」と認識されてきた。政治家たちは慣習への信頼を共有してきた。
日本国憲法はかなり短く、解釈の余地が大きい。だから、成文化されない部分は、年月をかけて確認されてきた解釈の蓄積を重視してきた。憲法の短さを不文律の合意や慣習によって保管してきたのである。
現政権は、歴史の風雪に耐えてきた解釈の体系を強引に変えてしまう。共有されてきたルールを守らない。慣習を重んじるはずの保守派が、平気で慣習をないがしろにする。過去の蓄積に対する畏敬の念を欠如させている。
このような政治の劣化に対応するためには、何をなすべきか。どうすれば慣習破壊の暴走を食い止められるのか。
真剣に検討しなければならないのが、「長い憲法」への漸進的移行である。これまで不文律の合意として共有してきたものを、しっかりと成文化し、明確な歯止めをかける。日本はもうその段階にきているのではないか。
この点で、山尾志桜里・衆議院議員が提起する「立憲的改憲」論は重要な意味を持っている。「立憲的憲法改正のスタートラインとは」(WEB RONZA 2017年12月26日)で山尾が問題視するのは、日本国憲法の「規律密度」の低さである。日本国憲法は分量が短いため、歯止め機能が不十分である。そのため「その行間を埋めてきた憲法解釈を逆手にとって解釈を恣意的に歪曲するタイプの政権に対して、その統制力が弱い」。だから規律密度を高める改正が必要である。
山尾が提起するのは、個別的自衛権を明文化し、その範囲を限定する憲法改正だ。集団的自衛権は認めない。「国会・内閣・司法、さらには財政面からなどのコントロール」を検討し、憲法による自衛権の制限を明確にする。さらに、憲法裁判所を設置し、恣意的憲法解釈を是正する手段を確保する。
このような改正は、安倍内閣が進めようとしている「自衛隊明記」とは根本的に異なる。安倍改憲は「歯止めなき自衛権の根拠規定を憲法に新設すること」であり、断じて認められない。「憲法による自衛権統制規範力をゼロにするものであって、グロテスクな『最悪の憲法改悪』として拒絶する。
この議論に賛意を示すのが、伊勢崎賢治である。彼は安倍改憲を批判するとともに、護憲派のごまかしについてもメスを入れる。「憲法9条を先進的だと思ってる日本人が、根本的に誤解していること」(WEB現代ビジネス2月6日)では、護憲のための解釈改憲を厳しく批判する。
現状において、個別的自衛権は憲法上、認められている。日本は他国からの攻撃に対して応戦する権利を有している。この自衛権の行使は、戦争にほかならない。
戦争では、国際人道法違反としての「戦争犯罪」が生じることを想定しなければならない。しかし、日本には戦争犯罪を扱う法体系が整備されていない。「自らが侵す戦争犯罪への対処を、想定すらしない」
なぜか、それは、自衛隊を軍隊と見なしてこなかったからだ。軍隊でない以上、軍司法制度は必要ない。そう見なされてきた。
この重大な瑕疵こそ非人道的であると、伊勢崎は主張する。日本はジブチに自衛隊を駐留させ、地位協定を結んでいる。自衛隊が公務内外で起こす事故について、その裁判権をジブチ政府に放棄させている。にもかからわず、過失を扱う法整備がなされていない。「これは詐欺である。極めて、非人道的な詐欺である」
なぜこんなことが放置されてきたのか。それは「戦後ずっと、アメリカの軍事的管理下にあったこと」と深くかかわっている。日本は地位協定を一度も改定せず、「世界で唯一、平和時において軍事的主権をアメリカに委ねたままの親米保護国」である。だから、自分たちで軍事的責任を負うことを想定してこなかった。この対米従属こそ、非人道的な「詐欺」に無頓着な状況を産み出している。
対米追随を強化すると同時に、立憲主義や不文律のルールをないがしろにする安倍内閣は、どう考えても危険である。国民による歯止めをかけるためには、立憲的改憲と地位協定改定をしっかりと議論の俎上にのせるべきではないか。「護憲」対「改憲」というイデオロギー化した二分法を超えた議論が求められている。(なかじま・たけし=東京工業大教授)」東京新聞2018年2月26日夕刊、4面論壇時評。
まあ、日本国憲法の保証する言論の自由、思想信仰の自由を享受する有り難さを身に染みて感じながら、精強な日本軍を持って他国に宣戦布告をできる権利をもちたいと願望する政治家は、とにかくここで一度憲法を変えてしまえば、後は一気呵成に天皇制国家を復活させることができると、着々と国民投票の準備をしている。しかし、安倍的ナショナリズムは基本的な矛盾を抱えていて、日本の独立した国家主権を追求するといいながら、政治的・軍事的な意思決定はすべて米軍の意のままで、日本のどこかで米軍の事故が起きても、自前の調査も捜査もできないお粗末な状況にある。かれらの考える「国家の独立」の中身は、昭和戦前のゾンビのような皇国思想と、最後の頼みの綱アメリカへの忠誠従属のセット以外は考えていない。そんなの独立でも自立でも何でもない。
しかし、とにかく後生大事に「平和憲法を守れ!」という護憲派の旧来の主張だけではもう、改憲の動きは押しとどめるのは難しい。むしろ憲法を真剣に議論し、あるべき日本国の姿を描くのなら、積極的な対案を出して国民投票を安倍政権の意図を逆手にとって、二度と大日本帝国を理想とするような奴隷的改憲を二度と立ち上がれないほどに国民投票で否定し、同時に現行憲法の不備、新たな理想を国家指導者に要求するような改憲案を出すことも必要かもしれない、と思った。