A.やや長めのあとがき
大澤真幸氏の『日本史のなぞ』を、こうして読んでみると「日本では革命は不可能である」という結論になるのか、それとも「日本でも革命は可能である」ということを言いたいのか、やはり判然とはしない。それは「革命」とは何か、をしっかり決めておかないと話がおかしくなるので、大澤氏は中国の易姓革命、そして西洋のキリストを範例とする革命に遡って「革命」を論じ、さてその「革命」を日本史にもってくるとどうなるかを考察する。そこでこの本では、鎌倉の北条泰時がやったことは、唯一の「革命」だったと主張しているわけだ。でも、天皇制の継続という点では、承久の乱やその後の鎌倉幕府がやったことを見ても、さほど変化はない。朝廷や公家は京都に存続した。それを継続と見るか、大きな変革と見るかで結論は変わってくる。
天皇制を擁護する日本史家の多くは、北条得宗体制の勝利で武家政権は確立し、朝廷の権力は減衰したものの、天皇を戴く「国のかたち」は継続したと考える。明治以降の日本帝国が、天皇親政による近代的君主国家だと考えるかどうかも問題だが、天皇が存続するかぎり「革命」などは起きていないし、起きることはない、という保守主義の無理がある。これに対して、天皇が存続すれば革命など起きていない、というのではなく、仮に天皇が存続しても革命はありうるのだと、大澤氏は主張したいのだろうか。それとも、1945年の敗戦によりGHQが行った占領改革は、やはり大きな革命に等しく、しかもそれは天皇存続と手を組んで進められたけれども、あそこで「国体」つまり天皇制を廃止する可能性もあった、と考えるのか。いずれにしても、最後の「やや長めのあとがき」を読んでみる。
「どのような社会にも、(不)可能性の臨界のようなものがある。その先を超えていくことができない、と暗黙のうちに想定されている境界線が、である。この境界線が維持されていることを前提にして、社会内のすべての活動がなされている。
しかし、ときに、その(不)可能性の臨界の内部では、社会が直面している基本的な困難を克服できなくなることがある。このとき、(不)可能性の臨界の向こう側に出ていき、臨界を設定するような変動を社会に引き起こすこと、これが革命である。つまり、普通の改革なのか、革命なのかを分かつ条件は、引き起こされる変化が、(不)可能性の臨界の内側にとどまるものなのか、それともその臨界を超えていくものなのか、である。
この臨界との関係で、社会には〈つぼ〉のようなものがある。それは、一見、社会の中の局所的な一点、ごく部分的なイシューであるかのような印象を与える。つまり、それは、ただの改革にかかわる案件に見える。しかし、そこを執拗に、妥協することなく刺激することは、結局、(不)可能性の臨界を動かすことにつながる。これが、社会の〈つぼ〉である。したがって、もし革命なるものがあるとすれば、それは、この〈つぼ〉への攻撃として始まる。
このように革命を捉えたとき、現代の日本社会に関して言えば、革命は十分に合法性の枠内で可能なはずである。つまり、現代の日本人は、「革命」という語で、非合法的な暴力活動のようなものを想像する必要はない。合法的な活動の積み重ねを通じて、ある種の〈暴力〉――ヴァルター・ベンヤミンが「神的」と形容したような暴力――に相当する効果をもたらすことができるのだ。なぜなら、(不)可能性の臨界は、法が形式的に許容している限界よりもはるかに手前にあるからである。
(不)可能性の臨界とは何か。まず比喩によって解説しておこう。結婚式における宣誓、何かの会への加入式、裁判で証言するときの宣誓のようなものを考えるとよい。これらは、すべて、いわゆるイニシエーションである。たとえば結婚式で、花婿(花嫁)であるあなたは、死が二人を分かつまで花嫁(花婿)を愛し続けるか、といった趣旨のことを問われる。問われている以上は、あなたには選択の自由がある。「イエス」か「ノー」か。どちらの返答も形式的には可能だ。が、しかし、もしあなたが、ここで(もしかしたら正直に)「ノー」の方を選択したとしたら、どうなるか。あなたが、「それほど長く愛し続けると確約することはできない」と答えたら、どうなるだろうか。結婚式は騒然とし、台無しになるだろう。つまり、あなたには「ノー」と答えることは、事実上、不可能なのだ。もっと厳密には、次のように言うべきである。あなたには、「イエス」と「ノー」のどちらをとる自由もある。ただし、絶対に「ノー」の方をとらない限りで。
これが、(不)可能性の臨界である。形式的には可能だが、実質的には不可能な選択を前提にして、すべてのことがなされる。結婚式では、あなたが、あの質問に「ノー」とは答えずに「イエス」と答えた、ということを起点にして、すべて進行する。繰り返し強調しておくが、このとき、(実質的に)不可能な(こととされている)ことは、(形式的には)可能だということが重要だ。もしあなたが。物理的な暴力によって脅迫されて「イエス」と言っているのだとしたら、あなたの回答はまったく無意味なものになってしまう。あなたには、「ノー」と答える自由があった、という想定が、決定的な前提である。
これと同じようなこと、これと類比的にとらえうることが現実の社会にもある。(不)可能性の臨界は、すべての社会にある。たとえば、世界で最も自由だとされている。アメリカが州国ではどうか。そこで起きてきたことを観察してくれば、すぐにわかる。たとえば、完全な銃規制とか、完全な公的保険(ユニヴァーサル。ヘルスケア)は、アメリカにとって(不)可能性の臨界にふれる〈ツボ〉である。
数々の悲劇的な銃乱射事件があったにもかかわらず、その度に多くの人に求められるにもかかわらず、アメリカ社会は、完全な銃規制をどうしても実現することはできない。一般の個人の銃の所持や使用を厳しく制限することは、アメリカ社会が基本的な前提として保持してきたことを著しく毀損すると、(当のアメリカ人に)感じられてきたからである。
もちろん、形式的には、民主的な家続きを通じて法や制度を改変することで、銃規制も、公的保険も実現できるはずだ。しかし、事実上は、それができない。完全な銃規制や完全な公的保険は、(不)可能性の臨界を動かさないことには実現できないのだ。言い換えれば、それらを実現することは、アメリカ社会にとっては、すでに一種の革命である。
では、日本社会はどうか。日本社会はとりわけ分厚い(不)可能性の臨界によって囲われている。日本人の日常語を用いるならば、それは「空気」という形態をとっている。つまり、一億人のスケールの「空気」があって、日本社会に、いくつもの(不)可能性の臨界を設定しているのだ。
中でも最も重要で、手強い臨界は、日米関係である。1945年の敗戦によって規定された、日米関係の型は、日本人にとって、乗り越えられない前提条件と受けとられてきた。言うまでもなく、この日米関係の型を直接的に表しているのは、日米安全保障条約、つまり日米の(非対称の)軍事同盟だ。
日米同盟は、しかし、外交や安全保障の領域に限定された主題ではない。それは、日本人の精神に深く浸透し、ときに内政に関わる決定にも影響を与える。つまり、政治的であると同時に精神的な対米従属は、現代の日本人に対して、(不)可能性の臨界を構成する。はっきり言おう。日本の首相の意志よりも、アメリカの政府高官や政治指導者の意向の方が、ときに、内政を含む日本の政治的決定を強く規定する、と。首相が望んでいても、実現できないことはたくさんある。しかし、アメリカの政府高官や国務省の、あるいはペンタゴンの――日本についての――強い意向(と日本人が想定していること)であれば、たいてい実現する。大多数の日本人の意志や願望に反していても、それは、実現するだろう。
その端的な証拠は、2009年の鳩山民主党政権のときの、普天間基地移設問題である。圧倒的に高い支持率で首相の座に就いた鳩山由紀夫氏は、普天間基地の「最低でも県外移設」を公約としていた。この公約は、沖縄ではもちろんのこと、日本全国で広く賛同を得ていたはずだ。しかし、鳩山首相は、米軍基地を視察したたった一日で、県外移設を断念してしまったのだ。首相は、もちろん、その稚拙な外交について国民から厳しく非難され、これが彼の早期の退陣につながったわけだが、驚くべきことは、一国の首相に対する、アメリカのこれほど露骨な内政干渉に対して、日本人は大した違和感を抱かず、この点を問題にした者はほとんどいなかった、ということである。自国の首相よりも、アメリカに対してもっと怒ってもよい状況だったのに、そうはならなかった(以下を参照。白井聡『永続敗戦論』太田出版)。アメリカの意向――しかもこのケースでは大統領や国務長官が出てきたわけではないのに――に反することができない、ということは、日本人にとって、ほとんど自覚さえされない前提になっていたのだ。
ここで留意しなくてはならないことは、日米関係という(不)可能性の臨界は、日本人にとってのみ、存在しているということである。アメリカにとっては、安保条約を核にした日米関係は、戦略的な選択肢のひとつであって、状況によって、柔軟に運用したり、改変したり、破棄したりできることである。
しかし、日本にとっては違う。もちろん、形式的には、主権国家の間の条約なのだから、日本は、それを破棄することだってできる。しかし、事実上は、日米の(非対称的な)同盟から離脱することはできない、離脱するわけにはいかない、ということを不動の前提にして、日本の政治的な意思決定はなされている。
もちろん、たまには、「日米安保破棄」を唱える政治家や政党もいる。しかし、このような政治家や政党も、ほんとうに安保条約を破棄できるとは思っていないのではないか。言い換えれば、絶対に破棄されないとわかっているからこそ、彼らは、安心して、破棄を主張しているのではないか。そのような疑いを持つ根拠がある。安保条約をほんとうに破棄するつもりならば、対米依存を前提にしてできている制度や法をどうするのかまでも示さなくてはならない。誰もが気づいているように、日米安保条約と日本国憲法(九条)は車の両輪のような関係にある。安保条約についての提案は、少なくとも、憲法についての提案とセットになって、はじめて、本気であるとみなされる。しかし、安保条約破棄を唱えても、そこまでの広がりをもって考え抜いている人は、ほとんどいない(念のために書いておけば、私は、九条を廃棄しても対米従属が解消されるとは思っていない。むしろ逆だと考えている。私の憲法についての考えは、以下を参照されたい。『憲法九条とわれらが日本』筑摩書房)。
もう一度、あの結婚式の比喩にもどろう。新郎新婦が絶対に「ノー」と答えないということを条件にして、われわれは、彼らには「ノー」と答える権利もあった、と主張する。同じように、日米安保条約が破棄されることはないということを前提にして、これに反対している人がいるのだ。
いずれにせよ、日米関係は、日本社会を取り囲む(不)可能性の臨界のひとつでしかない。ほかにも、いくつもの臨界がある。
本書によって私が示唆したかったこと、それは、日本社会は(何であれ)この種の(不)可能性の臨界を超えていくことができる、ということである。このような意味での革命は可能なのだ。私はこのことを、日本史についての「なぞ」を解くことを通じて、例示してきたつもりだ。
その際、私が重視したことは、歴史的な事実そのものではない。その事実を貫いている論理である。事実を見ている間は、われわれはこう思うだけである。「そういう立派な人もいたんだね(私にはできないけど)」と。しかし、論理を見出したときには違う。論理は、さまざまな状況に応じて具体化し、受肉することができる。本書で抽出した論理は、現在に適合した形で受肉することもできるはずだ。つまり、われわれの困難の源泉になっている(不)可能性の臨界を超え出ていくための方法として、これを具体化することができるはずだ(なお、現代日本社会における、「革命」の可能性の探索という主題については、以下の拙著をも参照されたい。『可能なる革命』太田出版)。
社会学的な主題としては、私は、「革命の比較社会学」という構想を抱いている。本書は、この構想へと向けた最初の一歩でもある。」大澤真幸『日本史のなぞ なぜこの国で一度だけ革命が成功したのか』朝日選書、2016年。pp.187-195.
1945年に天皇制という「国体」は史上最大の危機に瀕した。そしてそれを形式だけ存続させたのはアメリカだった。アメリカのもとで戦後の「革命」は進められたので、それ以後現在まで、アメリカが天皇の位置に座っていることを、日本人は無意識に、あるいは居心地悪いが仕方なく、認めているということになる。

B.高齢者の自殺
ぼくも十分高齢者になっているので、自殺する高齢者の心境がわかる、とはいえない。同じ時代を生きてきたとはいえ、人の生きる条件や個人としての意識、体力、そして人間関係は一人ひとり、みな違うからだ。自殺という行為も、その中身はみんな違うはずだ。ただ、放置してよいはずはない。
「健康まっぷ 「社会的孤立」がリスク高める 「共食」推進 つながる育む
家族やご近所、友人など他社との接触がほとんどない「社会的孤立」は、健康をむしばむ要因となる。高齢者では、他者とのつながりの乏しさが自殺のリスクを高めるという研究結果を、斉藤雅茂日本福祉大教授らのチームが発表した。
チームは2010~11年、愛知県など6道県の12自治体に住む、要介護認定を受けていない高齢者計約4万6千人を対象に「社会とのつながり」を調査。対象者のうち55人がその後、17年までに自殺しており、社会的孤立との関連を分析した。
すると「心配事や愚痴を聞いたり話したりする相手がいない」「病気で数日間寝込んだとき、看病や世話をしてくれる人がいない」「ボランティアなど社会的活動に参加していない」といった状況が自殺のリスクを高めるとの結果が得られた。
特に、食事を1人で取る「孤食」の状態にある人は、そうでない人に比べ自殺のリスクが2・8倍も高かった。日本全体で見ると、孤食が1年間に約1800人の高齢者の自殺に関連している可能性があるという。
4月に始まった政府の健康づくり計画「健康日本21(第3次)」は、誰かと食事を共にする「共食」の推進を掲げる。愛知県豊田市ではボランティアが高齢者宅に昼食を配達し一緒に食べる取り組みが進められている。
斉藤さんは「今回の結果は、共食など他者とのつながりを育める取り組みが自殺対策にも有効であることを示唆している」と話す。」東京新聞2024年6月19日夕刊2面。
「孤独死」は今日もどこかで起きているのだろう。ぼくは、少なくとも孤独を感じる境遇にはない。ほとんど一日、家にいて誰とも会わない日は多いけれども、やりたいことはまだたくさんあり、人とのかかわりが消えているわけではないからだ。これは、健康とともにきわめて恵まれているのかもしれない。
大澤真幸氏の『日本史のなぞ』を、こうして読んでみると「日本では革命は不可能である」という結論になるのか、それとも「日本でも革命は可能である」ということを言いたいのか、やはり判然とはしない。それは「革命」とは何か、をしっかり決めておかないと話がおかしくなるので、大澤氏は中国の易姓革命、そして西洋のキリストを範例とする革命に遡って「革命」を論じ、さてその「革命」を日本史にもってくるとどうなるかを考察する。そこでこの本では、鎌倉の北条泰時がやったことは、唯一の「革命」だったと主張しているわけだ。でも、天皇制の継続という点では、承久の乱やその後の鎌倉幕府がやったことを見ても、さほど変化はない。朝廷や公家は京都に存続した。それを継続と見るか、大きな変革と見るかで結論は変わってくる。
天皇制を擁護する日本史家の多くは、北条得宗体制の勝利で武家政権は確立し、朝廷の権力は減衰したものの、天皇を戴く「国のかたち」は継続したと考える。明治以降の日本帝国が、天皇親政による近代的君主国家だと考えるかどうかも問題だが、天皇が存続するかぎり「革命」などは起きていないし、起きることはない、という保守主義の無理がある。これに対して、天皇が存続すれば革命など起きていない、というのではなく、仮に天皇が存続しても革命はありうるのだと、大澤氏は主張したいのだろうか。それとも、1945年の敗戦によりGHQが行った占領改革は、やはり大きな革命に等しく、しかもそれは天皇存続と手を組んで進められたけれども、あそこで「国体」つまり天皇制を廃止する可能性もあった、と考えるのか。いずれにしても、最後の「やや長めのあとがき」を読んでみる。
「どのような社会にも、(不)可能性の臨界のようなものがある。その先を超えていくことができない、と暗黙のうちに想定されている境界線が、である。この境界線が維持されていることを前提にして、社会内のすべての活動がなされている。
しかし、ときに、その(不)可能性の臨界の内部では、社会が直面している基本的な困難を克服できなくなることがある。このとき、(不)可能性の臨界の向こう側に出ていき、臨界を設定するような変動を社会に引き起こすこと、これが革命である。つまり、普通の改革なのか、革命なのかを分かつ条件は、引き起こされる変化が、(不)可能性の臨界の内側にとどまるものなのか、それともその臨界を超えていくものなのか、である。
この臨界との関係で、社会には〈つぼ〉のようなものがある。それは、一見、社会の中の局所的な一点、ごく部分的なイシューであるかのような印象を与える。つまり、それは、ただの改革にかかわる案件に見える。しかし、そこを執拗に、妥協することなく刺激することは、結局、(不)可能性の臨界を動かすことにつながる。これが、社会の〈つぼ〉である。したがって、もし革命なるものがあるとすれば、それは、この〈つぼ〉への攻撃として始まる。
このように革命を捉えたとき、現代の日本社会に関して言えば、革命は十分に合法性の枠内で可能なはずである。つまり、現代の日本人は、「革命」という語で、非合法的な暴力活動のようなものを想像する必要はない。合法的な活動の積み重ねを通じて、ある種の〈暴力〉――ヴァルター・ベンヤミンが「神的」と形容したような暴力――に相当する効果をもたらすことができるのだ。なぜなら、(不)可能性の臨界は、法が形式的に許容している限界よりもはるかに手前にあるからである。
(不)可能性の臨界とは何か。まず比喩によって解説しておこう。結婚式における宣誓、何かの会への加入式、裁判で証言するときの宣誓のようなものを考えるとよい。これらは、すべて、いわゆるイニシエーションである。たとえば結婚式で、花婿(花嫁)であるあなたは、死が二人を分かつまで花嫁(花婿)を愛し続けるか、といった趣旨のことを問われる。問われている以上は、あなたには選択の自由がある。「イエス」か「ノー」か。どちらの返答も形式的には可能だ。が、しかし、もしあなたが、ここで(もしかしたら正直に)「ノー」の方を選択したとしたら、どうなるか。あなたが、「それほど長く愛し続けると確約することはできない」と答えたら、どうなるだろうか。結婚式は騒然とし、台無しになるだろう。つまり、あなたには「ノー」と答えることは、事実上、不可能なのだ。もっと厳密には、次のように言うべきである。あなたには、「イエス」と「ノー」のどちらをとる自由もある。ただし、絶対に「ノー」の方をとらない限りで。
これが、(不)可能性の臨界である。形式的には可能だが、実質的には不可能な選択を前提にして、すべてのことがなされる。結婚式では、あなたが、あの質問に「ノー」とは答えずに「イエス」と答えた、ということを起点にして、すべて進行する。繰り返し強調しておくが、このとき、(実質的に)不可能な(こととされている)ことは、(形式的には)可能だということが重要だ。もしあなたが。物理的な暴力によって脅迫されて「イエス」と言っているのだとしたら、あなたの回答はまったく無意味なものになってしまう。あなたには、「ノー」と答える自由があった、という想定が、決定的な前提である。
これと同じようなこと、これと類比的にとらえうることが現実の社会にもある。(不)可能性の臨界は、すべての社会にある。たとえば、世界で最も自由だとされている。アメリカが州国ではどうか。そこで起きてきたことを観察してくれば、すぐにわかる。たとえば、完全な銃規制とか、完全な公的保険(ユニヴァーサル。ヘルスケア)は、アメリカにとって(不)可能性の臨界にふれる〈ツボ〉である。
数々の悲劇的な銃乱射事件があったにもかかわらず、その度に多くの人に求められるにもかかわらず、アメリカ社会は、完全な銃規制をどうしても実現することはできない。一般の個人の銃の所持や使用を厳しく制限することは、アメリカ社会が基本的な前提として保持してきたことを著しく毀損すると、(当のアメリカ人に)感じられてきたからである。
もちろん、形式的には、民主的な家続きを通じて法や制度を改変することで、銃規制も、公的保険も実現できるはずだ。しかし、事実上は、それができない。完全な銃規制や完全な公的保険は、(不)可能性の臨界を動かさないことには実現できないのだ。言い換えれば、それらを実現することは、アメリカ社会にとっては、すでに一種の革命である。
では、日本社会はどうか。日本社会はとりわけ分厚い(不)可能性の臨界によって囲われている。日本人の日常語を用いるならば、それは「空気」という形態をとっている。つまり、一億人のスケールの「空気」があって、日本社会に、いくつもの(不)可能性の臨界を設定しているのだ。
中でも最も重要で、手強い臨界は、日米関係である。1945年の敗戦によって規定された、日米関係の型は、日本人にとって、乗り越えられない前提条件と受けとられてきた。言うまでもなく、この日米関係の型を直接的に表しているのは、日米安全保障条約、つまり日米の(非対称の)軍事同盟だ。
日米同盟は、しかし、外交や安全保障の領域に限定された主題ではない。それは、日本人の精神に深く浸透し、ときに内政に関わる決定にも影響を与える。つまり、政治的であると同時に精神的な対米従属は、現代の日本人に対して、(不)可能性の臨界を構成する。はっきり言おう。日本の首相の意志よりも、アメリカの政府高官や政治指導者の意向の方が、ときに、内政を含む日本の政治的決定を強く規定する、と。首相が望んでいても、実現できないことはたくさんある。しかし、アメリカの政府高官や国務省の、あるいはペンタゴンの――日本についての――強い意向(と日本人が想定していること)であれば、たいてい実現する。大多数の日本人の意志や願望に反していても、それは、実現するだろう。
その端的な証拠は、2009年の鳩山民主党政権のときの、普天間基地移設問題である。圧倒的に高い支持率で首相の座に就いた鳩山由紀夫氏は、普天間基地の「最低でも県外移設」を公約としていた。この公約は、沖縄ではもちろんのこと、日本全国で広く賛同を得ていたはずだ。しかし、鳩山首相は、米軍基地を視察したたった一日で、県外移設を断念してしまったのだ。首相は、もちろん、その稚拙な外交について国民から厳しく非難され、これが彼の早期の退陣につながったわけだが、驚くべきことは、一国の首相に対する、アメリカのこれほど露骨な内政干渉に対して、日本人は大した違和感を抱かず、この点を問題にした者はほとんどいなかった、ということである。自国の首相よりも、アメリカに対してもっと怒ってもよい状況だったのに、そうはならなかった(以下を参照。白井聡『永続敗戦論』太田出版)。アメリカの意向――しかもこのケースでは大統領や国務長官が出てきたわけではないのに――に反することができない、ということは、日本人にとって、ほとんど自覚さえされない前提になっていたのだ。
ここで留意しなくてはならないことは、日米関係という(不)可能性の臨界は、日本人にとってのみ、存在しているということである。アメリカにとっては、安保条約を核にした日米関係は、戦略的な選択肢のひとつであって、状況によって、柔軟に運用したり、改変したり、破棄したりできることである。
しかし、日本にとっては違う。もちろん、形式的には、主権国家の間の条約なのだから、日本は、それを破棄することだってできる。しかし、事実上は、日米の(非対称的な)同盟から離脱することはできない、離脱するわけにはいかない、ということを不動の前提にして、日本の政治的な意思決定はなされている。
もちろん、たまには、「日米安保破棄」を唱える政治家や政党もいる。しかし、このような政治家や政党も、ほんとうに安保条約を破棄できるとは思っていないのではないか。言い換えれば、絶対に破棄されないとわかっているからこそ、彼らは、安心して、破棄を主張しているのではないか。そのような疑いを持つ根拠がある。安保条約をほんとうに破棄するつもりならば、対米依存を前提にしてできている制度や法をどうするのかまでも示さなくてはならない。誰もが気づいているように、日米安保条約と日本国憲法(九条)は車の両輪のような関係にある。安保条約についての提案は、少なくとも、憲法についての提案とセットになって、はじめて、本気であるとみなされる。しかし、安保条約破棄を唱えても、そこまでの広がりをもって考え抜いている人は、ほとんどいない(念のために書いておけば、私は、九条を廃棄しても対米従属が解消されるとは思っていない。むしろ逆だと考えている。私の憲法についての考えは、以下を参照されたい。『憲法九条とわれらが日本』筑摩書房)。
もう一度、あの結婚式の比喩にもどろう。新郎新婦が絶対に「ノー」と答えないということを条件にして、われわれは、彼らには「ノー」と答える権利もあった、と主張する。同じように、日米安保条約が破棄されることはないということを前提にして、これに反対している人がいるのだ。
いずれにせよ、日米関係は、日本社会を取り囲む(不)可能性の臨界のひとつでしかない。ほかにも、いくつもの臨界がある。
本書によって私が示唆したかったこと、それは、日本社会は(何であれ)この種の(不)可能性の臨界を超えていくことができる、ということである。このような意味での革命は可能なのだ。私はこのことを、日本史についての「なぞ」を解くことを通じて、例示してきたつもりだ。
その際、私が重視したことは、歴史的な事実そのものではない。その事実を貫いている論理である。事実を見ている間は、われわれはこう思うだけである。「そういう立派な人もいたんだね(私にはできないけど)」と。しかし、論理を見出したときには違う。論理は、さまざまな状況に応じて具体化し、受肉することができる。本書で抽出した論理は、現在に適合した形で受肉することもできるはずだ。つまり、われわれの困難の源泉になっている(不)可能性の臨界を超え出ていくための方法として、これを具体化することができるはずだ(なお、現代日本社会における、「革命」の可能性の探索という主題については、以下の拙著をも参照されたい。『可能なる革命』太田出版)。
社会学的な主題としては、私は、「革命の比較社会学」という構想を抱いている。本書は、この構想へと向けた最初の一歩でもある。」大澤真幸『日本史のなぞ なぜこの国で一度だけ革命が成功したのか』朝日選書、2016年。pp.187-195.
1945年に天皇制という「国体」は史上最大の危機に瀕した。そしてそれを形式だけ存続させたのはアメリカだった。アメリカのもとで戦後の「革命」は進められたので、それ以後現在まで、アメリカが天皇の位置に座っていることを、日本人は無意識に、あるいは居心地悪いが仕方なく、認めているということになる。

B.高齢者の自殺
ぼくも十分高齢者になっているので、自殺する高齢者の心境がわかる、とはいえない。同じ時代を生きてきたとはいえ、人の生きる条件や個人としての意識、体力、そして人間関係は一人ひとり、みな違うからだ。自殺という行為も、その中身はみんな違うはずだ。ただ、放置してよいはずはない。
「健康まっぷ 「社会的孤立」がリスク高める 「共食」推進 つながる育む
家族やご近所、友人など他社との接触がほとんどない「社会的孤立」は、健康をむしばむ要因となる。高齢者では、他者とのつながりの乏しさが自殺のリスクを高めるという研究結果を、斉藤雅茂日本福祉大教授らのチームが発表した。
チームは2010~11年、愛知県など6道県の12自治体に住む、要介護認定を受けていない高齢者計約4万6千人を対象に「社会とのつながり」を調査。対象者のうち55人がその後、17年までに自殺しており、社会的孤立との関連を分析した。
すると「心配事や愚痴を聞いたり話したりする相手がいない」「病気で数日間寝込んだとき、看病や世話をしてくれる人がいない」「ボランティアなど社会的活動に参加していない」といった状況が自殺のリスクを高めるとの結果が得られた。
特に、食事を1人で取る「孤食」の状態にある人は、そうでない人に比べ自殺のリスクが2・8倍も高かった。日本全体で見ると、孤食が1年間に約1800人の高齢者の自殺に関連している可能性があるという。
4月に始まった政府の健康づくり計画「健康日本21(第3次)」は、誰かと食事を共にする「共食」の推進を掲げる。愛知県豊田市ではボランティアが高齢者宅に昼食を配達し一緒に食べる取り組みが進められている。
斉藤さんは「今回の結果は、共食など他者とのつながりを育める取り組みが自殺対策にも有効であることを示唆している」と話す。」東京新聞2024年6月19日夕刊2面。
「孤独死」は今日もどこかで起きているのだろう。ぼくは、少なくとも孤独を感じる境遇にはない。ほとんど一日、家にいて誰とも会わない日は多いけれども、やりたいことはまだたくさんあり、人とのかかわりが消えているわけではないからだ。これは、健康とともにきわめて恵まれているのかもしれない。















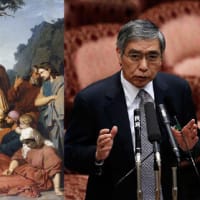










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます