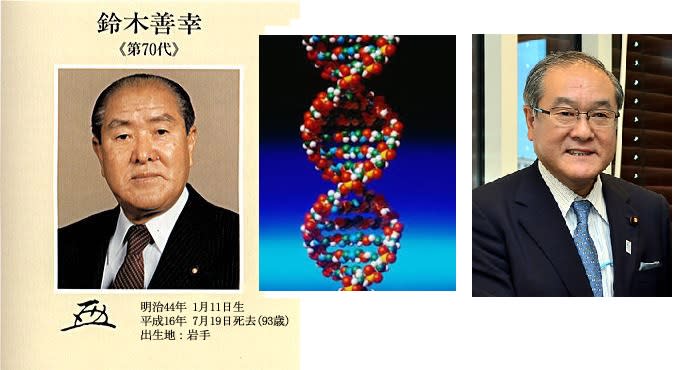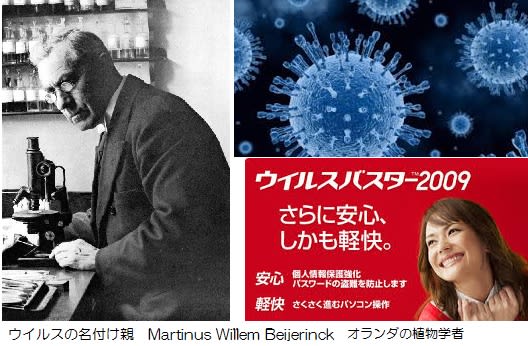A.「アメリカ的な」もの
イタリア在住の作家、塩野七生とその息子である映画人アントニオ・シモーネの対談集『ローマで語る』(集英社文庫.2015)からまたちょっと引用。この対談集は、おもに映画について気楽に母子がおしゃべりする、という本だが、母がいろんなテーマを質問してそれに息子が答えるという形をとっている。そのなかの「Bムービー賛歌」というお話。塩野さんが、フェリーニとか、ヴィスコンティとかヨーロッパの芸術映画のことしか関心がないかのようなので、アントニオはここで、アメリカのB級映画(B級とはつまり、映画祭の賞をとるような映画ではない大衆娯楽映画ということだが)のことをあえて語る。
「塩野:それでテーマを、Bクラスの映画にしたというわけね。
アントニオ:そう。そこでボクの考えるB級映画の定義ですが、まず第一に、芸術作品を狙って作られていないということ。だから、ハリウッドやカンヌやヴェネツィアという有名な映画祭では絶対に受賞できない。唯一の例外は『ロッキー』(一九七六年)で、あれだけはなぜかオスカーを受賞したけれど。
第二は、批評家には無視されても観客動員数では成功していること。これから挙げる映画は一九八〇年代から九〇年代に作られているのです。今からならば三十年も昔の作品。それでいて今でもDVDで売れつづけ、レンタルする人も後を絶たない。誰が観ているかって?作られた当時には生まれてもいなかった、今の若者たちですよ。
それでまず挙げたいのが『ランボー』(一九八二年)です。芸術映画派の塩野さんは観なかったと思うけど。
塩野:いえ、観てますよ。悪くなかった。
アントニオ:ボクの考えでは、戦争とはどういうものかをわからせてくれた、アメリカ映画の傑作のひとつです。 ベトナムから帰還した主人公が田舎の小さな町に立ち寄ったことで警官たちから冷遇され、それに怒って起こす騒動のアクションぶりで話題になった映画ですが、あの映画の良さは別のところにある。シルベスター・スタローン扮する帰還兵の暴力を止めるために呼び出された、ベトナムでの上官に、主人公が言うシーン。お前が起こす騒ぎで被害を受けて困っているのは罪もない人々だから、暴力での復讐はやめろと上官に言われて、彼は泣きながら言うんです。
「じゃあ、オレは何だって言うんです。彼らが望んで始めた戦争を戦って帰国したオレはやっかい者あつかいされ、追い出されたんだ。オレはただ、何か口に入れようと立ち寄っただけなのに。彼らには、家族も友人もいる。それなのにオレには誰もいない。みんな、死んでしまったんだ」
はじめは望んだ戦争でも敗北に終わった戦争となると、家族に戦死者が出たとか直接の関係者でもないかぎりは、忘れてしまいたいと思うのが、一般の人々の正直な気持ちなんです。ベトナムでは、アメリカは敗れた。そして、今ではイラクでも。二十六年前に作られたこの映画をイラクからの帰還兵が観たら、泣き出すんではないかと思う。
海兵隊員もグリーン・ベレーもレンジャースも、どんなに絶望的な状態になっても生き延びる技能ならば訓練されているので、誰にも負けなかったにちがいな。い『ランボー』でのアクション部分がそれを示しています。しかし戦争は、始めたからには勝たなければ意味がない。そして、始めてしまった戦争を勝利にもっていくのは、政治家たちの仕事です。それがうまくいかないと、実際に戦った兵士たちがまず先に犠牲になる。
塩野:あの映画は、私は続編は観ていませんがPart2も3も作られたのだから、興業的には大成功したんでしょう。ベトナム帰還兵氏が観たくらいでは大成功にはならない。
アントニオ:もちろん、ベトナム戦争には直接関係しなかったアメリカ人までが観たから、興業的にも大成功したんです。なぜかと言えば、彼らも、敗戦から十年が経った後にしろわかったんですよ。戦場に送り出す兵士に教えることは、いかに危機的な状態でも生き延びる技能ではなくて、勝つことだというのが。生きのびるだけならば、外国にまで戦争に行かず、国内でおとなしくしていればよいのだから。
それにしてもアメリカ人とは、不思議な人たちですよね。ベトナムで懲りたくせに、またイラクで繰り返しているのだから。無事に帰国しても社会に溶け込めない帰還兵を多く出していることも変わっていない。
塩野:まったく同感です。それで次は何でしょう。
アントニオ:『ブルーサンダー』(一九八三年)。これは『ランボー』の一年後に作られた映画で、主人公は、人間ではなくてヘリコプターです。それも普通のヘリではなくて、軍事用に実際に使われているという、万能ロボットみたいなヘリコプター。
まず静か。静かに接近して来ては撃つ。数キロ離れたところで話される会話も、機上のコンピューターでフォローするのも可能。つまり、市民一人一人のプライバシーの尊重なんて、知ったことではないという機械です。
これがB級映画である所以は、人間的とか心理的とかを考慮した理由づけをいっさいしていないこと。しかし、クールに展開するこの万能ヘリの活動を観ていくにつれて、何人かの人は考えますよ。第一に、アメリカ人とはなんと武器が好きな人びとなんだろう。それも、より大きくてより機能が進んだ武器でないと、安心できない人びとなのだ、ということを。
そして第二は、ボクがアメリカ人でなくてヨーロッパ人だからかもしれませんが、これほど完璧な武器を数多く持っていながら、なぜ戦争をすると負けるのか、ということです。歴史にはこれまでに多くの強国が登場したけれど、戦争の下手な超大国は、アメリカ合衆国が初めてではないかと思う。
もしかしたらアメリカ人自身も、それを感じているのかもしれない。なぜならアメリカ人は、間のヒーローが好きだから。
というわけで、次は、『ターミネーター』(一九八四年)と『プレデター』(一九八七年)の二作。
塩野:いずれもシュワちゃんが主役でしょう。だからというわけではないけれど観ていません。
アントニオ:ロボットというと日本ではドラえもんとかになるけれど、アメリカでは反対に非人間的になるんです。だが、アクション・ムービーとしても良くできている。とくにカメラの視点がオリジナルです。カメラが超人ロボットの側に立っているから、観客もやむをえず、ロボットに追われる人びとの側に立つしかない。アドレナリン満点の原因もここにあるんです。それを見透かした監督のジェームズ・キャメロンもジョン・マクティアナンも、職人としては一級です。つまり、客を呼べる映画をつくる達人ということですね。
「エンターテインメント」と聞くと、単なる娯楽作品だと思う人が多い。しかしこの言葉の真の意味は、楽しませることだけでなくて、「引きずりこむ」ことにあるんです。B級映画も良くできた作品には、必ずこの要素がある。メッセージを、わざわざ伝える必要はない。アクションであろうと何であろうと、観る人を引きずりこんで離さない、という要素が充分にあれば、興業的には間違いなく成功するんです。ボクは絶対に、これらBムービーを軽蔑できない。」塩野七生&アントニオ・シモーネ『ローマで語る』集英社文庫、2015. pp.201-207.
これで思い出したが、クリント・イーストウッドが監督した「アメリカン・スナイパー」(2014)という比較的最近の映画がある。これは イラク戦争の米海軍特殊部隊の狙撃手が主人公である。これは実在の兵士の自伝が元のようだが、娯楽アクション・エンタメ映画ではない。しかし、戦場の場面と帰還して平和な日常を家族と生きる時間の落差が次第に耐えい難いものになる。シリアスだが、「アメリカの戦争」自体はやはり正義の戦いとしながら、第2次世界大戦のような輝かしい勝利などではない。イラク戦争からの帰還米兵を描いたPTSD映画はいくつかあったが、「ランボー」はそれをハリウッド・アクション映画の中に埋め込んで大ヒット作にしたという意味で、記憶される。戦争は人を殺すからいけない、とは単純すぎるが、実際に銃で人を殺した人間はやはりふつうの市民生活を送れなくなる。武器の延長としての殺人ロボットにやらせれば罪の意識は薄らぐだろうか?ただの腕力も高度な兵器も、道具であるかぎり正義とも道徳とも無関係だ。なのにアメリカ人は、武器でことを解決できると思っている。アメリカの戦争に手を貸す道義的理由も政治的理由もないと思う。

B.生物学における創世記
アイザック・アシモフ『生物学の歴史』を読んできたが、これで読了。この本が書かれたのは1964年、昭和でいえば39年である。ぼくの歳でいえば15歳。中学生のぼくは学校で理科の先生に、生物の遺伝と進化の授業を聞いた数日後、こんな疑問をもって質問したことを覚えている。もし人間が生まれる前から両親の遺伝子で、能力も性格も決まっているのなら、勉強したり努力したりしても結果は決まっているんじゃないですか。天才からは天才が生まれ、凡才からは凡才しか生まれない、だとしたら社会も歴史もある予定された筋書きにしたがってすすむだけじゃないですか?ぼくは「運命」という決定論を否定したかったんだろうと思う。その時はまだ、優生学とか唯物論とかいう言葉を知らなかったが、生物学という学問が人間にとってある重要な問題を研究しているのだと思った。
そして、小柄でいかにも真面目そうなメガネの理科の先生は、そのときぼくに遺伝というのは親の形質のすべてを子に伝えるのではなく、一部しか伝えない。しかも、突然変異というものがあって、ソ連の遺伝学者ルイセンコとミチューリンの説では、環境によって獲得形質に変化が起こり、それが新しく遺伝するということが証明されたという。つまり、人間は決められた運命の中で生きるのではなく、社会や環境の変化が新しい人間の誕生を生み出す、こともあるんだという。よくはわからなかったが、中学3年生のぼくには、ルイセンコ=ミチューリン学説という名前と、遺伝子からの自由という希望があるような気がした。
「20世紀中ごろにおける分子生物学の進歩は、機械論者の地位を今までにないほど強いところへもたらした。遺伝学のすべては、生物にも無生物にも同様に適用される法則にしたがって、化学的に説明することができる。精神の世界でさえも、その本流の前に屈するきざしを示している。学習と記憶の過程は、神経の経路の確立や保存(一八九~一九〇頁参照)ではなくて、特別なRNAの合成と維持であるらしい(実際、非常に単純な生物である扁形動物は、すでにその作業を学習した他のなかまを食べることによって、その作業を学習することができることが示された。おそらく、食べたほうは、食べられたほうの完全なRNA分子を自分のからだにとりこんだのであろう)。
一九世紀の生気論者の立場に明らかな勝利をもたらしていた生物学の一面が残されていた。——自然発生の反証の問題である(一四四頁参照)。二〇世紀では、その反証は完全な意味では、それほど人を引きつけなくなっていた。実際、もし生物が無生物から決して発生することができないならば、生命はどのようにして始まったのであろうか。最も自然の仮説は、生命が何か超自然的なはたらきでつくられたと考えることである。しかし、その考えを受け入れることをこばめば、どうなるだろう?
一九〇八年スウェーデンの化学者、アレニウス(Svante August Arrhenius一八五九~一九二七年)は超自然に求めないで、生命の起源を考えた。彼は、萌芽が他の宇宙からわれわれの惑星に到着して、地球上での生命が始まったと考えた。この空想は、広大な何もない空間を横切ってただよい、星からの弱い力に引かれながら、そこここに着陸し、そこかしこの惑星を肥沃にする生命の粒子を引き出した。しかしながら、アレニウスの考えは問題を単に後退させたにすぎない。それは問題を解決しなかった。もし生命がわれわれ自身の惑星の上で生じたのでないならば、どこで発生したにしてもどのように発生したのであろうか。
もう一度、生命は無生物から発生することができないかどうか考え直す必要があった。パスツールは彼のフラスコを一定時間無菌状態に保ったが、10億年間もそのままにしておいたらどうなるであろうか。あるいは、フラスコの溶液を10億年間そのままにしておくのではなくて、海洋全体の溶液をそうしておいたらどうであろうか。そして、海洋が今日おかれているのとははるかに異なった条件のもとでそうしておかれたらどうであろうか。
生命をつくっている根本になる物質が、永劫の間、本質的に変化したと考えるべき理由はない。実際、それらは変化しなかったらしい。1000万年も前の化石に少量のアミノ酸が存在し、分離されたものは今日生きている生物組織にあるアミノ酸と同じである。それにもかかわらず、地球の化学は一般に変化したのかもしれない。
宇宙の化学についての知識がふえ、アメリカの化学者、ユーリー(Harold Clayton Urey一八九三~一九八一年)のような人たちは、原始地球を仮定するようになった。そこでは大気は“還元的”なものであり、水素や、メタン、アンモニアのように水素を含む気体に富んでいて、遊離の酸素はなかった。
そのような条件下では、大気の上層にオゾンの層はないであろう(オゾンは酸素の一つの形である)。そのようなオゾンの層は現在存在し、太陽の紫外線の大部分を吸収する。還元性の大気中では、このエネルギーに富む放射線は海にまで透過し、海洋中で現在はおこらない反応を引きおこすであろう。複雑な化合物がゆっくりと形成され、海洋中にすでに存在している生命をもたないこれらの分子は消費されるのではなく、蓄積されるであろう。ついに、複製する分子として役立つのに十分なほど複雑な核酸の分子が形成され、そしてこれが生命の本質的な要素となるのであろう。
突然変異と自然選択によって、はるかに有効な形の核酸がつくられるであろう。それらはついに細胞に発達し、またそれらのあるものはクロロフィルをつくり始めるであろう。光合成は(たぶん、生命のない他の過程の助けを得て)原始的な大気を、われわれにおなじみの遊離の酸素に富む大気へ変えるであろう。酸素のある大気中で、すでに生命に富んだ世界では、今のべたような型の自然発生はもはやありえないであろう。
これは大部分推測である(注意深く論じた推論であるが)。しかし一九五三年に、ユーリーの弟子の一人であるミラー(Stanley Lloyd Miller一九三〇~二〇〇七年)は、有名になった実験を行った。彼はまず水を注意深く浄化し、滅菌した。そして、水素・アンモニア・メタンよりなる“大気”を加えた。これを、密閉した装置の中で、放電を通して、循環させた。この放電は、太陽の紫外線のはたらきをまねるように設計されたエネルギーの投入に相当する。彼は一週間これを続け、次にその水溶液をペーパークロマトグラフィーで分離した。彼はそれらの成分の中に簡単な有機化合物と二、三の小さなアミノ酸を発見した。
一九六二年、カリフォルニア大学で同様な実験が繰り返された。そこでは、エタン(炭素一個のメタンと非常によく似た炭素二個の化合物)が大気に加えられた。より多くの種類の有機化合物が得られた。そして、一九六三年、重要な高エネルギーリン酸化合物の一つである、アデノシン三リン酸(二二七頁参照)が同様な方法で得られた。
これが小さな装置の中でおよそ一週間でなされるのであれば、10億年間に全海洋と大気をもって何ものもつくられないことがあるであろうか。
われわれはこれからも発見するであろう。地球の歴史をその曙までさかのぼる進化の経過を明らかにするのは困難なように思われるかもしれないが、もしわれわれが月に到着すれば生命の出現に先立つ化学変化の過程をもっとはっきり解明できるかもしれない。もしわれわれが火星に到着すれば、地球のとはまったく異なる条件下で発達した簡単な生物を研究できるかもしれない(きっとできるであろう)。そして、それもまたいくつかのわれわれの地球の問題に適用できるかもしれない。
われわれ自身の惑星の上ですら、大洋の深海溝というまったく違った条件下の生物について年ごとに学びつつある。というのは、一九六〇年、人間はもっとも深い海の底に到達できた。海の中で、われわれはイルカという人間以外の知能との通信を確立することさえも可能である。
人間の精神自体も、分子生物学者の探求に対してその神秘性を放棄するかもしれない。サイバネティックスとエレクトロニクスの知識が増すことによって、われわれは生命のない知能をつくり出すことができるかもしれない。
しかし、待つことのみが必要であるとき、なぜ推測をするのであろうか。いかに大きく前進し、未知のことについての知識がいかに驚くほどさかんに得られようと、未来に残されているものはつねにさらに大きく、さらに興味深く、さらにすばらしいものであるということは、たぶん科学的研究の最も満足すべき点であろう。
今生きている人々の存命中にも、なお何もあきらかにされないことがあるであろうか。」アイザック・アシモフ『生物学の歴史』太田次郎訳、講談社学術文庫、2014. pp. 268-273.
*訳注:サイバネティックスは、通信工学、操縦工学から、統計力学、統計学、生物体におけり協調、特に神経系や脳の生理学から心理学までを含む広い領域の間に、共通な統一理論を研究しようとする学問で、アメリカの数学者で電気工学者であるウィーナーが第二次大戦後提唱した。
レーニンが実現したマルクス主義による初めての国家、ソヴィエト連邦で、唯物論による自然科学の進歩を社会主義の正しさを実証するものとして称揚されたひとつが、遺伝学におけるルイセンコ=ミチューリン学説であり、ボストークの宇宙開発であった。『生物学の歴史』巻末にある訳者、太田次郎氏の「訳者あとがき」にはこうある。
「本書は「古代の生物学」から始まって、「分子生物学」で終わっている。分子生物学は本書の刊行以後、飛躍的に発展した。DNAの塩基配列とアミノ酸との対応が明らかになり、「遺伝子の暗号」が解読された。特にヒトの全遺伝子(ゲノム)の解読は、人間生活に大きな影響を与え、個人識別をもとにして犯罪捜査等で広く応用されるようになった。今やDNAは日常語となっている。また、遺伝子を操作する技術として「バイオテクノロジー」が進展し、医学、化学、農学、薬学への応用が進んだ。動物、植物、微生物の品種改良などでバイオテクノロジーという新分野が開発された。
このようなことを反映して、各大学に生命科学関係の学部・学科が次々に新設され、今や生命科学に関与する人は急速に増えている。このような人々にとって、生物学の歴史を振り返ることは決して無駄にはならないと思われる。またアシモフの語る生物学の歩みは、一般の方々にとっても格好のガイドブックとして興味深く有意義な読み物になってくれるのではないか。」アイザック・アシモフ『生物学の歴史』 pp. 276-277.
アシモフの本に書かれている知識は、今日では高校の生物学で教えられる基礎知識に類するものなのかもしれない。1960年代後半に高校で生物を教わったぼくには、進化論もDNAもなんだかつまらない運命論を追認する知識に思えていた。でもその後、バイオテクノロジーは飛躍的に進歩し、いまやバイオエシックスの問題提起にまで至って、文系哲学にまで影響を与える段階になった。小保方事件に見られるように、細胞の分子構造の研究は、人間の生命の神秘を操作可能なレベルにまで引き下ろす(引き上げる?)、科学上のホットな問題にしているのだろうが、「じゃあ、それで、なにが、ど~したの?」という感覚は、あるな。
イタリア在住の作家、塩野七生とその息子である映画人アントニオ・シモーネの対談集『ローマで語る』(集英社文庫.2015)からまたちょっと引用。この対談集は、おもに映画について気楽に母子がおしゃべりする、という本だが、母がいろんなテーマを質問してそれに息子が答えるという形をとっている。そのなかの「Bムービー賛歌」というお話。塩野さんが、フェリーニとか、ヴィスコンティとかヨーロッパの芸術映画のことしか関心がないかのようなので、アントニオはここで、アメリカのB級映画(B級とはつまり、映画祭の賞をとるような映画ではない大衆娯楽映画ということだが)のことをあえて語る。
「塩野:それでテーマを、Bクラスの映画にしたというわけね。
アントニオ:そう。そこでボクの考えるB級映画の定義ですが、まず第一に、芸術作品を狙って作られていないということ。だから、ハリウッドやカンヌやヴェネツィアという有名な映画祭では絶対に受賞できない。唯一の例外は『ロッキー』(一九七六年)で、あれだけはなぜかオスカーを受賞したけれど。
第二は、批評家には無視されても観客動員数では成功していること。これから挙げる映画は一九八〇年代から九〇年代に作られているのです。今からならば三十年も昔の作品。それでいて今でもDVDで売れつづけ、レンタルする人も後を絶たない。誰が観ているかって?作られた当時には生まれてもいなかった、今の若者たちですよ。
それでまず挙げたいのが『ランボー』(一九八二年)です。芸術映画派の塩野さんは観なかったと思うけど。
塩野:いえ、観てますよ。悪くなかった。
アントニオ:ボクの考えでは、戦争とはどういうものかをわからせてくれた、アメリカ映画の傑作のひとつです。 ベトナムから帰還した主人公が田舎の小さな町に立ち寄ったことで警官たちから冷遇され、それに怒って起こす騒動のアクションぶりで話題になった映画ですが、あの映画の良さは別のところにある。シルベスター・スタローン扮する帰還兵の暴力を止めるために呼び出された、ベトナムでの上官に、主人公が言うシーン。お前が起こす騒ぎで被害を受けて困っているのは罪もない人々だから、暴力での復讐はやめろと上官に言われて、彼は泣きながら言うんです。
「じゃあ、オレは何だって言うんです。彼らが望んで始めた戦争を戦って帰国したオレはやっかい者あつかいされ、追い出されたんだ。オレはただ、何か口に入れようと立ち寄っただけなのに。彼らには、家族も友人もいる。それなのにオレには誰もいない。みんな、死んでしまったんだ」
はじめは望んだ戦争でも敗北に終わった戦争となると、家族に戦死者が出たとか直接の関係者でもないかぎりは、忘れてしまいたいと思うのが、一般の人々の正直な気持ちなんです。ベトナムでは、アメリカは敗れた。そして、今ではイラクでも。二十六年前に作られたこの映画をイラクからの帰還兵が観たら、泣き出すんではないかと思う。
海兵隊員もグリーン・ベレーもレンジャースも、どんなに絶望的な状態になっても生き延びる技能ならば訓練されているので、誰にも負けなかったにちがいな。い『ランボー』でのアクション部分がそれを示しています。しかし戦争は、始めたからには勝たなければ意味がない。そして、始めてしまった戦争を勝利にもっていくのは、政治家たちの仕事です。それがうまくいかないと、実際に戦った兵士たちがまず先に犠牲になる。
塩野:あの映画は、私は続編は観ていませんがPart2も3も作られたのだから、興業的には大成功したんでしょう。ベトナム帰還兵氏が観たくらいでは大成功にはならない。
アントニオ:もちろん、ベトナム戦争には直接関係しなかったアメリカ人までが観たから、興業的にも大成功したんです。なぜかと言えば、彼らも、敗戦から十年が経った後にしろわかったんですよ。戦場に送り出す兵士に教えることは、いかに危機的な状態でも生き延びる技能ではなくて、勝つことだというのが。生きのびるだけならば、外国にまで戦争に行かず、国内でおとなしくしていればよいのだから。
それにしてもアメリカ人とは、不思議な人たちですよね。ベトナムで懲りたくせに、またイラクで繰り返しているのだから。無事に帰国しても社会に溶け込めない帰還兵を多く出していることも変わっていない。
塩野:まったく同感です。それで次は何でしょう。
アントニオ:『ブルーサンダー』(一九八三年)。これは『ランボー』の一年後に作られた映画で、主人公は、人間ではなくてヘリコプターです。それも普通のヘリではなくて、軍事用に実際に使われているという、万能ロボットみたいなヘリコプター。
まず静か。静かに接近して来ては撃つ。数キロ離れたところで話される会話も、機上のコンピューターでフォローするのも可能。つまり、市民一人一人のプライバシーの尊重なんて、知ったことではないという機械です。
これがB級映画である所以は、人間的とか心理的とかを考慮した理由づけをいっさいしていないこと。しかし、クールに展開するこの万能ヘリの活動を観ていくにつれて、何人かの人は考えますよ。第一に、アメリカ人とはなんと武器が好きな人びとなんだろう。それも、より大きくてより機能が進んだ武器でないと、安心できない人びとなのだ、ということを。
そして第二は、ボクがアメリカ人でなくてヨーロッパ人だからかもしれませんが、これほど完璧な武器を数多く持っていながら、なぜ戦争をすると負けるのか、ということです。歴史にはこれまでに多くの強国が登場したけれど、戦争の下手な超大国は、アメリカ合衆国が初めてではないかと思う。
もしかしたらアメリカ人自身も、それを感じているのかもしれない。なぜならアメリカ人は、間のヒーローが好きだから。
というわけで、次は、『ターミネーター』(一九八四年)と『プレデター』(一九八七年)の二作。
塩野:いずれもシュワちゃんが主役でしょう。だからというわけではないけれど観ていません。
アントニオ:ロボットというと日本ではドラえもんとかになるけれど、アメリカでは反対に非人間的になるんです。だが、アクション・ムービーとしても良くできている。とくにカメラの視点がオリジナルです。カメラが超人ロボットの側に立っているから、観客もやむをえず、ロボットに追われる人びとの側に立つしかない。アドレナリン満点の原因もここにあるんです。それを見透かした監督のジェームズ・キャメロンもジョン・マクティアナンも、職人としては一級です。つまり、客を呼べる映画をつくる達人ということですね。
「エンターテインメント」と聞くと、単なる娯楽作品だと思う人が多い。しかしこの言葉の真の意味は、楽しませることだけでなくて、「引きずりこむ」ことにあるんです。B級映画も良くできた作品には、必ずこの要素がある。メッセージを、わざわざ伝える必要はない。アクションであろうと何であろうと、観る人を引きずりこんで離さない、という要素が充分にあれば、興業的には間違いなく成功するんです。ボクは絶対に、これらBムービーを軽蔑できない。」塩野七生&アントニオ・シモーネ『ローマで語る』集英社文庫、2015. pp.201-207.
これで思い出したが、クリント・イーストウッドが監督した「アメリカン・スナイパー」(2014)という比較的最近の映画がある。これは イラク戦争の米海軍特殊部隊の狙撃手が主人公である。これは実在の兵士の自伝が元のようだが、娯楽アクション・エンタメ映画ではない。しかし、戦場の場面と帰還して平和な日常を家族と生きる時間の落差が次第に耐えい難いものになる。シリアスだが、「アメリカの戦争」自体はやはり正義の戦いとしながら、第2次世界大戦のような輝かしい勝利などではない。イラク戦争からの帰還米兵を描いたPTSD映画はいくつかあったが、「ランボー」はそれをハリウッド・アクション映画の中に埋め込んで大ヒット作にしたという意味で、記憶される。戦争は人を殺すからいけない、とは単純すぎるが、実際に銃で人を殺した人間はやはりふつうの市民生活を送れなくなる。武器の延長としての殺人ロボットにやらせれば罪の意識は薄らぐだろうか?ただの腕力も高度な兵器も、道具であるかぎり正義とも道徳とも無関係だ。なのにアメリカ人は、武器でことを解決できると思っている。アメリカの戦争に手を貸す道義的理由も政治的理由もないと思う。

B.生物学における創世記
アイザック・アシモフ『生物学の歴史』を読んできたが、これで読了。この本が書かれたのは1964年、昭和でいえば39年である。ぼくの歳でいえば15歳。中学生のぼくは学校で理科の先生に、生物の遺伝と進化の授業を聞いた数日後、こんな疑問をもって質問したことを覚えている。もし人間が生まれる前から両親の遺伝子で、能力も性格も決まっているのなら、勉強したり努力したりしても結果は決まっているんじゃないですか。天才からは天才が生まれ、凡才からは凡才しか生まれない、だとしたら社会も歴史もある予定された筋書きにしたがってすすむだけじゃないですか?ぼくは「運命」という決定論を否定したかったんだろうと思う。その時はまだ、優生学とか唯物論とかいう言葉を知らなかったが、生物学という学問が人間にとってある重要な問題を研究しているのだと思った。
そして、小柄でいかにも真面目そうなメガネの理科の先生は、そのときぼくに遺伝というのは親の形質のすべてを子に伝えるのではなく、一部しか伝えない。しかも、突然変異というものがあって、ソ連の遺伝学者ルイセンコとミチューリンの説では、環境によって獲得形質に変化が起こり、それが新しく遺伝するということが証明されたという。つまり、人間は決められた運命の中で生きるのではなく、社会や環境の変化が新しい人間の誕生を生み出す、こともあるんだという。よくはわからなかったが、中学3年生のぼくには、ルイセンコ=ミチューリン学説という名前と、遺伝子からの自由という希望があるような気がした。
「20世紀中ごろにおける分子生物学の進歩は、機械論者の地位を今までにないほど強いところへもたらした。遺伝学のすべては、生物にも無生物にも同様に適用される法則にしたがって、化学的に説明することができる。精神の世界でさえも、その本流の前に屈するきざしを示している。学習と記憶の過程は、神経の経路の確立や保存(一八九~一九〇頁参照)ではなくて、特別なRNAの合成と維持であるらしい(実際、非常に単純な生物である扁形動物は、すでにその作業を学習した他のなかまを食べることによって、その作業を学習することができることが示された。おそらく、食べたほうは、食べられたほうの完全なRNA分子を自分のからだにとりこんだのであろう)。
一九世紀の生気論者の立場に明らかな勝利をもたらしていた生物学の一面が残されていた。——自然発生の反証の問題である(一四四頁参照)。二〇世紀では、その反証は完全な意味では、それほど人を引きつけなくなっていた。実際、もし生物が無生物から決して発生することができないならば、生命はどのようにして始まったのであろうか。最も自然の仮説は、生命が何か超自然的なはたらきでつくられたと考えることである。しかし、その考えを受け入れることをこばめば、どうなるだろう?
一九〇八年スウェーデンの化学者、アレニウス(Svante August Arrhenius一八五九~一九二七年)は超自然に求めないで、生命の起源を考えた。彼は、萌芽が他の宇宙からわれわれの惑星に到着して、地球上での生命が始まったと考えた。この空想は、広大な何もない空間を横切ってただよい、星からの弱い力に引かれながら、そこここに着陸し、そこかしこの惑星を肥沃にする生命の粒子を引き出した。しかしながら、アレニウスの考えは問題を単に後退させたにすぎない。それは問題を解決しなかった。もし生命がわれわれ自身の惑星の上で生じたのでないならば、どこで発生したにしてもどのように発生したのであろうか。
もう一度、生命は無生物から発生することができないかどうか考え直す必要があった。パスツールは彼のフラスコを一定時間無菌状態に保ったが、10億年間もそのままにしておいたらどうなるであろうか。あるいは、フラスコの溶液を10億年間そのままにしておくのではなくて、海洋全体の溶液をそうしておいたらどうであろうか。そして、海洋が今日おかれているのとははるかに異なった条件のもとでそうしておかれたらどうであろうか。
生命をつくっている根本になる物質が、永劫の間、本質的に変化したと考えるべき理由はない。実際、それらは変化しなかったらしい。1000万年も前の化石に少量のアミノ酸が存在し、分離されたものは今日生きている生物組織にあるアミノ酸と同じである。それにもかかわらず、地球の化学は一般に変化したのかもしれない。
宇宙の化学についての知識がふえ、アメリカの化学者、ユーリー(Harold Clayton Urey一八九三~一九八一年)のような人たちは、原始地球を仮定するようになった。そこでは大気は“還元的”なものであり、水素や、メタン、アンモニアのように水素を含む気体に富んでいて、遊離の酸素はなかった。
そのような条件下では、大気の上層にオゾンの層はないであろう(オゾンは酸素の一つの形である)。そのようなオゾンの層は現在存在し、太陽の紫外線の大部分を吸収する。還元性の大気中では、このエネルギーに富む放射線は海にまで透過し、海洋中で現在はおこらない反応を引きおこすであろう。複雑な化合物がゆっくりと形成され、海洋中にすでに存在している生命をもたないこれらの分子は消費されるのではなく、蓄積されるであろう。ついに、複製する分子として役立つのに十分なほど複雑な核酸の分子が形成され、そしてこれが生命の本質的な要素となるのであろう。
突然変異と自然選択によって、はるかに有効な形の核酸がつくられるであろう。それらはついに細胞に発達し、またそれらのあるものはクロロフィルをつくり始めるであろう。光合成は(たぶん、生命のない他の過程の助けを得て)原始的な大気を、われわれにおなじみの遊離の酸素に富む大気へ変えるであろう。酸素のある大気中で、すでに生命に富んだ世界では、今のべたような型の自然発生はもはやありえないであろう。
これは大部分推測である(注意深く論じた推論であるが)。しかし一九五三年に、ユーリーの弟子の一人であるミラー(Stanley Lloyd Miller一九三〇~二〇〇七年)は、有名になった実験を行った。彼はまず水を注意深く浄化し、滅菌した。そして、水素・アンモニア・メタンよりなる“大気”を加えた。これを、密閉した装置の中で、放電を通して、循環させた。この放電は、太陽の紫外線のはたらきをまねるように設計されたエネルギーの投入に相当する。彼は一週間これを続け、次にその水溶液をペーパークロマトグラフィーで分離した。彼はそれらの成分の中に簡単な有機化合物と二、三の小さなアミノ酸を発見した。
一九六二年、カリフォルニア大学で同様な実験が繰り返された。そこでは、エタン(炭素一個のメタンと非常によく似た炭素二個の化合物)が大気に加えられた。より多くの種類の有機化合物が得られた。そして、一九六三年、重要な高エネルギーリン酸化合物の一つである、アデノシン三リン酸(二二七頁参照)が同様な方法で得られた。
これが小さな装置の中でおよそ一週間でなされるのであれば、10億年間に全海洋と大気をもって何ものもつくられないことがあるであろうか。
われわれはこれからも発見するであろう。地球の歴史をその曙までさかのぼる進化の経過を明らかにするのは困難なように思われるかもしれないが、もしわれわれが月に到着すれば生命の出現に先立つ化学変化の過程をもっとはっきり解明できるかもしれない。もしわれわれが火星に到着すれば、地球のとはまったく異なる条件下で発達した簡単な生物を研究できるかもしれない(きっとできるであろう)。そして、それもまたいくつかのわれわれの地球の問題に適用できるかもしれない。
われわれ自身の惑星の上ですら、大洋の深海溝というまったく違った条件下の生物について年ごとに学びつつある。というのは、一九六〇年、人間はもっとも深い海の底に到達できた。海の中で、われわれはイルカという人間以外の知能との通信を確立することさえも可能である。
人間の精神自体も、分子生物学者の探求に対してその神秘性を放棄するかもしれない。サイバネティックスとエレクトロニクスの知識が増すことによって、われわれは生命のない知能をつくり出すことができるかもしれない。
しかし、待つことのみが必要であるとき、なぜ推測をするのであろうか。いかに大きく前進し、未知のことについての知識がいかに驚くほどさかんに得られようと、未来に残されているものはつねにさらに大きく、さらに興味深く、さらにすばらしいものであるということは、たぶん科学的研究の最も満足すべき点であろう。
今生きている人々の存命中にも、なお何もあきらかにされないことがあるであろうか。」アイザック・アシモフ『生物学の歴史』太田次郎訳、講談社学術文庫、2014. pp. 268-273.
*訳注:サイバネティックスは、通信工学、操縦工学から、統計力学、統計学、生物体におけり協調、特に神経系や脳の生理学から心理学までを含む広い領域の間に、共通な統一理論を研究しようとする学問で、アメリカの数学者で電気工学者であるウィーナーが第二次大戦後提唱した。
レーニンが実現したマルクス主義による初めての国家、ソヴィエト連邦で、唯物論による自然科学の進歩を社会主義の正しさを実証するものとして称揚されたひとつが、遺伝学におけるルイセンコ=ミチューリン学説であり、ボストークの宇宙開発であった。『生物学の歴史』巻末にある訳者、太田次郎氏の「訳者あとがき」にはこうある。
「本書は「古代の生物学」から始まって、「分子生物学」で終わっている。分子生物学は本書の刊行以後、飛躍的に発展した。DNAの塩基配列とアミノ酸との対応が明らかになり、「遺伝子の暗号」が解読された。特にヒトの全遺伝子(ゲノム)の解読は、人間生活に大きな影響を与え、個人識別をもとにして犯罪捜査等で広く応用されるようになった。今やDNAは日常語となっている。また、遺伝子を操作する技術として「バイオテクノロジー」が進展し、医学、化学、農学、薬学への応用が進んだ。動物、植物、微生物の品種改良などでバイオテクノロジーという新分野が開発された。
このようなことを反映して、各大学に生命科学関係の学部・学科が次々に新設され、今や生命科学に関与する人は急速に増えている。このような人々にとって、生物学の歴史を振り返ることは決して無駄にはならないと思われる。またアシモフの語る生物学の歩みは、一般の方々にとっても格好のガイドブックとして興味深く有意義な読み物になってくれるのではないか。」アイザック・アシモフ『生物学の歴史』 pp. 276-277.
アシモフの本に書かれている知識は、今日では高校の生物学で教えられる基礎知識に類するものなのかもしれない。1960年代後半に高校で生物を教わったぼくには、進化論もDNAもなんだかつまらない運命論を追認する知識に思えていた。でもその後、バイオテクノロジーは飛躍的に進歩し、いまやバイオエシックスの問題提起にまで至って、文系哲学にまで影響を与える段階になった。小保方事件に見られるように、細胞の分子構造の研究は、人間の生命の神秘を操作可能なレベルにまで引き下ろす(引き上げる?)、科学上のホットな問題にしているのだろうが、「じゃあ、それで、なにが、ど~したの?」という感覚は、あるな。