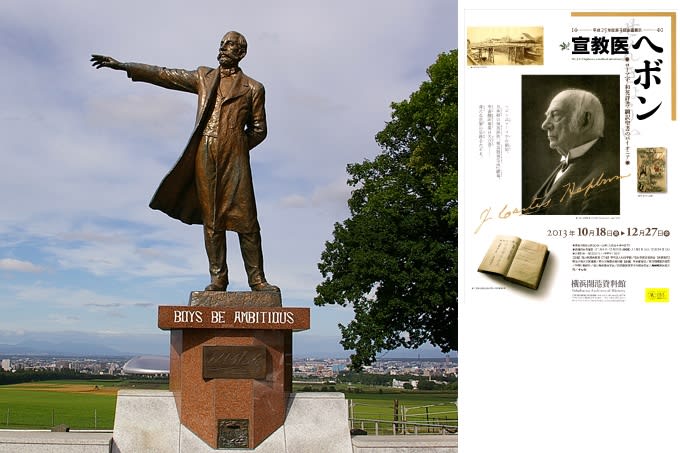A. 追悼!
8月26日、米倉斉加年さんが亡くなった。ちょうど先週、山田洋次の映画『小さなおうち』をDVDで借りて見たところだった。中島京子の直木賞受賞作の小説の映画化だが、この映画の最後の方に、重要な役で米倉さんが出演していた。妻夫木聡の演じた青年が訪ねた北陸の浜辺に住む老人役だった。最近あまり見ることがなかった人なので、なんだか懐かしかった。たくさんの映画やテレビドラマに出て印象深い演技をした俳優だったが、もともと劇団民芸の新劇出身であり、また絵を描く人で画集も多く出している。画家というかイラストレーター的な精密な絵で、絵本作家としてぼくは昔から好きだった。
今月初めまで講演などをされていたというが、腹部大動脈りゅう破裂のため、福岡市内の病院で80歳で亡くなったという。米倉さんが福岡市出身だというのを初めて知ったが、九州の大学を途中でやめて劇団民藝の演劇研究所に入り、舞台や映画に数多く出演した。ぼくには、NHK大河ドラマの「花神」の桂小五郎とか、最近では「坂の上の雲」の大山巌とか、記憶に残る印象があるが、そういう固い役より「男はつらいよ」での気の弱いサラリーマンみたいな役でこの人が細長い顔でくそまじめに喜劇を演じるのが意外に面白かった。
報道によれば、米倉さんは今月3日、戦争体験を語る講演会にも参加し、疎開中に生まれたばかりの弟を栄養失調で亡くした自らの経験を綴った絵本を朗読するなどして、平和の大切さを呼びかけていたという。
人が亡くなっていくのは、この世の摂理というか仕方のないことなのだが、俳優という仕事はある意味で幸福な職業だと思う。役者は自分自身ではなく、台本に書かれたさまざまな人物をあたかもそこに生きている人のように演じていく。それを見て、観客は共感したり反撥したりして記憶に留める。若い役者はその時代の若者の気分を代表し、中年の役者はその時代の力のある世代の姿を反映し、老年の役者は失われた時代の残り香を漂わせ、人々の記憶に確実なイメージを刻印する。俳優でもなければ、会ったこともないたくさんの人に、個人のパーソナルな姿、顔貌、体型、声、仕草まで記憶され想い出されるなんてことはないだろう。
でも同じ俳優でも女優と男優を比べてみると、もって生まれた若さや美貌を称賛される女優は、その後がきつい。人は誰でも歳をとって、若さや美貌などは儚く失われていく。それに抵抗してみてもしょせんは肉体をもった人間の限界は超えられない。そこへいくと男優は、若さイケメンで売る人はどうせ長持ちしないのは同じでも、別の道はある。米倉斉加年さんは元々二枚目とは無縁なので、演劇における実質的価値がよく分かっていたと思う。俳優は、所詮は監督や劇作家・脚本家や演出家の操作する道具のひとつに過ぎないのだが、役者が舞台の上やキャメラの前で動かなければ何も表現できない。だから、そこで劇中の人物になりきり、しかも自分の身体で生きた人間を観客の目の前に晒す技をもった人間だけが良い役者なのだ。

B.中島京子『小さいおうち』文藝春秋、を読んだ。
それまでこの人の小説は読んだことがなかった。この作品は直木賞を受賞し、山田洋次によって映画化され、一躍世間の片隅で注目を集めた。ただ、映画はストーリーを追うことに偏して、昭和戦前の東京山の手、という時空の細部までは丁寧に描ききれない。この小説は、丁寧に読む価値がある。
「こうしてわたしたちは、開戦の日を迎える。
真珠湾の日。十二月八日だ。
ぱっとしない一日だった。
二、三日前からラジオが壊れていて、終日流れていたという放送を、私も奥様も聞いていなかった。
やっと知ったのは、夕方になってからだ。
四年生になってから、ひとりで学校へ通われていたぼっちゃんが、駅から家までの坂道を全速力で駆けてきて、叫んだ。
「やったよ!戦争が始まったよ!日本がハワイの軍港へ、決死の大空襲だよ!」
奥様はおっとり出ていらした。
「あらまあ、それ、ほんとなの?恭ちゃん」
「そうさ、午後、校長先生が全校生徒を集めておっしゃったんだもの。ラジオ、聞かなかったの?」
「聞いてないわ。ハワイってどこ?蘭印?仏印?」
「なにを言ってるの?お母ちゃま!ハワイと言ったら、西太平洋じゃないか!」
「お母ちゃまは、地理があんまり得意ではないのよ」
「オランダでもフランスでもないよ。アメリカと戦争を始めたんだよ!」
「あらまあ、そうですか」
「そうですか、じゃないよ!だから女はだめなんだ」
ぼっちゃんは怒って二階に駆け上がり、奥様はふうとため息をつかれた。
「一昨日もお父様は、東條内閣はアメリカと戦わない方針だとおっしゃってたけれど」
奥様がつぶやくと、地獄耳のぼっちゃんは二階から、
「あんまりアメリカが悪いから、堪えに堪えていた日本がもう、堪忍できなくなったんだ。ああ、だから女は嫌なんだ」
と、聞こえよがしに怒鳴った。
奥様も今度はほんとうにひそひそ声で、
「支那との戦争だって四年も続いているのに、また新しい戦争だなんて、ちょっとうんざりするわね」
とおっしゃった。
女がだめだからどうなのか知らないが、たしかにこの日は平井家の男二人が異様に盛り上がり、夜中まで、「敵はァ、幾万、ありとてもォ!」と合唱して大騒ぎした。
旦那様もなぜだかすっかり、開戦派に変貌していたのである。
「アメリカもこれで、もう日本をバカにできないと思い知ったに違いない。日本、よくやった!万歳!」
旦那様は大きな声でそうおっしゃった。
「社長なども言うのだがね。米英は東洋人を一段下の人間と思っているんだ。それで呑めない条件を次々突きつけてくる。社長がアメリカに行ったとき、いきなり初対面の人間にシュウ、シュウ、と、まるで犬のようにあだ名で呼ばれて困惑したというんだよ」
「あらでも、以前、社長さんはそのお話を、アメリカ人がとても友好的だという例に、引いていらっしゃいましてよ」
「そこが、社長のいいところさ。なんでも好意的に解釈しようとする。日本人の美点でもある。ところが思い出してみると、白人がミスター何々と呼ばれているような場所でも、社長だけシュウだったというんだ」
直接聞いたわけではないから、社長さんがどんな思いでこの話をしたのかは、わからない。けれど旦那様の中では、「シュウの話」は、まるきり、逆の逸話に変っていた。
この日の盛り上がりには、正直、わたしもついていけなかった。
けれど翌日の朝刊の見出しを見たときに、何かがすっと私の中に入ってきて、いろいろなことがわかった気がした。
ああ、始まるのだ。新しい時代が始まるのだ、と思った。
それまで毎日、新聞は、日米交渉がいかにうまくいかないかを、ちまちました小さな活字で取り上げていたのだ。東條さんの渋い顔や、ハル国務長官の憎々しい顔が、黒っぽい写真で入っていて、来る日も来る日も進展しない和平交渉を伝えていた。
しかもその間に、いかにアメリカやイギリスが日本をバカにしているか、腰抜けだと思って見下しているか、無理難題を押しつけても言うことを聞くと思っているかを報道していたものだから、新聞を見るのは、うんと嫌だった。
ところが十二月九日の朝刊には、大きな活字でもって、『米太平洋艦隊は全滅せり』『我無敵海軍の大戦果』と、胸のすくような文字が躍動していたのだった。
わたしは表へ出て、深呼吸をした。」中島京子『小さいおうち』文藝春秋、文春文庫、2012, pp.204-207.
作者、中島京子はこの作品を書くにあたって、昭和戦前の新聞雑誌など、当時の普通の人々が生きていた情報空間を細かい部分に注意を払って探索したという。それはこの作品のリアリティをとてもよく支えていると思う。この日米戦争開戦の日の男たちの昂奮は、21世紀の現在こそ記憶するに値する。この日に生きていた人たちは、その後数年間に起きることを予想できなかった。そして、ありえないと思ったことが次々起こったのである。それでも日本軍は強いに決まっているのだから、いずれは勝つ、と信じた人々はこの戦争が自分たちの生活を焼土と殺戮のどん底に落とすまで、何も考えることができなかった。
日本が戦争などするわけがない、もし戦争をするとしても、どこか海外の遠いところでアメリカ軍と一緒にするだけだ、と考えている人々は、昭和15年の日本臣民と同様の妄想を信じている。どうしたらこんな愚かな政府と、その気分に無責任に便乗する人々を、止めることができるのだろう?
8月26日、米倉斉加年さんが亡くなった。ちょうど先週、山田洋次の映画『小さなおうち』をDVDで借りて見たところだった。中島京子の直木賞受賞作の小説の映画化だが、この映画の最後の方に、重要な役で米倉さんが出演していた。妻夫木聡の演じた青年が訪ねた北陸の浜辺に住む老人役だった。最近あまり見ることがなかった人なので、なんだか懐かしかった。たくさんの映画やテレビドラマに出て印象深い演技をした俳優だったが、もともと劇団民芸の新劇出身であり、また絵を描く人で画集も多く出している。画家というかイラストレーター的な精密な絵で、絵本作家としてぼくは昔から好きだった。
今月初めまで講演などをされていたというが、腹部大動脈りゅう破裂のため、福岡市内の病院で80歳で亡くなったという。米倉さんが福岡市出身だというのを初めて知ったが、九州の大学を途中でやめて劇団民藝の演劇研究所に入り、舞台や映画に数多く出演した。ぼくには、NHK大河ドラマの「花神」の桂小五郎とか、最近では「坂の上の雲」の大山巌とか、記憶に残る印象があるが、そういう固い役より「男はつらいよ」での気の弱いサラリーマンみたいな役でこの人が細長い顔でくそまじめに喜劇を演じるのが意外に面白かった。
報道によれば、米倉さんは今月3日、戦争体験を語る講演会にも参加し、疎開中に生まれたばかりの弟を栄養失調で亡くした自らの経験を綴った絵本を朗読するなどして、平和の大切さを呼びかけていたという。
人が亡くなっていくのは、この世の摂理というか仕方のないことなのだが、俳優という仕事はある意味で幸福な職業だと思う。役者は自分自身ではなく、台本に書かれたさまざまな人物をあたかもそこに生きている人のように演じていく。それを見て、観客は共感したり反撥したりして記憶に留める。若い役者はその時代の若者の気分を代表し、中年の役者はその時代の力のある世代の姿を反映し、老年の役者は失われた時代の残り香を漂わせ、人々の記憶に確実なイメージを刻印する。俳優でもなければ、会ったこともないたくさんの人に、個人のパーソナルな姿、顔貌、体型、声、仕草まで記憶され想い出されるなんてことはないだろう。
でも同じ俳優でも女優と男優を比べてみると、もって生まれた若さや美貌を称賛される女優は、その後がきつい。人は誰でも歳をとって、若さや美貌などは儚く失われていく。それに抵抗してみてもしょせんは肉体をもった人間の限界は超えられない。そこへいくと男優は、若さイケメンで売る人はどうせ長持ちしないのは同じでも、別の道はある。米倉斉加年さんは元々二枚目とは無縁なので、演劇における実質的価値がよく分かっていたと思う。俳優は、所詮は監督や劇作家・脚本家や演出家の操作する道具のひとつに過ぎないのだが、役者が舞台の上やキャメラの前で動かなければ何も表現できない。だから、そこで劇中の人物になりきり、しかも自分の身体で生きた人間を観客の目の前に晒す技をもった人間だけが良い役者なのだ。

B.中島京子『小さいおうち』文藝春秋、を読んだ。
それまでこの人の小説は読んだことがなかった。この作品は直木賞を受賞し、山田洋次によって映画化され、一躍世間の片隅で注目を集めた。ただ、映画はストーリーを追うことに偏して、昭和戦前の東京山の手、という時空の細部までは丁寧に描ききれない。この小説は、丁寧に読む価値がある。
「こうしてわたしたちは、開戦の日を迎える。
真珠湾の日。十二月八日だ。
ぱっとしない一日だった。
二、三日前からラジオが壊れていて、終日流れていたという放送を、私も奥様も聞いていなかった。
やっと知ったのは、夕方になってからだ。
四年生になってから、ひとりで学校へ通われていたぼっちゃんが、駅から家までの坂道を全速力で駆けてきて、叫んだ。
「やったよ!戦争が始まったよ!日本がハワイの軍港へ、決死の大空襲だよ!」
奥様はおっとり出ていらした。
「あらまあ、それ、ほんとなの?恭ちゃん」
「そうさ、午後、校長先生が全校生徒を集めておっしゃったんだもの。ラジオ、聞かなかったの?」
「聞いてないわ。ハワイってどこ?蘭印?仏印?」
「なにを言ってるの?お母ちゃま!ハワイと言ったら、西太平洋じゃないか!」
「お母ちゃまは、地理があんまり得意ではないのよ」
「オランダでもフランスでもないよ。アメリカと戦争を始めたんだよ!」
「あらまあ、そうですか」
「そうですか、じゃないよ!だから女はだめなんだ」
ぼっちゃんは怒って二階に駆け上がり、奥様はふうとため息をつかれた。
「一昨日もお父様は、東條内閣はアメリカと戦わない方針だとおっしゃってたけれど」
奥様がつぶやくと、地獄耳のぼっちゃんは二階から、
「あんまりアメリカが悪いから、堪えに堪えていた日本がもう、堪忍できなくなったんだ。ああ、だから女は嫌なんだ」
と、聞こえよがしに怒鳴った。
奥様も今度はほんとうにひそひそ声で、
「支那との戦争だって四年も続いているのに、また新しい戦争だなんて、ちょっとうんざりするわね」
とおっしゃった。
女がだめだからどうなのか知らないが、たしかにこの日は平井家の男二人が異様に盛り上がり、夜中まで、「敵はァ、幾万、ありとてもォ!」と合唱して大騒ぎした。
旦那様もなぜだかすっかり、開戦派に変貌していたのである。
「アメリカもこれで、もう日本をバカにできないと思い知ったに違いない。日本、よくやった!万歳!」
旦那様は大きな声でそうおっしゃった。
「社長なども言うのだがね。米英は東洋人を一段下の人間と思っているんだ。それで呑めない条件を次々突きつけてくる。社長がアメリカに行ったとき、いきなり初対面の人間にシュウ、シュウ、と、まるで犬のようにあだ名で呼ばれて困惑したというんだよ」
「あらでも、以前、社長さんはそのお話を、アメリカ人がとても友好的だという例に、引いていらっしゃいましてよ」
「そこが、社長のいいところさ。なんでも好意的に解釈しようとする。日本人の美点でもある。ところが思い出してみると、白人がミスター何々と呼ばれているような場所でも、社長だけシュウだったというんだ」
直接聞いたわけではないから、社長さんがどんな思いでこの話をしたのかは、わからない。けれど旦那様の中では、「シュウの話」は、まるきり、逆の逸話に変っていた。
この日の盛り上がりには、正直、わたしもついていけなかった。
けれど翌日の朝刊の見出しを見たときに、何かがすっと私の中に入ってきて、いろいろなことがわかった気がした。
ああ、始まるのだ。新しい時代が始まるのだ、と思った。
それまで毎日、新聞は、日米交渉がいかにうまくいかないかを、ちまちました小さな活字で取り上げていたのだ。東條さんの渋い顔や、ハル国務長官の憎々しい顔が、黒っぽい写真で入っていて、来る日も来る日も進展しない和平交渉を伝えていた。
しかもその間に、いかにアメリカやイギリスが日本をバカにしているか、腰抜けだと思って見下しているか、無理難題を押しつけても言うことを聞くと思っているかを報道していたものだから、新聞を見るのは、うんと嫌だった。
ところが十二月九日の朝刊には、大きな活字でもって、『米太平洋艦隊は全滅せり』『我無敵海軍の大戦果』と、胸のすくような文字が躍動していたのだった。
わたしは表へ出て、深呼吸をした。」中島京子『小さいおうち』文藝春秋、文春文庫、2012, pp.204-207.
作者、中島京子はこの作品を書くにあたって、昭和戦前の新聞雑誌など、当時の普通の人々が生きていた情報空間を細かい部分に注意を払って探索したという。それはこの作品のリアリティをとてもよく支えていると思う。この日米戦争開戦の日の男たちの昂奮は、21世紀の現在こそ記憶するに値する。この日に生きていた人たちは、その後数年間に起きることを予想できなかった。そして、ありえないと思ったことが次々起こったのである。それでも日本軍は強いに決まっているのだから、いずれは勝つ、と信じた人々はこの戦争が自分たちの生活を焼土と殺戮のどん底に落とすまで、何も考えることができなかった。
日本が戦争などするわけがない、もし戦争をするとしても、どこか海外の遠いところでアメリカ軍と一緒にするだけだ、と考えている人々は、昭和15年の日本臣民と同様の妄想を信じている。どうしたらこんな愚かな政府と、その気分に無責任に便乗する人々を、止めることができるのだろう?