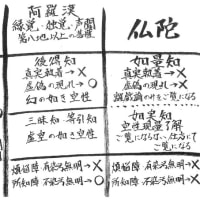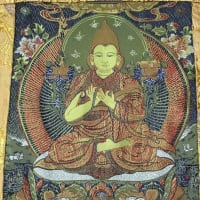四條縄手の戦いの戦闘経過は、当然に太平記を基準に考察されるのだが、物語的に脚色されているところもあるため、そのままを鵜呑みにはできない。
砂山城跡に初めて行ったが、山岳戦を戦うにはもってこいの要所であり、背後の神感寺城の役割を補完するにも十分と感じた。
しかし、生駒山の背後から佐々木道誉軍が進撃し、鷲尾砦、慈光寺砦、神感寺城と落され、客坊城、往生院城も襲われ、砂山城にも敵軍が迫ったのは、前線の正行にも伝えられたはずである。または、狼煙台が至るところにあり、急変を知ったはずだ。
正行には渡辺橋の美談があるように、敵でさえも戦闘が終われば救うようなお方であった。
そんな正行が、後方の味方が危ないと知った時に果たして無視して、更に高師直軍へ向けて進軍できただろうか。
答えは否である。
即座に引き返し、砂山城に迫った佐々木道誉軍へと猛然と攻め戻したと考えるのである。
当然に山を駆け上がり、不利な攻めであるが、味方を助けるために、下り縄手(瓢箪山付近)から四条、上四条と山へ向って戦いながら引き戻したのである。
結果的に砂山城付近は修羅場と化し、本丸は落され、更には東高野街道から攻め上がってきた敵軍と、山からの佐々木道誉軍に挾まれ、現在の上四条の山に入る手前あたり(字天王丿芝付近)にて、大激戦の末についに力尽きて、正時と自刃したのである。
だから、そのあたりには、小楠公終焉碑、小楠公碑、南朝忠臣えい骨碑、死骸の井戸、首洗い池、神宮寺小太郎首塚、和田賢秀供養塚などの遺構が無数に集中してあるわけなのである。字天王丿芝には、元々、正行、正時の五輪塔が建てられており、供養がなされていたのでもある。
激しく燃えている往生院の姿も正行の目にはきっと映っていたのであろう。いかなる思いが去来していたことであろうか。
あぁ、ここがやはり最期のところであったかと、そう思わずにはいられない現地である。
目を閉じればその戦いの様子が目に浮かぶようであった。
砂山城跡に初めて行ったが、山岳戦を戦うにはもってこいの要所であり、背後の神感寺城の役割を補完するにも十分と感じた。
しかし、生駒山の背後から佐々木道誉軍が進撃し、鷲尾砦、慈光寺砦、神感寺城と落され、客坊城、往生院城も襲われ、砂山城にも敵軍が迫ったのは、前線の正行にも伝えられたはずである。または、狼煙台が至るところにあり、急変を知ったはずだ。
正行には渡辺橋の美談があるように、敵でさえも戦闘が終われば救うようなお方であった。
そんな正行が、後方の味方が危ないと知った時に果たして無視して、更に高師直軍へ向けて進軍できただろうか。
答えは否である。
即座に引き返し、砂山城に迫った佐々木道誉軍へと猛然と攻め戻したと考えるのである。
当然に山を駆け上がり、不利な攻めであるが、味方を助けるために、下り縄手(瓢箪山付近)から四条、上四条と山へ向って戦いながら引き戻したのである。
結果的に砂山城付近は修羅場と化し、本丸は落され、更には東高野街道から攻め上がってきた敵軍と、山からの佐々木道誉軍に挾まれ、現在の上四条の山に入る手前あたり(字天王丿芝付近)にて、大激戦の末についに力尽きて、正時と自刃したのである。
だから、そのあたりには、小楠公終焉碑、小楠公碑、南朝忠臣えい骨碑、死骸の井戸、首洗い池、神宮寺小太郎首塚、和田賢秀供養塚などの遺構が無数に集中してあるわけなのである。字天王丿芝には、元々、正行、正時の五輪塔が建てられており、供養がなされていたのでもある。
激しく燃えている往生院の姿も正行の目にはきっと映っていたのであろう。いかなる思いが去来していたことであろうか。
あぁ、ここがやはり最期のところであったかと、そう思わずにはいられない現地である。
目を閉じればその戦いの様子が目に浮かぶようであった。