
こんにちは~♪
今日も この秋に見つけた木の実の続きです。
『 イヌツゲの実 』

モチノキ科 モチノキ属 常緑低木
山では何処ででも見かけるありふれた木ですねぇ~
枝葉が密生していて、強度に刈り込んで種々の形ができ、
垣根にもよく使われていますね。
雌雄異株で、花は6~7月に葉のわきから出て白い小花が多数咲きますが、
花や実は ほとんど目立ちません。

果実は球形で、10月~11月に黒く熟す。
この実を野鳥達が好んで食べるようですが
ペットとして飼われるサザナミインコも好物の実だそうよ。
『 ウワズミザクラの実 』

バラ科ウワミズザクラ属の落葉高木
上溝桜の名前は、宮中で占いの時に溝を彫って使ったことから
「ウワミゾザクラ」と呼ばれて、その名が付いたそうですよ。

赤から黒色に熟していく果実は、
英名が示す Japanese Bird Cherry の通り、野鳥が好んで食べる実。
新潟では、若い果実(緑色の時)を果実酒にしたものを
「あんにんご酒」と呼んで珍重するそうですよ~

Webよりお借りした写真ですが
ウワズミザクラは、春に咲く白い花より
秋の黄葉の紅葉の方が見栄えがしそうねぇ~
オレンジがかった奇麗な紅葉です。

花は、白い5弁の小さな花が密集して房状に咲き
とても桜らしくない桜ですが、
花姿は むしろライラックによく似ていますよ~

ブラシのように見えるのは針のように細くて長い雄しべ。
Webよりお借りした写真ですが、
拡大して見るとよく分かるでしょう~
『 ヤマコウバシの実 』

クスノキ科クロモジ属
別名:モチギ、モチシバ、ヤマコショウ
花期:4~5月で、葉と同時に花も展開。
展開し始めた葉の間から 淡黄色の小さい花が下向きに咲く。
雌雄別種で、日本には雌株しかないのに結実する樹として珍木。

Webからお借りした写真ですが、黄色い紅葉が見事ですね~
ヤマコウバシの名は
枝を折るとよい香りがするところから名付けられたようです。

この黒い果実は液果で アカゲラやツグミなどの餌になるそう。
落葉低木ですが、落葉せずに葉は枯れたまま春まで枝に残ります。
雑木林の中で冬越しする自生のヤマコウバシは
コブシが咲き競う3月下旬の林の中で
こんもりとした茶色い枯葉は ちょっと異質な光景だそうですよ。
この木の名前は初めて知りました。
今まで気に掛けもしなかった樹木や草花ですが
ブログネタの為 お蔭で少々物知りになり 嬉しいですね。
でも 忘れることも早いので 同じ事かしら~~

この写真もWebからお借りしてきましたが
葉の間から小さな淡い黄色の花がついています。
花びらがないような花ですね。
『 ガマズミの実 』

スイカズラ科ガマズミ属の落葉低木
日本の日当たりの良い山野で普通に見かける樹木です。
身近な「雑木」扱いをされているのか、
同じガマズミ(ビバーナム)属のオオデマリ(花が大きくて立派)や
チョウジカマズミ(花がかわいらしくて香りがよい)などと違い、
殆ど庭木として利用されていませんね。

実(果実)は、9~10月には赤くなりますが、
まだ甘味が少なく、渋みと酸味が強いです。
初冬には、甘くなり食べられるそうよ。
果実酒にするときれいな深紅の色になり、
昔から天然の着色料だったそうです~~

熟して甘みの出る初冬まで この赤い実は木に残っていないよね。
小鳥達に目立つように 鮮やかな赤い色をしているもの。。。

ガマズミの花(Webからお借りしました)
花は、5~6月に その年に出た枝先から散房花序を出し、
白い小さな花を沢山咲かせます。
この時期 日当たりの良い山野でよく見かけます。
『 サンショの実 』

ミカン科サンショウ属の落葉低木
山の薫り高い実であることから「山椒」の名が付けられたそう。
別名をハジカミといわれ、
山椒は和のハジカミ、生姜を呉のハジカミと呼ばれています。
山椒の種類には 鋭く大きな棘のある普通の山椒と、
棘が無く、香りが強いが辛味はあとまで残らない朝倉山椒がありますよ。
間近でこんなに大量に見たのは初めて!
最初は何を干しているのか分かりませんでしたよ~
実の中にこんな黒い種があるんですねぇ~

赤い実の中にある中から黒い種
一般的に日常使われすぎて珍しくもないけれど
使用される部位を掲載してみました。
・木の芽-山椒の若葉。
・花山椒-4月~5月に咲く小さな黄色い花。
・実山椒-青山椒とも言い 山椒の未熟の実で、
最も香りと辛味が強く、6月に出回ります。
・粉山椒-秋になると山椒の実が熟して皮が2つに割れます。(割山椒)
実は固くて食べられないが、皮に芳香があり これを粉にして使います。
鰻の蒲焼きに使われますね。
・辛皮-若い枝の皮で、塩水に漬け込んだものを戻してから
醤油で煮たり味噌漬けにして食べるそうです。

山椒の花 (Webよりお借りしました)
この花を沢山摘んで佃煮にするそうです。
ピリッとした香味があつて 炊きたてご飯の友に美味しいでしょうね。
リンゴや柿のように美味しく食べられる訳ではないのに
こんな木々の実を見つけると 何か楽しくなるから不思議ね。
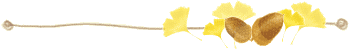
ところで 山鳥たちの好物の実ばかりアップしてるけど
干し柿作りに挑戦している コメントでお馴染みのお友達がいます。
美味しい秋の味覚の干し柿 アップしてほしいなぁ~

こんなのを期待してるんだけど
何しろ初心者! 今頃どうなっているのかなぁ~









































 ありがとうございます。
ありがとうございます。












































































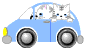
































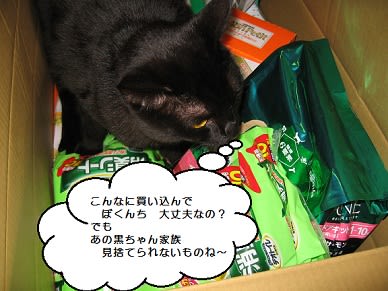
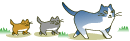














 お払い箱になりましたよ~~
お払い箱になりましたよ~~







