アリストテレス全集 12 岩波書店(1970)
書籍名; アリストテレス全集 12 岩波書店(1970)
編集者; 山本光雄、井上忠、加藤信朗
発行所;岩波書店
発行年、月;1968.4
本の所在;金田一図書館
初回作成年月日;H26.7.24
この書は、岩波書店が全17巻に及ぶアリストテレス全集を発刊するにあたって、1968年4月に始まった第1回目の配本。この事業は世界的にも評価された、大事業となっている。なぜならば、世界に先駆けてアラビヤ語全訳を完成したイスラムが、中世のヨーロッパを席捲し、その後、スペインのレコンキスタ(国土回復運動)で、ヨーロッパ人が手に入れて、それをラテン語に翻訳し、それがルネサンスの発端になったとの説が有力だからである。
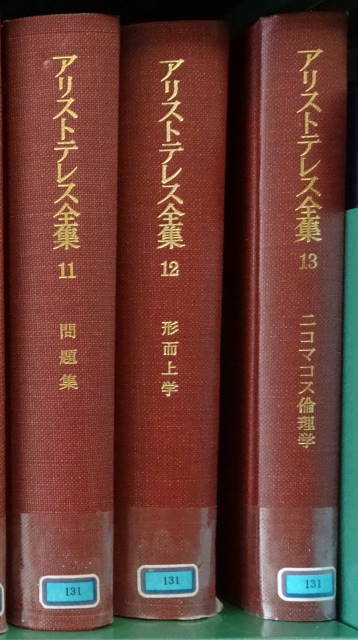
優れた日本文化の文明化のプロセス(18)番外3 イスラム文明の盛衰プロセス より、
第17回の話の中で、次の様に書きました。
『岩波書店がアリストテレス全集を発刊した際には、諸外国から賛辞が贈られたとの事実がある。西欧のルネッサンスがスペインでのレコンキスタがイスラム文明を導入するきっかけとなり、その際にアリストテレス全集のイスラム語版の存在を知り、あわてて西欧の言語訳を作り、それを当時の印刷技術で広めたことが、中世の非合理的な世界から抜け出す原動力となったとの説もある。ちなみに、それまでイスラム文化圏であった地域の多くは、アレキサンダー大王に支配された地域が多く、アリストテレスは若きアレキサンダーの師であった。古代ギリシャの自然科学の知見を素直に受け継いだイスラムが、中世のヨーロッパを席巻していたと時代と言えそうである。』
・14巻からなる大作の第1巻、第1章の目次は、「すべての人間は知るを欲する。人間の知能は感覚から、記憶、経験値、技術知を経て、知恵(理論的な認識・学・哲学)に進む。知恵または哲学は第一の原因や原理を対象とする棟梁的な学である。」とある。
第2章は、「知者(知恵のある者)についての一般の見解から推して知られる知恵の諸特徴。われわれの求める最高の知恵(神的な学)の本性と目標」とある。
ここで、第1章の表題は、古代ギリシャでは、全員参加型の民主主義が行われたが、政治家になるには、まず諸学問をマスターし、その後に哲学をある程度マスターしたものに参加資格が与えられたと聞いたことを思い出す。また、第2章の、「知恵の本性と目標」という言葉は、意味深長に感じる。
いずれにせよ、「形而上学」というものは、「抽象的な学問」とのレッテルを張られているが、具体的な中身を知れば、まったく当たらないということが明白になる。
・第6巻、第1章の目次は、「われわれの求むるは存在としての諸存在の原理や原因である。理論と実践と制作。理論学の三部門。自然学や数学に対してわれわれの学は第一の哲学である。」
・第12巻、第1章の目次は、「われわれの研究対象は実体である。実体は他のすべてに優先する。実体の三種(消滅的で感覚的な実体、永遠的な感覚的な実体、および永遠的で不動な実体)。」である。
レコンキスタについて、Wikipediaでは概要を次のように記している。『レコンキスタ(スペイン語:Reconquista)は、718年から1492年までに行われた、キリスト教国によるイベリア半島の再征服活動の総称である。ウマイヤ朝による西ゴート王国の征服とそれに続くアストゥリアス王国の建国から始まり、1492年のグラナダ陥落によるナスル朝滅亡で終わる。レコンキスタはスペイン語で「再征服」(re=再び、conquista=征服すること)を意味し、ポルトガル語では同綴で「ルコンキシュタ」という。日本語においては意訳で国土回復運動(こくどかいふくうんどう)や、直訳で再征服運動(さいせいふくうんどう)とされることもある。』
先年、スペインを旅行した時にはこの基本的な歴史的事実を知らずに、大いに恥ずかしかった。

この超長期間にわたるイスラムの西欧に対する優位性を明確に記した書物に出会ったので紹介したい。題名は、ストレ-トに、『奴隷になったイギリス人の物語―イスラムに囚われた100万人の白人奴隷』で、著者は大航海時代のノンフクション作家の第1人者として紹介された英国人。2006年にアスペクト社から発行された,406ページの大作だ。
意外な内容を紹介する前に、大航海時代のはるか後のある話を思い出した。『母をたずねて三千里』だ。あの話は、イタリアに住む少年が、アルゼンチンの裕福な家に出稼ぎに出たまま帰らない母親を訪ねる物語だったと思う。近代でも、多くの日本人移民が南米に渡ったのだから、このような地域の貧富(というよりは文明化の程度)のサイクリックな変化は、将来も続いてゆくものだと考えた方がよさそうに思う。
本題に戻る。物語は、モロッコに巨大な宮殿をつくり(歴史上最大と云われているが、材料が基本的には土だったので、砂漠の風で完全に風化してしまった)、巨大な軍隊を持っていた大スルタンのひろばでの儀式から始まる。そこでは、無理に太らされた白人奴隷の売買が行われていた。
当時(1700年前後)は、ヨーロッパ各地やアメリカ新大陸で、白人が奴隷として連れさられるケースが頻発したそうで、モロッコ、アルジェ、チュニス、トリポリなどで奴隷として長期間酷使された事実が、近年明らかになった。
主人公の少年は、11歳のときにたまたま乗っていた船が地中海で海賊に襲われ、以降23年間奴隷としてモロッコのスルタンの近くで働かされた。たまたま、上記の儀式でスルタンの目にとまり、その後を過ごしたので、王宮内部や外交にも接する機会が多く、歴史の証言者になることができた。しかし、拷問でイスラム教に改宗させられ、去勢されてから妻を娶らされる。この間、イギリス大使等との交渉で少数が帰国するが、だれも真実を語らず、また話の多くは現代まで信じられていなかった。しかし、この少年(23年後にはだれの目にも、キリスト教徒のイギリス人とは見えなかった)の話が、かつての友人の証言から信用できると判断がされたという記録が発見されて、著者がこの作品を書くきっかけとなった。
この事実は、8世紀から15世紀末までのイスラムの圧倒的な対西欧の有利が終わって、西欧にルネッサンスが広がった後でも、なをこのような優位性が長期間保たれていたことを示している。文明の衰退のプロセスとそれに要する期間についての、一つの貴重な事例になると思う。
訳者(元 朝日新聞出版局)は、あとがきで次のように記している。
『もうひとつ驚いたのは、イスラム教対キリスト教の対立は今と同じゃないか、という思いだった。十字軍やそれ以前からの宿敵対立の図は、まるで変化していない。サミュエルル・ハンチントンのいう「文明の衝突」は、永遠に続くのだろうか。・・・』
現代社会に暮らす日本人も、西欧文明の中心地を誇る欧米人も、この一千年に亘るイスラム優位の世界を過小評価していることは、文化の文明化のプロセスを考える際の要注意事項だと痛感する次第です。
書籍名; アリストテレス全集 12 岩波書店(1970)
編集者; 山本光雄、井上忠、加藤信朗
発行所;岩波書店
発行年、月;1968.4
本の所在;金田一図書館
初回作成年月日;H26.7.24
この書は、岩波書店が全17巻に及ぶアリストテレス全集を発刊するにあたって、1968年4月に始まった第1回目の配本。この事業は世界的にも評価された、大事業となっている。なぜならば、世界に先駆けてアラビヤ語全訳を完成したイスラムが、中世のヨーロッパを席捲し、その後、スペインのレコンキスタ(国土回復運動)で、ヨーロッパ人が手に入れて、それをラテン語に翻訳し、それがルネサンスの発端になったとの説が有力だからである。
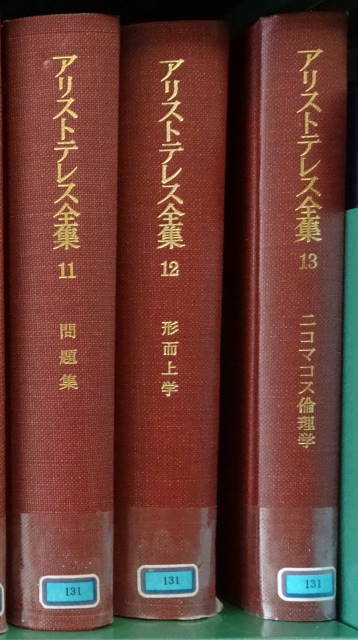
優れた日本文化の文明化のプロセス(18)番外3 イスラム文明の盛衰プロセス より、
第17回の話の中で、次の様に書きました。
『岩波書店がアリストテレス全集を発刊した際には、諸外国から賛辞が贈られたとの事実がある。西欧のルネッサンスがスペインでのレコンキスタがイスラム文明を導入するきっかけとなり、その際にアリストテレス全集のイスラム語版の存在を知り、あわてて西欧の言語訳を作り、それを当時の印刷技術で広めたことが、中世の非合理的な世界から抜け出す原動力となったとの説もある。ちなみに、それまでイスラム文化圏であった地域の多くは、アレキサンダー大王に支配された地域が多く、アリストテレスは若きアレキサンダーの師であった。古代ギリシャの自然科学の知見を素直に受け継いだイスラムが、中世のヨーロッパを席巻していたと時代と言えそうである。』
・14巻からなる大作の第1巻、第1章の目次は、「すべての人間は知るを欲する。人間の知能は感覚から、記憶、経験値、技術知を経て、知恵(理論的な認識・学・哲学)に進む。知恵または哲学は第一の原因や原理を対象とする棟梁的な学である。」とある。
第2章は、「知者(知恵のある者)についての一般の見解から推して知られる知恵の諸特徴。われわれの求める最高の知恵(神的な学)の本性と目標」とある。
ここで、第1章の表題は、古代ギリシャでは、全員参加型の民主主義が行われたが、政治家になるには、まず諸学問をマスターし、その後に哲学をある程度マスターしたものに参加資格が与えられたと聞いたことを思い出す。また、第2章の、「知恵の本性と目標」という言葉は、意味深長に感じる。
いずれにせよ、「形而上学」というものは、「抽象的な学問」とのレッテルを張られているが、具体的な中身を知れば、まったく当たらないということが明白になる。
・第6巻、第1章の目次は、「われわれの求むるは存在としての諸存在の原理や原因である。理論と実践と制作。理論学の三部門。自然学や数学に対してわれわれの学は第一の哲学である。」
・第12巻、第1章の目次は、「われわれの研究対象は実体である。実体は他のすべてに優先する。実体の三種(消滅的で感覚的な実体、永遠的な感覚的な実体、および永遠的で不動な実体)。」である。
レコンキスタについて、Wikipediaでは概要を次のように記している。『レコンキスタ(スペイン語:Reconquista)は、718年から1492年までに行われた、キリスト教国によるイベリア半島の再征服活動の総称である。ウマイヤ朝による西ゴート王国の征服とそれに続くアストゥリアス王国の建国から始まり、1492年のグラナダ陥落によるナスル朝滅亡で終わる。レコンキスタはスペイン語で「再征服」(re=再び、conquista=征服すること)を意味し、ポルトガル語では同綴で「ルコンキシュタ」という。日本語においては意訳で国土回復運動(こくどかいふくうんどう)や、直訳で再征服運動(さいせいふくうんどう)とされることもある。』
先年、スペインを旅行した時にはこの基本的な歴史的事実を知らずに、大いに恥ずかしかった。

この超長期間にわたるイスラムの西欧に対する優位性を明確に記した書物に出会ったので紹介したい。題名は、ストレ-トに、『奴隷になったイギリス人の物語―イスラムに囚われた100万人の白人奴隷』で、著者は大航海時代のノンフクション作家の第1人者として紹介された英国人。2006年にアスペクト社から発行された,406ページの大作だ。
意外な内容を紹介する前に、大航海時代のはるか後のある話を思い出した。『母をたずねて三千里』だ。あの話は、イタリアに住む少年が、アルゼンチンの裕福な家に出稼ぎに出たまま帰らない母親を訪ねる物語だったと思う。近代でも、多くの日本人移民が南米に渡ったのだから、このような地域の貧富(というよりは文明化の程度)のサイクリックな変化は、将来も続いてゆくものだと考えた方がよさそうに思う。
本題に戻る。物語は、モロッコに巨大な宮殿をつくり(歴史上最大と云われているが、材料が基本的には土だったので、砂漠の風で完全に風化してしまった)、巨大な軍隊を持っていた大スルタンのひろばでの儀式から始まる。そこでは、無理に太らされた白人奴隷の売買が行われていた。
当時(1700年前後)は、ヨーロッパ各地やアメリカ新大陸で、白人が奴隷として連れさられるケースが頻発したそうで、モロッコ、アルジェ、チュニス、トリポリなどで奴隷として長期間酷使された事実が、近年明らかになった。
主人公の少年は、11歳のときにたまたま乗っていた船が地中海で海賊に襲われ、以降23年間奴隷としてモロッコのスルタンの近くで働かされた。たまたま、上記の儀式でスルタンの目にとまり、その後を過ごしたので、王宮内部や外交にも接する機会が多く、歴史の証言者になることができた。しかし、拷問でイスラム教に改宗させられ、去勢されてから妻を娶らされる。この間、イギリス大使等との交渉で少数が帰国するが、だれも真実を語らず、また話の多くは現代まで信じられていなかった。しかし、この少年(23年後にはだれの目にも、キリスト教徒のイギリス人とは見えなかった)の話が、かつての友人の証言から信用できると判断がされたという記録が発見されて、著者がこの作品を書くきっかけとなった。
この事実は、8世紀から15世紀末までのイスラムの圧倒的な対西欧の有利が終わって、西欧にルネッサンスが広がった後でも、なをこのような優位性が長期間保たれていたことを示している。文明の衰退のプロセスとそれに要する期間についての、一つの貴重な事例になると思う。
訳者(元 朝日新聞出版局)は、あとがきで次のように記している。
『もうひとつ驚いたのは、イスラム教対キリスト教の対立は今と同じゃないか、という思いだった。十字軍やそれ以前からの宿敵対立の図は、まるで変化していない。サミュエルル・ハンチントンのいう「文明の衝突」は、永遠に続くのだろうか。・・・』
現代社会に暮らす日本人も、西欧文明の中心地を誇る欧米人も、この一千年に亘るイスラム優位の世界を過小評価していることは、文化の文明化のプロセスを考える際の要注意事項だと痛感する次第です。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます