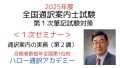ハロー花子が解説する2024年度<日本歴史>【大問2】
<1次セミナー>特別バージョン(その3 )
ハロー花子が、2024年度<日本歴史>【大問2】 を解説させていただきます。
<1次セミナー>特別バージョン(その3 )
ハロー花子が、2024年度<日本歴史>【大問2】 を解説させていただきます。
●ナレーションの確認
みなさん、こんにちは。
ハロー通訳アカデミーのハロー花子です。
今回は、2024年度全国通訳案内士試験「日本歴史」から、大問2の解説をお届けします。
テーマは「奈良の大仏」、つまり東大寺に鎮座する盧舎那仏に関わる歴史です。国家安泰を願ったこの大仏は、8世紀の造立から幾度も焼失と再建を経て、日本の歴史の大きなうねりを映し出しています。
では、順を追って設問を解説していきましょう。
まず、問1ですが、聖武天皇が、743年に「大仏をつくろう」と決意した場所を問う問題です。
この問いの正解は、「近江国の紫香楽宮」です。
当時、疫病や天災が続いており、聖武天皇は仏の力で国を守ろうと考えました。紫香楽宮はそのような思いの中で選ばれた場所だったのです。まさに、仏教によって国を安んじようという思想、「鎮護国家」の象徴的な場所ともいえます。
他の選択肢を見てみましょう。
まず、平城京は確かに奈良時代の首都ですが、大仏造立の詔が出されたのはそこではありません。
難波宮は、飛鳥時代から奈良時代にかけて使われた宮ですが、この詔との関係はありません。
恭仁宮も聖武天皇が一時遷都した場所ではありますが、詔が発せられたのは紫香楽宮です。
次に、問2ですが、1180年に大仏が焼失した背景と、その時代を動かしていた人物、平清盛の行動に関する問題です
正解は、「1159年の平治の乱で、平清盛が源義朝と藤原信頼の軍を破った」という出来事です。
この乱に勝利したことで、平清盛は事実上の政権を掌握し、平家の全盛期を築いていきます。そして、当時、奈良の寺社勢力はこの平家政権に反発していました。その対立が高まり、結果として東大寺を含む南都が戦火に包まれ、大仏が焼失したのです。
他の選択肢について補足します。
「平家納経」は、平清盛の子・重盛が奉納したものであり、直接の関連性は薄いです。
「娘の徳子を鳥羽天皇に嫁がせた」という選択肢ですが、正しくは高倉天皇に嫁いだので、誤りです。
また、「福原京への遷都」は確かに清盛の政策ですが、この設問の焦点である平治の乱とは関連がありません。
次に、問3です。
再建された大仏殿や南大門は、中国・宋の影響を色濃く受けていますが、その背景にあったのが、当時の活発な日宋貿易です。
その貿易で日本に輸入され、とりわけ珍重された品とは何だったのでしょうか?
正解は、「磁器」です。中国の景徳鎮という都市で焼かれた高品質な磁器は、日本では非常に高価な舶来品として大名や寺社に大切にされました。「景徳」の年号にちなんで名付けられた景徳鎮の名は、それだけ信頼されていた証ともいえるでしょう。
誤答に目を向けてみると、銅銭も確かに輸入品ではありますが、景徳鎮との直接的な関係はありません。
生糸も貿易品の一つでしたが、磁器ほどの象徴性は持ちません。
香料はむしろ東南アジア由来が中心で、景徳鎮とは無関係です。
次は、問4ですが、再び焼失の歴史に戻ります。1567年、再建された大仏は、ある戦国武将との戦火によって再び焼かれてしまいました。
その武将とは、誰でしょうか?
正解は、「松永久秀」です。
松永久秀は、戦国時代でも特に個性の強い人物で、時には織田信長に従い、時には反抗するという波乱万丈の生涯を送りました。奈良に拠点を築いた彼は、興福寺や東大寺とも対立し、結果的にこの寺を戦火に巻き込んだのです。
明智光秀は本能寺の変で知られていますが、この事件とは時期が異なります。
荒木村重も信長に背いた人物ではありますが、奈良の大仏焼失とは無関係です。
佐久間信盛は信長の重臣でしたが、衝突の歴史はありません。
最後の問5の問題は、豊臣秀吉と「新しい大仏」についてです。
織田信長の死後、実権を握った豊臣秀吉は、東大寺の大仏再建ではなく、新たに京都・東山で大仏を造立しようとしました。そのために全国から金属を集めたのですが、その際に出した法令が問われています。
正解は、「刀狩令」です。
1588年に出されたこの法令は、農民から武器を没収し、平和な社会を築くためのものでしたが、集められた金属は京都の大仏建立にも使われたと記録されています。秀吉にとってこの大仏造立は、国家統一の象徴でもあったのです。
他の選択肢はどうでしょうか。
太閤検地は土地の調査制度であり、大仏造立とは関係ありません。
人掃令は江戸時代の法令であり、時代が違います。
廃仏令は明治維新後に出されたもので、完全に時代が異なります。
最後にこの大問2のまとめです。
この大問2では、東大寺と奈良の大仏を中心に、日本の宗教と政治の関係が多面的に問われました。
仏教を国家の安定に活用しようとした聖武天皇の発願から、再建を支えた民衆や武士たちの思い、さらには秀吉の国家統治の象徴としての「新しい大仏」まで、その背後には常に、祈りと権力が交錯していたのです。
こうした歴史の流れを理解することで、単なる「正解」を超えて、日本史そのものの奥深さに触れることができるでしょう。
今回は、最後まで動画をご覧になっていただきましてありがとうございました。
この動画が、みなさんの学習に少しでもお役立つことができれば嬉しいです。
もし、よろしければ、「いいね」と「チャンネル登録」もお願いします。
ハロー通訳アカデミーのハロー花子でした。
それでは、また次回の動画でお会いできますことを楽しみにしています。
ありがとうございました。
ハロー通訳アカデミーのハロー花子です。
今回は、2024年度全国通訳案内士試験「日本歴史」から、大問2の解説をお届けします。
テーマは「奈良の大仏」、つまり東大寺に鎮座する盧舎那仏に関わる歴史です。国家安泰を願ったこの大仏は、8世紀の造立から幾度も焼失と再建を経て、日本の歴史の大きなうねりを映し出しています。
では、順を追って設問を解説していきましょう。
まず、問1ですが、聖武天皇が、743年に「大仏をつくろう」と決意した場所を問う問題です。
この問いの正解は、「近江国の紫香楽宮」です。
当時、疫病や天災が続いており、聖武天皇は仏の力で国を守ろうと考えました。紫香楽宮はそのような思いの中で選ばれた場所だったのです。まさに、仏教によって国を安んじようという思想、「鎮護国家」の象徴的な場所ともいえます。
他の選択肢を見てみましょう。
まず、平城京は確かに奈良時代の首都ですが、大仏造立の詔が出されたのはそこではありません。
難波宮は、飛鳥時代から奈良時代にかけて使われた宮ですが、この詔との関係はありません。
恭仁宮も聖武天皇が一時遷都した場所ではありますが、詔が発せられたのは紫香楽宮です。
次に、問2ですが、1180年に大仏が焼失した背景と、その時代を動かしていた人物、平清盛の行動に関する問題です
正解は、「1159年の平治の乱で、平清盛が源義朝と藤原信頼の軍を破った」という出来事です。
この乱に勝利したことで、平清盛は事実上の政権を掌握し、平家の全盛期を築いていきます。そして、当時、奈良の寺社勢力はこの平家政権に反発していました。その対立が高まり、結果として東大寺を含む南都が戦火に包まれ、大仏が焼失したのです。
他の選択肢について補足します。
「平家納経」は、平清盛の子・重盛が奉納したものであり、直接の関連性は薄いです。
「娘の徳子を鳥羽天皇に嫁がせた」という選択肢ですが、正しくは高倉天皇に嫁いだので、誤りです。
また、「福原京への遷都」は確かに清盛の政策ですが、この設問の焦点である平治の乱とは関連がありません。
次に、問3です。
再建された大仏殿や南大門は、中国・宋の影響を色濃く受けていますが、その背景にあったのが、当時の活発な日宋貿易です。
その貿易で日本に輸入され、とりわけ珍重された品とは何だったのでしょうか?
正解は、「磁器」です。中国の景徳鎮という都市で焼かれた高品質な磁器は、日本では非常に高価な舶来品として大名や寺社に大切にされました。「景徳」の年号にちなんで名付けられた景徳鎮の名は、それだけ信頼されていた証ともいえるでしょう。
誤答に目を向けてみると、銅銭も確かに輸入品ではありますが、景徳鎮との直接的な関係はありません。
生糸も貿易品の一つでしたが、磁器ほどの象徴性は持ちません。
香料はむしろ東南アジア由来が中心で、景徳鎮とは無関係です。
次は、問4ですが、再び焼失の歴史に戻ります。1567年、再建された大仏は、ある戦国武将との戦火によって再び焼かれてしまいました。
その武将とは、誰でしょうか?
正解は、「松永久秀」です。
松永久秀は、戦国時代でも特に個性の強い人物で、時には織田信長に従い、時には反抗するという波乱万丈の生涯を送りました。奈良に拠点を築いた彼は、興福寺や東大寺とも対立し、結果的にこの寺を戦火に巻き込んだのです。
明智光秀は本能寺の変で知られていますが、この事件とは時期が異なります。
荒木村重も信長に背いた人物ではありますが、奈良の大仏焼失とは無関係です。
佐久間信盛は信長の重臣でしたが、衝突の歴史はありません。
最後の問5の問題は、豊臣秀吉と「新しい大仏」についてです。
織田信長の死後、実権を握った豊臣秀吉は、東大寺の大仏再建ではなく、新たに京都・東山で大仏を造立しようとしました。そのために全国から金属を集めたのですが、その際に出した法令が問われています。
正解は、「刀狩令」です。
1588年に出されたこの法令は、農民から武器を没収し、平和な社会を築くためのものでしたが、集められた金属は京都の大仏建立にも使われたと記録されています。秀吉にとってこの大仏造立は、国家統一の象徴でもあったのです。
他の選択肢はどうでしょうか。
太閤検地は土地の調査制度であり、大仏造立とは関係ありません。
人掃令は江戸時代の法令であり、時代が違います。
廃仏令は明治維新後に出されたもので、完全に時代が異なります。
最後にこの大問2のまとめです。
この大問2では、東大寺と奈良の大仏を中心に、日本の宗教と政治の関係が多面的に問われました。
仏教を国家の安定に活用しようとした聖武天皇の発願から、再建を支えた民衆や武士たちの思い、さらには秀吉の国家統治の象徴としての「新しい大仏」まで、その背後には常に、祈りと権力が交錯していたのです。
こうした歴史の流れを理解することで、単なる「正解」を超えて、日本史そのものの奥深さに触れることができるでしょう。
今回は、最後まで動画をご覧になっていただきましてありがとうございました。
この動画が、みなさんの学習に少しでもお役立つことができれば嬉しいです。
もし、よろしければ、「いいね」と「チャンネル登録」もお願いします。
ハロー通訳アカデミーのハロー花子でした。
それでは、また次回の動画でお会いできますことを楽しみにしています。
ありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
植山とハロー花子が解説する「日本歴史の傾向と対策」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
はっきり申し上げます!
これでダメならダメです!
●2025年度<日本歴史>の傾向と対策(第1講)(動画)(植山)
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/c13401da33863e7ca013ab1d7d7fc342
●ハロー花子が解説する「日本歴史の傾向と対策」<1次セミナー>特別バージョン(その1)
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/60460438be540d4611abdf3c59a7373f
●ハロー花子が解説する2024年度<日本歴史>【大問1】<1次セミナー>特別バージョン(その2)
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/fb2ff3e18b188c0d46d80a4a48cd9a57
●ハロー花子が解説する2024年度<日本歴史>【大問2】<1次セミナー>特別バージョン(その3)
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/3fd71649bac8d9026556da7facee44a1
●<日本歴史>の問題(2024年度)(キレイに印刷できます!)
http://hello.ac/2024his.PDF
植山とハロー花子が解説する「日本歴史の傾向と対策」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
はっきり申し上げます!
これでダメならダメです!
●2025年度<日本歴史>の傾向と対策(第1講)(動画)(植山)
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/c13401da33863e7ca013ab1d7d7fc342
●ハロー花子が解説する「日本歴史の傾向と対策」<1次セミナー>特別バージョン(その1)
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/60460438be540d4611abdf3c59a7373f
●ハロー花子が解説する2024年度<日本歴史>【大問1】<1次セミナー>特別バージョン(その2)
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/fb2ff3e18b188c0d46d80a4a48cd9a57
●ハロー花子が解説する2024年度<日本歴史>【大問2】<1次セミナー>特別バージョン(その3)
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/3fd71649bac8d9026556da7facee44a1
●<日本歴史>の問題(2024年度)(キレイに印刷できます!)
http://hello.ac/2024his.PDF
●上記、ご自分で印刷できない方は、<ハローカラー印刷サービス>をご利用ください。
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/ebb0fe30d2134dc5ce0c238d02856180
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「ハロー花子」のありえへん<AI解説>!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2025年度全国通訳案内士試験のガイドラインの主な変更点
https://youtu.be/kABd1nwtPvY
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2025年度<1次セミナー>資料・動画
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
各科目とも、順次、<1次セミナー>を YouTube にて公開していく予定です。2025年度の受験者は、下記の資料を印刷して、予習、準備をしておいてください。
はっきり申し上げます!
これでダメならダメです!
2025年度<1次セミナー>資料・動画
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
各科目とも、順次、<1次セミナー>を YouTube にて公開していく予定です。2025年度の受験者は、下記の資料を印刷して、予習、準備をしておいてください。
はっきり申し上げます!
これでダメならダメです!
●2024年度日本歴史の問題
http://hello.ac/2024his.PDF
●<日本歴史>
<日本歴史>の傾向と対策(資料)(キレイに印刷できます!)
http://www.hello.ac/2025.his.pdf
http://hello.ac/2024his.PDF
●<日本歴史>
<日本歴史>の傾向と対策(資料)(キレイに印刷できます!)
http://www.hello.ac/2025.his.pdf
「松尾芭蕉」が「日本歴史」に7回出題される理由
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/1cadcf2be0d77f46d9a6b4720b745c32
「親鸞」が「日本歴史」に7回出題される理由
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/6fe6b4d5e8875d4a252bd6976b0e452d
「法隆寺」が「日本歴史」に6回出題される理由
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/483089b1327020c566267b6f06c5e081
●<通訳案内の実務の傾向と対策>(第1講) https://youtu.be/KTtmkRrmYLI
資料(1)「通訳案内の実務の傾向と対策」(キレイに印刷できます) http://www.hello.ac/2025.jitumu.pdf
資料(2)「通訳ガイドテキスト」(キレイに印刷できます) http://www.hello.ac/2025.guidetext.pdf
●<一般常識> 「一般常識の傾向と対策」(キレイに印刷できます) http://www.hello.ac/2025.gen.pdf
●<日本地理> 「日本地理の傾向と対策」(キレイに印刷できます) http://www.hello.ac/2025.geo.pdf
●上記、ご自分で印刷できない方は、<ハローカラー印刷サービス>をご利用ください。 https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/ebb0fe30d2134dc5ce0c238d02856180
以上