故・中谷宇吉郎博士(1900~62)の「森羅万象帖展」の続き。
空から降ってくる雪の結晶を研究することによって天候状態を
解明していったそうだけど、それに加えて仮説を実験室で再現
するために人工雪を作る実験に向かう。
3年がかりだったそうだけど、1936年(昭和11)には大学の低
温実験室(-50度だって!)で人工雪の製作に世界で初めて成功。


北大低温実験室での研究の様子。写真はこちらから。
人工雪の成功に関する番組がBBCで作られてて、当時の様子や、
雪の結晶が生成する過程がよくわかる。英語やし、いつまで残
ってるかわかんないけどw
Ukichirō Nakaya (中谷宇吉郎) - Artificial Snowflakes
結晶の枝っていうのか、にょきにょき伸びていく様は植物みた
い。人工という感じがしなくって、有機的生態的な感覚が強く、
きっと自然界でもこうして結晶がうまれるんだろうって思う。
博士はこの生成過程を写真、映像で記録していったことも、こ
の番組からも伺える。これが後に岩波科学映画を作ることに繋
がるのだろう。
北海道での研究がどんどん世界レベルになっていく。温度と水蒸
気量の値を変えれば結晶の形が違ってくることがわかり、測定値
をグラフ化するのね。

のちに中谷ダイヤグラムと呼ばれて世界的に知られるようになった
図だそうだ。よくわからないけど、美しいなぁと思う。
雪の結晶分類表というのも作成され、六花だけでなく、針、砲弾、
角柱、扇、段々鼓なんていうのある。結晶のパターンが40種類だ
っていう指針を出すということが大きな業績なんやろう。

博士は雪の基礎研究に基づきながら、実社会での応用にも積極的
だったそうだ。鉄道線路が霜柱などで土が盛り上がる現象「凍上」
に対する解決策は今でも使われているっていう話には驚く。
飛行機の翼やプロペラへの着氷防止、滑走路の霧の消散といった風
土と結びついた課題を追求し続けたそうだ。
「科学で大切なのは役に立つことだ」という師・寺田寅彦さんの教え
を受けついだことが、この点でもわかる。
空から降ってくる雪の結晶を研究することによって天候状態を
解明していったそうだけど、それに加えて仮説を実験室で再現
するために人工雪を作る実験に向かう。
3年がかりだったそうだけど、1936年(昭和11)には大学の低
温実験室(-50度だって!)で人工雪の製作に世界で初めて成功。

そっと取り出して顕微鏡で覗いてみると、この出来
立ての雪は天然の雪よりもいっそうの見事さである。
立ての雪は天然の雪よりもいっそうの見事さである。

北大低温実験室での研究の様子。写真はこちらから。
人工雪の成功に関する番組がBBCで作られてて、当時の様子や、
雪の結晶が生成する過程がよくわかる。英語やし、いつまで残
ってるかわかんないけどw
Ukichirō Nakaya (中谷宇吉郎) - Artificial Snowflakes
結晶の枝っていうのか、にょきにょき伸びていく様は植物みた
い。人工という感じがしなくって、有機的生態的な感覚が強く、
きっと自然界でもこうして結晶がうまれるんだろうって思う。
博士はこの生成過程を写真、映像で記録していったことも、こ
の番組からも伺える。これが後に岩波科学映画を作ることに繋
がるのだろう。
北海道での研究がどんどん世界レベルになっていく。温度と水蒸
気量の値を変えれば結晶の形が違ってくることがわかり、測定値
をグラフ化するのね。

のちに中谷ダイヤグラムと呼ばれて世界的に知られるようになった
図だそうだ。よくわからないけど、美しいなぁと思う。
雪の結晶分類表というのも作成され、六花だけでなく、針、砲弾、
角柱、扇、段々鼓なんていうのある。結晶のパターンが40種類だ
っていう指針を出すということが大きな業績なんやろう。

博士は雪の基礎研究に基づきながら、実社会での応用にも積極的
だったそうだ。鉄道線路が霜柱などで土が盛り上がる現象「凍上」
に対する解決策は今でも使われているっていう話には驚く。
飛行機の翼やプロペラへの着氷防止、滑走路の霧の消散といった風
土と結びついた課題を追求し続けたそうだ。
「科学で大切なのは役に立つことだ」という師・寺田寅彦さんの教え
を受けついだことが、この点でもわかる。













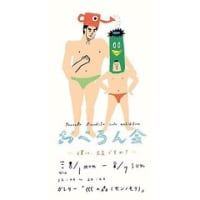






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます