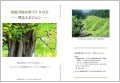運営委員長の岡野です。
スウェーデンが計画的に緑の福祉国家=エコロジカルに持続可能な国づくりを進めていることは、すでに繰り返しご紹介してきたとおりです。
福祉国家を創りあげることができた大きな要因として、その経済政策をリードしたストックホルム学派経済学があると考えられます。
グンナー・ミュルダール(1898-1987)はストックホルム学派の代表的な理論家で、1920年代末から30年代にかけて政府の要職も務め、後にノーベル経済学賞も受賞しています。
スウェーデン・モデルを学ぶ中、ストックホルム学派やミュルダールの経済学についてももっと知りたいと思っていましたが、最近、遅ればせながら藤田菜々子『ミュルダールの経済学 福祉国家から福祉世界へ』(2010、NTT出版)の存在を知りました。
本格的な学術書なので(その割には明快な文章で一般の読者にも十分読めるものになっていますが)、関心を共有するみなさん全員に全体を読み通していただくのは難しいかもしれませんが、その要点だけでもシェアできるといいと思い、本会の会員でもある増田満氏に、私の主宰する『サングラハ』誌に紹介書評を書いていただきました。
増田氏ご本人の承認を得て、以下何度かに分けて転載します。
持続可能な国づくりに向けた、さらなる学びの素材にしていただけると幸いです。
* * * * *
『ミュルダールの経済学 福祉国家から福祉世界へ』(藤田菜々子 NTT出版)を読む
増田満
カール・グンナー・ミュルダールは、スウェーデン型福祉国家形成に多大な寄与をなし、1974年にノーベル経済学賞を受賞した大学者です。
彼の研究領域は極めて幅広く、アメリカの財団に依頼され黒人差別問題を研究したり、あるいはインドに渡り低開発国経済を研究したり、また国会議員や国連機関の委員となって自国および国際社会での政策作成に携わったりしました。このような多面性の故に、これまで彼の経済学の全体像を統合的に描くような研究はなかったそうです。そのような状況を世界で初めて打開したのが本書『ミュルダールの経済学』(2010年)です。同書で藤田菜々子氏は、ミュルダール経済学の全体像が「累積的因果関係論」を中心にして展望できると論じ、さらにはミュルダールが理想とした福祉世界というヴィジョンについて詳しく述べています。
読後特に印象に残ったことにミュルダール経済学が平等を最高の価値だと明確に規定していることがあります。拡張しすぎた貧富の格差を是正すべきだと多くの人々が訴えている今、平等を目指すミュルダールの考えは極めて示唆に富むものだと本書は指摘していますし、私もその通りだと思いました。そこで皆様に是非本書を手に取っていただきたいと考え、以下で本書の一部概要をご紹介することにした次第です。
ところで、「サングラハ」142号と143号でご紹介しましたピケティの税制案は、まさに格差是正を目指したもので、その目的はミュルダール経済学のものと重なります。そこで彼の考えとミュルダール経済学との比較もしてみました。また、「緑の福祉国家」という環境問題の解決も視野に入れたスウェーデン発の新しい福祉国家像を、古典的福祉国家建設に力のあったミュルダール経済学の枠組みで扱うとどうなるのかも検討してみました。
経済学は価値判断から独立し得ない
『人間主義経済学序説』(新思索社、2007年)の著者である後藤隆一氏は、既存の経済学についてネット対談で次のように語っています。
経済学は、人間を扱う学問ですから、価値や意味を問うことは避けられません。しかし、自然科学を模倣して出発した経済学は、それを避け、むしろ隠そうとしてきました。事実、経済学は、価値判断からの自由を建前としながら、功利主義哲学と自然法思想を前提としています。しかし、欲望や目的の内容を問うことを避け、その手段の効率のみを追求してきました。しかし、隠された欲望の目的は、功利主義哲学の「営利」であり、快楽の追求と苦痛の回避ですから、経済学を根元的に批判すると功利主義の批判になります。
もう一つの隠された前提は、自然法思想で、「市場経済では、欲望を追求する個人の行動によって自動的に社会の需要と供給は均衡する」という予定調和の思想です。この思想をめぐって、経済学のイデオロギーは、自由主義と社会主義に分かれてきたと言ってもよいほどだと思います。
(ネット対談、話し手 後藤 隆一、 聞き手 山本 克郎 「小島志ネットワーク」代表幹事、 テーマ『ヒューマノミックスとは何か、そこで、何が問われるのか』より)
この引用文にあるような、経済学が暗黙裡に自然法や功利主義に基づく価値判断を前提にしているという考えは、ミュルダールに強く自覚されていたことです。そこで彼はどうすれば経済学を価値判断とか政治的思弁から独立した客観的科学にできるかと問うことになります。そして『経済学説と政治的要素』(1930年)で次のように結論します。「あらゆる形而上学的要素を徹底的に切り捨ててしまえば、一団の健全な実証的経済理論が残り、そしてそれらは価値判断からまったく独立」(『ミュルダールの経済学』p.78、以下断りがなければ引用は同書からです)なので、経済学を客観的な科学にすることができるだろうと。そうして「選択された一組の価値前提」を、そのような経済学によって得られた事実に関する客観的知識につけ加えれば、政治的結論を推論できるとしたのです。
しかしその後ミュルダールは価値判断から独立した一団の科学的知識が得られるという信念を素朴な経験主義であるとしてしりぞけます。それは次のように考えたからです。
事実というものは、ただ観察によって概念や理論に組織化されるのではない。なるほど概念や理論の枠がなければ科学的事実はなく、混沌があるだけである。どんな科学的な作業にも欠くことのできない先験的要素がある。答えが与えられる前に問いが発せられなければならない。問いはいやしくもわれわれの関心の表現であり、それらは根底において価値判断である。したがって価値判断は当然、われわれが事実を観察し理論的分析を行う段階ですでに含まれており、決してわれわれが事実と価値判断とから政治的推論を引き出す段階で現れるだけではない(p.78)。
たとえば、自由競争の理論や最適人口の理論といった伝統的経済理論や、経済学において頻繁に使われる「均衡」などの諸概念は、暗黙のうちに政治的に望ましいものを示していて、従って政治的偏向を含むというのです。すなわち「専門用語のほとんどが『価値を担っている』のであり、用語の直接的使用のなかに規範は隠されている」(p.72)のです。