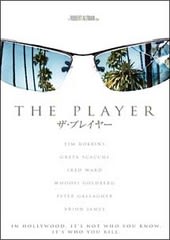またしてもオリヴェイラにしてやられた!と思ったラストシーン。結末を宙づりにしつつ、観客を煙に巻くことをひょっとして歓びとしている?
物語は、心の傷を癒しながら生きる老優の姿をユーモアをもまぶして描く。名優と謳われたジルベール・ヴァランスは既に年老いていたが、まだまだ現役の役者として舞台に映画に活躍していた。だがそんな彼のもとに悲報がもたらされる。妻と娘夫婦が事故で亡くなったのだ。遺された幼い孫を心の支えに、それでもジルベールは今日も舞台に立つ。ある日、アメリカ人監督がやってきて、病気で降板してしまった役者の代役をジルベールに依頼する。クランクインは3日後、しかも英語のセリフだ。難しい役だけれど、ジルベールならできるはずだった…
冒頭、延々と舞台劇をそのまま映す。この映画には劇中劇がいくつもあって、それがけっこう長いものだから退屈してしまいそうになる。それに、「なんでこんなシーンが挟まってるの?」と不可解に思うような「無意味な場面」があるので、これまた退屈。ところがところが、この「無意味な場面」は無意味どころか、すべてに意味を持たせてあるのだ。最後まで見ればなるほどと納得する場面ばかり。同じシーンを繰り返すことによってもたらされるユーモアとペーソスの心憎いばかりの按配や、困難な役をオファーされた頑固な老優が懸命に演じるスリルある場面は、優れた演出の賜だ。
最初のうち退屈だと思っていたこの物語にどんどんのめり込み、最後はほとんど手に汗握っているから不思議。そして「衝撃の」ラストシーン。年老いていくことの苦しさ惨めさが否応なく見る者の心に残る。
メイキャップの場面が面白い。とても丁寧に撮られていて、メイク担当者の手際のよさがよくわかる。わたしみたいに化粧しない人間には化粧の場面は新鮮に見えるのだ。若作りの化粧を施されて最後は鬘をつけられたジルベールだが、これが全然似合わない。元のはげ頭のほうが似合っているし美しい。こういうことってあるのか! この場面にも、若作りする老優のどこか不機嫌で忸怩たる思いがそこはかとなく漂ってくる。
特典映像に監督インタビューがあって、この映画の意図をオリヴェイラは「文明批判」だと述べている。しかし、そのような大仰な意図はこの映画から直接くみ取ることは難しい。それよりも、もっと身近な「老い」の辛さのほうがわたしの胸に迫る。ジルベールがオファーされた作品がジョイスの『ユリシーズ』であるというところも何か含蓄深いものを感じるし、何よりも、わたしが去年から読み始めて文庫本第2巻の途中でうっちゃったままになっている丸谷才一ほか訳『ユリシーズ』のことを思い出してぎっくとしてしまった。(レンタルDVD)
-----------------------------------------
JE RENTRE A LA MAISON
ポルトガル/フランス,
2001年、上映時間 90分
監督・脚本: マノエル・デ・オリヴェイラ、製作: パウロ・ブランコ
出演: ミシェル・ピコリ、カトリーヌ・ドヌーヴ、ジョン・マルコヴィッチ、アントワーヌ・シャピー、レオノール・シルヴェイラ