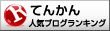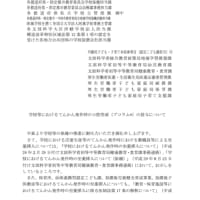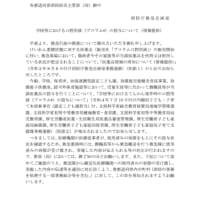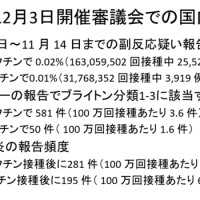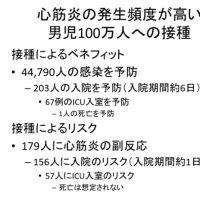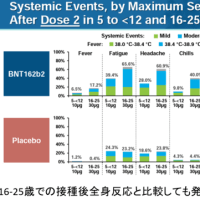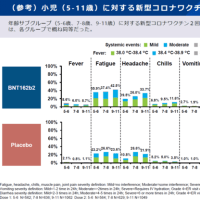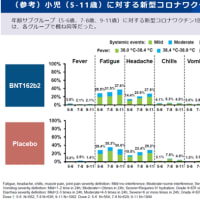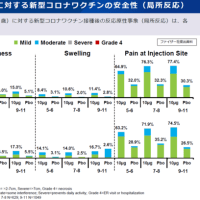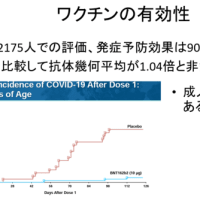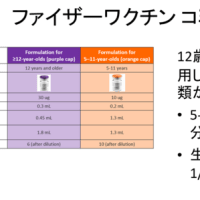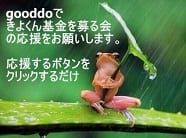薬剤血中濃度に関する半減期と投与間隔の関係
- 蓄積率は薬物の消失速度定数と投与間隔によって規定されるが、消失速度定数から算出される半減期が投与間隔に等しい場合には、蓄積率2と計算され、定常状態における血中濃度は初回投与時の2倍に上昇する(1)。
- また、投与間隔が半減期よりも長いばあいには蓄積率は2に至らず、逆に投与間隔が半減期よりも短い場合には蓄積率は2を超えるので、薬物の連続投与を行う場合には、その薬物の半減期と投与間隔との比較をすることによって、初回投与時から定常状態に到達した時の血中濃度の上昇の程度が比較的簡単に予測できる(1)。
持続投与により薬物血中濃度が定常状態となるまでの時間
- 薬物の持続投与開始から定常状態に達するまでに必要な時間は、薬物の投与速度とはかかわりなく、繰り返し吸息静脈内投与時と同様に、投与開始から半減期の2倍の時間が経過すると定常状態の血中濃度の50%、3倍では88%、5倍では97%まで到達する(1)。
- 薬物の投与速度を変更することにより、その血中濃度は変化するが、定状状態に到達するまでの時間は変わらない(1)。
- 薬物の半減期の値の約7倍の時間が経過すると、蓄積の加速度はなくなり、血中薬物濃度は定常状態に到達し、臍高血中薬物濃度と最小血中薬物濃度との間を単に上下に変動するようになる(2)。
8時間の半減期の薬剤の投与間隔と投与量に関する薬物血中濃度の推移の関係
Reference: