
図書館にて借りる。最近図書館利用復活中。
実はもう返してしまったので手元にないのだけど、タイトル通り大正昭和平成の100年間に女性に関するトピックを丁寧に解説したものです。
これ、実を言うと私にはそれほど感激というほどではなかったのですね。大体知ってるような?特別そうだったのかと頷きもしないし?とか思ってたのですが、いやこれは後世に残す歴史本なのでありまして私のような当事者に向けて書かれたわけではないのですよね。むしろこれはごく若い男性女性、そして女性の歴史にさほど興味を持たずに生きてきた年配の男性に読んでいただきたい本なのです。
しかし女性の歴史って、いや日本の女性の歴史、というべきでしょうけどこの100年間、進んできたようで進んでないような「女は強くなった」「でしゃばってきた」「これ以上女が強くなったらどうなる」とか言われ続けてきたのですが、案外「三歩進んで二歩下がる」という感じでじれったいことこの上ない気がします。
結局政治家や社長になった女性は少ないし、法律でも女性に関することはあれもこれも未解決で、例えば母子家庭の貧困の酷さとかは女性の立場のなさを物語ってますし、ピルの理解度の低さ、産婦人科の理解度の低さ、いまだに大学入試での女性差別、セクハラ・痴漢の横行、給料の男女差、家庭内での男女の役割分担の相変わらずさ、などなど果たして100年間にどれくらい改善されたのか、むしろ後退してたりしないのかとすら思ってしまいます。いやさすがに後退はしてないと願いたいですが。
最近になってやっと知ったというか、気づいたことで本当に今更なんですが先の戦争で変わったのはやはり男女差別の問題なんですよね。
よく「戦後女性は強くなった」と耳タコくらい聞いていたのですが、全然理解してなくて実は本当にそうだったのですね。(ほんとに今更)というのは先日松本清張の本を読んでて初めて「あっ」と気づいたのですよ。
たしか「この戦争で日本の男はくじけてしまった。戦争で負け、米軍が入ってきて日本の女性をちやほやした。向こうの男たちにとってはそれは当たり前のことだったけど、日本の女はそういうことは初めてだったので驚いた。そういうことがあってもいいのだと初めて気づいたのだ。それを日本の男たちは目の当たりにしても何もできなかった。負けた男には言い分がなかった。日本の女たちは初めて解放された」というような文章があって、それで初めて「戦後女は強くなった」の意味が解ったのです。
戦争は絶対反対で絶対あってはならないけどその恐ろしい戦争がなければここまで男女の価値観が変わることはなかったのかもしれません。
(だとしても戦争はだめですよ)
ただ悲しいのは戦後物凄い勢いでそういった価値観の改革があったのだけど、その後はまたずるずるしてしまったようにも思えるのですね。
それは改革しきれない(私も含めた)女性側の弱さも原因だし、女性を解放しきれない男性側の弱さ(女性に甘えたいという)も原因ですね。良くも悪くも気質の弱い国民なのだと思います。
革命、という言葉が好きだけどなかなかそれを実行できない国民性なのです。
タイトル作「百年の女 - 『婦人公論』が見た大正、昭和、平成」を読んだ感想としては「その半分以上生きてきた女としては結構イライラする本でした」という感じでしょうか。
丹念に書かれているだけになんだかずーっと空しい繰り返しをしているようでがつんと一発ぶちかましてやったことは何もないように思えるのでした。
でも上で言ったように若い男女と女の歴史に興味のなかった年配男性は是非読んでみてください。
日本の女性の100年の歴史、確かに刻まれていると思いますよ。










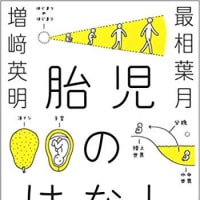



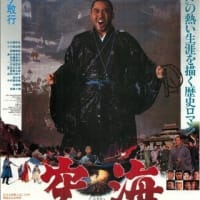

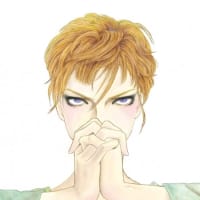

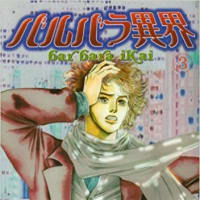
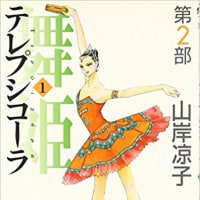
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます