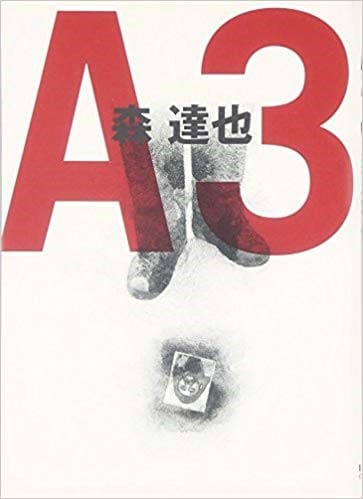宗教についていろいろ本を読んでいたらネットを見ててもその文字が目に飛び込んできます。やはり気にしているからでしょうね。
それとも誰もが宗教について考えている時期なのでしょうか。
森達也氏の「A3」しかり、家入一真氏の問いかけ「あなたにとって宗教とはなんですか?」しかり。
私にとって宗教とは。自分にとっての宗教は生活・人生に当たり前の一部分であってきましたし、これからもたぶんそのままなのかなとは思います。
というのは、よく「日本人は無宗教」的なことを言いますね。私も大方と同じような感じであまり熱心に宗教活動をしてはいませんがお葬式関係は仏教で年末の鐘の音に反感は持たないしむしろ良いと思いますし、結婚式やお祝いが神前なのも当然だと思ってますし、悪い人には罰が当たると思ってますしお天道様はご存じだよ、と思います。ご飯を食べる時に(あまり言いませんが)いただきます、というのは良いことですし悪い言葉を口にするのは気が進みません。そういったことは日常の中に当たり前として溶け込んでいて宗教とも思わないで守っているわけです。
そして多くの人のように極端な宗教活動には懐疑心が湧きます。自分だけで信じている分にはいいのですが家を訪問したり一般常識とかけ離れた(例えば輸血を禁じるとか避妊をしないとか離婚できないとか)規則を厳守するのには抵抗がある、というような平凡な日本の中の一市民であります。
そんな自分自身には緩い宗教観の人間ですが宗教について考えることにはとても興味があります。
以下、考えながら書いていってしまいます。
宗教には二つの意義があって「やさしさ」と「強さ」です。この二つは互いに絡み合っています。
「宗教のやさしさ」は人々の心を救ってくれます。魂と言ってもいいです。不安になった時なにかに支えてもらわないと倒れそうな時がありますがなかなかそんな時にさっと支えてくれる人は現れません。でも宗教を信じていればその主が手を差し伸べてくれると信じられるというわけです。「やさしさ」がために強くなれるわけですね。
「宗教の強さ」はそういう人々を救ってくれる「やさしい宗教」をどのくらい強く真剣に信じているか、と問われ証明することです。困難な修行もそうですし厳しい規律を守ることもそうでしょう。そして次第にそんな素晴らしい宗教を信じないという異宗教と戦いどちらが優れた宗教であるか、どちらの宗教を信じているものが正しい人間なのかを懸けて殺し合う、という事態に発展していきます。
互いに「私の宗教のほうが真実やさしいのだ」と主張ながら殺し合うあけです。
隣人を殺しても姦淫してもいけないが、異教徒は人間でないから殺害しても凌辱してもかまわない、という規律は多くの宗教で成立してしまうようです。(その場合民族、という宗教も現れてきます)
さあて宗教はあった方がいいのでしょうか。ないほうがいいのでしょうか。
現実としては「悪い方向へ走ろうとする宗教は抑えながら、やさしい宗教を守ることがベター」というチョイスになるのではないでしょうか。
宗教の是非を単純に決めてしまうのはそれも危険なのですね。
宗教は現存の神様仏様だけではありませんね。科学・経済・主義の神様、というのも恐ろしいものであるからです。科学・経済・主義が神になる時どんな怖ろしいことになるかはもう実証済みですね。
歯止めのない科学、極端な自由経済、歪んでしまう共産主義、どれも恐ろしいし、実際腐敗してしまいました。
だからと言って科学の発展は望ましいし、経済も社会を考えることも大切なことなのです。
宗教もまた必要であるか、ないかの二択にするわけにはいかないのです。
宗教は良いけど新興宗教は怖い。
これも私もそう思うのですがそうだと決めつけるわけにはいきません。
当たり前ですが、どの宗教も始まりはあるわけだし、長い時間の中で改善され洗練されていくものですし、また長い間に腐敗し悪化していくこともあるわけですから。
イデオロギー(主義)もまた同じですよね。
つまりなんでも緩い感覚の中でゆったりと考えながら進んでいく、という状態でありたいということです。
突き詰めた極限的な世界観、宗教観はかっこいいですが、やはりすぐに無理が来ます。
そしてどこか間違ってますし、そこから歪んでくるのです。
異なったイデオロギー、異なった宗教を持った人ともゆったり話し合えるような宗教であるならいいなと思います。
力の弱い人、子供や病人や貧しい人やマイノリティにやさしい宗教であるなら良いなと思います。
戦争をせず、男女差別がなく、人種差別がなく、何事も無理強いをしない宗教であるなら良いなと思います。
そして違った宗教があることも楽しいことだと思います。
それとも誰もが宗教について考えている時期なのでしょうか。
森達也氏の「A3」しかり、家入一真氏の問いかけ「あなたにとって宗教とはなんですか?」しかり。
私にとって宗教とは。自分にとっての宗教は生活・人生に当たり前の一部分であってきましたし、これからもたぶんそのままなのかなとは思います。
というのは、よく「日本人は無宗教」的なことを言いますね。私も大方と同じような感じであまり熱心に宗教活動をしてはいませんがお葬式関係は仏教で年末の鐘の音に反感は持たないしむしろ良いと思いますし、結婚式やお祝いが神前なのも当然だと思ってますし、悪い人には罰が当たると思ってますしお天道様はご存じだよ、と思います。ご飯を食べる時に(あまり言いませんが)いただきます、というのは良いことですし悪い言葉を口にするのは気が進みません。そういったことは日常の中に当たり前として溶け込んでいて宗教とも思わないで守っているわけです。
そして多くの人のように極端な宗教活動には懐疑心が湧きます。自分だけで信じている分にはいいのですが家を訪問したり一般常識とかけ離れた(例えば輸血を禁じるとか避妊をしないとか離婚できないとか)規則を厳守するのには抵抗がある、というような平凡な日本の中の一市民であります。
そんな自分自身には緩い宗教観の人間ですが宗教について考えることにはとても興味があります。
以下、考えながら書いていってしまいます。
宗教には二つの意義があって「やさしさ」と「強さ」です。この二つは互いに絡み合っています。
「宗教のやさしさ」は人々の心を救ってくれます。魂と言ってもいいです。不安になった時なにかに支えてもらわないと倒れそうな時がありますがなかなかそんな時にさっと支えてくれる人は現れません。でも宗教を信じていればその主が手を差し伸べてくれると信じられるというわけです。「やさしさ」がために強くなれるわけですね。
「宗教の強さ」はそういう人々を救ってくれる「やさしい宗教」をどのくらい強く真剣に信じているか、と問われ証明することです。困難な修行もそうですし厳しい規律を守ることもそうでしょう。そして次第にそんな素晴らしい宗教を信じないという異宗教と戦いどちらが優れた宗教であるか、どちらの宗教を信じているものが正しい人間なのかを懸けて殺し合う、という事態に発展していきます。
互いに「私の宗教のほうが真実やさしいのだ」と主張ながら殺し合うあけです。
隣人を殺しても姦淫してもいけないが、異教徒は人間でないから殺害しても凌辱してもかまわない、という規律は多くの宗教で成立してしまうようです。(その場合民族、という宗教も現れてきます)
さあて宗教はあった方がいいのでしょうか。ないほうがいいのでしょうか。
現実としては「悪い方向へ走ろうとする宗教は抑えながら、やさしい宗教を守ることがベター」というチョイスになるのではないでしょうか。
宗教の是非を単純に決めてしまうのはそれも危険なのですね。
宗教は現存の神様仏様だけではありませんね。科学・経済・主義の神様、というのも恐ろしいものであるからです。科学・経済・主義が神になる時どんな怖ろしいことになるかはもう実証済みですね。
歯止めのない科学、極端な自由経済、歪んでしまう共産主義、どれも恐ろしいし、実際腐敗してしまいました。
だからと言って科学の発展は望ましいし、経済も社会を考えることも大切なことなのです。
宗教もまた必要であるか、ないかの二択にするわけにはいかないのです。
宗教は良いけど新興宗教は怖い。
これも私もそう思うのですがそうだと決めつけるわけにはいきません。
当たり前ですが、どの宗教も始まりはあるわけだし、長い時間の中で改善され洗練されていくものですし、また長い間に腐敗し悪化していくこともあるわけですから。
イデオロギー(主義)もまた同じですよね。
つまりなんでも緩い感覚の中でゆったりと考えながら進んでいく、という状態でありたいということです。
突き詰めた極限的な世界観、宗教観はかっこいいですが、やはりすぐに無理が来ます。
そしてどこか間違ってますし、そこから歪んでくるのです。
異なったイデオロギー、異なった宗教を持った人ともゆったり話し合えるような宗教であるならいいなと思います。
力の弱い人、子供や病人や貧しい人やマイノリティにやさしい宗教であるなら良いなと思います。
戦争をせず、男女差別がなく、人種差別がなく、何事も無理強いをしない宗教であるなら良いなと思います。
そして違った宗教があることも楽しいことだと思います。