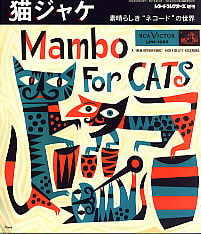新ブログhttp://jazzlab.blog67.fc2.com/もご覧ください。
新ブログhttp://jazzlab.blog67.fc2.com/もご覧ください。ジャズ入門書や指南書の類は、巷に佃煮にして売れるほど沢山存在ますが、ジャズを題材にした小説となるとぐっと少なくなります。ましてやミステリ小説となると皆無ですね。僕の知る限りでは、ジャズ関連のミステリ小説を書く作家は田中啓文しかいません。
自身もテナー・サックスを吹く現役のジャズ・プレーヤーであり、関西で活動をしている“ ザ・ユナイテッド・ジャズ・オーケストラ ”のバンドマスターでも田中啓文は、93年に本書にも収録されている表題作 『 落下する緑 』 で 「 鮎川哲也の本格推理 」 に入選し作家デビューを果たした作家です。
彼の著書の中で、この永見緋太郎の事件簿シリーズだけがジャズがらみのミステリです。本書 『 落下する緑 』 ( 東京創元社 ) が発売されたのは2005年で、今年になり文庫版が発売になっています。上にアップした表紙は文庫本のものです。実は8月に永見緋太郎シリーズの第二弾 『 辛い飴 永見緋太郎の事件簿 』 ( 東京創元社 )が発売になっています。こちらもただいま熱読中ですが、滅多にお目にかかれないジャズ・ミステリですので、ゆっくり味わいながら読んでいます。
さて、このジャズ連作ミステリ小説 『 落下する緑 』 には7編の短編が収録されています。ほとんどが東京創元社が発行しているミステリ専門誌『 ミステリーズ 』に連載されていた短編です。 ジャズしか頭にない世間知らずのフリー系の若きテナーサックス奏者、永見緋太郎が、身近に起きた事件、謎をその鋭い推理力で次々と解決していくミステリです。隋書に散りばめられたジャズ用語は、ややもすると、ジャズの知識のない読者には抵抗感があるかもしれませんが、逆にジャズ好きにはたまらないスパイスとなり、臨場感、リアリティー感を増幅させてくれます。
傲岸不遜な名ベーシストの所有する高価なベースが何者かに壊されてしまう話や、レコード会社の担当者を鼻で使う横行跋扈なジャズ評論家への復讐ミステリ、などなど、これは絶対モデルとなる人物がいるなぁ~、きっと( ̄∇ ̄; とニンマリしながら読める面白い話ばかりです。 あまり読むのが速くない僕でさえ、面白さのあまり一晩で読み終えてしまったほどです。
それそれの短編の終わりには、ストーリーに関連したCD, LPが3枚づつ紹介されており、ジャズ・ファンには嬉しいオマケとなっています。まずは文庫化されて読みやすくなった本書を手にいれ、気に入ったら新作の単行本『 辛い飴 永見緋太郎の事件簿 』を買われてはいかがでしょうか。