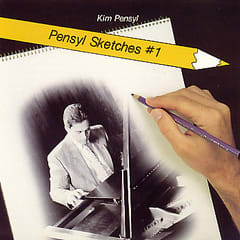彼の音はあまり低音を強調せず,どちらかというと mid を持ち上げた音で,サステインが短めで,時に速いパッセージをスタカートぎみに,ポッ,ポッ,ポッ,ポッっと軽い感じで弾いてみせるあたりが独特です。従来の 4 beat のウォーキングに全く支配されない,独創的な音列,リフパターンの創作,それらから生み出される中近東風の哀愁を帯びたメロディー。確かにこんなベーシストは今までいなかったのではないでしょうか。
チックと組んだ「 New Trio 」や「 Origin 」でのアヴィシャイの演奏は好きだけど,彼のリーダーアルバムはちょっと食指が伸びないというファンも多いかもしれません。リーダー作になるとウード( oud : 琵琶みたい弦楽器)などを取り得れた民族音楽の色調が強い作品が多く,聴き手を選ぶ傾向にあります。僕もあまり民族楽器が入ったジャズは好きではないので,彼の作品が全て良いとは思っていません。ただ,彼のファンになった決定的な愛聴曲があるのです。僕には。それはファースト・アルバム 『 Adama 』に収録されている 《 Madrid 》 という彼のオリジナル曲なんです。
ほとんどアドリブなどない,哀愁感のあるテーマだけで聴き手を虜にする4分50秒の短い楽曲です。Low D のベース・アルコに乗ったウードのイントロからはじまり,ホーンによる中近東哀愁メロディーが奏でられ,短い Adam Cruz (アダム・クルーズ)の ドラム・ソロをはさんで再びテーマへ。このメロディー,一発でアヴィシャイに夢中になってしまった僕にとっては思い出の曲です。この曲は昨年 King Records の「低音シリーズ」で発売になった彼の6枚目の作品 『 At Home 』で再演されています。こちらは前作よりスロー・テンポでウードも入っていないので聴きやすいかもしれません。
個人的にはファーストに収録されていたヴァージョンの方が好きですが,現在,ちょっと入手し難いアルバムかもしれません。どうしても聴いてみたい方は,『 Chick Corea Presents Originations 』(2000 stretch )という「 Origin 」関連のコンピレーションが発売になっていますので,これなら何処でも手に入りますよ。しかも国内盤1800円です。「 Origin 」の名曲(と僕は思っている) 《 wigwam 》も収録されているお買い得盤です。
《 madrid 》の試聴はamazonのこちらでできますが,なにしろ1分の試聴ではイントロで終わってしまって,肝心のテーマまでたどり着けません。試聴システムの弱点ですね。残念。
アヴィシャイ・コーエンの Official HP はこちら。
ここも試聴はできるがたった30秒。役にたちません。
関係ないけどチック・コリアの全アルバム・リストはこちら。