お父さんが買ったのか、
実家の本棚にながいこと置いてあった養老孟司の「死の壁」
読んだら、もやもやしていた気持ちがふっきれたのでリコメンド

同著者、400万部突破の「バカの壁」
この本読んだおかげで、話が通じなかったり、
最初っから人の話聞き入れる気がない人と話す度に、
「あ、こいつ、こいつー、バカの壁 」と判断して
」と判断して
無駄なエネルギーを使わずに済んだ
アホにかぎって、自分の中にへんな答えやルールが強固にあって、
人の話を聞き入れる柔軟な頭を持ち合わせていないのだ

養老さんは、厳しい言葉の中にも、真実を伝えて
世捨て人のような若者、弱ってる人、悩んでる人、
もちろんバカに対しても、深い慈愛をもって世の中を
一喝してくれる
一喝するだけなら、

と一緒になっちゃうけど、養老さんの場合は、
現状を理解させる腑に落ちる解説と
一歩目を踏み出せるヒントや勇気をくれるのだ
「死の壁」、父の死を経験しなかったら、
ここまで真剣に読んでなかったと思う
なぜなら、人生で一番 恐れていたことが
恐れていたことが
”両親の死” だった私にとって、そのことがおこって
しまったから。
父を救うことができなかった罪悪感 、
、
一所懸命がんばったつもりでも、
あれもできなかった、これもできなかったという後悔の念
「死」について、あれやこれやと、もやもや考える日々が
どうしても続いてしまうのだ。。。


著者が「解剖」の道に進むことになったのは、
終戦のとき小学生だった彼は、「騙された」と思い、
何か確実なものを求めたくなった
医学の中で最も変わらぬものは「死体」だった
それと著者が4歳のときに、お父さんを結核で亡くしていて
このことも、「解剖」へつながるつらい体験だったんだと思う
あんなに沢山の名言を残す養老さんが、実は30代まで
”挨拶が苦手”だったそうです。身内の通夜や葬式をやる
うちに、地下鉄の中で、ふと、挨拶が苦手なことと、
お父さんの死が結びついた瞬間があったそうです。
お父さんは夜中に亡くなり、臨終の間際に親戚から
「お父さんにさよならを言いなさい」と言われ、
何もしゃべれなかった、その後、お父さんは微笑んで
喀血(かっけつ)して亡くなったそうです。
つまり著者が挨拶が苦手だったのは、挨拶をすると
誰かが死んでしまうのではないか、という無意識からくる不安、
そして、ちゃんとお父さんに挨拶ができなかったことで、
自分はまだ別れの挨拶をしていない、
だからお父さんとはお別れをしていないと
お父さんの死自体を認めていなかった、
そのことを地下鉄で気づいたときに、止めどもない涙が
溢れてしまったということです。そこではじめてお父さんの
死を受け入れることができた。そしてこのことを
きちんと語れるようになったのは50代になってからだそうです。
解剖学をやっていて、世の中を冷静に見つめ、
正しい答えを唱えてくれる人生の大先輩、養老さんのような人にも、
肉親の死というものが、これほどまでにもつらく重く
のしかかるものなんだ
そして、養老さんは言ってる
「死」とは「仕方ない」ものなのだと。。
「死にいい面があるというとなかなか理解されないでしょう。
だから別の言い方でいえば、死は不幸だけれども、その死を
不幸にしないことが大事なのです。「死んだら仕方ない」
というふうに考えるのは大切なことなのです。それを知恵
と呼んでもいい。」
こういった言葉こそが、肉親の死に苦しむひとたちの頭を
客観的に整理し、救いの方向へと導いてくれるんだと思います。
「長い目で見て、その死の経験を生かす生き方をすればよいの
ではないかと思うのです。それが生き残った者の課題です。
そして生き残った者の考え方一つで、そういう暮らしは出来る
はずなのです。」
死は、理不尽にやってきます
問題は、そのときに、それを奇貨として受け止めるかどうか
ではないでしょうか。
こんな風に考えて、お父さんに教わったコト
生かして行こうと思いま〜す



「死の壁」、他にも様々な死に関するお話、考え方を綴ってくださっています。
死の壁にぶち当たった時に、読書強力リコメンドー デスッ
デスッ










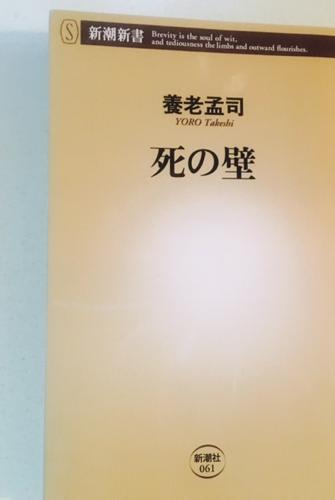




 」と反省する気持ち、
」と反省する気持ち、
 」
」











































