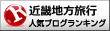本日の作業 ・トウモロコシ---液肥 ・トマト---芽欠き、ト-ン噴霧、アブラムシ・駆除 ・全野菜---液肥 キヌサヤ、ネギ---収穫
永照寺(下の坊) 奈良県天理市福住町265 PKあり 名阪国道の福住インターで降りる 細い道を入った奥に大きな婆羅門スギと尖った屋根の建物が見える 聖武天皇の勅願により良弁僧正の創建と伝わる。中世まで上・中・下之坊を始め湯屋坊など六坊があったが、延享元年(1429)大火にあい、本堂一宇を残すのみとなってしまった。その後に六坊のうち、下之坊だけが再建されたという。 現在は無住の寺



 入り口のところ
入り口のところ 本堂
本堂 婆羅門杉
婆羅門杉
 聖武天皇の位牌
聖武天皇の位牌

 婆羅門杉の石段の前に石龕があり、中に不動石仏
婆羅門杉の石段の前に石龕があり、中に不動石仏  境内墓地の宝篋印塔1455年
境内墓地の宝篋印塔1455年  杉
杉  お寺を西へ5分ほど行くと広場に出くわす
お寺を西へ5分ほど行くと広場に出くわす
 切石の石龕の中に、受け取り地蔵。その周辺に多数の地蔵群。
切石の石龕の中に、受け取り地蔵。その周辺に多数の地蔵群。
 up
up

 峠
峠
元興寺小塔院跡 奈良市新町45 PKなし 法相の有名な学僧である護命は小塔院僧正とよばれ、834年(承和元年)この小塔院で亡くなった。現存の護命の供養のために創られた宝篋印塔は鎌倉時代後期。また現在元興寺極楽坊にある国宝の五重の小塔は、かってこの小塔院に安置されていたとされる。元興寺小塔院跡として1965年(昭和40年)に国指定の史跡となっている。 前回訪ねた時におった老人がなにやら細工物を拵えていた。もっとここを宣伝したらというと、99歳の母親が反対するらしい。老人の兄(二代目)は西大寺に勤務しているらしい 虚空蔵堂は1707年に建てられ、 ここには東京のお客さんがよくくるらしい http://www.geocities.jp/KAWAFUNE3/真言律宗小塔院
![]()


 反対の入り口
反対の入り口 虚空蔵堂
虚空蔵堂 内部
内部 南にあるお堂
南にあるお堂![]()
 絵馬
絵馬 お堂内部
お堂内部 護命僧正の供養塔
護命僧正の供養塔
崇道神社 奈良市西紀寺町45 PKなし 璉城寺の北東に鎮座。 祭神は崇道天皇(早良親王)。 俗に紀寺天王と称し、往古は璉城寺の鎮守であった。 長禄2年(1458)の霊安寺御霊大明神略縁起私記(藤井家蔵)に「又奈良ノ南ノ紀寺ノ天王ト申スモ、崇道天皇ニテマシマスナリ」とみえ、怨霊を鎮止するために祀った御霊神社の一天満宮
井上神社 奈良市井上町 PKなし 井上神社は市内循環・田中町バス停前、ならまち交番の隣にある小さなお社 延暦19年(800)勅命によってこの地に社を造り、井上内親王と他部親王の霊を祭神として祀った。しかし、宝徳2年(1450)の元興寺と興福寺の争いで大火で類焼し、宝徳3年に元興寺が現在の薬師堂町に社殿を造り御霊宮と称した(上記の御霊神社)。後に旧社地である当地の井上町に社を造り2神の霊を慰め、町内の安全を祈願して今日に至っているという
12日ぶりの畑
本日の作業 ・サツマイモ---液肥 以後2週間に一回 ・ワケギ---堀上げ ・生姜---乾燥させないように液肥
・全野菜----液肥、消毒 ・トマト-芽欠き・トマトト-ン噴霧 ・タマネギ、キヌサヤ---収穫
特別公開「法隆寺秘宝展」 夢殿(救世観音)、西院伽藍、大宝蔵院 ¥800 中学、高校の修学旅行生が入れ代わり立ち代わり、大賑わい 6/30まで http://www.horyuji.or.jp/hihouten2.htm展示品リスト
 以和為貴
以和為貴![]() 中門
中門 東大門
東大門 南大門
南大門 南大門の前の鯛石-大和川が氾濫して、大和の国が洪水に見舞われても、この鯛石のところまでしか水が来なかったといわれる
南大門の前の鯛石-大和川が氾濫して、大和の国が洪水に見舞われても、この鯛石のところまでしか水が来なかったといわれる 本坊のつつじ
本坊のつつじ
 灯籠の獅子
灯籠の獅子 五重塔の鎌-五重の塔の相輪の下に、鎌が4丁ついている。長さ2mにもおよぶ大鎌(相輪の高さは10m)。雷をよせつけず、大風を切るといわれる。
五重塔の鎌-五重の塔の相輪の下に、鎌が4丁ついている。長さ2mにもおよぶ大鎌(相輪の高さは10m)。雷をよせつけず、大風を切るといわれる。 聖霊院・ここで御朱印をもらう
聖霊院・ここで御朱印をもらう 五重塔・邪気
五重塔・邪気 金堂・龍の彫刻
金堂・龍の彫刻 獅子の彫刻
獅子の彫刻 夢殿露盤
夢殿露盤
![]() 救世観音
救世観音![]() 百済観音
百済観音![]() 百済観音
百済観音  釈迦三尊
釈迦三尊 九面観音
九面観音 橘夫人念持仏
橘夫人念持仏 玉虫厨子
玉虫厨子 如来及び両脇侍立像
如来及び両脇侍立像 薬師如来・西円堂
薬師如来・西円堂 百萬塔 画像はpost cardより
百萬塔 画像はpost cardより
大念仏寺 大阪市平野区平野上町1-7-26 谷町線・平野、北へ800m 今日が最終日 本堂の廊下から撮影 二十五菩薩練供養 同じような格好であるが、持ち物によって区別できる 面を被っているので前が見えないが来迎橋の中央に細い線が2本貼ってあるのでそれを踏んで進む 「万部おねり」は大阪市指定無形民俗文化財に指定されている。 25人の菩薩が娑婆(外側)から極楽浄土(本堂)に練り歩き、絢爛豪華な来迎の世界を体現している。<o:p></o:p>
 天得如来
天得如来 


![]() 来迎橋
来迎橋

 稚児行列
稚児行列


 観世音
観世音 勢至菩薩
勢至菩薩 薬王菩薩
薬王菩薩 薬上菩薩
薬上菩薩 普賢菩薩
普賢菩薩 金蔵菩薩
金蔵菩薩 師子吼菩薩
師子吼菩薩 華厳王
華厳王 虚空蔵
虚空蔵 徳蔵
徳蔵 宝蔵
宝蔵 法自在
法自在 金剛蔵
金剛蔵 山海慧
山海慧 光明王
光明王 陀羅尼
陀羅尼 衆宝
衆宝 日照王
日照王 月光王
月光王 定自在
定自在 三昧王
三昧王 大自在王
大自在王 白象王
白象王 大威徳王
大威徳王 無辺身菩薩
無辺身菩薩 本堂内
本堂内 円通殿
円通殿
奥不動寺 奈良県桜井市辻728 PKあり ダンノダイラから西へ200m・奥不動寺へ向かう 92歳の耳の遠い老僧がおられて御朱印を書いてもらい、お茶と饅頭の接待に預かった。初めは私一人であったが、あとで車で来た若者が二人のみ 、奥不動寺は、大神神社の神宮寺であった大御輪寺(現若宮社の地)の奥の院といわれている。老僧は日本で一番古い寺だと自慢していた。十二柱神社へ帰るのに1時間15くらいかかった。途中で道が消えてしまうので、方位磁石は必携  奥不動寺が見えてきた
奥不動寺が見えてきた



 山門脇の活花
山門脇の活花 本堂
本堂 木魚
木魚 獅子脅し
獅子脅し 閼伽水
閼伽水






![]() 中腹からの段々畑
中腹からの段々畑
十二柱神社 桜井市出雲650 PKあり(再訪) 大昔は神殿がなく、「ダンノダイラ」という三輪山の当方にある古代イズモ族の住んでいた地にある磐座を拝んでいた。 ・出雲邑の氏神。 ・狛犬をよく見ると、四人の力士が支えている。 ・武烈天皇泊瀬列城宮伝承地である。
本日の作業 今年からキュウリとなすはヤメ 毎日水やりが出来ないため
トマト10,ゴーヤ2,パプリカ2,坊ちゃん(小玉南京)2,小玉西瓜1,アスパラ1、ハバネロ1-植えつけ
新聞紙で風よけの行燈
 アスパラ植え付け
アスパラ植え付け イチゴ去年のイチゴの株をほっておいても蕾ができている
イチゴ去年のイチゴの株をほっておいても蕾ができている エンドウ
エンドウ ゴーヤ
ゴーヤ ジャガイモ・玉葱
ジャガイモ・玉葱 モモタロウ
モモタロウ モモタロウ10
モモタロウ10 ラッキョウ
ラッキョウ 下仁田ネギ
下仁田ネギ 小玉西瓜 植穴にオルトラン1g 腐葉土と赤土を混ぜたもの-パプリカ、ハバネロを植える
小玉西瓜 植穴にオルトラン1g 腐葉土と赤土を混ぜたもの-パプリカ、ハバネロを植える
ダンノダイラ- 桜井市出雲、巻向山にあるダンノダイラへゆく 出雲村の人々が年に一度、このダンノダイラへ登り、相撲などをして遊ぶ風習が明治初期まであったそう 十二柱神社に車を停めて、神社の手前にあるデイリーヤマザキの北の端にある、舗装の坂道を登ってゆく、初めから勾配がきつく何回も休みながら登る 神社近辺の爺さんに聞くと1時間で登れるということだが2時間ちかくかかった。
司馬遼太郎 出雲の不思議(司馬遼太郎が考えたこと)
出雲人は奸譎(かんけつ)-よこしまで、心に偽りが多いことである。出雲の王族は天孫民族(大和政権)により、身柄を大和に移され三輪山のそばに住んだ。三輪氏の祖がそれである。三輪山を中心に出雲の政庁があった。奈良県人は神武天皇の橿原神宮より、大神神社を尊崇している。<o:p></o:p>