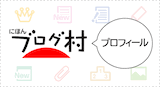先日参加したスズカ8時間エンデューロ用に買った軽量クリンチャータイヤ
【パナレーサー RACE L Evo2】です。アマゾンでポチッとやると翌日には手元に届いているという簡便さ。こんなに簡単にモノが買えて、しかも、すぐに手元に置くことができるとは何とも恐ろしい時代になったものだ。いや、恐ろしいのは時代ではなくて、そういうことを可能にしてしまった「アマゾン」か。
当ブログをお読みいただいてありがとうございます!
こういうもので、少しでも交流の輪が広がればという思いでブログランキングに参加しています。
順位が上がれば、記事を書くモチベーションもアップします!!
もし良ければ、こちら「ロードバイクブログ村」のバナーにポチッとクリックよろしくお願いします。
 にほんブログ村
にほんブログ村

お約束の重量測定。カタログ値180gのところ、実測174gを記録。下記のインプレ表の中では実測190gとあるので、メイドインジャパンの製品としては珍しく製品によってバラつきがあるのかな。
サイクルスポーツ(八重洲出版)2013年5月号特集より

最近はあまり買わなくなった自転車専門雑誌サイクルスポーツですが、以前、この雑誌の中に興味深い企画がありました。3名の評価者(吉本司氏・安井行生氏・小笠原崇裕氏)によるクリンチャータイヤ全23モデルのインプレ特集記事(2013年5月号)です。
クリンチャータイヤ派の私にとってはなかなか気になる内容になっていました。
上記の表はクリンチャータイヤの中でも、軽量化されたモデル8種のインプレから、3氏の評価点を平均化し、私が短時間で調べ得る限りの最安値を記載した表です。
この中でも、パナレーサーRACE L Evo2 のコストパフォーマンスは圧倒的です。グリップ感は他のモデルを圧倒しての1位評価。転がりの軽さもコンチ・グランプリスーパーソニックに次ぐ2位となっています。
3氏の【RACE L Evo2】のインプレを概説すると、
「グリップ感が強く、ダウンヒルのコーナリングでも安心感がある」「抗パンクベルトも挿入され、レースでも安心」「軽量タイヤの枠を超えてオールマイティな性能」とはっきり言ってベタ褒め状態。軽量タイヤだからといって、ヒルクライムに限定したモデルではなく、オールマイティに使うことができる好タイヤと軒並みの評価の高さでした。ネガティブなコメントが全くなく、それはそれでちょっと不安な気もしますが。
そして、コスパにとって重要なのは「販売価格」という問題。
【RACE L Evo2】は販売価格表を見てもらっての通り、他モデルと比較して明らかに
『安い』。アマゾンのプライム会員であれば、この価格に送料無料、即日もしくは翌日配達で手元にやって来るという素晴らしさ。
逆に驚いたのが、クリンチャータイヤの最軽量(らしい)として名高い、ヴェロフレックス・レコードの評価がそう高くはないということ。重量はこのモデルの中では最軽量ですけど、カタログ値からすると実測はずいぶん高めで、そうインパクトのある数字でもない。加えて値段も高いし。
コンチのスーパーソニックは試してみたいけど、それを購入する前に決戦用ホイールにカーボンチューブラーを手にしてしまう可能性の方が高いかな。決戦用チューブラータイヤがあれば、軽量クリンチャータイヤの必要はないだろうし、トレーニングやツーリングには、耐久性と抗パンク性の高いタイプのクリンチャータイヤを履くだろうし。

スズカ8時間エンデューロには、カンパ・バレットウルトラに
【RACE L Evo2】を履いて参戦しました。このために購入したタイヤなのでね。
路面の質が高いサーキットコースでは、これまでに履いたクリンチャータイヤでは味わえなかった転がり感の軽さとグリップ力を体感しました。高速コーナーでもしっかり路面にグリップしてくれるので、怖さを感じることは無かったですね。インプレ記事でグリップ力の最高評価を得ているのも頷けます。いくらオールマイティとは言っても耐久性は低いので、普段使いには使用せず、レースやスピードを意識したヒルクライム時に使用するに留めておきたいですね。
インプレ記事に登場していたタイヤでは、ボントレガーR4ロードを使用したことがあります。マドン6をプロジェクトワンシステムでオーダーした時に格安でアッセンブルされていたました。軽量で良いタイヤであることには間違いありませんが、何せ高い。定価では7,000円弱。しかも安売りもされていないし、あえてこのタイヤを買うことはありまんせよね。

アップダウンの大きなグリーンピア三木での早朝エンデューロソロは、レーシングゼロにこの
【RACE L Evo2】を履かせて参戦するつもりです。と言っても、すでにグリーンピア三木のコースでの練習もこの組み合せでしてるんですけどね。タイトな下りが多かったり、路面もひび割れや水たまりのような危険な箇所もあるGP三木のコースですが、このホイールとタイヤのペアで頑張りたいと思います。
こんシーズンはカーボンチューブラーホイールを履く予定もないし、いくつか参戦予定のエンデューロではこの組み合わせが主戦力となります。