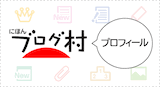先日の日曜日から月曜日にかけての台風による大雨は大変でした。報道では、嵐山や福知山市街が川の氾濫でとんでもない被害に遭っていました。嵐山も福知山も自転車旅で何度もお世話になった土地なので心配です。また、報道されている場所以外にも多くの土地で様々な被害に遭われているのだと思います。私に何もできる事はありませんが、被害に遭われた方が一刻も早く日常を取り戻されることを祈願したします。
上の写真は宝塚大橋から武庫川上流方向を撮影した写真です。普段は穏やかな武庫川が溢れんばかりに増水しています。そんな川の状態にも関わらず、濁流のすぐ傍で多くの人たちが平然と過ごしていることに驚きました。まぁ橋の上で写真を撮っている私も五十歩百歩ですが、いつ増水するやもしれないという危機感は強く抱いていました。
ともあれ、台風一過で晴天が戻り、すっかり涼しくなりこんな時に自転車に乗らない訳にはいきません。事情で職場に置きっぱなしになっていた折り畳み自転車、KHS・F20RCを回収するのと、せっかく時間があるので、宝塚から神戸までのポタリングを楽しみながら、帰りは神戸電鉄に乗って輪行で三田まで戻ろうという計画です。
私と同じように台風一過の晴天の下、うずうずして自転車で走りに行かれた方も、
そうでない方もぜひ下のバナーをポチッとお願いします。

まずは、尼崎市は武庫元町にあるなじみの自転車屋さん「アップル自転車商会」に向かうため、武庫川沿いを南下します。河川敷の武庫川CRは流石に怖いので、土手の上の道路を通りますが、武庫川の中下流域に来ても水量が衰えていません。いやはや恐ろしいですね。

アップル自転車商会にて、ディレイラーワイヤーの交換と調整をお願いしました。そして作業がてらの会話を楽しみます。いつ来ても店長のHさんとのよもやま話は尽きません。Hさんとの話の中で、サイクルベースあさひの塚口店の店長だった人が独立して小径車専門店を立ち上げて頑張っているらしい、というのがありました。お店の名前は「ムーブ」ということで早速スマホでチェック。西宮市の国道43号線よりも更に海側の酒蔵通りという東西に走る通りに店があるので、神戸に行くついでに立ち寄ってみることにしました。

南へ南へ。武庫川左岸の土手の上の道路を進んで行きます。自転車のバーテープの汚れが目立ってきたので、ショップに着いたら交換しようかな。色は何がいいかな?なんて呑気な事を考えて走りました。

9月から10月にかけての終盤戦が絶望的に弱い阪神タイガースの本拠地、阪神甲子園球場の脇を通り過ぎていきます。本当にもう何とかならんのかいなぁ。いつもクライマックスシリーズに出ても貧打で負けてるイメージしかないですしね。

なんだ、かんだと西宮市を南の方へ走っていくと、酒蔵通りに出ました。江戸時代から西宮から神戸にかけては清酒の名産地として有名だったことは知っていました。「酒蔵通り」という名称もそこから来たのだろうとは思っていましたが、このMAPのように、酒蔵巡りの観光ができるような場所とは知りませんでした。
今日は偶然、この場所に来ましたが、折り畳み自転車でゆったり街中をポタリングするのにもってこいの場所ではないですか。今日はラッキーだなぁ。ゆるキャラの「みやたん」も可愛いぞ。片手で酒樽を平然と持っているのは怖いけど。

ということで、さっそくブラブラと造り酒屋の町並みをポタリングです。最初に訪れたのは、MAPにもある今津灯台。製造した清酒を日本各地に流通するための樽廻船のための灯台だったそうです。

清酒、大関の工場です。現在でももちろん創業しています。江戸時代からずっと今でも操業している製酒工場がこの界隈には何軒もあります。

こちらは、「日本盛はよいお酒♪」のCMで有名な日本盛さんですね。

こういう観光名所で欠かせないのが、ご当地ミュージアム。当地の歴史や文化を知るのに手っ取り早いですね。

お、酒樽を運んでいた大八車が展示されていました。当方、自転車乗りなので気になるところといえば・・・・

大八車の車輪の回転部分。車輪は木製ですが、外周部は鉄の板が巻かれていました。車輪にはベアリング機構みたいなものが入っているのかなぁ。一体どんな風になっているんでしょうね。気になりました。

そして、酒蔵の風景です。時間もあまり取れないのでサッと見て回っただけですが、質の良い清酒を造るための条件みたいなことが書いてあり、それが一番心に響きました。曰く、
清酒作りに大事なのは、「水」「酒米」そして「杜氏」だそうです。
水は、六甲山系から伏流水となって流れ落ちてくる水(いわゆる宮水)が製酒には良いそうで、酒米には、裏六甲地域の気候が酒米を生産するのに気候が良いのか、三木や吉川が有名な酒米「山田錦」の一大産地になっています。そして、人。酒作りの行程はさまざまなファクターが重なり合う繊細なもので、職人にはこの微妙な違いを感知できるセンサーが求められるそうです。杜氏はそうした酒作りの職人の長という存在ですが、「丹波の杜氏」といって、優れた腕の杜氏が丹波から冬期だけ出稼ぎでやってきたそうです。

さて、酒蔵の町を堪能している合間に、酒蔵通りの交差点にある折り畳み、ミニベロ専門店「ムーブバイシクルズ」を訪れてみました。

こじんまりとした店内に折り畳み自転車がたくさん展示されていました。ダホン、ターン、オリバイク、ブルーノ等が多かったですね。そして、店長さんは、初見の私とも気さくに色々なお話しをさせていただき、とても楽しい時間が過ごせました。今度、小径車関係で何かを購入する時にはこのお店のお世話になろうかなと思える印象でした。

そして、このお店で売っていたバイクリボンのバーテープを購入して、ついでに巻いてもらおうと思ったのですが、「¥1,500円かかりますがいいですか?」と言われたので、「え、高いなぁ」と思わず呟いてしまうと、そこは店長さんもこだわりがあるようで、 「バーテープ巻く作業一つにも全力で取り組みたい。費用は工賃ではなく技術料だと考えている」「この費用は一切まける気はありません」と強く仰っていました。私が特に値切った訳でもありませんが、この店長さんのショップ経営哲学の現れということなのでしょう。
「もしご自分でされるならやってもらってもいいですよ」とのことなので、結局、ハサミ等の道具を少しお借りして自分で巻きました。バーテープは、自分で使用する分くらいはなんとか巻けるので、今回は自分で巻きましたが、別の考えとしては、¥1,500を支払ってプロのこだわりの技の一端を盗ませてもらうのも悪くはなかったかな・・・という思いもありました。買うかどうかは分かりませんが、小径車関係で次に買うアイテムはやはり走りに直接繋がってくるホイールとタイヤでしょう。ホイールの相談やメンテナンスはこのお店にお願いすると安心感がありそうです。

坂蔵通り、酒造の町、今津郷や西宮郷を離れ、一路神戸へ。時間もずいぶんと過ぎてしまいました。あとは輪行で三田まで帰るだけですが、せっかく神戸に来たので、いつもの北野の萩原珈琲でコーヒーを飲んで帰ることにしました。

営業時間を僅かに過ぎ、店の片づけをされていましたが、「どうぞ、ゆっくり過ごしてください」ということで、珈琲も淹れていただきました。サントスニブラというブラジル産の珈琲豆の深煎り珈琲です。まったり、こってり濃密な味わいでした。ここでも結局1時間は長居してよもやま話で過ごしました。
今日は、アップル自転車商会の店長さん、ムーブバイシクルズの店長さん、萩原珈琲北野店のマスターと長い時間話をしましたが、自転車に乗ってる時間よりも話していた時間の方が長いかも・・・って感じですが、そういうのもまた自転車のもつ魅力でもありますね。

輪行で、神戸電鉄三田駅まで帰ってきました。折り畳み自転車での輪行は車体を折り曲げて、輪行袋を上から被せるだけでOKなので、ホイール外して、ディレイラーを守るガードを付けて、といった面倒な作業が一切不要なので便利なことこの上ないです。台風一過、午後からのサイクリングはこんな風に過ぎて行きました。

白鹿記念酒造博物館で頂いたお土産の吟醸酒をキーンと冷やしてお風呂上りに晩酌です。