シリコンバレーで働く梅田望夫さんが書いたのが標題の本「シリコンバレーから将棋を観る」。子ども時代に将棋をけっこう指しても、その後は仕事などで指す機会がなかなか得られないし、だから強くもなれない人が多い。それでも将棋は好き、といえるのでは? という提起がいいですねえ。野球ができなくても野球は観られるし、音楽ができなくても音楽は楽しめる、小説家でなくても小説は読める。同じように「将棋を観る」ことは楽しめるし、それだって立派なファンの形態だという。なるほど、と思いました。
=以下アマゾンから=
好きなものがありますか?極めたいことは何ですか?―ベストセラー『ウェブ進化論』の著者が「思考の触媒」として見つめ続けてきたものは、将棋における進化の物語だった。天才の中の天才が集う現代将棋の世界は、社会現象を先取りした実験場でもある。羽生善治、佐藤康光、深浦康市、渡辺明ら、超一流プロ棋士との深い対話を軸に、来るべき時代を生き抜く「知のすがた」を探る。
特に羽生さんや谷川浩司さん、深浦さんら、たしかにみていいるだけで惚れ惚れとするような、厳しさを極めて人間的にも優れたように思われる人たちが将棋を指す姿を楽しむことはできます。現代将棋は筆者も書いているように、とにかくすざまじいほどの変革の真最中で普通のアマチュアでは正直、ほとんど指しての意味がわからない。でも、羽生さんらトッププロがそこまで身を削る理由が将棋の深さを表しているのだ、と観るのは可能。その一端でも感じ取れれば将棋のふかーーーい魅力を知ることになる。
羽生さんの思考を一般にもわかりやすく提示しただけでもこの本は意味がある。自画自賛の臭いがややいやらしいのですが、ネットによるリアルタイム観戦記という新しい分野の道を開いた筆者の功績は大きいと思います。あと、少々、トッププロとの交友を誇らしげに話す感じ鼻につくのが玉に瑕ですけど、ま、ご愛嬌ということで。社会現象を将棋のトッププロが先取りしているというのは、ある部分同意。ある部分「?」でした。
あと、プロは羽生さんのような人格者ばかりではなく、ほとんど人格崩壊し、モノの見方も黒白的にしか見られなくなったような偏った人物も散見されることもまあ、頭の片隅にでも。あくまで梅田さんと違って私は一般の報道から知る姿ですけど、奇行で雑誌をにぎわせる人もけっこういますもの。天才とナントカは、ですからね。ま、それも含めて将棋の世界は面白い、ともまた思うのではありますけれど。
=以下アマゾンから=
好きなものがありますか?極めたいことは何ですか?―ベストセラー『ウェブ進化論』の著者が「思考の触媒」として見つめ続けてきたものは、将棋における進化の物語だった。天才の中の天才が集う現代将棋の世界は、社会現象を先取りした実験場でもある。羽生善治、佐藤康光、深浦康市、渡辺明ら、超一流プロ棋士との深い対話を軸に、来るべき時代を生き抜く「知のすがた」を探る。
特に羽生さんや谷川浩司さん、深浦さんら、たしかにみていいるだけで惚れ惚れとするような、厳しさを極めて人間的にも優れたように思われる人たちが将棋を指す姿を楽しむことはできます。現代将棋は筆者も書いているように、とにかくすざまじいほどの変革の真最中で普通のアマチュアでは正直、ほとんど指しての意味がわからない。でも、羽生さんらトッププロがそこまで身を削る理由が将棋の深さを表しているのだ、と観るのは可能。その一端でも感じ取れれば将棋のふかーーーい魅力を知ることになる。
羽生さんの思考を一般にもわかりやすく提示しただけでもこの本は意味がある。自画自賛の臭いがややいやらしいのですが、ネットによるリアルタイム観戦記という新しい分野の道を開いた筆者の功績は大きいと思います。あと、少々、トッププロとの交友を誇らしげに話す感じ鼻につくのが玉に瑕ですけど、ま、ご愛嬌ということで。社会現象を将棋のトッププロが先取りしているというのは、ある部分同意。ある部分「?」でした。
あと、プロは羽生さんのような人格者ばかりではなく、ほとんど人格崩壊し、モノの見方も黒白的にしか見られなくなったような偏った人物も散見されることもまあ、頭の片隅にでも。あくまで梅田さんと違って私は一般の報道から知る姿ですけど、奇行で雑誌をにぎわせる人もけっこういますもの。天才とナントカは、ですからね。ま、それも含めて将棋の世界は面白い、ともまた思うのではありますけれど。
















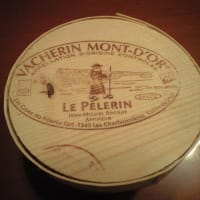



jamsession123goもこの本は読みました。
子供の頃はさておき、将棋はほとんどやったことがないのですが、この本から伝わってくる将棋の面白さは格別ですね。
この本で紹介されていた、「頭脳勝負―将棋の世界」と「人間における勝負の研究―さわやかに勝ちたい人へ」を借りて読みましたが、これもまた、楽しめる本でした。
てのさんは将棋を指されるようですね。