随分遅くなったが映画「海難1890」を観た。

映画のキャッチコピーに「日本人が知らない・・・」などとあったが、私はこのトルコ軍艦の遭難のあれこれと、在留邦人救出のために、イランへトルコが救援機を飛ばしてくれた二つのことは知っていた。アジアの両端に位置する我が国とトルコとは、現在でも特別な友好関係にある。どうしてかと調べると、それはこの映画、トルコ軍艦「エルトゥールル」号の台風による遭難事件に必ずたどり着くからだ。
 どれぐらい大事故であったかというと、日本でコレラにかかって死んだ10人を引いた乗員640名中の生存者はわずか69名というから、和歌山沖の島の海岸は死体で埋まったような状態であっただろう。かつ台風の中での救出活動は危険であり、島民も命懸けの救出であっただろうと思う。しかしこの悲劇が、その後の百年を超える両国の友好の礎となった。
どれぐらい大事故であったかというと、日本でコレラにかかって死んだ10人を引いた乗員640名中の生存者はわずか69名というから、和歌山沖の島の海岸は死体で埋まったような状態であっただろう。かつ台風の中での救出活動は危険であり、島民も命懸けの救出であっただろうと思う。しかしこの悲劇が、その後の百年を超える両国の友好の礎となった。
この映画は実に美しい映像で、しかも史実に忠実でありながらスペクタル十分に描かれている。全く言葉の通じない、何もかも異なる民族、ただ一つ共通しているのは西欧に対し、一方は衰えつつなお抵抗した月の国、もう一方はその支配をこじ開けつつある日の昇る国だったという点である。
私たちが行う毎年のパトモスやイスラエルの派遣には、よくトルコ航空を使う。目的地に対し、イスタンブールを経由する最短ルートであるだけでなく、料金も安く食事も対応もなかなか良い航空会社である。この映画を観て、なおさら親しみを感じる。なおトルコは確かにイスラム国ではあるが、イスラム圏で唯一の政教分離したRepublic(共和国)、民主的な政体の国である。観ておいて損はない映画であると言える。 ケパ

映画のキャッチコピーに「日本人が知らない・・・」などとあったが、私はこのトルコ軍艦の遭難のあれこれと、在留邦人救出のために、イランへトルコが救援機を飛ばしてくれた二つのことは知っていた。アジアの両端に位置する我が国とトルコとは、現在でも特別な友好関係にある。どうしてかと調べると、それはこの映画、トルコ軍艦「エルトゥールル」号の台風による遭難事件に必ずたどり着くからだ。
 どれぐらい大事故であったかというと、日本でコレラにかかって死んだ10人を引いた乗員640名中の生存者はわずか69名というから、和歌山沖の島の海岸は死体で埋まったような状態であっただろう。かつ台風の中での救出活動は危険であり、島民も命懸けの救出であっただろうと思う。しかしこの悲劇が、その後の百年を超える両国の友好の礎となった。
どれぐらい大事故であったかというと、日本でコレラにかかって死んだ10人を引いた乗員640名中の生存者はわずか69名というから、和歌山沖の島の海岸は死体で埋まったような状態であっただろう。かつ台風の中での救出活動は危険であり、島民も命懸けの救出であっただろうと思う。しかしこの悲劇が、その後の百年を超える両国の友好の礎となった。この映画は実に美しい映像で、しかも史実に忠実でありながらスペクタル十分に描かれている。全く言葉の通じない、何もかも異なる民族、ただ一つ共通しているのは西欧に対し、一方は衰えつつなお抵抗した月の国、もう一方はその支配をこじ開けつつある日の昇る国だったという点である。
私たちが行う毎年のパトモスやイスラエルの派遣には、よくトルコ航空を使う。目的地に対し、イスタンブールを経由する最短ルートであるだけでなく、料金も安く食事も対応もなかなか良い航空会社である。この映画を観て、なおさら親しみを感じる。なおトルコは確かにイスラム国ではあるが、イスラム圏で唯一の政教分離したRepublic(共和国)、民主的な政体の国である。観ておいて損はない映画であると言える。 ケパ














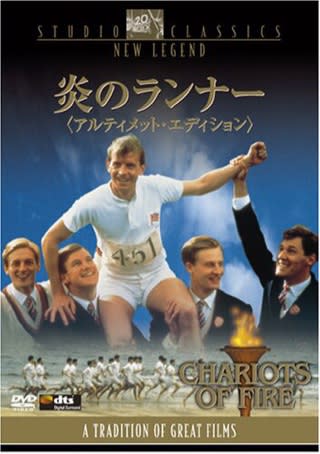






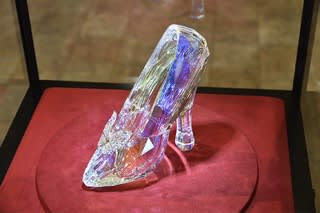 また、それだけてなく、亡き母と約束した「勇気とやさしさを忘れないで」を最後まで貫くとか、最後に過酷なまでに自分を虐めた母を「あなたを許すわ」と言わせてみたりしているところが新しい。このような力の背景にあるのは、十字架の上で、すべての敵を許した、キリスト教社会ならではの価値観であると感じる。
また、それだけてなく、亡き母と約束した「勇気とやさしさを忘れないで」を最後まで貫くとか、最後に過酷なまでに自分を虐めた母を「あなたを許すわ」と言わせてみたりしているところが新しい。このような力の背景にあるのは、十字架の上で、すべての敵を許した、キリスト教社会ならではの価値観であると感じる。






