
ジョン・ホプキンス大学のCOVID-19患者数の世界統計ページです
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
世界中で、日本の感染者数が恣意的に抑えられているのではないかと強く疑問視されているようです。
検査数が1日当たり2000件以下に抑え込まれていますので、感染者数がコントロールされていると国外から批判されても仕方ないと思います。
私は、上昌広医師の言われることを全面的に支持します。
https://mainichi.jp/sunday/articles/20200312/org/00m/010/002000d
私がもう一つ疑問に感じていることは、イランの回復者数です。患者数が1,000人以下であった3月1日から回復者数は世界第二位。ものすごい違和感がありました・
どうなっているのでしょうね??
以下は上昌広医師の日本のPCR検査等に対する意見です。
新型肺炎のさらなる拡大で国民を不安にしているのは、唯一の感染判定法であるPCR検査を受けられる体制が整わないことだ。安倍政権の錯誤、専門家会議の鈍さは何に起因するのか。患者と臨床第一に医療体制を批判してきた医師が、収束まで1年以上と予想、身を挺して「不実の構造」を告発する。
収まる気配を見せないコロナウイルス禍。このへんで中間総括が必要ではないか。誰もが不思議に思う謎が二つある。その解明だ。
一つは、PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)検査体制の遅れだ。PCRは、ウイルス感染の有無判定の唯一無二の手段。遺伝子増幅技術を使った簡便検査法で、「測定機械は一般の大学や研究機関、民間の検査企業にかなりの台数がある」(児玉龍彦・東京大先端科学技術研究センター教授=3月8日号)とされ、民間活用まで広げれば相当な検査件数を稼げるはずであった。
にもかかわらず、である。2月12日時点で1日最大300件、その後も1日平均900件(18〜24日)ペースで、後発国だったはずの韓国が同じ時期に1日1万件検査できる体制を作り上げたのに比べ、あまりにスローモーだ。現時点では検査能力4000件体制を確保、3月6日からようやく民間での保険適用が可能となるが、それでも加藤勝信厚労相によると、10日段階で民間、大学で600件程度が増えるのみ、という(2日参院予算委答弁)。
対ウイルス戦は検査データ増が至上命題だ。分母を多くすればするほどに正確な感染率、重・軽症率、回復率、致死率が出てくる。地域別、男女別、年齢別、状況別のデータ解析で、ウイルスの危険度の実相が見え、正しく恐れることが可能になる。政策の優先順位がはっきりし、エビデンス(証拠)のある行政指導で、国民と対話をしながら政策を浸透させる。「首相決断」でいきなり一斉休校を求めるような乱暴な措置はもとより論外となる。
二つに、クルーズ船対応の大失態だ。封じ込めるつもりが結果的に感染拡大の培養器と化した。3894人の乗員乗客の2割、700人が感染、外国人を含む6人が死亡、厚労省職員や検疫官まで感染した。情報開示が遅れ、国別乗客数さえ公開されなかった。下船後も船内感染の可能性を想定せず公共交通機関で帰宅させた。このツケは重い。国賠訴訟のリスクだけではない。日本の検疫・危機管理能力の低さが世界に周知され、医療・衛生大国としての信用を失墜、「第二の武漢」「人体実験船」と酷評されるにまで至った。
PCR検査体制の不備が選択肢を狭めた。スムーズな全員検査により陰性の人々を早々に下船、自宅待機させることもできたはずである。児玉教授も指摘していたことではあるが、何よりも船内隔離された人の感染拡大阻止、治療、介護といった人権的、臨床的視点が致命的に欠落していた。
つまり、安倍晋三政権の対ウイルス対応は、最も基本的作業の段階で躓(つまず)き、最も勝負どころの場面で汚名を稼いだだけであった。なぜそこまで悲劇的なことが起きているのか。何がネックなのかを解明しない限り、後手後手ではすまない。誤手誤手化を避けられない。
その謎の一つの「解」が、上(かみ)昌広・医療ガバナンス研究所理事長(52)から提供された。上氏の専門は血液・腫瘍内科学、真菌感染症学、メディカルネットワーク論。東大病院の内科医だったが、研究中心、患者二の次の体制に嫌気がさし30歳で飛び出て、その後自立。臨床症例報告の地道な積み重ねの大切さを訴え、国の医療行政に辛口論評を加えてきた人物だ。
上氏によると、キーワードは現体制の行き過ぎた「臨床軽視・研究至上主義」と「情報秘匿体質」にあり、人事で体制を一新することが唯一の解決策となる。
現体制とは、対ウイルス戦の参謀本部ともいえる「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」(専門家会議=2月14日発足)であり、事の本質を理解するためには、これを構成する4組織、つまり、国立感染症研究所(感染研)、東京大医科学研究所(医科研)、国立国際医療研究センター(医療センター)、東京慈恵会医科大学(慈恵医大)というカルテットの前身やルーツにまで遡(さかのぼ)る必要がある、という。
帝国陸海軍から継続する隠蔽体質
「一つの鍵は、人事と予算をどこが牛耳っているかだ。専門家会議12人のうち8人は4組織の関係者が占め、残りは学会代表、広域代表、充て職だ。緊急対策費19・8億円にしても感染研12・2億円、医療センター3・5億円、医科研1・5億円と大半を占有。予算をつけた厚労省医系技官の大坪寛子(内閣官房健康・医療戦略室次長)氏は慈恵医大卒、感染研を経て、同省に就職している。予算決定も執行もこの4組織だ」
「もう一つは、4組織の拠(よ)って来る歴史だ。感染研も医科研もルーツは、伝染病研究所(伝研)にある。伝研は1892年に北里柴三郎が立ち上げた民間の研究機関だったが、1914年東大に移管される際にその運営方法をめぐる北里と東大側の対立が当時の政界をも絡めた一大騒動に発展、北里が職員を連れて退職。その後伝研は陸軍との関係を深めていく。戦後の伝研は47年GHQの指示で半分が厚生省所管の国立予防衛生研究所(その後感染研)として分離独立、半分が伝研として残り、67年に医科研に改組された。ただ戦後も軍との関係は残った。予防衛生研幹部に陸軍防疫(731)部隊関係者が名を連ねたのはその一例だ」
他の2組織のルーツは?
「医療センターは帝国陸軍の中核病院だった。戦後厚生省に移管され国立東京第一病院、国立国際医療センターと名前を変え、2010年に独法化、現在に至る。慈恵医大は、海軍軍医学校創設者の一人、高木兼寛が中心になって設立した医師受験予備校が母体で、日本初の私立医学専門学校となる。昭憲皇太后が名付け親で天皇家や海軍との関係が深い。つまり4組織はいずれも帝国陸海軍と深い関わりを持っていた」
ルーツが今回どう作用?
「我々一般の臨床医との違いは、情報開示への姿勢だ。クルーズ船対応にもその秘匿主義が出た。敵軍との対峙(たいじ)が前提の軍隊には情報開示は求められない」
PCR検査の遅れも?
「韓国にできて日本にできない理由はない。国内には約100社の民間検査会社があり、約900の検査センターを運用している。一つの検査センターで1日に20人を検査すると1万8000人が可能になるが、それをしないのは感染研の処理能力を超え、彼らがコントロールできない状況になるのを恐れた。感染研は『研究所』だ。現行のPCR検査が『研究事業』の延長だからこそ、臨床医がPCRが必要と判断しても断ることが許容されてきた」
臨床的視点が薄い?
「『受診の目安』(2月17日政府発表)で、高齢者は2日以上の発熱が続いた段階で帰国者・接触者相談センターへ相談しろ、とか、PCR検査は肺炎の確定診断にのみ用いるといった基準が罷(まか)り通っている。早期診断・早期治療は医療の鉄則だ。特に高齢者は治療の遅れが致命的になる。発熱すれば、体力低下、脱水になる。2日間も我慢せず、点滴や解熱剤を服用した方がいい者もいる。そもそも高齢者肺炎の大半は致命的だ。PCRで『感染』の診断が出たとしてもデータを集める意味はあるが、患者にとっては無益だ」
軍のDNAは他にも?
「軍隊のもう一つの特徴が自前主義だ。かつて帝国陸海軍は伝研と協力して、ワクチンを確保したが、現在もインフルエンザワクチンの製造・供給体制だけは、国内メーカー限定4社と感染研が協力する『オールジャパン』体制で、官民カルテル体制を死守している。海外企業の参入や国際共同による治験が認められている他の薬剤とは全く扱いが違う。感染研にはその対価として施設設備費や試験研究費という税金が投入され、一種、利権化している。軍を中心とした戦前のワクチン開発・提供体制が生き残った形で、最も成長が期待される分野で、日本の競争力を停滞させている」
薬害エイズ、C型肝炎問題と同じ構図
クルーズ船対応では?
「検疫の目的は国内へのウイルス流入防止だが、被検者側からすると、健常者を対象に新薬をテストする第一相治験に近い。普通治験では被験者の安全に細心の注意が払われ、一例でも死亡例が出たら中止となる。今回の検疫も同様に扱うべきだったが、厚労省は乗客や乗員の人権を軽視し続けた。結果的に船内では1人の感染者から平均5・5人が感染した、との調査結果が出ている。中国が武漢を対象に感染力を推定した2・2人の倍以上だ。政府は武漢の日本人を専用機で救出したが、クルーズ船乗客には何もしなかった」
そこに軍由来のものは?
「顧客に向き合わず、データを取ることに向いていた。高齢者を船内に閉じ込めれば、こうなることは容易に予想できたはずだ。結果的に人体実験をしてしまった、ともいえる。亡くなった方々も海外旅行に出るくらいだから、検疫前は元気な人たちだったのだろう。彼らの死には回避可能性、予見可能性があるから業務上過失致死を問われてもおかしくない。多分海外から集団訴訟されるだろう」
米国の疾病対策センター(CDC)のような「感染症の司令塔」を作るべきとの議論もある。
「CDCは第二次大戦後の46年7月に国防総省マラリア対策部門の後継機関として立ち上がった。戦前の日本の伝研に相当する組織だ。日本が大戦で勝利していたら、伝研こそがCDCとなっていただろう。CDCの特徴は、政府から独立して、感染症対策を立案・遂行できることだ。情報開示の圧力を避け、独走することが可能になる。まさに731部隊がやったことだ。果たして、そんなものが日本に必要なのだろうか。私から見ると、感染研の人たちのメンタリティーがすでにCDCになっている。国民の方を見ていない。帝国陸海軍の亡霊たちが、専門家会議の委員にとりつき、復活を果たそうとしているように見えて仕方がない」
一斉休校にも反対と?
「国家が介入すべきことではない。地域に委ねるべきだ。そもそも学校が休校になるとお母さんが働けなくなるし学童がもっと過密化する。どっちに被害が多いか。それぞれが試行錯誤して情報開示し、一番合理的なところに落ち着く。権威で規範を作ってもうまくいかない。現時点では高齢者対策こそ強化すべきだ」
いつごろを収束と読む?
「1年以上かかると思う。(ピークは?)だらだら続く。世界中をぐるぐる回る。SARSの時とは比べにくい。もっと世界がグローバル化しているからだ」
この局面、どう転換?
「なぜこうなったのかを検証し、責任問題をはっきりさせ、専門家会議のメンバーを研究開発したいだけの人たちではなく、本当に患者さんに向き合う人たちに入れ替えることだ。半分は高齢者医療の専門家で、残り半分は小児科、産婦人科の医師や看護師といった立場の人たちに切り替える」
4組織はどうする?
「彼らをマイナーポジションに押し込めないと、また研究開発をやりだす。研究開発するならファイザーと戦ってくださいと言いたい。これは安倍首相の人事だ。厚労相ではできない。ここで思い切った転換をしないと薬害エイズ事件と同じ構図になる。C型肝炎問題もこの人たちだ。肝炎も血液製剤も特殊だから国がやるといって、カルテルを組んできた。731部隊から連綿と続く構造だ」
未(いま)だに731の亡霊か?
「それを払拭(ふっしょく)するいい機会でもある。実は、日本には新型コロナウイルス克服で世界をリードするポテンシャルがある。それは国民皆保険制度があるからだ。すべての国民が一定の自己負担を支払うことで、医療を受けることができる。新型コロナウイルスは指定感染症になっているので、診断されれば、医師は厚労省へ届け出が必要になる。普通に診療するだけでデータが蓄積する。こういったマスデータが取れるのは日本だけだ。この膨大なデータを解析して公開、多くの研究者が議論に参加し、論文を書く。世界中で議論し、コンセンサスが形成される。エビデンスに基づいた政策や経営判断が可能になる。それこそ中国、韓国と共同で東アジアプロジェクトを立ち上げる手もある」
上氏ならではの身を挺(てい)しての直言だ。4組織関係者には耳に痛いことばかりであっただろう。ただ、PCR検査の遅れもクルーズ船対策の失態も、臨床軽視、研究優先、秘匿体質という3本の歴史的補助線を引くことで見えてくるものがあることも確かである。
前号では、安倍氏に全面謝罪による与野党一体化の道をお勧めし、今号では、賢明なる人事権行使による局面転換を進言することになった。このウイルス禍、正しく恐れるべきではあるが、当面は社会的混乱と経済縮小の悪循環が続くことは容易に予想される。一安倍政権の崩落を超え、日本国の命運を左右する情勢にまで至ったとの危機感がある。いま安倍政治であることの不幸をもうこれ以上増幅せざることを切に望む。
かみ・まさひろ
1968年生まれ。医師。医療ガバナンス研究所理事長。虎の門病院、国立がんセンター中央病院で臨床研究に従事したのち、医療ガバナンスを研究。著書に『ヤバい医学部』『病院は東京から破綻する』ほか
イランの回復者数に対してのコメントは、探しても見つかりませんでした。
何か情報ありましたら、教えていただけたら嬉しいです!










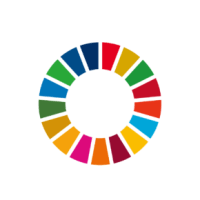
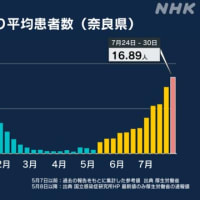

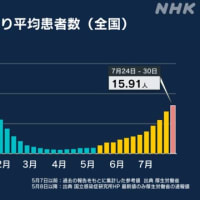

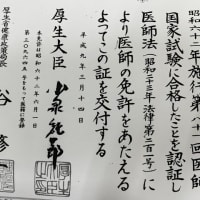


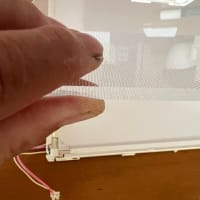
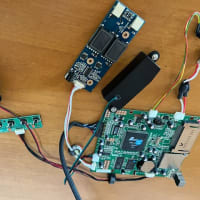
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます