
1587年の10月1日、
北野天満宮で「北野大茶湯」がひらかれました。
この年の8月に、洛中をはじめ畿内一円に高札が立てられたそうです。
「身分上下の別なく、
数寄者であれば手持ちの道具を持参し参加せよ、
茶のない者はこがしでもよい」
そうか、
このころの募集要項というのは、「札」だったわけですね。
全国から集まった参加者は800を超えるほどといいますから、
わずか2カ月で、すごい集客です。
これだけ人が集まってお茶を点てるとなると、
お水はどうしたのかな、と気になります。
北野天満宮の、今は駐車場になっているところに、
「太閤井戸」の跡が残っていました。
当日は、ここから水が汲まれたそうです。
天満宮の敷地内にも、他に井戸はあります。
近隣の井戸も使ったと記されています。
でも、井戸の水って、そんなに供給できるものなのですか?
と、考えていると、
元気なおじさま方のご一行が現れ、
「北野大茶会の時の水は、岐阜から運んだんですよ~!」
と教えてくださいました。
岐阜から?水を運ぶ?
どうやって運んだのでしょう。
可児(かに)市の兼山の水だそうですが、
京都まで何か水運が利用できたのでしょうか。
可児といえば、
森蘭丸。
なにかご縁が続いていたのでしょうか。
お茶は皆さん思い思いのお茶を持ち寄ったのでしょうが、
水はさすがに京都に来てから、いや会場に着いてから調達したわけでしょう。
その辺のインフラがとっても気になります。
北野天満宮で「北野大茶湯」がひらかれました。
この年の8月に、洛中をはじめ畿内一円に高札が立てられたそうです。
「身分上下の別なく、
数寄者であれば手持ちの道具を持参し参加せよ、
茶のない者はこがしでもよい」
そうか、
このころの募集要項というのは、「札」だったわけですね。
全国から集まった参加者は800を超えるほどといいますから、
わずか2カ月で、すごい集客です。
これだけ人が集まってお茶を点てるとなると、
お水はどうしたのかな、と気になります。
北野天満宮の、今は駐車場になっているところに、
「太閤井戸」の跡が残っていました。
当日は、ここから水が汲まれたそうです。
天満宮の敷地内にも、他に井戸はあります。
近隣の井戸も使ったと記されています。
でも、井戸の水って、そんなに供給できるものなのですか?
と、考えていると、
元気なおじさま方のご一行が現れ、
「北野大茶会の時の水は、岐阜から運んだんですよ~!」
と教えてくださいました。
岐阜から?水を運ぶ?
どうやって運んだのでしょう。
可児(かに)市の兼山の水だそうですが、
京都まで何か水運が利用できたのでしょうか。
可児といえば、
森蘭丸。
なにかご縁が続いていたのでしょうか。
お茶は皆さん思い思いのお茶を持ち寄ったのでしょうが、
水はさすがに京都に来てから、いや会場に着いてから調達したわけでしょう。
その辺のインフラがとっても気になります。











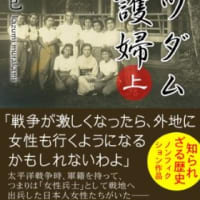








連日楽しく読ませていただいてます。茶はすそ野も広く歴史も興味深いですね。
その北野大茶之湯の会に運んできた水のことをちょっと調べてみました。
兼山のお話 ↓
http://sekibi.hp.infoseek.co.jp/page136.html
このホームページによれば、その水は
「金山城址」の鳥が峰より湧き出る湧水とのこと。
この湧水は、「菊の水」または、「不老水」と呼ばれて珍重されているらしいです。
太閤秀吉が、北野大茶会を催した時・・・・金山城主 森忠政公(仙千代)は
この清水を、茶坊主の鳥屋尾不省に持参させたところ、太閤秀吉公は大層喜び、賞味されたと伝えられています。森蘭丸の母親であります妙向尼も、常々この清水の水を飲み、73歳の長寿を保たれたそうです。
また、別のHPからは、
天正(1587)15年10月1日には、北野天満宮の松原で豊臣秀吉が北野大茶会を催した。このイベントに限っては、身分・国籍を問わずに参加でき、1500もの茶席が出た。
森忠政は、金山の「小関の清水」を取り寄せて茶坊主・鳥屋尾不省(とやのおふせい)に茶を立てさせた(『金山記』。)
輸送は2ルートが考えられます。
●木曽川を下り伊勢長島あたりから東海道を経て京へ運ぶ
●関ヶ原を越え、伊吹山から北近江に出て琵琶湖の水運を利用して京へ運ぶ
どのくらいの分量の水をどんな容器で何人の人手をかけて運んだか・・・ですね。
なお、戦国時代には金山衆といえば、土木工事・井戸掘り技術者集団であったのです。武田の金山衆は特に有名でした。主な活躍の場は、
・敵の城の水の手を絶つ仕事
・簡易トンネルを掘って忍者を忍び込ませる仕事
・自分の城が敵に囲まれたときの抜け道用トンネルを用意する仕事
などをしていたらしいです。
秀吉はそういう今までの自分の天下取りに加わってくれた人々をもてなすために慰労の意味をこめて茶会を催したのでしょう。秀吉の初手柄・・・美濃攻めゆかりの地も近い金山の不老水で点てたお茶!
運んできてくれた意気にも感じて、たいそう美味しかったに違いないですね。