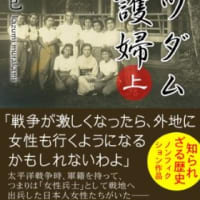売茶翁の詩を味わいたくても、
漢詩がなかなか読めない・・・
読めても意味がわからない・・・
というレベルの私にありがたき一冊!
この本には、
現代語訳と
丁寧な解説がついています。
全5巻で、
1巻は田能村竹田などの文人
2巻は新井白石などの儒者
3巻は梁川紅蘭などの女流詩人
4巻は吉田松陰などの志士
そして
5巻が売茶翁などの僧門となっています。
漢詩は奈良平安のころからメジャーな日本文学で、
平安時代に「詩」といえば和歌ではなく、
漢詩のことをいったそうです。
江戸から明治にかけて頂点を迎えていて、
知識人はさくっと漢詩を詠んだのです。
漱石、鴎外あたりを最後に、
愛好家のものとなっていったそうです。
5巻に納められているのは他に、
大典顕常(だいてんけんじょう):
日本で初めて茶経の注釈書『茶経詳説』を著した人。
大潮元晧(たいちょうげんこう):
大典顕常の詩文の師で売茶翁の法弟。
独菴玄光(どくあんげんこう):
曹洞宗の学僧。
があって、
売茶翁の茶を煮る姿も詠まれています。
この時代の禅僧の交友関係などがわかってくると、
売茶翁がどんなお茶を使っていたかとか、
道具はどんな物を使っていたのかが、
さらにわかってくるでしょう。
でも私には、
臨済宗、天台宗、曹洞宗、黄檗宗の
違いもよくわからずで・・・
売茶翁の詩の一言一言がわかる日は
いつのことやらです。
『江戸漢詩選5僧門』
注者 末木文美士
堀川貴司
1996年1月発行
岩波書店
全巻品切重版未定
図書館で探しましょう。
茶坊主様のレポートのお陰様で
すっかり売茶翁がマイブームになってきました。
漢詩がなかなか読めない・・・
読めても意味がわからない・・・
というレベルの私にありがたき一冊!
この本には、
現代語訳と
丁寧な解説がついています。

全5巻で、
1巻は田能村竹田などの文人
2巻は新井白石などの儒者
3巻は梁川紅蘭などの女流詩人
4巻は吉田松陰などの志士
そして
5巻が売茶翁などの僧門となっています。
漢詩は奈良平安のころからメジャーな日本文学で、
平安時代に「詩」といえば和歌ではなく、
漢詩のことをいったそうです。
江戸から明治にかけて頂点を迎えていて、
知識人はさくっと漢詩を詠んだのです。
漱石、鴎外あたりを最後に、
愛好家のものとなっていったそうです。
5巻に納められているのは他に、
大典顕常(だいてんけんじょう):
日本で初めて茶経の注釈書『茶経詳説』を著した人。
大潮元晧(たいちょうげんこう):
大典顕常の詩文の師で売茶翁の法弟。
独菴玄光(どくあんげんこう):
曹洞宗の学僧。
があって、
売茶翁の茶を煮る姿も詠まれています。
この時代の禅僧の交友関係などがわかってくると、
売茶翁がどんなお茶を使っていたかとか、
道具はどんな物を使っていたのかが、
さらにわかってくるでしょう。
でも私には、
臨済宗、天台宗、曹洞宗、黄檗宗の
違いもよくわからずで・・・
売茶翁の詩の一言一言がわかる日は
いつのことやらです。
『江戸漢詩選5僧門』
注者 末木文美士
堀川貴司
1996年1月発行
岩波書店
全巻品切重版未定
図書館で探しましょう。
茶坊主様のレポートのお陰様で
すっかり売茶翁がマイブームになってきました。