 Alice Kaplan, The Interpreter (The University of Chicago Press)
Alice Kaplan, The Interpreter (The University of Chicago Press)
著者はブラジヤック裁判を扱った"The Collaborator"で知られる。ロジェ・グルニエ(『黒いピエロ』他)、ルイ・ギユー『OK、ジョー』の英訳者でもある。謝辞によれば、ギユーの作品を知るきっかけを与えたのがグルニエだった。第二次大戦末期に米軍の通訳を務めたギユーの日記、軍の文書記録を参照し、存命の関係者や家族に会い、入念な調査の上で書かれた本。
1944年8月、アメリカ第3軍司令官パットンは全部隊にメモを送り、フランスの民間人に対する暴力犯罪増加に、深い懸念を表明した。
にも関わらず事件は起きた。小さな村プリュモーダン(地図)に滞在中の補給部隊兵卒ジェイムズ・ヘンドリックスは、酔って農家に押しかけた。手にはライフル銃を持つ。ブートン家では夫人にキスしかけるのを息子が制し、卵を渡して帰らせた。今度は向かいのビニョン家のドアを叩く。片言のフランス語で「ドイツ人か」("Boches !")と叫ぶ。家の中から返事があるが、彼には理解できない。「開ける、お嬢さん」("Ouvrir, Mademoiselle ! ")を繰り返した挙句、ドアに向け発砲、貫通した弾は主人ヴィクトル・ビニョンを死亡させた。娘ジャニーヌと母親ノエミは、ブートン家に逃げ込む。娘は素早く姿を隠したが、追ってきたヘンドリックスは男たちを銃で威嚇、ノエミを強姦しようとする。必死の抵抗にかなわず退散、キャンプから駆けつけた指揮官らが、ヘンドリックスを麦畑で見つけてMPを呼んだ。
『OK、ジョー』の元になったもう一つの事件は、ブレストに近い町レヌヴァンLesnevenで起きた。ホテルのバーで、レジスタンスの戦士フランシス・モランが、ドイツのスパイではないかと疑われる。飲んでいたレンジャー部隊の大尉ジョージ・ウィッティントンは、庭でモランを射殺する。大尉はノルマンディー上陸作戦で勲功をあげた英雄だった。
フランシス・モランは自称オーストリア生まれ、フランス外人部隊に在籍後、帰化したという。米兵に怪しまれたドイツ訛りも説明がつくが、履歴には謎が残る。事件の日には、英米の軍服をまぜこぜに着ていた。正規軍ではないFFI(フランス国内軍)の兵士は、米兵の目には規律を欠き胡散臭く感じられた。
黒人兵ヘンドリックスは絞首刑を宣告される。ウィッティントン大尉は無罪。ギユーは二つの裁判の対照に驚く。一度も証言の機会を与えられないヘンドリックス。落ち着き払って、雄弁に事件を語って見せるウィッティントン。厳しい反対尋問を受けることもなく、ウィッティントンの物語が、そのまま真実にされて行く。
ヘンドリックスを弁護したラルフ・フォガティ中尉はロー・スクールこそ出ているが、弁護士経験はない。検事のジョゼフ・グリーン中尉はブルックリンの弁護士。
実は証人の誰一人、あの夜の兵士がヘンドリックスだとは断言できなかった。ジャニーヌは法廷で答えたのを覚えている、「闇の中で、黒人をどうやって見分けろというのですか?」 軍の法務局による裁判後の報告には、「フランスの証人は黒人の特徴や顔に馴染みがない」 証人たちに言えるのは、男が黒人だったということだけ。グリーン中尉は質問の際、加害者の人種だけを強調した(「あなたと争った黒人兵士は・・・」)(p.54-55)
著者は考える、被告の心神喪失を主張することはできなかっただろうか(p.66) アメリカ第3軍は次第に戦争の心理的ストレスに敏感になり、軍法会議にかけられた戦闘部隊combat unit 兵士には、精神鑑定を求めていた。しかしヘンドリックスは( 黒人兵の80%がそうであったように)補給部隊 service unit に配属された。鑑定は必要と判断された場合に限られる。泥酔状態(軍法会議では情状酌量に値するとされないが)も、部隊での「半分気が変」half-crackedとの評判も、法廷で問題にされることがない。経験不足のフォガティの弁護では、辣腕グリーン中尉を相手に、勝ち目はなかった。そのグリーンが、ウィッティントン大尉の裁判では弁護に回る。
『OK、ジョー』でギユーはグリーンをモデルにしたロバート・ストーン中尉を登場させる。初対面から語り手と「ボブ」「ルイ」と呼び合う。明朗で気取りのないアメリカ流。グリーンのヴァイオリン趣味も、ストーンの人物造型にうまく生かされている。
ギユーの英語熱は、少年時からのものだった。サン=ブリューの港で英国の船乗りに話しかけた。13歳の夏には、親しくなったジャーナリストに、英国の家に招待された。1920年代から文芸翻訳で糊口をしのいだ。(Kaplan, P.15)
アメリカの軍服を着たギユーの写真が収録されている。「解放」のさなか、米軍と行動を共にしたことは、新鮮な体験だったに違いない。同時にアメリカ的な法と正義への、違和感のようなものを抱かせた。
通訳の難しさは、ビニョン夫人の証言で際立った。仏語と英語、日常の言葉と、法廷で求められる言い方のずれ。外国人ばかりの法廷に引き出され露骨な質問を受ける女性の辛さを、ギユーは思いやらずにいられない。
連合軍の将校には、住民との接し方のハンドブックが渡されていたという。内向的で、外人嫌いのブルトン人。それらの紋切型に混じって、ブルターニュの女は「生まれつき好色」だとする一節さえあった。
One should not pay much attention to the lapses of Breton women with the Germans ―the race is naturally erotic. (p.21)
ヘンドリックスが訓練を受けたミシシッピー州のCamp Van Dorn では、基地周辺には黒人の入れる飲食・娯楽施設がなかった。北部出身の黒人が多い連隊では、反抗や暴動まで起きている(p.31)
『OK、ジョー』の「私」の疑問、「なぜ黒人ばかりが」に、この本は人種隔離撤廃以前の軍隊で黒人兵の置かれた状況を示すことで答えようとする。
ギユーには語り得なかった部分にも、照明が当てられる。ヘンドリックスの部隊指揮官、ドナルド・タッカー中尉は数少ない黒人将校の一人だった。偏見があるからこそ黒人兵には非の打ち所のない振舞いを求め、法廷では、指揮官としての自分も裁かれているのを意識せねばならない中尉の苦渋を、著者は想像してみる(p.70)
ウィッティントン大尉は英雄として故郷に帰る。ミズーリ大学でジャーナリズムを学び、一時は新聞社を経営、石油の出るおじの地所を遺贈され、ケンタッキー州ヘンダーソンに移り住む。妻アグネスと共に地域のリーダーとなった。1956年、公立学校での人種隔離撤廃に抗議し白人家庭で登校拒否が行なわれた時には、敢えて息子を学校に行かせた。「バイブル・ベルトの無神論者、言論の自由と中絶、ゲイの権利を支持し、政府の介入を忌み嫌った」(p.134) 晩年、事件のことを妻に打ち明けたが、多くを語らなかった。
ロジェ・グルニエによる本書の紹介
Roger Grenier, Introduction to Alice Kaplan’s presentation of THE INTERPRETER










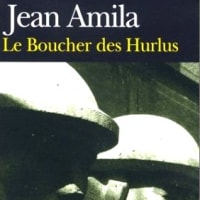
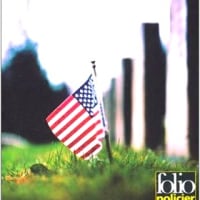
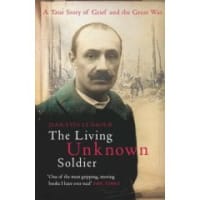







おみそれいたしやす。
今後も更新楽しみにしております。