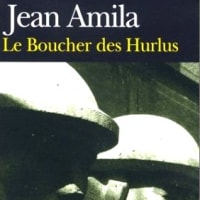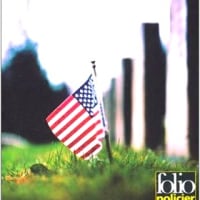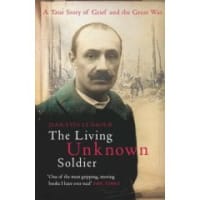Jean Amila La lune d'Omaha (Folio policier)
Jean Amila La lune d'Omaha (Folio policier)
ノルマンディー上陸作戦の「Dデイ」、物語はLCA(上陸用舟艇)からの視点で書き出される。
On ne voyait rien que le ciel bas, sauf quand la barque piquait du nez ; alors on distinguait la plage lointaine en rideau grisâtre. La France !
垂れ込めた空しか見えなかった、だが時おり舟の舳先が沈む、すると遠くの砂浜が、灰色がかったカーテンになって見えるのだった。フランスだ!
高波に舟には水が入り、兵士たちはヘルメットで水をかい出す。重苦しい幕開け。オマハ・ビーチ上陸は他の地点と桁違いの死傷者を出した。ライリー軍曹や兵卒ハッチンズにとって、この戦闘はかつて体験したことのないものだった。
二十年後、軍曹は浜を見下ろす米軍墓地の管理人になっている。庭師だった老人、アメデ・ドゥルイの死。老人は死ぬ前、戦後の混乱した時期に、戦死者の骨も牝牛の骨も一緒くたにして埋めたと告白する。軍曹もひそかに感じていた。整然と並ぶ十字架、完璧に手入れされた芝生、星条旗、それらが覆っているのは一つの巨大な共同墓穴だ。? Du bidon pour les familles ! ?(家族のための嘘っ八)
戦場から逃亡し、フランス人ジョルジュ・ドゥルイとして生きていたハッチンズが現われ物語は急展開する。アメデ・ドゥルイはハッチンズが自分の子に成りすますのに協力した代わり、金をゆすり続けていた。アメデの実の子フェルナンとその妻、軍曹と若いフランス人の妻クローディーヌ、軍曹の上官、メイスン大尉と夫人。抜け目のないノルマンディーの農民と、墓地を管理するアメリカ人が形づくる小さな社会に、ハッチンズの帰還は波紋を引き起こす。
ハッチンズの小隊はオマハ・ビーチで、後方にいる味方からの砲撃を受けた。混戦の中、実際にそんなことが起きたのかは(牝牛の話同様)わからない。倒れても倒れても兵士を送り込む、「場」だと感じさせるような作戦。それを計画した者への怒り。兵士が戦場で何かに目ざめ、どんなことをしても生き延びようとするまでは、序章で説得的に描き出されていた。
妻に付き添われ、ジョルジュ・ドゥルイと名乗って現われた時、ハッチンズには今の生活を捨てる気はない、ただ老人の死で恐喝が終わることを願っていた。じっと息をひそめ生きてきた男が、やがてジョージ・ハッチンズに戻ろうとする、その劇的な変わり様。夫の保護者を演じていた妻ジャニーヌ、脇役にすぎなかった軍曹の妻クローディーヌ、彼女たちの役割も刻々変化して行く。謎解き小説の技巧とは異なるが、作劇術の見事さで引き込み、驚かせてくれる小説。初版は1964年の叢書「セリ・ノワール」版。
アミラ(1910-1995)の本名ジャン・メケールによる?La marche au canon?(1939~40年の「奇妙な戦争」を一兵卒の目で描く)の巻末伝記によれば
パリ10区で1910年11月24日生まれる。第一次大戦中の1917年、アナーキストの父は塹壕から脱走、妻子を捨てて新たな人生を始める。噂を止(や)ませるため、母親は夫が「見せしめに銃殺」されたことにする。メケールは「セリ・ノワール」の一冊として出版された小説で、この修正された家庭ドラマに肉付けを行なうだろう。驚くべき混同現象によって、虚構が現実に取って代わる。作者に当てられた伝記的記事はみな、小説版をメケール/アミラの実人生として示すだろう。作家自身、インタビューでの問いには、その時次第、どちらかの答え方をしている。
銃殺されたか否か、いずれにせよ夫を失いメケール夫人の精神的安定は乱される。隣近所の目には夫人はボルシェヴィキであり、彼らの態度は、状況をいっそう耐えがたくする。彼女は二年の間ル・ヴェジネの病院に収容され、ジャンはクールブヴォワのプロテスタント孤児院で四年を過ごすことになる。
 八歳の少年ミシェルが主人公のLe Boucher des Hurlus (Folio policier)がその「小説版」である。父は1917年、突撃の命令に従わず銃殺された。休戦からまだまもない頃、「臆病者」の妻と子は日々罵られ侮辱を受ける。ある日、同じアパートの女に傘の先で打たれた母親は、たまりかね反撃する。女と亭主の訴えで、母親は警察署に連れて行かれる。孤児院に入れられたミシェルは、同じように父親が銃殺された三人の少年と脱走、兵士に無意味な犠牲を強(し)い、屋 le Boucher と仇名された将軍に復讐しようとする。
八歳の少年ミシェルが主人公のLe Boucher des Hurlus (Folio policier)がその「小説版」である。父は1917年、突撃の命令に従わず銃殺された。休戦からまだまもない頃、「臆病者」の妻と子は日々罵られ侮辱を受ける。ある日、同じアパートの女に傘の先で打たれた母親は、たまりかね反撃する。女と亭主の訴えで、母親は警察署に連れて行かれる。孤児院に入れられたミシェルは、同じように父親が銃殺された三人の少年と脱走、兵士に無意味な犠牲を強(し)い、屋 le Boucher と仇名された将軍に復讐しようとする。
戦争の長期化につれフランス軍の士気は低下した。1917年には西部戦線で、ニヴェル将軍の指令による「シュマン・デ・ダームの戦い」la bataille du Chemin des Damesが多くの犠牲者を出し、厭戦・反戦の気運を高める。この年「五月から六月にかけて、三万~四万の兵士が不服従の行動にでた。『反乱』兵のうち五五四人に死刑判決がくだされ、四九人が処刑された」(福井憲彦編『フランス史』山川出版社)
戦後、少数だが「反乱」兵士のための記念碑が設けられた。クレルモン=フェランに近いリオム Riom の墓地には、「祖国に命を捧げた」戦死者の記念碑と向かい合って、銃殺された兵士のためのオベリスクが立っている。1922年の除幕式では警官隊が介入し、「戦争と戦おう」Guerre à la guerre と記された横断幕や旗をもぎ取ろうとした。(?Dès 1922, Riom a érigé un monument pour les fusillés de 1917?, Le Monde 12.11.98)
休戦80周年の1998年にはジョスパン首相が、クラオンヌCraonneの式典席上、シュマン・デ・ダームの戦いのさなか銃殺刑を受けた兵士の名誉回復を図り、シラク大統領らがこれに異議をはさんでいる。(World War I Sets Off A New Battle In France -The New York Times)
Souain-Perthes- lès-Hurlus では四人の伍長が処刑されたが、1915年のこと。キューブリック監督の『突撃』は「一部この事件に霊感を得」( Wikipédia)ている。それに似た出来事が、1917年にもあったのか?(アミラの小説では、「屋」将軍の名は戯画的な Des Gringuesになっている)
孤児院から逃亡した子供たちはパリの東駅で、軍の「フィアンセ」に会いに行く娼婦たちと出会う。女将のマダム・ジェルメーヌは子供たちに同情、列車に乗せてもらうことになる。「戦争孤児」を盾に取り、大人を利用してしまうあたりの皮肉なおかしみ。Châlonsから先は危険な「荒廃地帯」les régions dévastés だが、「何とか大尉」le capitaine Machinの好意で軍用バスに同乗。将軍殺害の武器を戦場で手に入れるはずだったが、あるのはただ堆く積み上げられた骨の山、村は跡形もない(Perthes-lès-Hurlusはそのまま復興されることなく、Souainと合体して一つのコミューンになる)
将軍を殺す計画も、空想好きの少年たちならではのとんでもないもので、おかしさも、挫折の物悲しさも、大人を主人公にしたのでは得られなかっただろう。この作品も、謎解き小説ではない。1982年の作。