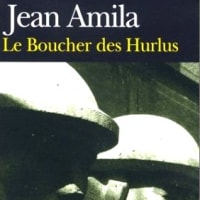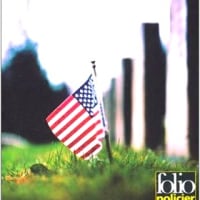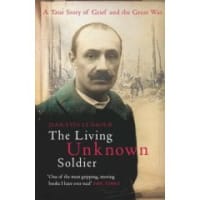『サリド』の語り手は、家の壁に無数の新聞の切り抜き、写真、ポスター、ビラを貼っていた。中国での戦争、ウィーンに入るヒトラーの軍隊、イタリアやスペインでの対ファシズム抵抗運動が、「壁新聞」には記されていた。大戦に向かってすべてが走り出した今、駅の陸橋に佇み、サイレンの音を聞きながら、彼は「壁新聞」を引き剥がし、捨てようと思う( Folio, p.27)。
『サリド』の語り手は、家の壁に無数の新聞の切り抜き、写真、ポスター、ビラを貼っていた。中国での戦争、ウィーンに入るヒトラーの軍隊、イタリアやスペインでの対ファシズム抵抗運動が、「壁新聞」には記されていた。大戦に向かってすべてが走り出した今、駅の陸橋に佇み、サイレンの音を聞きながら、彼は「壁新聞」を引き剥がし、捨てようと思う( Folio, p.27)。
1936年2月にはスペイン、6月にはフランスで、左翼人民戦線政府が成立した。7月に軍部の反乱でスペイン内戦が勃発。レオン・ブルム政府はスペイン政府の支援要請を受けるが、右翼や急進社会党の反対、またイギリスの圧力で内戦不干渉を提唱。ダラディエが首相の1939年2月、フランスはイギリスと共にブルゴスのフランコ政府を承認する。
人民戦線の歴史的敗北の苦味、虚脱感?小説は「私」の思いを、未整理のままに示す。
難民支援を行なう le Secours rougeは共産党系の組織だが、彼は党員ではない。1934年、アストゥリアスの労働者蜂起鎮圧以後、スペインからの政治難民がこの町に来るようになり、支援を始めた。
カタロニアの農民サリド中尉は、フランス語を話せない。特徴のない顔に、目だけが変に鋭い。ル・ヴェルネの収容所(Le camp du Vernet d'Ariège, 1939 ? 1944)に移される前に病院から逃亡、「私」は仲間たちと、彼に力を貸す。サリドはモスクワ行きを望むが、パリの共産党「同志」たちは、彼の処遇を決めかねている様子。直接交渉に赴くサリド、難民受け入れセンターの料理人ゴーティエおばさんla mère Gautierがお供をするが、二人はパリで道に迷う。旅は無駄骨に終わる。
兵役を免除されている「私」は、県の難民受け入れ活動に従事したいと申し出、断わられた。サリド逃亡の件は、語り手と地域の間に齟齬を生んでいた。戦時体制への移行と共に社会参加の道が閉ざされ、「私」は宙に浮いてしまう。 本来の「仕事」に戻る時が来たのか?
戦争の始まりだけを、一個人の視点で書く『サリド』は「奇妙な戦争」と敗北以降を語らない。予兆めいたものを読み取ることは、読者に委ねられる。「これまで」と「これから」の間、空白の地点に立つ「私」―当然叙述は直線的に進まない―、そして何人かの人物の肖像。小説が描くものは、それに尽きる。
1976年、『サリド』と合わせ一巻として刊行された『OK、ジョー』 O.K., Joe ! は、米軍のため通訳を務めたギユーの体験に基づく。1944年夏から秋、連合軍によるフランス解放が進行中の物語。
米軍兵士による住民相手の犯罪、軍法会議の裁き。レイプ事件を起こすのは、判で押したように黒人兵。あっさりと罪を認め、絞首刑を宣告される。どうして黒人ばかりなんだ?「私」の素朴な疑問は、アメリカの軍人を困らせ、苛立たせる。
レンジャー部隊の白人将校が、フランス人を射殺する。黒人兵とは明らかに違った扱いを受けた上、無罪放免された将校の表情に「私」は大口開けて笑う人食い鬼 ogre を連想する(p.272)。
反米小説?「私」と接するアメリカ人は知的で快活、気持ちの良い人物揃いである。シカゴの学徒兵ビルはフランス系で、一番親しくなる。ビルは口癖のように、出征前に聞いた司教の訓戒を引く。? Mes garçons ! Si c’est pour maintenir le monde comme il est que vous allez là-bas, alors n’y allez pas ! Mais si c’est pour le changer, alors allez-y ! ?(p.111 「 諸君!世界をそのままに保つため彼の地へ向かうなら、行ってはならない。しかし世界を変えるためなら、行き給え」)
アメリカ流の理想主義、使命感、衛生観念、道徳的潔癖さ。ビルに言わせれば、黒人は「自分に規律を課す」s'imposer une disciplineことができない(p.199)。「私」は無心な聞き手、観察者として、驚いたり不思議がったりして見せながら、それらを物語る。
ドイツ軍との局地戦は続いている。対独協力者への私刑が行なわれる一方、親独民兵隊の残虐さも追想される。『OK、ジョー』は「解放」の語感とはうらはらの、薄闇の印象を残す。