1953年の春、マンディアルグと夫人ボナはミラノ郊外ブルゲリオBrugherio(地図)の病院に≪神経の病≫で入院しているフィリッポ・デ・ピシスを見舞う。
ボナのおじ、画家Filippo de Pisis(1896-1956)は第一次大戦中フェラーラでジョルジョ・デ・キリコやサヴィニオ、カッラと「形而上絵画」の運動を興した。初期には詩や散文を書いていた。デ・ピシスの絵画http://www.palazzodiamanti.it/index.phtml?id=383にマンディアルグは十八世紀のグワルディGuardiや特にマニャスコMagnasco、現代ではスーティンの影響を見る。スーティンとの共通点は、レンブラントの『皮剥ぎにされた牡牛』に幻惑され、何度もこの絵を霊感源としたこと。
入院後三年になるデ・ピシスは見る影もなく痩せ、大きかった目は半ば閉じ、唇は「薄くてカーテンの紐のよう」minces comme des cordons de rideau 唾を飲み込めず絶えず吐き出す。De cela, il s’excuse,avec une sorte de sourire, car il n’a rien perdu de sa grâce ni de sa gentillesse.(これについて、彼は詫びを言う、微笑みのようなものを浮かべて。気品もやさしさも、まったく失っていない)
デ・ピシスの顔はゆがみ、片方の目がもう一方より下にある。非対称は、血の気の失せた肌の色に劣らずマンディアルグを動転させる。
Voilà ce que les électrochocs, dont il a subi des séries nombreuses, et je ne sais quelles piqûres mauvaises (malignes), dont se servent les médecins psychiatres, ont fait d’un homme admirable.
数重なる連続電気ショックと、精神科医が用いる何やらよくない(有害な)注射が、一人の素晴らしい人間をこうしてしまった。
電気ショックといえばロボトミーと並び非人間的、残虐のイメージがある。ロデスの精神病院でアルトーの治療に当たったフェルディエール医師Gaston Ferdière (1907-1990)の名は、電気ショック療法と結びつけて記憶される。
しかし電気ショック療法 実は現役の治療法(風野春樹氏「私家版・精神医学用語辞典」)のような記事もある。
André Roumieux et Laurent Danchin, Artaud et l'asile Nouvelles Éditions Séguier, 1996 も、決して電気ショックを理由にフェルディエール医師を鬼扱いするわけではないようだ。Florence de Mèredieu Sur l’électrochoc- le cas Antonin Artaud という本も出ている。1943年から46年までをロデスの病院で送ったアルトーは、イタリアで1938年に開発されてまもない、全身麻酔や筋弛緩剤の投与など「修正」(風野氏、前出)を経る以前の電気ショック療法と遭遇したことになる。










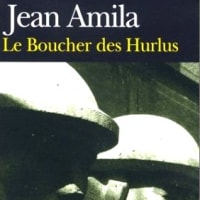
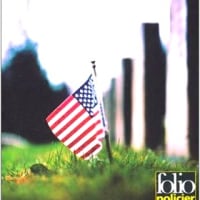
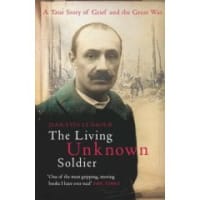







アルトーについて学んでいる者ですが、フェルディエールの治療については、電気ショックそのものというより、その回数、頻度に問題があったようです。meredieuの著作によれば、1945年の時点で、ある程度回数を制限しなければ危険だという研究があったのですが(一回の治療で8から9回を超えてはならない)、Roumieuxの著作によれば一回の治療で12回から13回の電気ショックを行っています。
ちなみにアルトーは電気ショックが直接的に与える苦痛についても周囲に訴えていましたが、何よりも電気ショックが前提としている医学哲学的な理念に反対していたと思います。要はジャクソン主義的な発達という考え方にアルトーは強く反発していました。
「シュルレアリストの友」らしい人が電気ショックを多用したことに矛盾を感じてきましたが、もっと精神医学の歴史を知る必要がありそうです。アルトー自身の言葉でフェルディエールと精神医学がどう語られているかも。
ネットでちょっと調べて知らないことまで書きたがるのは悪癖で、アルトーは余分かな、と思ったのです。けれどもおかげで貴重なコメントをいただくことができました。