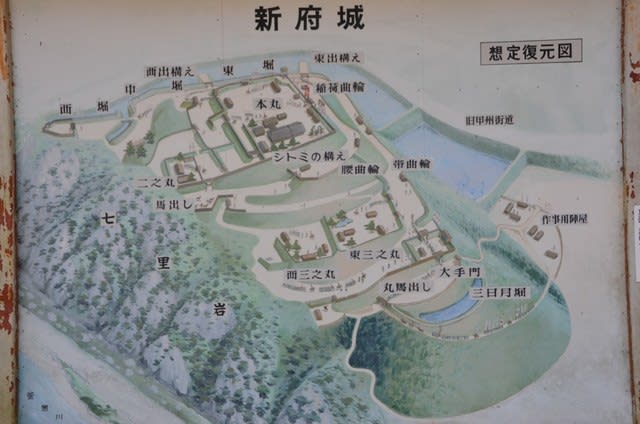現存12天守巡りは、姫路城・松江
城・彦根城・松本城・松山城(伊予)
・丸岡城・弘前城に続いて犬山城です。
これで国宝5天守(姫路城・松江城・
彦根城・松本城・犬山城)の登頂を達成
しました。
犬山
桜が少し咲き始めた3月半ば(かなり
時間が過ぎてしまいましたが)、犬山城
を訪ねました。
名鉄犬山公園駅で降りて、木曽川遊歩道
を歩いていくと、徐々に犬山城天守が見
えてきました。

1537年(天文6年)、織田信康(信
長の叔父)が木之下城を移して築城した
と伝えられます。
1547年、信康が岐阜の稲葉山城で戦
死すると、子の信清が城主となります。
この後、城主はめまぐるしく入れ替わり
ます。

1584年、小牧・長久手合戦の際には
、羽柴秀吉は大軍を率いてこの城に入り
、小牧山に陣をしいた徳川家康と戦いま
した。
江戸時代になり1617年、尾張藩付家
老成瀬正成が城主となってからは、成瀬
氏が代々受け継いで幕末を迎えました。

明治維新で犬山城は廃城となり、天守を
除いて櫓や門の大部分は取り壊され、公
園となりました。
天守の創建年代については、天正説(1
573-92年)、慶長説(1600年
頃)などいくつかの説があるそうです。

犬山城は別名「白帝城」と呼ばれます。
江戸時代の儒者荻生徂徠が、李白の詩か
らとって命名したと伝えられます。
李白の詩にいう白帝城は、長江の上流四
川省の山地にあり、犬山城の眼下に木曽
川を有する様から例えられたそうです。

天守から見た南方向の風景。
遠方の左側の小高い山が尾張富士(27
5m)。尾張3大奇祭のひとつ石上祭が
8月におこなわれます。

天守から見た西方向の風景。
手前の橋がライン大橋。正面が伊木山(
173m)。山頂付近には戦国時代の山
城、伊木山城跡があり、「夕暮れ富士」と
も呼ばれ親しまれているそうです。
(撮影日は3月20日)