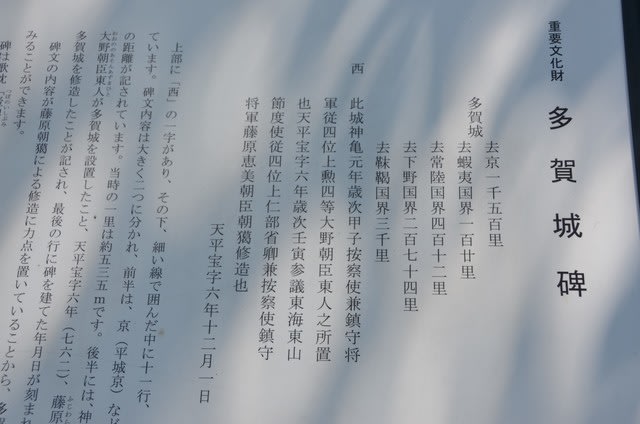(竜王さんのクス)
10月下旬、四国の徳島・高知を
旅しました。
徳島
「竜王さんのクス」は、城山で最大の
クスノキの古木で、樹齢600年くらい。
近くに竜王神社があったことから、こう
呼ばれました。昭和9年の室戸台風で倒
れました。
徳島城は、JR徳島駅の北側、標高61
メートルの城山に築かれた山城と周囲の
平城からなる平山城です。
城跡は徳島中央公園として整備されてい
ます。

(鷲の門)
鷲の門は蜂須賀氏が正門として建てまし
た。明治維新の廃城令により、鷲の門を
除くすべての建築物が撤去されました。
鷲の門も昭和20年の徳島大空襲により
消失し、現在の門は平成元年に復元され
たものです。

この地は、鎌倉時代より伊予国の河野氏
が支配し、室町時代に細川頼之が城山に
小城を築きました。
戦国時代になると、阿波の地は群雄割拠、
城主が入れ替わります。

1582年(天正10年)、土佐国の
長宗我部元親が侵攻し、阿波が平定さ
れます。

(蜂須賀家政の銅像)
1585年の豊臣秀吉の四国攻めで蜂須
賀家政が入城、中世に築造された城を修
築して徳島城としました。以後、江戸時
代を通して、徳島藩蜂須賀氏25万石の
居城となりました。
阿波踊りの起源について、徳島城が竣工
した際、家政が城下に「城の完成祝いと
して、好きに踊れ」という触れを出した
ことが発祥という説もあります。

(本丸跡)
徳島城の山城は連郭式であり、いくつか
の曲輪が段差を持って連続していました。
西から順に、三の丸、西二の丸、本丸、
東二の丸です。
1588年に天守が築かれますが詳細は
不明。元和年間(1615-1624年)
に取り壊されたとされます。
城山では、夏になると阿波踊りの有名連
がここで練習している風景が目立つそう
です。

(城山の貝塚)
城山の貝塚は、約4000~2300年
前の縄文時代後期~晩期の遺跡です。
「赤い靴」など作詞した野口雨情は、昭
和11年2月この地を訪れ、歌を詠みま
した。
「むかし忍んで徳島城の
松に松風絶へやせぬ」
徳島駅から城跡へ向かう歩道橋の近くに
歌碑が建っています。