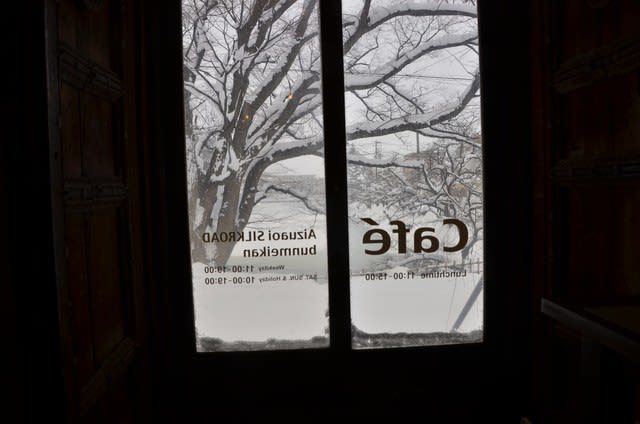松田町
2月中旬の冬とは思えないポカポカ
陽気の日、松田町を訪ねました。
小田急線新松田駅から、バスで30分
余り終点「寄(やどりき)」で下車し
ました。
無料送迎車で「寄ロウバイ園」へ。

寄ロウバイ園は11年前に、標高380
メートルの荒廃農地を整備し、寄中学校
卒業生が250本のロウバイを記念植樹
したのが始まりです。
今では2万本、1万3千平方メートルと
日本最大級のロウバイ園となりました。

ロウバイの花は、蝋細工の梅のように
見えたため蝋梅(ロウバイ)と名付け
られたそうです。
一旦駅まで戻り、今度はJR松田駅から
シャトルバスに乗り、西平畑公園での
「まつだ桜まつり」に向かいました。

松田山の斜面にある公園では、早咲きの
河津桜360本がピンクの花を咲かせま
す。
この日はまだ3分、4分咲きといった
ところです。

(縄文時代の屋外炉)
平成1年から2年の東名高速道路拡幅
工事中に、松田山の根石台地で発掘さ
れた、縄文時代の住居跡群にあった
「炉」を移築したものです。
約4000年前、山の獲物や川の魚を
この炉で焼いたり煮たりしていたので
すね。

「まつだ桜まつり」は3月11日まで
開催中です。
又、近くにあるあぐりパーク嵯峨山苑
では、3月18日まで「菜花まつり」
が開催され、菜花と桜と紅梅の競演が
見られます。