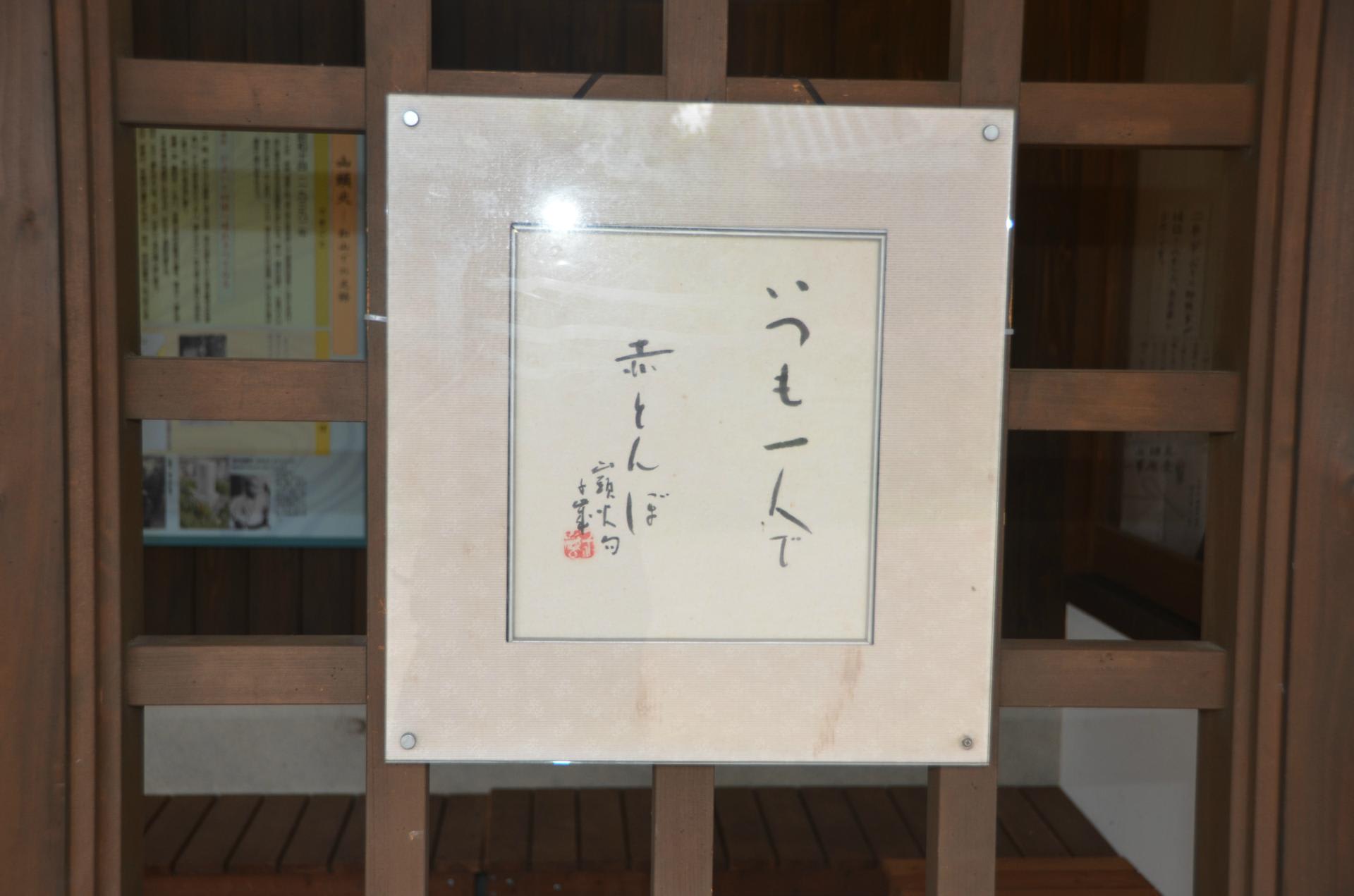「世界の都市(アジア)」シリーズは
北京に続いて西安です。
(撮影は2010年8月です。)
西安その1
古都西安はかつて長安と呼ばれ、
紀元前11世紀から10世紀初頭まで、
2000年にわたって多くの王朝が
都を置きました。
唐代には世界最大の都市に成長し、
日本でも平城京や平安京は長安に
倣ったと考えられます。
現在の西安は中国西北部の政治経済の
中心地、観光都市で人口は約620万人。

今から約2200年前に「最初の皇帝」
を名乗り、中国大陸に統一王朝を打ち
立てた秦の始皇帝。
その陵墓のほど近くに埋められた
「兵馬俑」。
1974年、井戸を掘っていた農民に
より偶然発見され、20世紀考古学の
最大の発見のひとつといわれます。

兵馬俑は、全体でひとつの軍団を写した
ものです。将軍、歩兵、騎兵など、
さまざまな役割の将兵が表されて
います。
兵士の身長は平均178センチメートル
で、顔立ちはそれぞれ異なります。
そのリアルさと大きさには圧倒されま
した。
7000の兵士俑、100の戦車、
400の陶馬などからなります。

競合する国々を滅ぼし、それまで国に
よって異なっていた度量衡、貨幣など
を統一し、始皇帝は新たな支配体制を
確立しました。

始皇帝はなぜ兵馬俑や銅車馬を陵墓の
周囲に埋めさせたのでしょうか。
死後も皇帝として永遠に世界を支配
したいという野望を抱いていたとの
説もあります。
そのスケールの大きさは桁はずれです。
(続く)