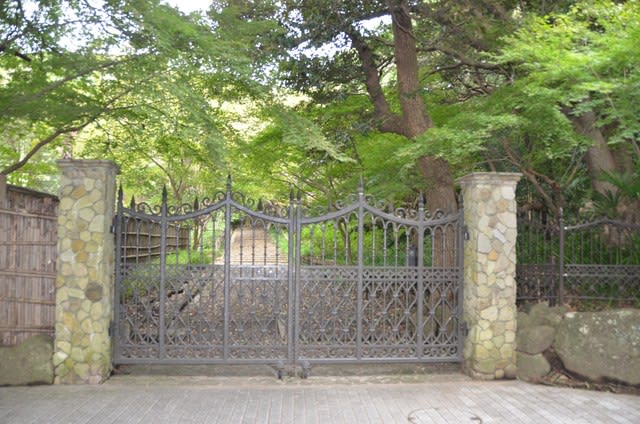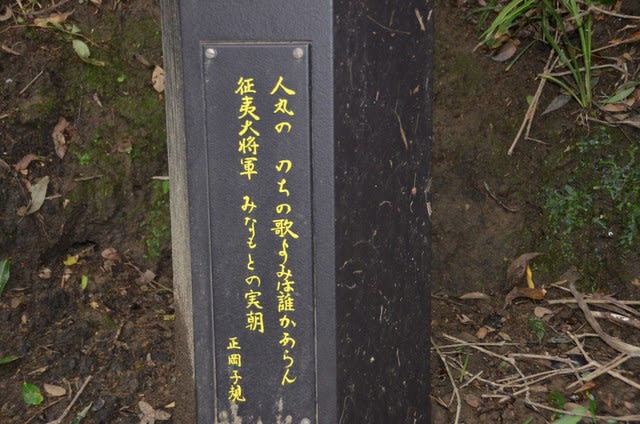(高瀬川)
京都
(撮影は10月末です。)
京都の秋旅2日目は快晴でした。
朝ホテルを出て、大宮通を数分歩くと
西本願寺です。

(太鼓楼)
堀川通に面して立つ「太鼓楼」は、
江戸中期に建てられた2層の楼閣。
1865年(慶応元年)新撰組は隊士の
増加で西本願寺境内に移り、北集会所と
太鼓楼に駐屯しました。

(阿弥陀堂門)
阿弥陀堂門から境内に入ると、早朝です
が外国人観光客の姿がちらほら。
西本願寺は浄土真宗本願寺派の本山。
1272年、宗祖親鸞の遺骨を東山の
大谷から吉水の北に改葬、大谷廟堂を
建て、親鸞の影像を安置したのが本願寺
の起源です。
その後、山科から石山に移った本願寺は
天下統一をめざす織田信長と11年にお
よぶ対立をします。(石山戦争)
1591年、豊臣秀吉から六条堀川の地
を与えられ、現在に至っています。
一方1602年には、徳川家康が教団の
内部対立を利用して、七条烏丸に本願寺
を別立し東本願寺としました。

(阿弥陀堂)
南無阿弥陀仏の「南無」は「おまかせす
る」「帰依する」の意味だそうです。
「多少の修業善行による成仏を願うので
なく、阿弥陀如来の本願を信じて念仏し
て浄土に往生する。貧富・門閥・性別・
人間的器量のいかんをとわず、ただ念仏
によって救われる」と親鸞は説きました
。
堀川通から七条通に出て、朝のウオーキ
ングです。
高瀬川と鴨川を渡ると、東山七条の手前
に京都国立博物館があります。

(京都国立博物館)
重厚なバロック様式の建物の前には、開
門前からすでに長蛇の列です。
開門後も開場まで30分待ちました。
昭和51年以来41年ぶりの「国宝」展
です。
この日は第Ⅲ期の初日でした。

日本肖像画の最高峰ともいわれる、伝源
頼朝像・伝平重盛像・伝藤原光能像の神
護寺三像が見られました。

最小の国宝「金印」は間近で見るために
20分ぐらい列に並びました。
やっとたどり着いても、小さすぎてよく
見えません。
人が多すぎて、とてもゆっくり鑑賞とは
いきませんが、特に印象に残ったのは、
やはり長谷川久蔵「桜図」と彼の死後制
作されたといわれる、父等伯の「松林図
屏風」です。
桜に託した躍動的な生命の輝きと、かた
や夢か幻かはるか霞む静寂の世界とが
緊張感をもって対峙しています。