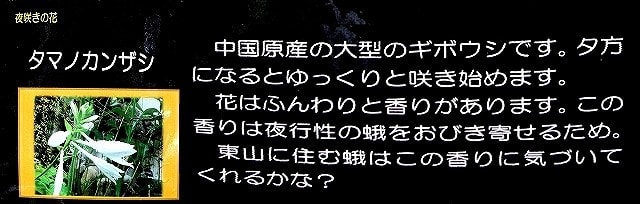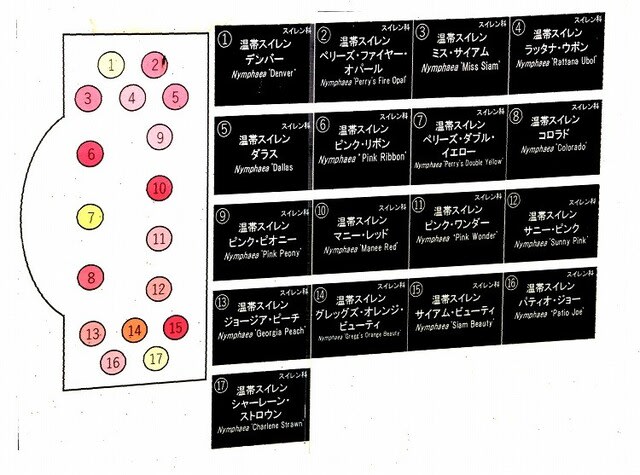9月になりましたが、今年はいつまでも結構暑い日が続きますね、植物園では早咲きの彼岸花が8月の下旬から咲き始めましたが、毎年早いですね、普通の彼岸花はお彼岸の直前にに咲きますね!!

《 コヒガンバナ(小彼岸花) 》 ヒガンバナより小形という意味だが、外見上の違いはない。違うのは、このコヒガンバナには種ができること。生物学的には細胞の染色体数が基本数の二倍の二倍体。ヒガンバナは三倍体で種ができない。白い花の シロバナヒガンバナ は三倍体ですね。



《 セファランサス 》セファランサスは、北アメリカの東部および南部が原産のアカネ科セファランサス属の落葉低木です。園芸店やホームセンターなどでは「谷渡りの木」という名前で販売されていることがありますが、タニワタリノキ(Adina pilulifera)という別種の木と混同されているようです。タニワタリノキというのは、屋久島原産のタニワタリノキ属の常緑低木です。花の形がよく似ていますが、こちらは耐寒性はありません。
セファランサスの特徴は、シベが飛び出して花火のように見える白い球状の花にあります。

《 オオハナオケラ 》オケラの近縁種で中国原産、日本の自生はなく、名前の通り大きな花をつけ、管状花は紅紫色をしています。 草丈は 30~80cm程(栽培種)になります 。

《 ボタンヅル 》センニンソウとよく似ており遠目では見分けができないが、葉が3枚葉で、形がボタン の葉に似ているのが、このボタンヅル。花は繊細だが、家畜も近づかない毒性がある。

《 緑花タマアジサイ 》蕾が玉のように見えることからタマアジサイと名付けられた。 · ・開花は7~9月

《 サクラタデ 》細長い地下茎があり、地中を横に伸長して増える。茎の下部は斜上し、多少分枝し、上部は直立して高さ30-100cmになる。茎は円柱形で細く、節がやや太く、節間はふつう毛は無く、まばらに黄色の腺点がある。

《 シュクコンリナリア 》宿根リナリアは穂状の花を初夏から秋に咲かせる耐寒性のある宿根草です。(多年草)です。ひとつひとつの花はとても小さく繊細で、風に揺れるように咲く姿がとても ...開花時期: 5月~7月

《 シューウカイドウ 》日本の各地で半野生化していることから、日本原産と思われがちですが、江戸時代に中国から渡来した帰化植物です。バラ科の海棠(カイドウ)に似た花を秋に咲かせていることから、秋海棠(シュカイドウ)との名がつきました。林床などの湿り気のある半日陰でよく繁茂します。

《 ギボウシ 》ギボウシ属は世界の温帯地域で栽培されている多年草です。野生種は東アジアの特産で、最も多くの種が分布する日本列島では各地に普通に見られます。海岸近くの低地から亜高山帯、湿原から岸壁まで生息環境も多様です。

《 タマノカンザシ 》
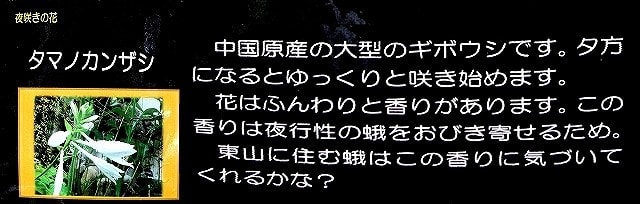

《 ヒレタゴボウ 》鰭田牛蒡.はアカバナ科チョウジタデ属の植物。アメリカミズキンバイともいう。 
《 鉄砲うり 》ウリ科のつる性多年草。 地中海沿岸、カフカス地方、北部アフリカの原産で、観賞用に栽培される。 全株は肉質で粗毛がある。葉は長柄のある三角状心臓形で互生する。 花は葉腋につき、先が五裂した黄色花。

《 ガーキンメロトリア 》「マイクロきゅうり」、あるいは「きゅうりメロン」「ガーキンメロトリア」と呼ばれている小さな実は、ウリ科ではありますがキュウリやメロンがキュウリ属であるのに対し、メロトリア属という別のグループに分類される植物に分類されています。メロトリア属というのは和名ではスズメウリ属といい、近縁種の「スズメウリ」は国内にも自生しています。

《キンミズヒキ 》バラ科キンミズヒキ属の多年草。道端や山野で見られ、夏から秋に小さくて黄色い花が総状に集まって咲く。果実にはとげがあって、動物などにくっついて散布される。

《 ヤマボウシ 由来は、中心に多数の花が集まる頭状の花を法師(僧兵)の坊主頭に、花びらに見える白いを白い頭巾に見立てたもので、「山に咲く法師」(山法師)を意味するといわれている

《 萩色々 》秋の七草の一つであるハギは、『万葉集』に最も多く詠まれていることからも、古くから日本人に親しまれてきた植物だといえます。ハギの仲間は種類が多く、なかでも最も広く栽培されるのが、ミヤギノハギ(Lespedeza thunbergii)です。刈り込んでも枝を1m以上伸ばすほど生育おう盛です。枝垂れて、晩夏から秋にかけて、多数の赤紫色の花を咲かせるのが特徴です。



《 ゲンノショウコ 》フウロソウ科フウロソウ属の多年草。日本全土の山野や道端に普通に見られる。
《 くずの花 》秋の七草の1つである。 肥大した根からは葛粉がとれる。 葛粉は葛切りや葛餅などの原料となる。 根を干したものを生薬で葛根(かっこん)といい、発汗・解熱剤とされる。