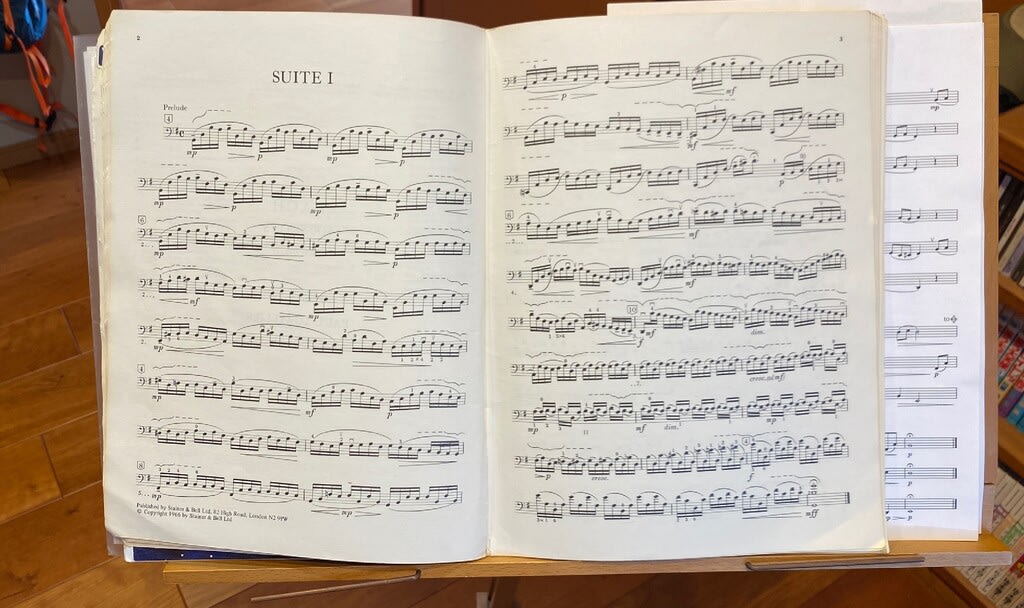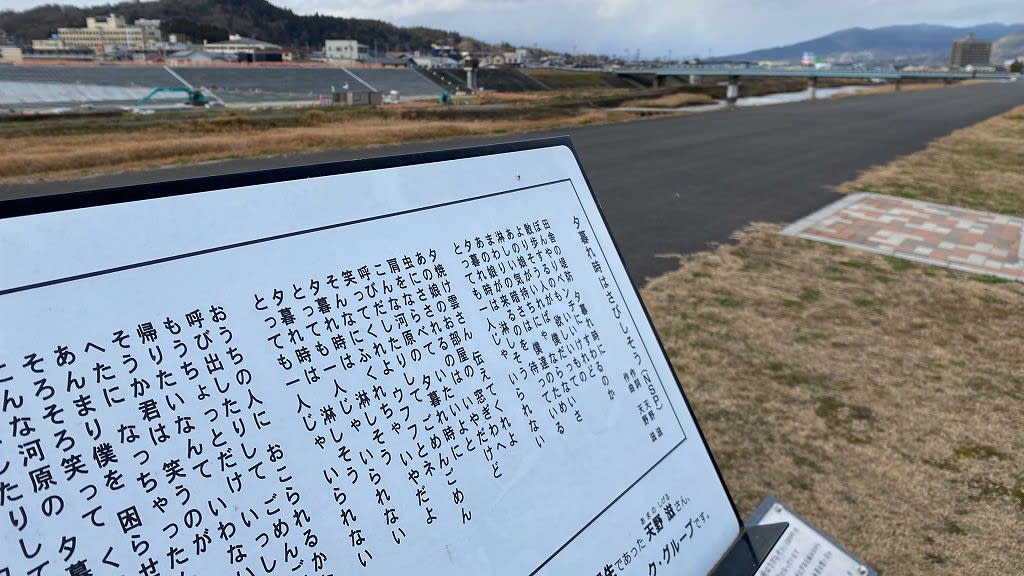何年かぶりかで新譜の洋楽CDを買いました。
Yesのジョン・アンダーソンがバンド・ギークスとコラボして作ったニューアルバム。
バンド・ギークスというのは10年ほど前から活動しているプロ、アマチュア混在のバンドで個人スタジオで録音したカバー曲をyoutubeで配信していました
イエスのナンバーも何曲も公開されていて、私も過去に目にしたことはあります。カバーバンドとしてはとてもレベルが高かった。
詳しい経緯は知らないのですが、そのバンド・ギークスにジョン・アンダーソン自らが一緒にツアーをしようと声をかけたらしいのです。
イギリス、アメリカを回るツアーは好評でした。日本でもやればいいのにと思っていたのですがまさかアルバムを作ってしまうとは。
ジョンは在籍中も、イエスと袂を分かった後も多くのソロアルバムを出しています。
でも、その中にイエスを思い起こさせるような曲は多くありません。というかほとんどない。イエスとは異なるジョン自身の世界観を表現したかったんでしょう。
ところが今回の「TRUE」というアルバムは相当にイエス成分が多い。
楽曲そのものはいかにもジョンらしい輝きに満ちた旋律に満ちているんですが、それを取り囲むバンドの音がイエス。
曲の中に過去のイエスの曲を喚起するそれぞれの楽器の特徴的なフレーズの模倣が山ほど出てきます。
どの曲でどれとはいちいち書きませんが、Going for the oneやIn the presence ofのベースライン、Homewaorldのキーボードなど。これはイエスのパロディかと思いました。
ギターもスティーヴ・ハウらしいフレーズを本人より安定した技術で入れてきます。ギタリストはアイアン・メイデンの現メンバーですがハウの文法を体得しています。
必要に応じてトレバー・ラビン的なフレーズやエレアコの独特な籠った音色も随所で聞かれますのである意味8人イエス的な響きにも聞こえるのが面白い。
極端なことを言ってしまえば、ジョンのあの歌声があれば、他の4人が模倣でもそれは充分イエスたり得るということです。
逆に言うとあの声がなければイエスには聞こえない。バンドにおけるボーカルの重要性は楽器隊と同等ではないということです。(個人の感想です)
昔、イエスファンの集まっているところで「Drama」は長いこと聞く気にならなかった、という話をしたらある人から強く非難されました。まあ人それぞれです。
先ほど模倣とかパロディという表現をしましたが、このアルバムに一番ふさわしいのはイエスのクローンかも知れません。
本家のイエスが主に年齢的なことで劣化してしまった部分を、DNAを引き継いだ若いバンドメンバーが後世に繋いでいくようなイメージです。
79歳になるジョンの声はイエス在籍期終盤程度の力を維持しています。大したもんだ。こうなるとクリスのコーラスがないことが残念でなりません。
このアルバムには、何か新しい物が生まれているような新鮮さはありませんが「ladder」や「magnification」レベルの魅力は充分に感じられる楽曲となっています。
Facebookでジョンが2025年にはハワイと日本に行くという発言をしていました。実現することを心から願っています。
一つだけ文句を言わせていただければ、ジャケットデザインがひどすぎます。最低のブートよりさらにダサい。
次作があるなら改善してもらいたいものです。