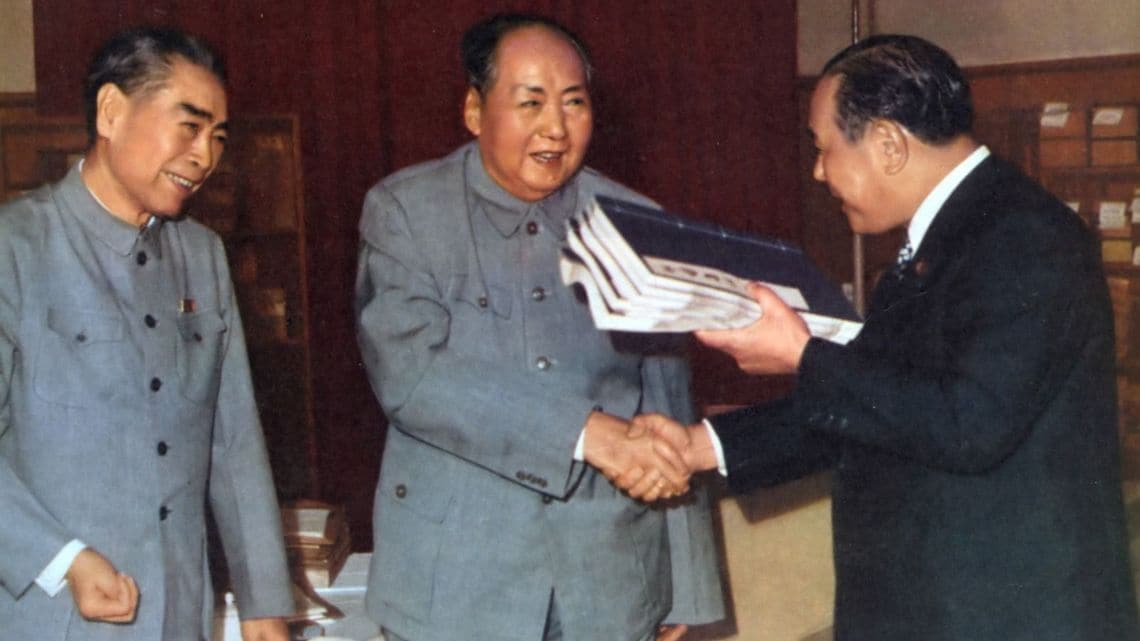【卓上四季】:こぼれ落ちるもの
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【卓上四季】:こぼれ落ちるもの
「学者はその無限多様な現実を掬(すく)い上げるもので、そのときに網の目からこぼれた、指の間からこぼれたものに対する無限の哀惜の念を持ってなければいけない」。政治を深く見つめた丸山真男の言葉だ。養老孟司さんが紹介している(「虫とゴリラ」毎日新聞出版)▼学者は研究対象を文字で表現し、分類する。その過程で「いろんなものがこぼれ落ち」、対象はあるがままの姿を失ってしまうという。だがそこにも目を向けなければ、全体像は把握できず、本質にたどりつけない。だから神経を研ぎ澄まし、対象を見る。丸山の慧眼(けいがん)はその真摯(しんし)な姿勢を土台にしていたのだろう▼現実の社会で人がこぼれ落ちれば生命に関わる。この人はその重大さに気付くのだろうか。菅義偉首相のことだ▼目指す社会像は「自助、共助、公助そして絆」。まずは自分でやってみる。そのうえで、地域や家族が助け、最後が政府の安全網らしい▼「自助」から始まる社会に怖さを感じる。病気や障害などで、自ら考え、動くことができない人がいる。コロナ禍で追い詰められ、声すら上げられない人もいよう。この実情が目に入っていれば、「自助」がどれほど残酷か分かるはずだ▼安倍前政権の路線継承を掲げる首相である。格差が広がる現実に目を向けずに、そのまま放置する懸念が拭えない。こぼれ落ちたものに対する「哀惜の念」など顧みることなしに。2020・9・27
元稿:北海道新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【卓上四季】 2020年09月27日 05:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。