【岸田政権】:コロナ禍で困窮のさなか介護料を月6.8万円爆上げの鬼畜! ■安倍・菅政権の弱者切り捨て棄民政策を続行
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【岸田政権】:コロナ禍で困窮のさなか介護料を月6.8万円爆上げの鬼畜! ■安倍・菅政権の弱者切り捨て棄民政策を続行
岸田文雄首相が打ち出した、過去最大の55兆7000億円にものぼる過去最大の経済対策。しかし、コロナで打撃を受けている生活に困窮する人をフォローできるような内容にはまったくなっていない上、あれだけ衆院選で訴えていた介護や看護、保育の現場で働く人たちへの賃金引き上げも、蓋を開けてみれば保育士や介護職員が月額9000円、看護師は月額4000円という“雀の涙”にすぎない結果に。これでは格差の是正どころか格差はどんどん広がるばかりだ。

首相官邸HPより
しかも、ここにきて、安倍・菅政権の「自助」政策の実施によって大きな悲鳴があがっている。というのも、今年8月から介護保険制度が見直され、介護施設の利用者の負担額が目玉が飛び出すほど爆上がりをしているのだ。
今月24日にも中国新聞デジタルが「特養の月額利用料2万2千円も上がった…「あまりに負担重い」なぜ今?」という記事を配信し、話題となったが、爆上がりしているのは特別養護老人ホームなどの介護保険施設での食費や居住費(部屋代)だ。
今年7月までは、住民税非課税世帯で、預貯金などの資産が単身で1000万円以下、夫婦で2000万円以下ならば食費や居住費を補助する「補足給付」が受けられた。だが、8月からはこの「補足給付」の要件が厳しくなり、年金などの収入に応じて、資産が単身で500万円〜650万円、夫婦で1500万円〜1650万円に厳格化。対象から外れると食費・居住費は全額自己負担となるため、「補助額の大きかった低収入の人ほど負担増額が膨れ上がり、最大月6万9000円に上る」という(しんぶん赤旗9月15日付)。
住民税非課税世帯に対し、預貯金が単身650万円をわずかにも超えただけで補助の対象外にし、年間にして約83万円もの負担増を強いる──。これだけでも衝撃的だが、さらに問題となっているのは、「補足給付」の対象者でも負担が増している、ということだ。
たとえば、収入が年120万円超〜155万円以下の場合、特養などの施設での食費は1日650円だったが、8月からは1360円に。7月までは月約2万円だったのが月4万1000円と倍以上に跳ね上がったのだ。これは年間にして約24万円も負担が増す計算になる。さらに、こうした食費の負担増はショートステイを利用した場合でも同様だ。
◆安倍政権がコロナ前に決めた弱者切り捨て政策をコロナ下に強行する岸田政権
厚労省によると、今回の見直しによって約27万人もの人たちの負担が増えたというが、当然ながら、これほど負担が大きくなると、施設を退所せざるを得ない人や入所できないという人が出てくるのは必至だ。
低所得かつ預貯金も心もとない高齢者やその家族に対し、さらに鞭をふるう政府──。しかも問題にすべきは、このような生活が苦しい人たちに負担を強いる制度の見直しを、なぜ消費増税やコロナによって困窮する人が増加している状況のなかで実行したのか、という点だ。
この「補足給付」の要件見直しは、コロナ前の2019年の年末、つまり安倍政権時代に厚労省の社会保障審議会介護保険部会で了承され、菅政権時の今年3月31日に政令として公布されたものだ。つまり、法改正ではないため国会審議はおこなわれていないのだが、国会では野党議員がこの「補足給付」の見直しを問題視し、たびたび追及をおこなっていた。
たとえば、昨年1月23日に参院本会議でおこなわれた安倍首相の施政方針演説に対する代表質問では、立憲民主党の福山哲郎・参院議員が「消費税率が引き上げられ、生活がさらに苦しくなるなか、一層の支援が必要な低所得者にとっては負担増になります。これでは何のための消費増税だったのかという声が上がっても仕方がありません」と言及したが、対する安倍首相は「在宅で介護を受ける方との公平性の観点から御自身で負担していただく」「年金収入の水準いかんによっては助成額に大きな差異が生ずる場合もある」などと正当化。実態は生活困窮世帯をさらに苦しめる施策であるにもかかわらず、あたかも公平性を担保するためであるかのように語っていた。
さらに、「補足給付」の問題を繰り返し取り上げてきた日本共産党の倉林明子・参院議員は、今年6月1日の参院厚労委員会で「コロナの影響による収入減で支える家族の援助も限界」「本人の年金だけでは払えない」「退所に追い込まれる人が出てくる」「いまだ見直しがあるということを知らない利用者・家族も少なくない」と指摘。だが、当時の田村憲久厚労相は「制度を持続していかなきゃならぬわけでございまして、負担能力に応じて御負担をいただきたいというのが今回の決定」と押し通した。
◆安倍・菅政権による弱者切り捨て棄民政策を岸田政権も続行!
消費増税やコロナによる生活への打撃はまったく無視。ようするに、安倍政権も菅政権も、この「補足給付」見直しによって窮地に立たされる人が続出することをさんざん指摘されても、コロナで生活困窮者が増加して事態が深刻化しても、まったく意に介そうともしなかったのだ。
だが、それも当然なのかもしれない。そもそも介護施設での食費や居住費は、2000年の介護保険制度スタート時には保険給付の対象だった。それを小泉純一郎政権の2005年に保険給付から外して全額自己負担にし、その際、低所得者の負担軽減のために「補足給付」という制度が導入された。ところが、2014年に安倍首相が「補足給付」に手を付けて、資産要件を追加。また、配偶者が課税世帯だと補助を打ち切るとしたのだ。
安倍政権は2017年の介護保険法改正をはじめとして利用者に負担増を強いてきたが、この「補足給付」も2度にわたって改悪し、低所得者を狙い撃ちにしたのである。つづく「自助」を掲げた菅政権がこれを踏襲したのは、言うまでもない。
しかも、こうした介護保険制度の見直しによる負担増の流れは、岸田首相に代わったからといって止まることはない。実際、岸田首相が設置した「新しい資本主義実現会議」では、さっそく経団連の十倉雅和会長が「社会保障制度の見直し」を提言。そして、その経団連は、今年10月11日に公表した提言において、「介護保険の2割負担の対象者拡大」「介護のケアプラン作成に利用者負担を導入」などを政府に求めているのだ。
それでなくても、つい最近も介護保険料の滞納によって預貯金などが差し押さえられた65歳以上の人が過去最多の2万1578人(2019年度)となったと発表されたばかりだが、安倍政権を継承する岸田首相や、同じく社会保障の縮減を訴える維新が党勢拡大をはかるなか、どんどん弱者は切り捨てられていくことになるだろう。(編集部)
元稿:LITERA・リテラ(本と雑誌の知を再発見) 主要ニュース 社会 【社会問題・】 2021年11月26日 06:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
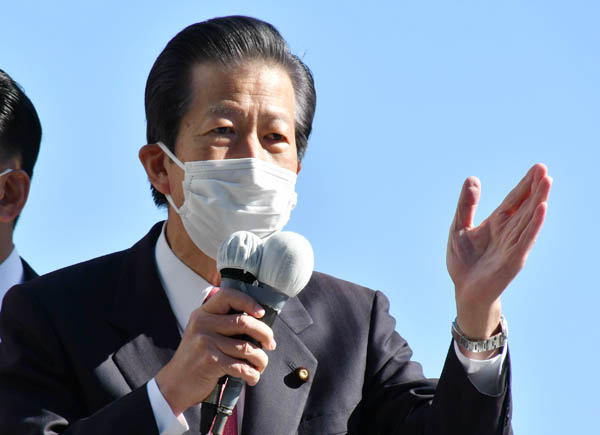 </picture>
</picture>

















