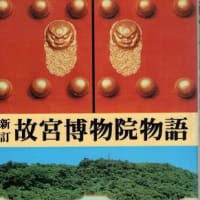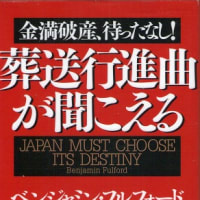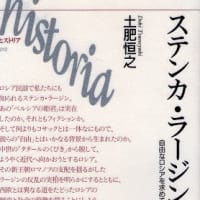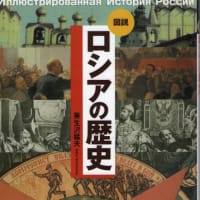例によって図書館から借りてきた本で、「誰がための官僚」という本を読んだ。
いや、読もうとしたが、途中で棒折れになった。挫折だ。
最後まで読み通せなかった。
相当に長大なもので、かなり読みでがあると思って借りてみたが、内容が悪い。
読んでいる最中に先に進むのが嫌になってしまった。
平成5年から始まった省庁再編成が行政改革の一環ということはわかるが、われわれ一般国民の側から見て、行政システムのあまりにも細部にわたる知識というのは大した意味がない。
省庁間の力関係などというのは知らないでも済んでいく問題に他ならない。
著者自身があとがきで述べているように、「省庁改革という大がかりな手術を受けることになった霞が関の内部の動きを追ったレポート」となっているが、われわれ国民の側から見て、霞が関の内部の動きなど問題ではない。
霞が関の外に対する動き、外に向かうインパクト、国民に向けた、思考、意思、対応が問題なわけで、内部で如何様にマグマが躍動しようとも、それは国民の側に立てば二次的なものにすぎない。
われわれにとって大事なことは、国民に対してどういうアプローチをするかであって、内部の動きなどどうでもいいことである。
ただこの本の言わんとするところは、政治家が官僚の下に位置する現状を憂いているわけで、その部分は傾聴に値する。
そもそも官僚は行政という意味からしても、政治家の下で、政治を具現化することが彼らの本来の使命のはずであるが、政治家が不勉強なるがゆえに、この立場が逆転している点については、この本の著者の指摘は的を得ている。
この本の「官僚」という文字に惹かれて、読む気が喚起されたが、内容は読むに値しないものであった。
ただ「官僚」という言葉には、本の内容の如何に関わらず、私なりの思いがある。
官僚、いわゆる国家公務員というのは、基本的に公僕であるべきだと思う。
公の僕であるべきだと思う。
公の僕であったからこそ、戦後の一時期、手当ても非常に少なく、給料だけではとても生活が維持できない時があり、官僚としての暗黒の時代があったことは確かである。
そういう状況を鑑みて、戦後もしばらくの間、公務員のなり手のない時期もあった。
しかし、公務員、官僚というのは、給料の高においては民間企業に及ばないが、安定した職業だという認識は太古から連綿と息づいている。
だから封建主義の残滓を引きずっていた戦後もしばらくの間は、長男は家を守らねばという立場上の制約から、地方の官吏に応募したケースがしばしばある。
そして、戦後の復興期を経ると、民間企業との格差が広がり、その格差を縮める措置が取られた。
ところが、民間企業というのは景気の変動に左右されて、給料も上がったり下がったりする。にもかかわらず、官吏、公務員というのは法律で給料が定められているので、景気の変動にリンクしていない。
景気の変動にリンクしていないという点が、極めて安定した職業というわけで、この安定した職業という点が人々を魅了したのである。
日本人は誰でも義務教育を受け、その中の一部のものは更に高等教育を受けて社会に巣立つが、この高等教育の段階で成績の優秀なものはその大部分が民間企業に流れる。
それは高級という経済の面もあるが、その前に民間企業には挑戦に値するチャンス、あるいは頑張ればその見返りが期待できる、ということも覇気に富んだ若い人を引き付ける大きな要因だと思う。
当然、大勢の若者の中には最初から国家公務員を目指す者もいるが、それはそれで立派なことである。
ところが、問題は、公務員を目指す動機である。
いい若い者が、未来に対す挑戦から逃げて、安定しているからとか、給料の変動がないからとか、仕事が楽だからとか、少々給料が安くても天下りがあるという動機で公務員を選択したとしたら、極めて由々しき問題だと思う。
現実には公務員を選択する若者の職業選択の動機は案外こういうものであるようだ。
国家公務員が安定した職業だ、という言葉の中には、何もしなくても出世が出来る、という意味も含まれているのである。
国家公務員、官僚の仕事は、とにかく何もしないことだと思う。
すればしただけ失敗のチャンスが多くなり、それはすべてマイナス評価につながるわけで、最初から手を出さなければ失敗することもなく、マイナス評価になることもない。
これが官僚の世界だと思う。
民間企業では、採用したばかりの優秀な社員に自社の伝統としての企業理念を植え付ける教育を施し、企業存立のコンプライアンスを教え込み、ビジネスに果敢に挑戦することを教え込むが、官僚ではこういうことは無いわけで、どこまで行っても、保身の術を模索するのみで、新しいことへの挑戦というのはありえないと思う。
無理もない話で、如何なるシチュエーションでも、官僚自らが考え、企画し、推進するということは無いわけで、その全てが民間への丸投げであるからして、彼らは許認可権さえしっかり握っていれば、それで存在価値を示したことになる。
民間企業では上から下まで如何に儲けるか、如何に利潤を上げるか、如何にコストを下げるか、乾いた雑巾を絞るように知恵を出し合っているが、公務員にはこういう試練は最初から無いわけで、あるとすれば一度確保した予算を如何にゼロに使いきるかということでしかないと思う。
そして彼らは自分の仕事を自分で作って、それをあたかも国民からの希求でもあるかのように見せかける。
この仕事というのが国民の福祉につながるものであるならば、それはそれで公務員としての存在価値を認めざるをえないが、この仕事というのが公務員のための公務員の仕事になっているところが、国民不在の行政と言われる所以である。
例えば公立学校の先生も教育公務員であるが、彼ら彼女らの仕事の多さというのは一体どういうことなのであろう。
子供に授業を教えるという、純粋に先生という職務のほかに、何故にああも余分な仕事があるのであろう。
その一つ一つの仕事に、それぞれに存在意義があるのだろうれど、果たして本当にその仕事が必要かどうかはまた別の問題だと思う。
もろもろの雑用を「しなければならない!!」という発想そのものが、極めて公務員的であり、官僚的なわけで、その発想の元を考察する勇気がないのである。
しなくてもいい仕事がだいぶあるように思うが、彼らに言わせればその全部が大事な仕事というわけだ。
どうでもいい仕事を大事な仕事と思うところが、官僚の官僚たる所以である。
教育公務員に、いわゆる学校の先生に、過度な仕事を押し付けているのが、案外、国民の側にあることも確かである。
幼児、児童の殺害事件が多くなると、その保護まで先生の仕事に押し付けるなどということは、確かに国民の側の官僚あるいは国家に対する過大な要求なわけで、このあたりの説明責任こそメデイアの責任のはずであるが、日本のメデイアはそういう方向には全く機能しない。
子供が自分の親、あるいは家庭内で危害を加えられても、校長先生がコメントを求められている。
こんなバカな話もないではないか。
子供の命が大事だということは当然のことであるが、家庭内のことまで校長先生のコメントを求めるという感覚は明らかおかしいが、メデイアはそれに全く気がついていないではないか。
こういうことが先生に過度な仕事を押し付ける原因だと思う。
こういうメデイアの非常識な対応がモンスター・ペアレントを生み出している。
いや、読もうとしたが、途中で棒折れになった。挫折だ。
最後まで読み通せなかった。
相当に長大なもので、かなり読みでがあると思って借りてみたが、内容が悪い。
読んでいる最中に先に進むのが嫌になってしまった。
平成5年から始まった省庁再編成が行政改革の一環ということはわかるが、われわれ一般国民の側から見て、行政システムのあまりにも細部にわたる知識というのは大した意味がない。
省庁間の力関係などというのは知らないでも済んでいく問題に他ならない。
著者自身があとがきで述べているように、「省庁改革という大がかりな手術を受けることになった霞が関の内部の動きを追ったレポート」となっているが、われわれ国民の側から見て、霞が関の内部の動きなど問題ではない。
霞が関の外に対する動き、外に向かうインパクト、国民に向けた、思考、意思、対応が問題なわけで、内部で如何様にマグマが躍動しようとも、それは国民の側に立てば二次的なものにすぎない。
われわれにとって大事なことは、国民に対してどういうアプローチをするかであって、内部の動きなどどうでもいいことである。
ただこの本の言わんとするところは、政治家が官僚の下に位置する現状を憂いているわけで、その部分は傾聴に値する。
そもそも官僚は行政という意味からしても、政治家の下で、政治を具現化することが彼らの本来の使命のはずであるが、政治家が不勉強なるがゆえに、この立場が逆転している点については、この本の著者の指摘は的を得ている。
この本の「官僚」という文字に惹かれて、読む気が喚起されたが、内容は読むに値しないものであった。
ただ「官僚」という言葉には、本の内容の如何に関わらず、私なりの思いがある。
官僚、いわゆる国家公務員というのは、基本的に公僕であるべきだと思う。
公の僕であるべきだと思う。
公の僕であったからこそ、戦後の一時期、手当ても非常に少なく、給料だけではとても生活が維持できない時があり、官僚としての暗黒の時代があったことは確かである。
そういう状況を鑑みて、戦後もしばらくの間、公務員のなり手のない時期もあった。
しかし、公務員、官僚というのは、給料の高においては民間企業に及ばないが、安定した職業だという認識は太古から連綿と息づいている。
だから封建主義の残滓を引きずっていた戦後もしばらくの間は、長男は家を守らねばという立場上の制約から、地方の官吏に応募したケースがしばしばある。
そして、戦後の復興期を経ると、民間企業との格差が広がり、その格差を縮める措置が取られた。
ところが、民間企業というのは景気の変動に左右されて、給料も上がったり下がったりする。にもかかわらず、官吏、公務員というのは法律で給料が定められているので、景気の変動にリンクしていない。
景気の変動にリンクしていないという点が、極めて安定した職業というわけで、この安定した職業という点が人々を魅了したのである。
日本人は誰でも義務教育を受け、その中の一部のものは更に高等教育を受けて社会に巣立つが、この高等教育の段階で成績の優秀なものはその大部分が民間企業に流れる。
それは高級という経済の面もあるが、その前に民間企業には挑戦に値するチャンス、あるいは頑張ればその見返りが期待できる、ということも覇気に富んだ若い人を引き付ける大きな要因だと思う。
当然、大勢の若者の中には最初から国家公務員を目指す者もいるが、それはそれで立派なことである。
ところが、問題は、公務員を目指す動機である。
いい若い者が、未来に対す挑戦から逃げて、安定しているからとか、給料の変動がないからとか、仕事が楽だからとか、少々給料が安くても天下りがあるという動機で公務員を選択したとしたら、極めて由々しき問題だと思う。
現実には公務員を選択する若者の職業選択の動機は案外こういうものであるようだ。
国家公務員が安定した職業だ、という言葉の中には、何もしなくても出世が出来る、という意味も含まれているのである。
国家公務員、官僚の仕事は、とにかく何もしないことだと思う。
すればしただけ失敗のチャンスが多くなり、それはすべてマイナス評価につながるわけで、最初から手を出さなければ失敗することもなく、マイナス評価になることもない。
これが官僚の世界だと思う。
民間企業では、採用したばかりの優秀な社員に自社の伝統としての企業理念を植え付ける教育を施し、企業存立のコンプライアンスを教え込み、ビジネスに果敢に挑戦することを教え込むが、官僚ではこういうことは無いわけで、どこまで行っても、保身の術を模索するのみで、新しいことへの挑戦というのはありえないと思う。
無理もない話で、如何なるシチュエーションでも、官僚自らが考え、企画し、推進するということは無いわけで、その全てが民間への丸投げであるからして、彼らは許認可権さえしっかり握っていれば、それで存在価値を示したことになる。
民間企業では上から下まで如何に儲けるか、如何に利潤を上げるか、如何にコストを下げるか、乾いた雑巾を絞るように知恵を出し合っているが、公務員にはこういう試練は最初から無いわけで、あるとすれば一度確保した予算を如何にゼロに使いきるかということでしかないと思う。
そして彼らは自分の仕事を自分で作って、それをあたかも国民からの希求でもあるかのように見せかける。
この仕事というのが国民の福祉につながるものであるならば、それはそれで公務員としての存在価値を認めざるをえないが、この仕事というのが公務員のための公務員の仕事になっているところが、国民不在の行政と言われる所以である。
例えば公立学校の先生も教育公務員であるが、彼ら彼女らの仕事の多さというのは一体どういうことなのであろう。
子供に授業を教えるという、純粋に先生という職務のほかに、何故にああも余分な仕事があるのであろう。
その一つ一つの仕事に、それぞれに存在意義があるのだろうれど、果たして本当にその仕事が必要かどうかはまた別の問題だと思う。
もろもろの雑用を「しなければならない!!」という発想そのものが、極めて公務員的であり、官僚的なわけで、その発想の元を考察する勇気がないのである。
しなくてもいい仕事がだいぶあるように思うが、彼らに言わせればその全部が大事な仕事というわけだ。
どうでもいい仕事を大事な仕事と思うところが、官僚の官僚たる所以である。
教育公務員に、いわゆる学校の先生に、過度な仕事を押し付けているのが、案外、国民の側にあることも確かである。
幼児、児童の殺害事件が多くなると、その保護まで先生の仕事に押し付けるなどということは、確かに国民の側の官僚あるいは国家に対する過大な要求なわけで、このあたりの説明責任こそメデイアの責任のはずであるが、日本のメデイアはそういう方向には全く機能しない。
子供が自分の親、あるいは家庭内で危害を加えられても、校長先生がコメントを求められている。
こんなバカな話もないではないか。
子供の命が大事だということは当然のことであるが、家庭内のことまで校長先生のコメントを求めるという感覚は明らかおかしいが、メデイアはそれに全く気がついていないではないか。
こういうことが先生に過度な仕事を押し付ける原因だと思う。
こういうメデイアの非常識な対応がモンスター・ペアレントを生み出している。